
大阪で御香典で包む不祝儀袋のマナーを解説。表書きや中袋・袱紗(ふくさ)の整え方は?

突然の訃報でお通夜や葬儀に参列する時、大阪では御香典の包み方マナーが気に掛かりますよね。包む金額で変わる不祝儀袋の選び方や、お札の入れ方まで、いざ整える時には戸惑う声も多いです。
また大阪では同僚など連名で御香典を包むことも多く、マナーも少しずつ変わります。仕事関係であれば、失礼なく整えて準備をしたいですよね。
今回は、大阪で御香典を包む時の基本的なマナーを、連名や人数が多い場合、中袋や持ち歩きのマナーまでお伝えします。
大阪で御香典で包む不祝儀袋のマナーを解説。表書きや中袋・袱紗(ふくさ)の整え方は?
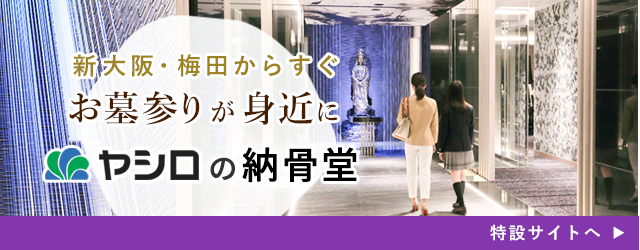
御香典の包み方、書き方の考え方
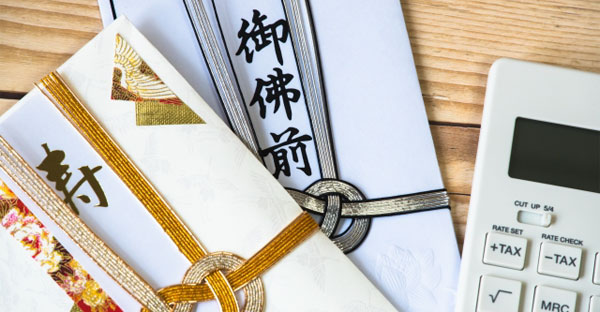
大阪では御香典の包み方マナーを大切にする一方、お祝儀でも失礼のないように気を配りますよね。御香典は弔事、お祝儀(結婚式など)は慶事となりますが、本来の考え方では弔事と慶事でお金を包む時のマナーは「反対」でなければなりません。
例えば大阪で御香典を包むマナーでは、水引の本数は陰の数として偶数(二本・四本・六本など)とされますが、お祝儀を包む慶事において水引の本数はめでたい陽の数で奇数(三本・五本・七本など)です。
今では多くが市販の不祝儀袋・祝儀袋を利用しますので、あまり水引まで配慮する必要が無くなりましたが、他にも、弔事と慶事で「反対」のマナーが多々あります。
● 大阪で御香典を包むマナーとして最も意識したいポイントは、最後に上包みを折り畳む向きです。弔事(御香典)では下向き、慶事(お祝儀)では上向きに整えます。
→ 覚え方では、弔事の時には哀しみのために下を向き(下向き)、慶事では喜びのために上を向く(上向き)が有名です。
近年では滅多にありませんが、奉書氏(ほうしょし)で御香典を包む方もいますよね。この場合も奉書氏は慶事と反対の折り方で進めます。また、弔事は「忌むべき数字(重ねる)」を避けるため、二枚重ねは避け、一枚で包むのが大阪の御香典マナーです。
また、ここでは大阪の葬儀で包む御香典マナーをお伝えしていますが、ご住職にお渡しするお布施や、一周忌・三回忌などの法要で包む大阪の御香典マナーも少しずつ変わりますので、ご注意ください。
(1)お布施 … お布施ではそもそも水引が必要のない地域が多いですが、もしも水引を付けるとしても白黒ではありません(不幸があったことへのお布施ではないため)。
※実は紅白でも良いとされていますが、さすがに弔事では気が引けます。そのため白黄や双銀の水引を利用する方が多い傾向です。
(2)法要 … 一周忌や三回忌などの法要においても、必ずしも白黒とは限りません。本来の水引は「白」ですが、地域によって白黄や黄色、双銀を選びます。
大阪の御香典マナーでは、お通夜や葬儀での水引は白黒ですが、一周忌や三回忌などの法要では「白」が本来は正式です。白黒やしばしば白青などの水引も法要では見受けますが、これらは本来は略式とされています。
● また、大阪では御香典マナーとして、不祝儀袋は包んだ金額に比例したものを選びます。
→ 印刷されている不祝儀袋は千円~三千円ほどまで、五千円以上は水引が別に掛けられたものを選び、10万円以上になれば大きく豪華な不祝儀袋、と言った具合です。
表書きの書き方マナー
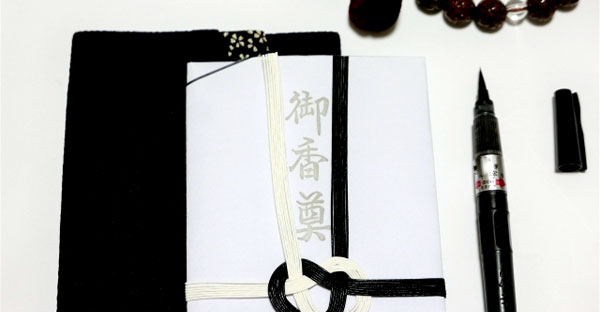
本来、大阪で御香典を包むマナーとしては「表書き=目録」と捉えますから、包みの内容(御香典)、数量(金額)、差出人(姓名)の三つを書くとされてきました。
ただ、昭和時代には金額を表に記すのはデリカシーがないとして、金額は表に記さず、裏面や(一枚封筒の場合)、中袋の表に書き添えます。
● 弔事で用いる墨は薄墨です。「故人の訃報を知り、涙で墨が薄くなった」と言う弔意を込めて薄墨を使用します。書体は本来楷書ですが、目上の方であれば楷書が安心ではあるものの、行書体の方も多いでしょう。
<上包みの表書き>
・上半分 … 「御香典」「御香料」「御霊前」「御仏前(浄土真宗)」など(※)
・下半分 … 姓名(前述したように、なかにはここに金額を入れる方もいます。)
<中袋>
・表に金額(※2)
・裏に住所と氏名
(※)表書きでは「御香典」や「御霊前」が多いですが、キリスト教では御花料、神式では御玉串料などと表書きを変えることもあります。
詳しくは別記事「大阪で包む御香典。地域性や宗旨宗派で違う包み方マナーとは」でお伝えしていますので、コチラをご参照ください。
● 御香典は大字を使います。一から五までの数字は「壱・弐・参・(四は用いず)・伍」、千円・万円は「阡円・萬円」です。また、数字の頭には「金」を入れます。
→ 例えば三万円を包むのであれば「金参萬円」、五千円なら「金伍阡円」です。
大阪の葬儀で御香典を包む金額相場は、別記事「大阪で包む御香典。立場によって違う金額相場と持参マナー」で詳しくお伝えしていますので、コチラを併せてご参照ください。
また、大阪では連名で御香典を包むこともありますよね。このような場合にも、名前の順番にマナーがあります。
● 大阪で連名の御香典マナーでは、右側から目上の方の氏名を書き、左側へ続けての記載です。表書きに連名を連ねる場合、多くても3~4名までにします。
3~4名以上の連名で御香典を包む時には、集まりの名前+「有志」と書き(例えば「〇〇課有志」など)、別紙にて名前を記載して内側に添えるのが一般的です。この場合にも目上が右側、を意識すると良いでしょう。
お札の入れ方と持ち運び
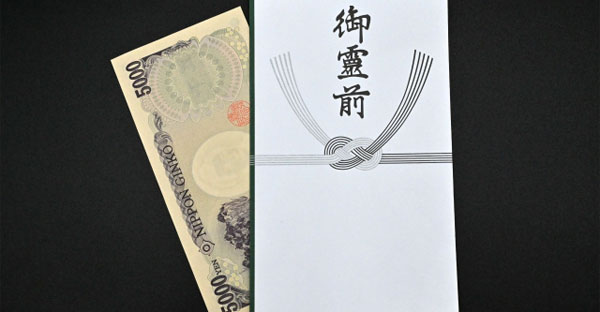
大阪の御香典マナーでは、お札の入れ方まで注意をしなければなりません。お札の入れ方や向きには、弔事用と慶事用のマナーが反対になっているためです。これが反対になると、葬儀の席では失礼なことになってしまいます。
● 喪主が袋を開けた時、お札は裏側(お顔のない側)、そしてお顔が見えないように数字側に入れてください。
→ 「訃報を知っていて準備をしていた」として新札は避けるとされていますが、現在のマナーとしては、新札を縦にひと折りして入れるようになっています。
…また、ビジネスとしてのお付き合いが強い場合、ご遺族に分かりやすいように(また、後々の整理もしやすいよう)、大阪の御香典マナーでは、しばしば上包みの表書き、氏名の部分に名刺を貼る事例も増えました。
この他、家族葬による御香典辞退があっても何か弔意を示したい場合、時にはお線香などの供物を用意することもあります。(御香典と供物の両方を用意することも多いです。)
この時には、供物の箱の全面に奉書紙を巻いて、御香典の表書きと同じように準備をすると良いでしょう。
最後に準備をした御香典の持ち運びですが、大阪の御香典マナーとしては、袱紗(ふくさ)を利用します。
● 弔事用の紫や黒、草色などの地味な色目のものを選び、レースなどの装飾のない、シンプルなものを選んでください。
→ 袱紗(ふくさ)の他にも小さな風呂敷や黒いハンカチなどに包んで持ち運ぶ方もいます。急な訃報で袱紗(ふくさ)の準備ができない場合は、このようにして持ち運ぶと良いでしょう。
袱紗(ふくさ)について、詳しくは別記事「大阪で御香典の持ち運びは袱紗(ふくさ)を利用。包み方や差し出し方、添える言葉を解説」で、より詳しくお伝えしていますので、コチラを併せてご参照ください。
いかがでしたでしょうか、今回は大阪で包む御香典マナーについて、表書きや中袋の書き方、お札の準備や入れ方について詳しくお伝えしました。
また、コロナ禍になってからはお通夜や葬儀に参列できず、御香典を郵送する機会が増えました。
大阪で御香典を郵送する時のマナーについては「大阪で御香典を送る時のマナーとは☆送るタイミングや注意点、御香典には手紙を添えた方がいいの?」でも詳しくお伝えしています。
※お通夜や葬儀に参列する時の服装マナー「大阪の葬儀に参列する時の服装マナーを解説。数珠の選び方や、御香典の持ち運び作法まで」も併せて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
まとめ
御香典の不祝儀袋や表書きマナー
●御香典マナーの基本
・御祝儀の反対
・お布施や法要とは水引が違う
・包む金額に合わせて外袋を選ぶ
●表書き
<上包み>上に目録、下に氏名
<中袋>表に金額、裏に住所と氏名
・文字は薄墨
・数字は大字(壱・弐・参など)
●連名
・右側が目上
・表書きには3~4名まで
・4名以上は別紙に書く
●お札の入れ方
・開けた時に裏側・数字側
・新札を縦にひとつ折りして入れる
●その他
・名刺を貼ることもある
・供物は奉書紙で包み、表書き
・持ち運びは袱紗(ふくさ)
・袱紗(ふくさ)は地味でシンプルなもの
●コロナ禍で御香典の郵送も増えた
お電話でも受け付けております















