
定年前後にガクンと収入が減額する4つのタイミングとは。収入減額の理由を知って対策を
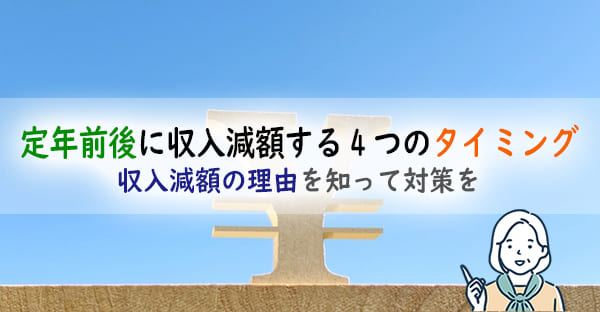
「定年前後に収入が大幅に減額しないか不安」
「定年前後は現役時代とどれくらい収入が違うの?」
「定年後に収入が大幅に減額しない対策は?」
「定年後、収入が大幅に減額した時はどうする?」
なかなか給与が上がらない現代の日本でも、現役世代は健康でさえあれば何とか対応ができる側面もあります。けれども定年前後の収入減額には注意が必要です。
毎月の固定収入が半減するリスクも充分にあり得ますが、現役時代から事前に定年前後の収入が減額するタイミングを把握することで対策も取れますよね。
本記事を読むことで、定年前後に大幅な収入の減額が起こり得る、4つのタイミングと対策が分かります。
定年後の収入減①役職定年

「役職定年」とは、一定の年齢を迎えると役職から外れる制度です。会社側としては、人材の新陳代謝や、上のポストを開けて若手のモチベーションを上げる目的があります。
役職定年制度を設けている企業は全体で16%とパーセンテージだけみるとごく僅かに感じますが、300人以上規模の会社で30%ほどが採用している制度です。
規模の大きな会社に勤めている方こそ、役職定年制度を把握しておきましょう。
役職定年を迎える年齢
企業により制度の詳細は異なりますが、平均的に役職定年を迎える年齢は55歳~57歳です。全ての役職ではなく、特定の役職のみが定年を迎える企業もあるでしょう。
国としては65歳定年制度を推奨していますが60歳定年制度を採用する企業が多いためです。今後65歳定年制度が進めば、役職定年の年齢も上がることが予想されるでしょう。
役職定年により予想される減収
役職を降りることで役職手当が無くなるため、役職定年を迎えた90%以上の方々が収入が減額しています。
令和4年に厚生労働省が行った「賃金構造基本統計調査」によると、役職定年を迎えることで約30%~40%も減収する方も多いです。
また役職定年制度では一度に大きな収入の減額を受けるのではなく、段階的に減収する給与システムもあるのでご確認ください。
・厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」
役職定年で困窮する事例
例えば月額60万円の給与の方が役職定年により20%収入が減額したとすると月収48万円です。「月収60万円-月収48万円」の差額は12万円ですよね。現状で毎月12万円が貯蓄、遊び等ゆとり費になっているならば、まだ良いでしょう。
ただ毎月12万円の全額が住宅ローンや車のローン等の返済に充てられる等の理由で、家計にゆとりがなければ大変になります。特に50代では子どもの大学資金等、子どもの教育費への懸念があるでしょう。
一方で子どもが成人していても、やっと子どもの教育費を払い終えこれから老後資金を貯める人生計画も少なくありません。
役職定年による大幅な収入の減額リスクを鑑みると「定年までに老後資金を貯めよう」と先延ばしにする考え方が一番危険とも言えます。
公務員の役職定年制度は?
では公務員の役職定年制度はどうなっているのでしょうか。
公務員の役職定年は60歳です。公務員が役職定年を迎えると基本給・ボーナスが以前の70%まで減収するでしょう。一方で通勤手当・住宅手当は役職定年後も収入の減額対象にはなりません。
公務員の場合、そもそも定年制度が60歳定年から65歳定年へと伸びています。この65歳定年制度に伴い役職定年制度が採用されました。
役職定年を確認しよう
会社によって給与体系は違うため、まず「自分の会社に役職定年制度があるか」から確認しましょう。そのうえで下記項目の確認が不可欠です。
・自分は役職定年制度に該当する立場なのか
・役職定年制度に該当する手当はどれにあたるのか
・役職定年制度に該当する手当は毎月いくらもらっているか
・役職定年の後は、該当する手当がどのように変わっていくか
会社の就業規則も確認しておくと尚安全です。規模の大きな企業こそ役職定年制度を採用しているため、社内HP等で詳細を確認できることもあるでしょう。この他、総務や人事に確認しても問題はありません。
定年後の収入減②再雇用

定年退職後の再雇用も大幅な収入減が予想されるタイミングです。当然ですが定年退職の後に再雇用・再就職しない方は収入がなくなります。
「再雇用制度」とは、一度定年退職をした後で再び雇用契約を結ぶことです。定年退職後も現役時代と同じ会社で継続して働くことは、大きなメリットのひとつでしょう。
再雇用制度の注意点
再雇用制度の場合、一度退職して再び雇用契約を結ぶため現役時代と同じ契約内容ではありません。
再雇用での契約形態は会社によりさまざまに違いがありますが、嘱託社員、契約社員、パートタイム等もあるので契約内容の確認は不可欠です。この他、ボーナスがなくなったり、時給計算になる等の変化が起こり得ます。
一般的に定年退職後に再雇用された後の収入は約40%~60%に減額しているでしょう。現役時代が月収60万円だったとしたら、月収36万円~24万円まで減額することになります。
定年退職年齢は60歳が多い
国では定年退職年齢65歳制度を推奨しており、年金受給開始年齢も60歳から65歳へと引き上げられました。けれども現実的には300人以上の大規模な会社でも77%が60歳定年退職制度を採用しています。
ただ高齢者雇用安定法があるので、何らかの形で60歳以上も働き続けることはできるでしょう。実際に定年退職後も60歳以上の方々のうち90%が継続して働いています。
・人事院「令和2年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要」
再雇用制度を利用する目的の違い
定年後の再雇用制度による大幅な収入の減額は、働き続ける目的によっては困窮します。
張り合いのある老後、社会とのつながりを維持する、老後の健康を目的とするなら、定年後の収入減にも納得できるかもしれません。
再雇用による収入が趣味・娯楽等のゆとりを目的とするなら対応できるでしょう。一方で老後資金を貯めるために働く、生活費のために働くならば対策が必要です。
再雇用契約の内容を確認しよう
再雇用で収入が減額しても働く時間が短くなる等、プライベートな時間に余裕があるならまだ良いものの、そうはならない再雇用契約も少なくありません。
定年後の再雇用契約により、労働時間や責任の質は変わらずに収入だけが減ることがあるためです。
このような再雇用契約を会社側から突き付けられた場合、仕事を続けるモチベーションが保てる契約内容かを判断しなければなりません。
夫婦世帯の場合は、配偶者の収入も併せて検討します。
再雇用よりは定年延長
60歳以上も現役時代に働いていた企業で働き続ける制度には「定年延長」もあることはご存じでしょうか。定年延長の場合、定年退職年齢が延長されるため一度退職する必要はありません。
再契約に至らないため、定年後の再雇用よりも収入が減額されるリスクが少ないです。定年延長制度を採用している企業は高齢者にとって良心的と言えます。
高齢者雇用安定法により65歳まで働ける世の中になってはいますが、企業によって採用する制度が異なるため「65歳まで働いて老後資金を準備しよう」と言う考え方は危険です。
定年後の収入は再雇用制度・定年延長制度のどちらかによって待遇が大きく変わるため、事前に調べておくことをおすすめします。
定年後も働き続ける制度について、詳細は下記コラムをご参照ください。
・定年後の再雇用で給与が70%に減額?勤務延長制度との違い・再雇用6つの注意点とは?
定年後の収入減③年金受給開始
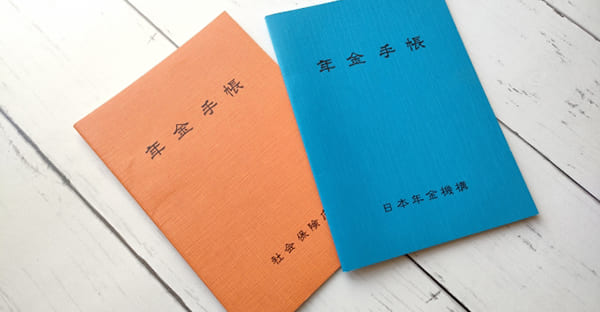
仕事を辞めて年金暮らしをスタートするタイミングも、定年後に年金を受給しながら働くとしても、現役時代と比べると定年後の収入は減額する方が一般的です。
年金収入は加入期間と現役時代にどれくらい稼いでいたのかによって違うため、人によって変化します。定年後にもらえる年金収入を把握しておくことが対策の第一歩です。
また定年後に働きながら年金受給を受ける場合、在職老齢年金制度により年金額の一部カット・全額カットの可能性もあります。詳しくは下記コラムをご参照ください。
・在職老齢年金とは?年金が減額する「50万円の壁」の計算、年金停止額早見表もご紹介!
年金生活での収入はどれくらい?
定年後に受け取る公的年金の金額は人によって違い、現役時代にどれ程年金を積み上げてきたかで決まります。
平均としては65歳以降の男性が受け取る公的年金は年間約185万円、月収約15万円~16万円です。
65歳以上の女性が受け取る公的年金は年間約107万円、月収約9万円が平均値となります。税金・健康保険料・介護保険料が支払われるため手取りはさらに少なくなるでしょう。
・働きながら年金を受給すると税金がかかる?確定申告が必要・不要なケース、申告方法は?
老後資金2000万円問題とは
生活費が年金収入だけでは賄えない場合、現役時代に蓄えていた老後資金を切り崩すことになり、かつて「老後資金2000万円問題」として話題にもなりました。「老後資金2000万円問題」は2019年6月に金融庁が発表した老後資金の報告書が発端です。
モデルケースとなる夫婦世帯が平均寿命まで生きた時「年金収入-支出」を計算すると-2000万円としたことから「老後資金2000万円問題」と騒がれました。
ただしあくまでもモデルケースなので、全ての人がこれにあたるとは限りません。冷静に自分達世帯の家計を見直し、相応の対応を進めることが重要です。
・「老後2000万円問題」とは?その発端や根拠は?「老後2000万円問題」が嘘とは?
年金生活開始までの対策
老後資金2000万円問題はコロナ渦で急速に広がり多くの人々を不安にさせましたが、急に2000万円蓄えろと言われても現実的ではありませんよね。
まずは年金生活を始める前に生活費をサイズダウンすることがポイントです。定年を迎えたからと急に暮らしぶりをサイズダウンしようとしても、なかなか簡単には進みません。
現役時代からゆとり費・娯楽費をサイズダウンして、老後費用に充てることから始めましょう。
年金収入・生活費を確認しよう
定年後に収入の減額に賢く対応するには、まず家計簿を付けて家計を見直すことが先決です。一度も家計簿を付けていない家庭であれば3ヵ月を目安に付けましょう。
家計の見直しは家計簿を付けていれば自然にできますが、不安があればファイナンシャルプランナー等の専門家に相談するのもおすすめです。
続いて年金収入を試算します。自宅に郵送される「ねんきん定期便」、ネット上では「公的年金シュミレーター」で試算できるでしょう。
ただし年金の試算は、現在の収入が60歳まで続いたことを前提としているため、役職定年等で大幅な収入の減額があった場合、年金収入も少なくなる可能性も考慮しなければなりません。
・厚生労働省「公的年金シュミレーターの使い方ホームページ」
定年後の収入減④配偶者の死亡

年金受給を開始すると生きている限りは受給できます。けれども年金は夫婦それぞれに支給されるものです。
夫婦の年金収入で生活を賄っていた場合に配偶者が亡くなると、1人分の年金額がまるまる停止するため、家計にも大きなダメージを受けます。
日本では女性の方が平均寿命が長いのですが、一般的には現役時代の収入から男性の方が年金額が高い夫婦世帯が多いです。その分、夫に先立たれた定年後の女性にとって深刻な問題になることも少なくありません。
そのため夫婦逆の立場・対等に収入を得ている夫婦もありますが、ここでは現代日本の50代・60代に多い夫婦世帯を一例として解説します。
遺族年金はどうなるの?
2024年現在50代・60代の夫婦世帯では、扶養期間が多い妻(女性)が多いため厚生年金が夫より少なくなります。
また国民年金から支給される「遺族基礎年金」は18歳未満の子どもがいた場合の養育費として支給されるため、高齢世帯では遺族基礎年金の支給はないでしょう。
夫の厚生年金から支給される「遺族厚生年金」のみが妻に支給されますが、今まで夫がもらっていた老齢厚生年金額がそのまま支給される訳ではありません。
「夫の老齢厚生年金×3/4-妻の老齢厚生年金=遺族厚生年金」ですので、この金額を踏まえて今後の家計をサイズダウンする必要があります。
遺族年金の具体例
例えば夫婦それぞれが下記のように年金受給を受けていたとします。夫の年金額は年間185万円(月15万4,200円)・妻の年金額は年間105万円(月8万7,500円)、合計額は年間290万円(月24万1,700円)です。
●夫
・老齢厚生年金…105万円
・老齢基礎年金…80万円
●妻
・老齢厚生年金…25万円
・老齢基礎年金…80万円
●合計…290万円
この世帯で夫に先立たれた場合18歳未満の子どもがいない限り、国民年金から支給される遺族基礎年金は支給されません。夫の老齢基礎年金80万円にあたる部分です。
一方、「遺族厚生年金」にあたる夫の老齢厚生年金105万円からは、105万円×3/4から妻の厚生年金額25万円が引かれた54万円が支給されます。
●妻
・遺族厚生年金…54万円
・老齢厚生年金…25万円
・老齢基礎年金…80万円
●合計…159万円
夫に先立たれた後、妻の年金収入は年間合計159万円です。夫婦世帯から単身世帯になったとは言え年間131万円が年金額の減額となります。
年間159万円の年金額であれば月額13万2,500円、持ち家があれば何とか暮らしていけるかもしれませんが、賃貸住宅等では年金収入だけでは生活費が賄えない可能性もあるでしょう。
ちなみに妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金の3/4を超えている場合は、夫に先立たれた後の遺族厚生年金を受け取ることができません。
まとめ:定年前後に収入が減るタイミングを知って対策を

「老後2000万円問題」等、現代の日本では老後の暮らしを不安視する声が数多く溢れています。40代・50代世代では「常に老後生活への不安が拭えない」との声も多くありました。
ただ不安そのものは直視することで軽減する側面もあります。年金収入や定年後に働き続けた場合の収入・雇用形態等を具体的な数字とともに算出することで、老後生活のサイズ感を実感するでしょう。
確かに定年後の収入が減額すると、現役時代のような暮らしぶりは難しいかもしれません。けれどもサイズダウンしたなりの小さな楽しみを、現役時代から見つけてみるのも不安が軽減する方法のひとつです。
・厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
・おひとりさま老後の生活費は毎月7,723円の赤字?楽しくできる9つの節約術を解説!
お電話でも受け付けております
















