
2025年は年金改正でどうなる?主婦年金廃止?在職老齢年金は?国民年金は期間延長?
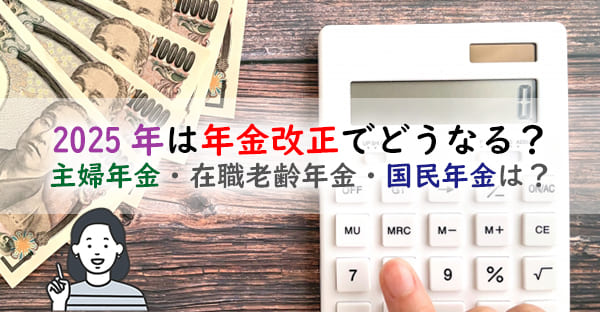
・2024年・2025年に年金改正で変わることは?
・第三号被保険者「主婦年金」が廃止されるって本当?
・働く人の年金「在職老齢年金」の収入上限が変わる?
・国民年金が65歳まで、5年間延長するって本当?
2024年の財政検証により、2025年の年金改正が検討されたことで、国民年金保険・年金制度に戦々恐々としている方は多いですよね。
今までの老後計画も「2025年以降の年金改正によっては、見直さなければならない」と考えている家族も多いでしょう。
本記事では2024年の財政検証によって決まった、2024年・2025年の年金改正の内容、今後の年金改正として検討されている内容を、分かりやすく解説しました。
老後の不安を解消するため、適切な老後資金計画にお役立てください。
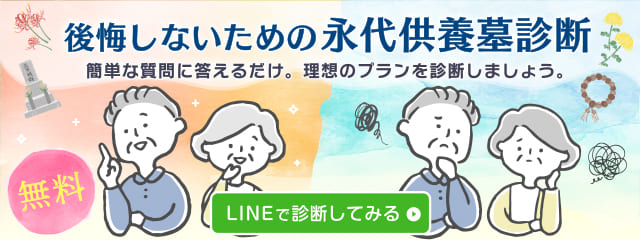
2025年年金改正案が検討された「財政検証」とは

◇「財政検証」とは、年金財政の定期的な健全性のチェックです
厚生労働省では「財政検証」について「公的年金財政の定期健康診断に当たるもの」と伝えています。
財政検証は継続基準、非継続基準、積立上限額に係る財政検証の3つの軸です。
財政検証ま毎年行われるのではなく5年ごととなり、前回は2019年(令和1年)に検証されました。
・厚生労働省「いっしょに検証!公的年金」~年金の仕組みと将来~
財政検証の目的は?
◇年金給付と国民年金保険料の負担とのバランスを調整することが目的です
定年を迎えた60歳~65歳以上の世帯では、物価が高くなる一方で年金が少なく、暮らしが成り立たないと嘆く世帯もあります。
一方で年金を納付している現役世代は、年金が高く負担が重くなっている上に、物価が高くなり生活費も上昇し、少子高齢化により将来的な年金受給にも不安を抱く世代です。
そのなかで財政検証の目的は、公的年金財政を定期的に見直して、年金給付と国民年金納付の負担、双方のバランスを維持し、将来世代にも安定した年金を提供することを目的としています。
2024年・2025年から年金改正で変わることは?
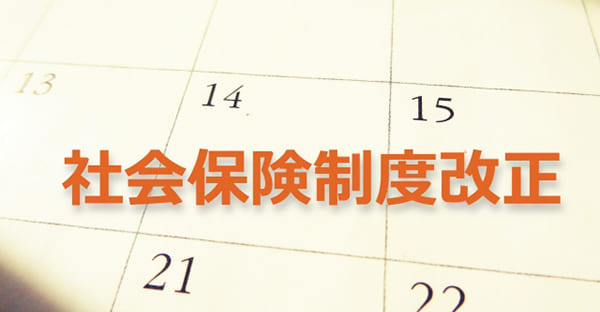
◇2024年財政検証により、大きく5つの年金改正が検討されました
2024年の財政検証で検討された5つの年金改正のなかでも、「主婦年金」とも呼ばれる第三号被保険者の改正案が大きいでしょう。
世間では「主婦年金は廃止される」と心配する声があちこちで聞こえますが、主婦年金と呼ばれる第三号被保険者が撤廃されることはありません。
…また懸念された遺族年金の制度改正も、今回は財政検証を見送りました。
ただし、第三号被保険者に適用する枠は狭くなり、扶養から外れて厚生年金加入義務が求めらえる人々も増える可能性があります。
下記より2024年・2025年以降の年金改正、及び検討された内容を詳しく解説しますので、どうぞ参考にしてください。
・厚生労働省「令和6年財政検証の基本的枠組み」
2024年10月年金改正:主婦年金
①2024年10月の年金改正でどう変わる?
◇第二号被保険の対象者は、月額8万8千円以上です
2024年10月以降、新しく厚生年金加入の対象となる人々は、下記4つ全てが含まれる人々となり、多くのパート労働者が対象となるでしょう。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8千円以上
・2か月を超える雇用見込み
・学生ではない
ここで今までの第二号被保険対象者枠には、企業規模による条件もありました。
2016年10月時点では501人以上に適用した企業規模条件は、2022年に101人以上と枠が狭くなっていましたが、2024年にはさらに中小企業まで適用されます。
②企業規模条件の変化
◇2024年10月より、従業員51人以上の企業にも適用します
従業員の数え方は「フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」です。
| <企業規模条件の変化> |
|
| [年度] | [企業規模] |
| (2016年10月~) | 従業員数501人以上に適用 |
| (2022年10月~) | 従業員数101人以上に適用 |
| (2024年10月~) | 従業員数51人以上に適用 |
この人数は「現在の厚生年金保険の適用対象者」となる、パートやアルバイト社員も含まれています。
そのため従業員60人ほどの企業で年収130万円以下の範囲内に抑えて働いていたパート・アルバイト社員の場合、このまま稼いでいると、2024年10月以降は社会保険の加入対象者になるでしょう。
・厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト「従業員数100人以下の事業主のみなさま」
そもそも「主婦年金」の条件は?

◇第二号破保険者の扶養に入る保険者です
「主婦年金」の正式名称は「第三号被保険者」で、配偶者など、第二号被保険者の扶養に入っている家族などを指します。
第三号被保険者の枠には年収制限があり、これを「130万円の壁」と言いました。
| <第三号被保険者とは> ●第二号被保険者に扶養されている |
|
| [条件] | ・20歳以上60歳未満 ・年収130万円未満 |
そのため一般的に社会保険に入っていないパートの人々や、専業主婦などが第三号被保険者に多いことが、「主婦年金」と呼ばれる所以です。
第三号被保険者は、配偶者など第二号被保険者の扶養に入るため、保険料を払わなくても国民年金に加入しているとみなされ、負担がありません。
では「第二号被保険者」の仕組みは?
◇社会保険に加入している会社員などです
「第二号被保険者」に適用する人々は、一般的に社会保険に加入している会社員などで、収入や契約条件により、パート社員や派遣社員なども含まれます。
第二号被保険者の支払いは保険料の一部、従事する会社との折半です。
| <第二号被保険の仕組み> |
|
| ・第二号被保険者 | …月の給与に対し9.15%を負担 |
| ・従事する会社 | …残りの9.15%を負担 |
このようなことから、昔から働く人々のなかには「主婦年金」と呼称される第三号被保険制度に対して「ずるい」「不平等だ」などの声も散見されました。
一方で子育て真っただ中の若い世帯では、第三号被保険者であるよう、「130万円の壁」の枠内で働く人々が多いのも現状です。
・2020年12月厚生労働省年金局「令和元年厚生年金保険・国民年金事業の概況」
第二号被保険者になると、保険料はどうなる?
◇年収106万円の場合、年間約15万6千円の負担が推測されます
第三号被保険者の状況にもよりますが、仮に年収106万円の収入があった第三号被保険者が、社会保険に加入して第二号被保険者になった場合、当然ですが保険料を毎年支払わなければなりません。
| <年収106万円で社会保険に加入した場合> |
|
| ・厚生年金 | …約8千円 |
| ・健康保険額 | …約5千円 |
| ・年間合計額 | …約15万6千円 |
それでも2024年の財政検証で第二号被保険者の枠が拡大された背景には、前述したように働く人の不平等感「公平性に欠けるのではないか?」との批判的意見があるでしょう。
さらに年収130万円以内に抑えることで、働き控えによる人手不足が生じていた問題を解消する目的もあります。
「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いは?
◇被扶養者として認めらえる年収条件が「106万円の壁」です
第三号被保険者として扶養内で働きたい場合、106万円の年収を超えると社会保険の加入義務が発生するため、健康保険料・厚生年金保険料の支払い義務が生じます。
そのため106万円を超えると給与から保険料が天引きされることになり、給与明細上の収入は上がっても、手取り金額が下がる可能性があるのです。
けれども年収130万円以上の年収になると、全ての人に社会保険への加入義務が生じて、扶養から外れることになります。
ただし「106万円の壁」には、残業手当やボーナス、通勤手当などは該当しません。
2025年以降に予想される年金改正は?

◇企業規模の撤廃や、月額賃金要件の減額も検討されました
2024年10月時点では施行されないものの、2024年の財政検証では、さらに予想される第二被保険者適用枠の拡大枠の年金改正が検討されています。
2025年以降も、緩やかに年金改正が進むことが予想されるため、先々の改正内容も見据えた対応、働き方を検討する必要があるでしょう。
下記より、2025年以降に予想される年金改正案について、簡単に解説していきます。
①企業規模の撤廃
◇51人以下の企業に従事していても第二号被保険者適用の可能性
2016年10月以降、企業規模501人→101人→51人と、ゆっくりと進めてきた企業規模条件の条件ですが、今後は撤廃する方針が固められたことが予想されます。
この企業規模条件の撤廃は、来年の通常国会に関連法案を提出すると発表がありました。
そのため今後は企業規模に関係なく、週20時間以上・月収8万8千円以上の人は、強制的に第二号被保険者に適用されるでしょう。
月額賃金要件の減額
◇月額賃金の条件が5万5千円へと減額する可能性
さらに2025年以降の年金改正では「月額賃金8万8千円まで」の条件から、「月額賃金5万5千円まで」へと、減額する可能性も出てきました。
今まで配偶者の扶養に入り第三号被保険者であるためには、働いても年収106万円の枠内で働く「106万円の壁」がありましたよね。
では2025年以降に月額賃金の減額が決まった場合はどうなるでしょうか?
月額賃金が約5万5千円×12か月の計算になるので、「70万円の壁」が生じるでしょう。
週の所定労働要件の撤廃
2024年・2025年の年金改正:国民年金の延長

◇国民年金の加入期間が「40年→45年」に延長されます
そのため国民年金額は年間約20万円ですから、5年間延長されることで、約20万円×5万円の計算により、1人あたり約100万円の負担が増えるかもしれません。
そもそも公的年金の仕組みは?
◇公的年金は「国民年金+厚生年金」の二本立てです
現在は60歳からの選択もできますが、受給開始年齢65歳で受け取る年金の内訳は「老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金(厚生年金)」の二本立てです。
| <国民年金・厚生年金とは> |
|
| ①国民年金 | ・20歳~60歳未満までの40年間加入義務 |
| ②厚生年金 | ・会社員・パート・公務員の人々が入る ・国民年金が含まれる ・任意で60歳~70歳未満まで加入 |
このように国民年金が含まれているため、厚生年金を支払うことで国民年金・厚生年金の両方を受け取ることができます。
2024年、国民年金の5年間延長とは?

◇国民年金加入期間の5年延長を検討しています
具体的には、現行20歳~60歳未満までの国民年金加入期間が、20歳~65歳未満までに延長される改正案で、5年間の延長で約100万円の負担が増える人々が出てきます。
ただし国庫負担の影響で、過去2回検討され、2回見送られたことのある改正案です。
国民保険の延長で負担になる人々は?
◇厚生年金に加入していない人々にとっては負担増です
国民保険は前述したように、社員として厚生年金に加入している場合、国民年金も含まれるため、厚生年金に加入していない人々にとっては、60歳~65歳の保険料が負担になります。
具体的には、国民年金に加入している自営業者の人々の他、60歳未満で退職して60歳~65歳の時点で厚生年金に加入していない人々などです。
・自営業者
・60歳未満で定年退職
・専業主婦
この他、専業主婦の人々にとっても5年間の保険料が負担になるでしょう。
65歳未満の国民年金を払えない場合は、「国民年金保険料の免除申請」を検討します。
国民年金の延長がメリットになる人々
◇厚生年金に加入している人々にとってはメリットです
60歳~65歳の時点で社員として働き、厚生年金に加入している人々にとっては、保険料負担が生じないどころか、むしろ年金が増える形になるでしょう。
例えば、60歳の定年退職年齢で勤めていた会社と雇用延長契約をしていたり、再就職した人々、会社員ではなくとも、パートや派遣社員で働き、厚生年金に加入しながら働く人々にはメリットです。
・60歳で雇用延長
・60歳で再就職
・パート、派遣社員
厚生年金に加入しながら60歳以上も働く場合、厚生年金保険料率は現役世代同様に、個人9.15%、会社9.15%の負担となり変わりません。
そのため「むしろ年金が増える」ためメリットになります。
2024年年金改正:在職老齢年金の緩和
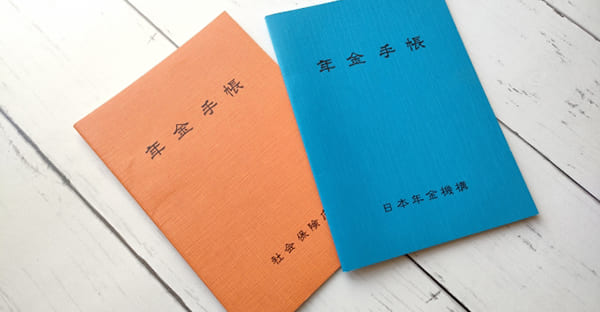
◇在職老齢年金の上限が月額50万円へと緩和されました
「在職老齢年金」とは65歳以降、働きながら年金をもらう場合、収入が一定額を超えると年金支給が一部停止・全額停止になる制度です。(自営業者は対象外)
年金支給が一部停止・全額停止することで、総収入額が減額しないために、一定収入より高くならないよう労働時間を抑える傾向があります。
今回の在職老齢年金の緩和は、労働意欲が削がれることを懸念した年金改正となりました。
在職老齢年金について、詳しくは下記コラムをご参照ください。
・在職老齢年金とは?年金が減額する「50万円の壁」働きながら年金をもらう人の税金は?
①具体的な内容は?
◇年金が減額される上限「月額48万円→50万円」への緩和です
2023年4月から施行されていた年金カット基準は、60歳~64歳の人々が月額収入48万円まで、65歳以上の月額収入が48万円まで、とされていました。
これが2024年4月時点の年金カット基準が、60歳~64歳で月額収入50万円まで、65歳以上で月額収入50万円までと緩和されており、今後も在職老齢年金の緩和・撤廃案の検討されています。
厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします 」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
2024年年金改正:マクロ経済スライド

◇「マクロ経済スライド」により年金額は抑えられています
2023年度・2024年度の年金額の改定率は、2024年に至っては2.7%の増額と、2年連続でバブル期並みのかなり高い増額率を見せています。
けれども2004年(平成16年)の年金制度改正で導入された、賃金や物価の変動率を考慮し、年金額の改定率を調整する制度により、年金の給付水準を抑えました。
マクロ経済スライドとは
◇年金給付額を調整する制度です
日本では2004年に導入された「マクロ経済スライド(マクロスライド)」とは、社会の経済状況や年金の被保険者数の変化、平均寿命の変化に対応し、年金給付額を調整する制度です。
マクロ経済スライド調整率により、現役世代の年金負担と年金受給者とのバランスを取り、年金上昇を調整する役目を果たします。
マクロ経済スライド調整率の算出方法は「年金被保険者の減少率×平均余命の伸び率」です。
年金被保険者の減少率は少子化の数値、平均余命の伸び率は高齢化の数値と言えます。
2024年年金の改定率2.7%の算出方法
◇賃金変動率にマクロ経済スライドで差し引いています
年金の改定率は、新しく年金受給を始める「新規裁定者」は賃金変動率、既に年金給付を受けている「既裁定者」は物価変動率を指標として改定されますが、賃金変動率よりも物価変動率が高い場合、賃金変動率よりも高くなりません。
2024年度は賃金変動率が+3.1%、物価変動率が+3.1%、マクロ経済スライド調整率が-0.4%でした。
| <年金改定率の指標> |
|
| ●2024年度の指標 | ・賃金変動率…+3.1% ・物価変動率…+3.2% ・マクロ経済スライド調整率…-0.4% |
| ①新規裁定者 | …賃金変動率+マクロ経済スライド調整率 (2024年)3.1%-0.4%=2.7% |
| ②既裁定者 | …物価変動率+マクロ経済スライド調整率 ※物価変動率が賃金変動率より高い場合、物価変動率に合わせる (2024年)3.1%-0.4%=2.7% |
このような事情から、2024年度は年金改定率が2.7%と大幅に増額していますが、マクロ経済スライドにより実質的には年金減額が続いているのが現状です。
2024年に公的年金はいくら減額した?
◇マクロ経済スライドにより、実質より-0.4%の減額をしています
つまりマクロ経済スライド調整率、2024年度は-0.4%分の実質的な減額が行われ、高齢少子化対策が行われました。
2023年(令和5年)度から2024年(令和6年)に掛けて、+2.7%の年金増額となったため、マクロ経済スライドにより減額された具体的な金額例は標準世帯では下記になります。
| <マクロ経済スライドの影響> |
|
| ●国民年金 (満額1人世帯) |
・2023年(令和5年) …66,250円/月額 ・2024年(令和6年) …68,000円/月額 [マクロ経済スライド] …-260円/月額 (年額-3,120円) |
| ●厚生年金 (標準的な夫婦2人世帯例) |
・2023年(令和5年) …224,482円/月額 ・2024年(令和6年) …230,483円/月額 [マクロ経済スライド] …-900円/月額 (年額-10,800円) |
以上はモデル世帯として老齢基礎年金を満額受け取り、老齢基礎年金を含む、標準的な年金額を受け取っている夫婦2人分の標準的な年金額として算出していますので、全員に当てはまる数字ではありません。
・日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
マクロ経済スライドによる調整期間は?
2024年年金改正:標準報酬月額の上限

◇厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げが検討されました
2024年現在、厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円ですが、今回の財政検証ではこの引き上げも検討されました。
「厚生年金保険法第20条第2項」によると、毎年3月31日の年度末に下記の状態である場合、上限の更なる等級追加が可能とされます。
・今後もその状態が継続する
2004年(平成16年)時点では、厚生年金の標準報酬月額の上限は62万円でしたが、2020年(令和2年)の9月から、上限は65万円に改定されています。
まとめ:2024年・2025年年金改正で主婦年金が縮小されます
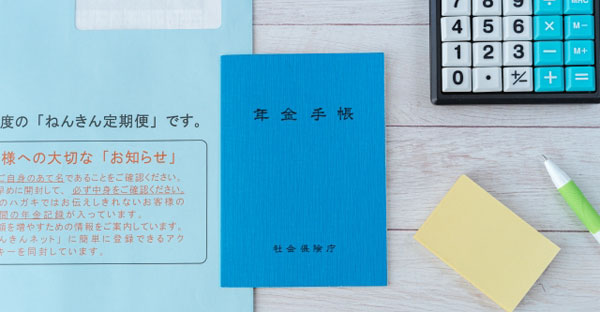
以上が2024年財政検証による年金改正の内容ですが、一般家庭に影響が大きい、最も大きな2024年・2025年以降の年金改正は、第三者被保険者「主婦年金」枠の縮小でしょう。
主婦層などの扶養枠内でのパート・アルバイト労働に対して、今後も更なる年金改正が進む予想が立っています。
扶養内の働き方については「106万円の壁」の前に、所得税の納税義務が生じる「103万円の壁」もありますよね。
2024年・2025年の年金改正は、社会保険に加入してより大きな稼ぎを計画するか、扶養内に収まる働き方を再検討していくか、将来的な人生設計の見直しが必要になるかもしれません。
お電話でも受け付けております

















