
生命保険の死亡保険金に掛かる相続税の非課税枠とは?所得税や贈与税が掛かるケースは?
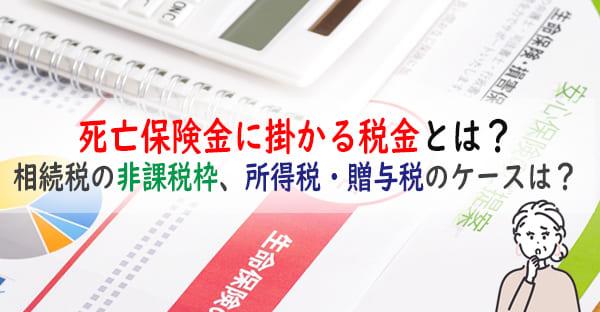
・死亡保険金は相続税が掛かる?
・死亡保険金の相続税「非課税枠」とは?
・死亡保険金は所得税や贈与税は掛かる?
生命保険の死亡保険金には相続税が掛かりますが、非課税枠があります。
また被保険者と契約した人、受け取り人によって、掛かる税金も変わるでしょう。
本記事を読むことで、生命保険の死亡保険金を受け取ると、相続税はどれくらい掛かるのか?
非課税枠や契約形態で変わる税金の種類、計算方法が分かります。

死亡保険金に相続税は掛かるの?
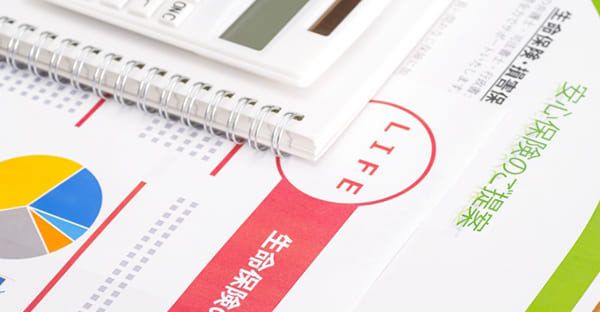
◇被保険者と契約者が同じ、受け取り人が相続人だった場合に、死亡保険金の相続税は掛かります
例えば被保険者である夫が生命保険を契約し、受け取り人が妻だった場合、夫が亡くなった時に死亡保険金を妻が受け取ると、相続税がかかるでしょう。
「保険金には税金が掛からない」との声もありますが、税金が掛からない保険金には条件があるためです。
| <税金(所得税)が掛からない保険金とは> | |
| [条件] | ①心身に損害が加わった ②突発的な事故 |
| [例] | ・入院 ・手術 ・放射線治療 ・がん診断 ・先進医療 ・就業不能 ・通院 ・疾病・災害療養 |
被保険者が、がん診断や突然の病気や怪我の療養により掛かったお金、休業を余儀なくされた生活の負担を補填する保険金などについて、所得税が課税されません。
死亡保険金に相続税が掛かる契約とは?

◇被保険者と契約者が同一人物、受け取り人が相続人の時に、相続税が掛かります
死亡保険金に相続税が掛かるのは、受け取り人が相続人であるためです。
また契約者が生命保険を契約した被保険者である場合に、相続税が発生します。
| <死亡保険金に相続税が掛かる契約とは> ●妻の死亡保険金を夫が受け取った場合 |
|
| [被保険者] | ・妻(夫) |
| [契約者] | ・妻(夫) |
| [受け取り人] | ・夫(妻) ※法定相続人 |
この契約形態が最も一般的ですが、被保険者と契約者、受け取り人の関係性によって掛かる税金の種類も、所得税・贈与税と変わります。
死亡保険金の相続税「非課税枠」とは
◇死亡保険金には相続税が掛かりますが、非課税枠があります
死亡保険金が相続税対策と言われるのは、相続税の「非課税枠」が理由です。
法定相続人の人数により、死亡保険金の非課税枠は変動します。
| <死亡保険金の相続税「非課税枠」> | |
| [非課税限度額] | ●法定相続人の人数×500万円=非課税限度額 |
| [例] | [被保険者] ・夫 [法定相続人] ・妻 ・子ども2人 [非課税限度額] ・3人(妻+子ども2人)×500万円=1,500万円 |
上記のケースで法定相続人3人が死亡保険金を受け取ったケースでは、死亡保険金に関して1,500万円まで非課税になる計算です。
ただし相続税は、相続財産全体に対して基礎控除額が適用されます。
こちらも合わせて計算しましょう。
相続税の基礎控除額とは
◇相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」です
生命保険の死亡保険に対する相続税にも非課税枠がありますが、そもそも相続税全体にも基礎控除額が差し引かれます。
ただし相続財産全体ですので、不動産財産なども含まれる点は注意をしてください。
| <相続税の基礎控除額> ●妻は1億6,000万円まで非課税対象 |
|
| [計算式] | ●3,000万円+600万円×法定相続人=基礎控除額 |
| [非課税財産] | ・葬儀費用 ・債務(マイナスの遺産) ・祭祀財産(お墓など) |
| [例] | [被保険者] ・夫 [法定相続人] ・妻 ・子ども2人 [基礎控除額] ・3,000万円+600万円×3人(妻+子ども2人) =4,800万円 |
このように相続税には全体的にも基礎控除額が適用されます。
それぞれのパターンがあるので一概には言えませんが、所得税・贈与税を支払う生命保険の契約形態と比較しても、相続税の非課税枠を利用した生命保険の契約が適切と言えます。
・国税庁「相続税」
死亡保険金は相続税以外の税金が掛かるの?
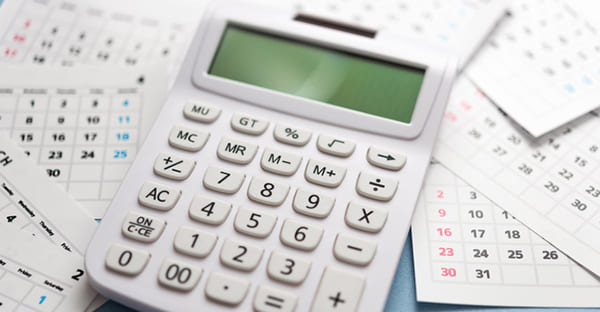
◇被保険者・契約者・受け取り人の関係性によって、税金の種類が変わるでしょう
一般的な被保険者と契約者が同じ契約形態では、受け取り人が法定相続人である限り相続税が掛かります。
ただ被保険者と契約者が違う場合に違うのは、支払う税金の種類です。
ここでは妻が亡くなり、夫が保険金を受け取ったとして、生命保険の契約形態と、支払う税金の種類の違いを解説します。
| <契約形態で違う税金の種類> | |
| [税金の種類] | [例] |
| ●相続税 (被保険者と契約者が同じ) |
・被保険者…妻 ・契約者…妻 ・受け取り人…夫 (法定相続人) |
| ●所得税 (契約者と受け取り人が同じ) |
・被保険者…妻 ・契約者…夫 ・受け取り人…夫 (法定相続人) |
| ●贈与税 (全て違う) |
・被保険者…妻 ・契約者…夫 ・受け取り人…子ども (法定相続人) |
つまり契約者が死亡保険金を受け取ると考えます。
例えば生命保険の契約者が夫である場合、被保険者が妻であっても、契約者が取得した死亡保険金として税金が課せられるため、所得税を申告する流れです。
贈与税では、契約者である夫が取得した死亡保険金を、子どもが贈与されていると考えます。
死亡保険金に所得税が掛かるケース
◇生命保険の契約者と受け取り人が同一人物の場合、申告する税金は所得税です
一般的な保険金は、お金を受け取った日をもって申告しますが、死亡保険金に関しては、被保険者が亡くなった日をもって申告します。
死亡保険金の受け取り方は、一時金・年金形式の2種類があり、それぞれ申告の項目や計算方法が変わるため、注意をしてください。
| <死亡保険金の所得税> | |
| [受け取り方] | [項目] |
| ・一時金 | ・一時所得 |
| ・年金形式(分割) | ・雑所得 |
所得税なので、その年の所得金額を申告して税金を納めるためです。
夫が妻の生命保険を契約し、妻の死亡後に死亡保険金を受け取っています。
そのため夫は妻の生前、毎月の保険料も支払っていることになり、この支払い分は差し引きされる計算式です。
| <受け取り方で違う、所得税の計算式> | |
| [一時金(一括)で受け取り] | |
| ●死亡保険金-払った保険料-特別控除額(50万円)×1/2 =一時所得(課税対象) |
|
| [年金形式(分割)して受け取り] | |
| ●その年の年金額-払った保険料 =雑所得(課税対象) |
|
例えば死亡保険金が3,000万円、死亡保険金の受け取りまで500万円支払っていたとします。
一時金の計算式に基づくと「3,000万円-500万円-50万円(特別控除額)×1/2=1,225万円」となり、1,225万円が、所得税の課税対象額です。
・国税庁「No.1750死亡保険金を受け取ったとき」
・【不動産の相続】故人の代理で行う「準確定申告」。手続きの進め方や必要書類、期限まで
死亡保険金に贈与税が掛かるケース
◇贈与税が掛かるケースは、受け取り人・被保険者・契約者の全員が違う場合です
例えば夫が契約した生命保険の被保険者が妻だったとします。
この場合、生命保険の取得者は夫ですので、受け取り人が違う場合、夫から受け取り人への死亡保険金の贈与です。
贈与税は年間110万円の基礎控除があるため、死亡保険金から110万円を差し引いた額に対して課せられます。
| <死亡保険金の贈与税> | |
| [課税対象額] | |
| ●死亡保険金-基礎控除額(110万円)=贈与税の課税対象 (年間贈与額) |
|
贈与税の税率、控除額は受け取った金額により変動します。
贈与を受けた相手の契約者が父や母、祖父母など直系尊属だった場合、さらに受け取り人が20歳以上だった場合、「特別贈与」として特例税率が適用する仕組みです。
ここでは死亡保険金が3,000万円、父親が契約者で、直系尊属である子どもが保険金を受け取ったとして具体例を計算します。
| <贈与税の計算> ●死亡保険金3,000万円、父親が契約者 |
|
| [基礎控除] | ・3,000万円-110万円=2,890万円 |
| [贈与税45%] | ・2,890万円×45%=1,300万5千円 |
| [控除額] | ・1,300万円-265万円=1,035万5千円 |
特別贈与の枠で1,500万円~3,000万円までの特別贈与税の税率は45%、控除額が265万円でした。
3,000万円~4,500万円であれば特別贈与枠の税率は50%、控除額は415万円と、受け取る死亡保険金の金額で贈与額も変化します。
いずれにしても贈与税は税率が高いので、相続税の非課税枠を利用するなど、他の方法を検討すると良いでしょう。
・【大阪で終活】相続税対策に役立つ3種類の生前贈与とは。2022年の非課税枠は延長?
・国税庁「No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」
まとめ:死亡保険金は相続税の対象ですが非課税枠があります
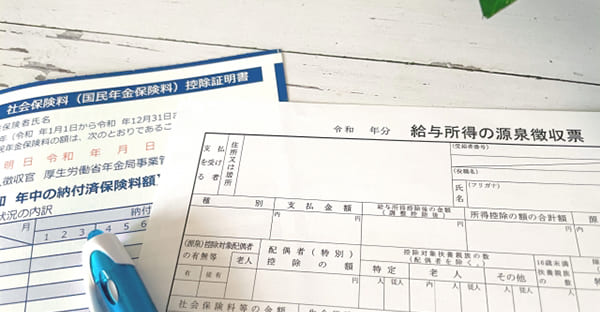
死亡保険金は確かに相続税の課税対象ですが、法定相続人1人に対して500万円の非課税枠が設けられる点がポイントです。
さらに配偶者(妻・夫)の相続であれば、1億6,000万円まで相続税が掛かりません。
一方、法定相続人ではない第三者を生命保険の受け取り人とした場合、課せられる税金は相続税額の2割加算分を収めます。
生命保険のなかには受け取り人が「第二親等以内の親族」と定められるものもあるでしょう。
そこで長男の嫁を死亡保険金の受け取り人にしたい時、長男の嫁を養子縁組するなどの対策も見受けます。
お電話でも受け付けております
















