
【家族が亡くなったら】死亡診断書を受け取ったら行う3つの手続きを解説|永代供養ナビ
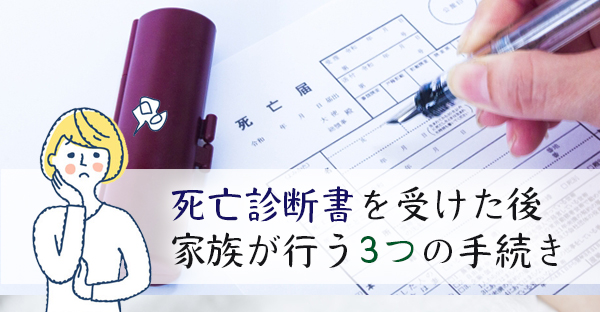
家族はご臨終の確認後、死亡診断書を医師よりもらいます。
ショックや哀しみのなかでも通夜や葬儀の準備など、こなす事柄が短時間にどんどん迫ってきますよね。
この間にも、病院で受け取った死亡診断書から始まる、さまざまな行政手続きが必要です。
通夜や葬儀、納骨式に合わせて許可を得るため、行政手続きと葬儀の準備は並行して行わなければなりません。
今回は、家族が亡くなったら医師からいただく死亡診断書から始まる、一連の葬送で必要な3つの行政手続きを時系列でお伝えします。
【家族が亡くなったら】死亡診断書をいただいたら行う3つの手続きを解説|永代供養ナビ

死亡診断書を受け取る
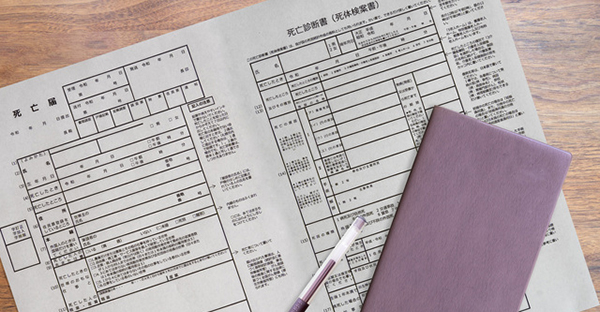
家族が亡くなったら、ご臨終を確認した医師から死亡診断書を受け取りますが、一般的に人が危篤状態になった時、下記3つの場所でご臨終を迎えます。
(1)病院でご臨終を迎えた場合
(2)自宅でご臨終を迎えた場合
(3)突然亡くなった場合
ご臨終を確認した医師が死亡診断書を書いて渡してくれるので、ご家族が用意をする必要はありません。
死亡診断書の左側が「死亡届」になっているので、このまま死亡当日~翌日頃には、市区町村役所の戸籍係に提出します。
(1)病院でご臨終を迎えた場合
病院で家族が亡くなったら、ご臨終を確認した医師が死亡診断書を書いてくれます。
その後、病院の霊安室へご遺体が移送されるので、霊安室へいる数時間~24時間ほどで、ご遺体を搬送してくれる葬儀社と、ご自宅などの搬送先(ご遺体の安置場所)を決めてください。
(2)自宅でご臨終を迎えた場合
ご自宅で家族が亡くなったら、かかりつけ医(訪問医)がいれば、すぐにかかりつけ医を呼んでください。
ご臨終後でも数時間以内であれば、かかりつけ医の判断により死亡診断書を書いてくれます。
(3)突然亡くなった場合
突然、自宅で家族が亡くなった場合、警察署(110番)に連絡をすることになりますが、まだ息があれば救急車(119番)を呼んでください。
病院でご臨終が確認されると死亡診断書を渡してもらえますが、警察署に連絡をすると、ご遺体は警察署へ搬送され「死体検案書」を渡されることになります。
警察で死体検案書が提出される事例の多くは、下記3つのケースです。
・事故死
・変死
・自死
この「死体検案書」が「死亡診断書」の代わりにはなりますが、状況によっては検視(検死)が長引き、ご遺体の受け取りが延びしまう可能性もあるためです。
・【家族が亡くなったら】家族が危篤になった時、慌てず行うべき5つのこと|永代供養ナビ
死体火葬許可証を受け取る
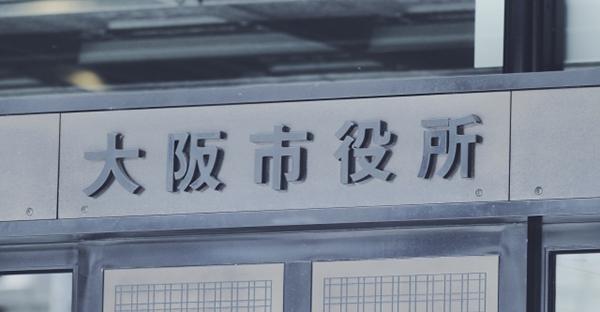
死亡届(死亡診断書)を提出すると、窓口で「死体火葬許可証」を出してくれます。
死亡届は、下記3つの地域、いずれかの市区町村役所の「戸籍係」窓口に提出してください。
●下記3つの市区町村役所の「戸籍係」に提出
(1)亡くなった人の本籍地の役所
(2)届出人の住所がある地域の役所
(3)亡くなった場所の役所
死亡届には故人の本籍住所が必要ですが、しばしばこの本籍住所が不明で家族が慌てる事例があります。
本籍住所は現在住んでいる住所がある市区町村役所で、本籍地が記載された住民票を出して確認(戸籍除票後の場合は「住民票除票」の写し)すると良いでしょう。
必要な書類
死亡届(死亡診断書)の提出に必要になる書類は、下記2点です。
・届出人の印鑑
・故人の健康保険証
死亡届(死亡診断書)はお正月も含めて一年365日、24時間受け付けてくれます。
死亡届(死亡診断書)の提出期限
死亡届(死亡診断書)は、死亡して七日間以内の提出です。
けれども死亡届(死亡診断書)を提出して「死体火葬許可証」を交付されないと、火葬場でご遺体を火葬できません。
そのため現実的には家族が亡くなったら、ご臨終の当日~翌日には死亡届を提出している場合がほとんどです。
死亡届(死亡診断書)は誰が提出するの?
死亡届(死亡診断書)はご遺族が提出するのがベストですが、ご遺族はご家族が亡くなったら、通夜や葬儀の準備で忙しくなるでしょう。
法的にご遺族以外の人々でも代理で死亡届(死亡診断書)の提出は可能です。
知人や友人などにお願いする他、今では葬儀社スタッフが代行してくれるケースが多いでしょう。
埋葬許可証を受け取る

死亡届(死亡診断書)を市区町村役所の戸籍係へ提出し、死体火葬許可証を交付されると、火葬場でご遺体の火葬ができます。
この埋葬許可証によりお墓に納骨できるため、大切に保管してください。
一般的には、火葬されたご遺骨の骨壺の上に置かれます。
その上に布で包んでくださるので、納骨時まで無くさないよう、骨壺とともに保管すると良いでしょう。
分骨は火葬場で行う
「分骨」とは、ご遺骨を分けることを差します。
一部分は郷里の先祖代々墓、残りは自宅近くに新しく建てた個人墓に建てる、…などのケースです。
この分骨証明書がないと、お墓にご遺骨を埋葬できないので、火葬場で分骨して証明書をもらってください。
(※)「分骨証明書」は火葬場によって名称が違う場合があります。
最後に
今回は、家族が亡くなったらご臨終を確認した医師よりいただく「死亡診断書」から始まる、3つの行政手続きについてお伝えしました。
最後に解説した「埋葬許可証」ですが、お墓の納骨時に必要になるため、近年増えた手元供養を選んだ家では、ついついないがしろにしがちです。
手元供養はご遺骨を粉骨して小さくまとめ、ご自宅や身近に置いて供養をする葬送スタイルなので、確かに埋葬許可証は直接的に必要がないかもしれません。
けれども後々、主に供養をしている配偶者が亡くなった場合など、いつしかお墓に埋葬される必要が出てくるでしょう。
このような時に紛失していると家族が困るので、ご遺骨とともに大切に保管をしてください。
・墓じまいで取り出した遺骨を手元供養する家が増えた?複数の遺骨を収蔵する「お墓」型仏壇
まとめ
死亡診断書の後、納骨までの3つの手続き
●死亡診断書を受け取る
・医師からもらう
・死亡診断書と死亡届は一体
●死体火葬許可証を受け取る
・死亡届を役所に提出
・死体火葬許可証の交付
●埋葬許可証を受け取る
・火葬場で受け取る
・分骨時は分骨証明書を受け取る
お電話でも受け付けております















