
【お墓Q&A】家の庭にお墓を建てることはできる?遺髪を埋葬するならOKってホント?
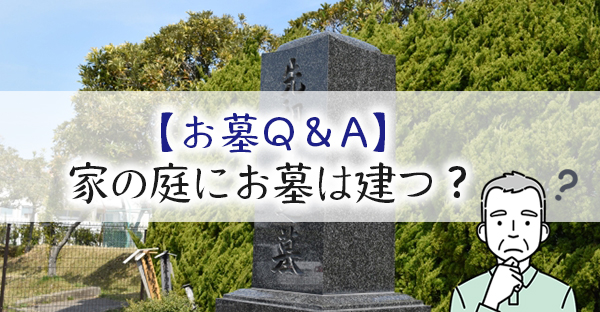
遺言書などで故人が、家の庭にお墓を建てることを望むケースがあります。
それが父や母だった場合など、残された遺族は「何とか故人の遺志を叶えたい」と相談に来ますが、家の庭にお墓を建てることは、現実的ではありません。
ただ法的なお墓でなければ、家の庭に建てることも可能です。
今回は、両親が生前に希望していた家の庭にお墓を建てる遺志を実現した、事例をお伝えします。
【お墓Q&A】家の庭にお墓を建てることはできる?遺髪を埋葬するならOKってホント?
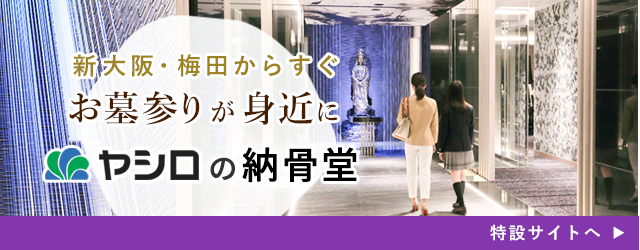
両親の「家の庭にお墓を建てる」遺志

今回「家の庭にお墓を建てることはできますか?」との相談は、30代・40代の3人兄弟です。
38歳の長女、42歳の次男はそれぞれ結婚をして家を出ており、48歳の長男も結婚していましたが、両親と同居していました。
長い闘病生活の後、母親が亡くなってから3ヶ月後、元気だった父親も亡くなったとのことです。
●両親が生前に兄弟によく話していた事柄が、「自分達が亡くなったら、家の庭にお墓を建ててくれないか」と言うものでした。
父親が若い頃に自分達で建てた家で、とても思い入れがあること、家の庭にお墓を建てることで、子どもや孫の様子を見ながら、死後も過ごせると考えていたようです。
法的に「家の庭にお墓を建てる」ことはできない
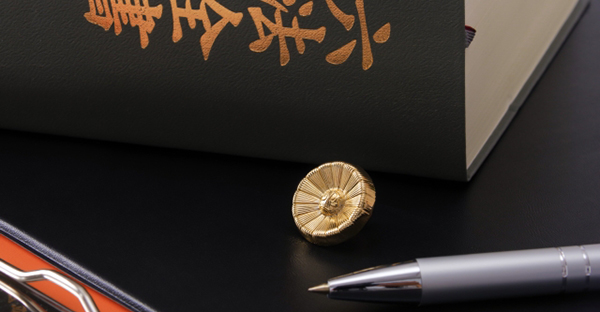
結論から言えば、法的には「家の庭にお墓を建てる」ことはできません。
確かに戦後間もなくの頃までは、所有する家の裏山にお墓を建てることもあり、そのようなお墓が現代も残っている家はあるでしょう。
けれども現代の日本では、墓埋法第2条及び4条により、個人が所有する土地にお墓を建てることはできないためです。
お墓を建てることや埋葬に関する法律は、「墓埋法」で定められています。
…ではまず、個人所有の土地にお墓を建てることができないとする、第4条を見てみましょう。
●第4条
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
「墓地以外の区域」とありますが、どのようにして墓地として認められるのでしょうか。
都道府県知事に許可を得ることで、墓地として扱われ、遺骨を埋葬できます。
これは墓埋法第2条、第5項にて明記されています。
●第2条、第5項
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
…このような墓埋法の法律より、沖縄県や山間僻地において一部例外はあるものの、現代の日本では家の庭にお墓を建てることができません。
「お墓」は建てることができないが…
ただここで注意したいポイントが、「何をもってお墓とするのか?」です。
法律上では「墳墓(ふんぼ)」と言われるお墓は、死体や遺骨が埋葬・埋蔵された施設を差し、同じく墓埋法の第2条、4項で明記されています。
<墓埋法第2条、4項>
●第2条、第4項
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
つまり法律上で「墳墓」とされるお墓の定義は、故人の遺体や遺骨が埋葬・埋蔵された施設を差す訳で、他のものであれば、そもそも「お墓」とされない訳です。
遺体や遺骨が埋葬・埋葬されていないのであれば、それは法的に墳墓(お墓)ではないので、家の庭に「お墓」と呼ばれるものを建てても問題はありません。
※以上「昭和二十三年、法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律」より
慰霊碑を置く選択

遺体や遺骨が埋葬されていないお墓を建てるとは、一般的には「慰霊碑」や「石碑」を建てることになるでしょう。
●そこで今回の相談者は、両親の遺髪を埋葬した石碑をお墓として建てることにしました。
例え遺体や遺骨が埋葬されていなくても、家族がそれを「お墓」と呼ぶことは、何も法律に触りません。
また石碑だからと言って「○○の墓」と彫刻してはならない、…と言う法律もないため、今回の事例では「○○家の墓」と彫刻したお墓を建てることになりました。
※お墓を建てる時の費用に関しては、下記に詳しいです。
・【大阪の終活】夫婦で入るお墓「夫婦墓」の費用相場☆継承者がいなくても建墓はできる?
慰霊碑にも開眼供養
法律上はお墓ではないのですが、お墓を建てるにあたり開眼供養も行います。
実家にはお仏壇も新調したため、お仏壇とお墓の両方を開眼供養してもらいました。
菩提寺がないため、遺骨の埋葬を決めた霊園に相談したところ、出張してくれる僧侶派遣サービスを紹介してくれました。
●今回の開眼供養は料金が明瞭になっており、3万円/1回の読経供養です。
→お仏壇の開眼供養+お墓(慰霊碑)の開眼供養で、6万円を包みました。
ちなみに料金は明瞭に提示されたものの、やはり供養行事と言うことで、白い封筒にお布施として包んでお渡ししています。
またお墓(慰霊碑)を建てるにあたり建墓費用は175万円、同居していた長男家族が100万円、次男家族が40万円、末っ子の長女が35万円を出しました。
今回の開眼供養の費用はそれぞれ2万円ずつ、均等に出しています。
※お墓を建てる時の開眼供養の流れや手順は下記に詳しいです。
・【大阪でお墓を建てる】施主が進める開眼供養の準備と流れ
夫婦の遺骨は自然葬に

そこでご夫婦の遺骨は霊園の自然葬を契約し、埋葬しました。
●遺骨を土に埋葬する葬送で、時間とともに土に還元されます。
自然葬のなかでも個別の区画に埋葬されるタイプを選び、夫婦の遺骨が隣り合わせになるようにした購入し、25万円/1人だったため、夫婦で50万円の予算です。
今回兄弟が選んだ自然葬では、埋葬後も埋葬区画の脇にある石碑に両親の名前が彫刻されるものでした。
石碑に対しても手を合わせますが、個別埋葬で埋葬された区画がハッキリとしているので、兄弟はそちらに向かって手を合わせています。
また、永代供養として合同供養法要が毎月行われるため、兄弟は両親の供養に数カ月に一回、参加するようになりました。
(合同供養法要なので基本的には無料ですが、気持ちとして数千円を包む日もあるそうです。)
※自然葬や樹木葬に関しては、下記で詳しく説明しています。
・【樹木葬の選び方】自然(土)に還るシンボルツリー型樹木葬|仕組みで選ぶ6つのポイント
最後に
今回は両親の遺志を反映して、家の庭にお墓を建てる体験談をお伝えしました。
両親が家の庭にお墓を建てることを希望した意図は、思い出深い家に思い入れがあったこと、そして愛する子どもや孫と、亡き後も一緒に暮らしたいとの想いからでしょう。
これを汲んで兄弟は家の庭にお墓を建てることを決めました。
(実際には遺髪を埋葬した、慰霊碑ですが…。)
大人になってそれぞれに家族ができ、しばらく疎遠だった兄弟も、今回の出来事をきっかけに、距離が近くなったと言います。
そのため毎年お盆には欠かさず兄弟家族が集まり、両親のお仏壇の前でわいわいと行事を進めているそうです。
ちなみに、兄弟が家の庭にお墓を建てることが難しいと知った時、もうひとつ検討した方法が「手元供養」でした。
マンションなど庭のない家や、お墓を建てるほど予算のない家では、手元供養もひとつの方法かもしれません。
※手元供養に関しては、下記記事に詳しいです。
・大阪で増える手元供養、残りの遺骨はどうする?お墓を建てずに供養できる3つの選択肢とは
まとめ
慰霊碑や石塔なら家に建てることは自由!
・墓埋法で墓地以外に遺骨の埋葬は不可
・墓地は知事の許可が必要
・墳墓(お墓)は遺体や遺骨を埋葬/埋蔵する施設
・遺髪などの埋葬は可能
・慰霊碑や石塔をお墓と呼ぶのは自由
・慰霊碑や石塔に「墓」と彫刻するのは自由
お電話でも受け付けております















