
位牌なしで供養する方法とは?仏壇などを置かない人が増えている理由も紹介

「位牌の置き場所がないけど、置かなくてもいい?」
「位牌や仏壇なしで供養する方法ってないのかな?」
日本人のライフスタイルが変化したことにより、従来までの位牌や仏壇を用いた供養が難しいと感じる人も増えてきています。
この記事では、仏壇や位牌を置かない人が増えている理由、位牌なしで供養する方法を紹介しています。
この記事を読むことで、位牌を置くことにどのような意味があるのかを知り、位牌なしの供養という選択があることを知ることができます。
また、さまざまな事情により、既に所有している位牌を処分しなければならないこともあります。処分する際に、位牌を供養する方法や処分を後悔しないために注意するポイントもあわせて紹介しています。
位牌なしで供養する方法を検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
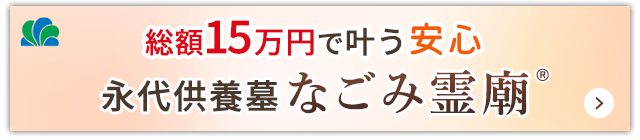
位牌なしでは供養した事にならない?

位牌とは、故人の戒名などが記された木札のことです。位牌には故人の魂が宿るとされ、従来の仏教の教えでも、必ず必要とされてきました。位牌なしでは故人の魂の行き場がなく、供養することができないと考えられているためです。
しかし、無宗教の場合、遺骨や写真を安置して故人を偲ぶ人もいます。死に対する考えは、人により異なるため、位牌が必要かどうかについても個々人の考え方によります。しきたりも大切ですが、より大切なことは、故人を偲ぶ気持ちです。
もとから位牌が不要な宗派もある
仏教の宗派によっては、もともと位牌を使用しない場合もあります。浄土真宗では、基本的に位牌を用いません。その理由は、浄土真宗の教えにあります。
浄土真宗では、「亡き人は阿弥陀仏の救いにより浄土に生まれ、仏さまになる」とされています。このため、位牌に故人の魂が宿るという考え方もされていません。
浄土真宗で故人を偲ぶ際は、「過去帳」を仏壇に置きます。「過去帳」は、先祖代々の法名や亡くなった日などを記した記録帳のようなものです。
仏壇・位牌なし供養を選ぶ人が増えている理由

近年、仏壇や位牌なしの供養を選ぶ人が少しずつ増えています。和室や仏間がない家が増えたことに伴い、仏壇のない家も増えたというのが理由として考えられます。それぞれの事情により、仏壇や位牌を置かない理由を3つ紹介します。
家族間のトラブルを避けるため
仏壇は夫の家系に置かれる事が多く、一家に一つという印象があります。ここで問題となるのは、妻側の家系に、妻以外の承継者がいなくなった場合です。
このときに、宗派が違うことが原因で、家族間のトラブルになることもあります。これを避けるために、あえて仏壇を置かない人もいます。
仏壇などを置けるスペースがない
仏壇などを置くには、それなりのスペースが必要です。空間が狭いマンションやアパートなどでは、仏壇を置くことが難しい場合もあるでしょう。
その他に考えられるのは、高齢で施設に入居する際などに、仏壇を置くスペースがなく管理できなくなってしまうパターンです。置きたいという気持ちがあっても、置くことができないという状況になってしまいます。
ライフスタイルに合わない
昔ながらの仏壇は、独特な重厚感と存在感があります。洋風化が進んだ日本の住宅とマッチせず、置き場所に悩むこともあるでしょう。
しかし、仏壇もそのニーズとともに変化し、供養の方法も多様化してきています。このあと、現代のライフスタイルにあった供養の方法をいくつか紹介します。
位牌なしで供養する方法

一昔前までは、遺骨はお墓に入れるものだと考えられてきました。しかし、仏教の教えでこのような考え方はありません。墓離れが進む昨今では、供養の方法も変化しています。故人をいつも身近に感じられ、生活習慣の変化に対応できる供養の方法を紹介します。
手元供養
「手元供養」とは、遺骨をお墓に入れず、自宅などに置いて供養することです。細かい形式がなく、故人を身近に感じることのできる供養といえます。
また、揃えなくてはならない仏具の決まりなどがなく、さまざまな形を選ぶことができます。従来の仏壇やお墓を購入するのに比べ、金銭的な負担が少なくて済むというのも利点の一つです。
手元供養は現代のライフスタイルの変化の中で生まれた、新しい供養のかたちです。そのため、周囲の人と話し合いながら決める必要があるでしょう。
ここでは、手元供養の方法の中から、「ミニ骨壷」と「遺骨ペンダント」を紹介します。
ミニ骨壺
火葬場で使用される骨壷は大きく、そのままでは場所を取ってしまいます。「ミニ骨壷」とは、自宅保管用に作られた小さな骨壷です。
写真などとあわせて、小さなスペースにも置くことができます。また、素材やデザインも幅広く、部屋のインテリアにあわせて置くことが可能です。
遺骨ペンダント
「遺骨ペンダント」は、外出の際に身につけることのできる手元供養の方法です。遺骨や遺灰の一部を納め、身につけることができます。
ペンダントの他にも、指輪やブレスレット、バックなどに付けられるキーホルダータイプもあります。
ミニ仏壇・供養台
「ミニ仏壇」はその名の通り小さな仏壇で、従来の仏壇を小型化したものからモダンなデザインのものまで、多種多様です。床置きや上置きタイプの他に、壁にかけるタイプも作られており、好みにあわせて選ぶことができます。
「供養台」は、手元供養をするための台で、写真やミニ骨壷、小型のモダン位牌などをあわせて飾ることができます。箱型ではないため堅苦しい雰囲気はなく、普段の生活に馴染むデザインで作られているのが特徴です。
既にある位牌を処分する際は?

知っての通り、位牌は簡単に処分できるものではありません。故人の魂が宿る、大切なものとされているためです。しかし、仏事の流れで処分する場合や「墓じまい」などの個人的な事情で処分する場合もあるでしょう。位牌の種類に応じた処分法を紹介します。
白木位牌の場合
白木位牌とは、主に葬儀のときに使用される、故人の戒名が記された仮の位牌です。四十九日の法要を終えるまで祭壇に祀られます。
四十九日の法要後に、故人の魂を抜き取る閉眼供養を行い、お焚き上げをしてもらいます。白木位牌から抜き取った魂は、本位牌に移されるというのが一般的な流れです。
本位牌の場合
本位牌を処分する理由はさまざまですが、「墓じまい」のタイミングで、位牌の処分をすることが増えています。そのほか、位牌が古くなり作り替えをするケースもあります。いずれの場合も、寺院や仏具店などに相談し、供養してもらいましょう。
供養の方法は、位牌を完全に処分するか否かによって異ります。位牌を完全に処分する場合は、白木位牌のときと同様に、閉眼供養とお焚き上げをしてもらいます。
また、位牌を処分せず、寺院や霊園に「永代供養」をしてもらうことも可能です。承継者がいない場合でも、位牌堂などに安置され、一定の期間供養してもらうことができます。期間は、依頼する寺院などで異なるため確認が必要です。
位牌を処分する際には、家族や親族に相談し、理解を得る必要があるでしょう。仏壇などとは違い、位牌は後々買い替えができるものではありません。トラブルにならないように、事前に確認することが大切です。
自分のライフスタイルに合った位牌なしの供養を選ぼう

手元供養は、遺骨を自宅に置いたり、その一部を身に着けたりすることで、故人を身近に感じられる供養の方法です。日々の暮らしの中で、故人に見守られているような安心感を感じることができます。
宗教的な考え方も大切ですが、常識にとらわれすぎずに、ライフスタイルにあった方法を選択することが大切です。故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、自分自身も負担に感じることのない位牌なしの供養を選びましょう。
お電話でも受け付けております















