
永代供養墓の歴史とは?起源や人気が高まっている理由についても紹介

「最近よく聞く永代供養とはどういうもの?」
「永代供養にはどういう歴史があるの?」
「なぜ、永代供養が増えてきているの?」
自分のお墓について考えている人の中には、永代供養がどういったものなのか、その歴史などを知りたいという人も多いのではないでしょうか。
また、遠方にあるなどの理由でお墓になかなかお参りに行けない、お墓の後継者がいないという問題を抱えている人もいるでしょう。
この記事では永代供養の歴史や、ネガティブなイメージがあったにもかかわらず永代供養を選択する人が増えている理由などについて紹介しています。
この記事を読み、永代供養の歴史やどのようなものなのかを知ることで、永代供養を選択される理由がわかり、現代社会のニーズに合っていることを理解できるでしょう。
永代供養を検討している方、興味がある方はぜひこの記事をチェックしてみてください。
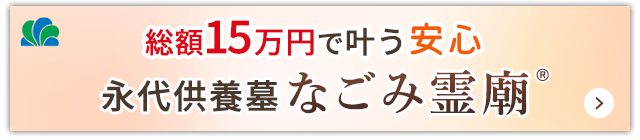
永代供養とは?

永代供養(えいたいくよう)とは、霊園や寺院が遺骨の管理や法要を行ってくれる埋葬方法のことです。元々は永代供養は跡継ぎがいない、身寄りがないという人への供養として利用されてきました。
しかしながら、昨今では「管理をしなくていい」「墓石などを買わなくていい」というメリットから、「子どもに手間をかけさせたくない」「お墓を建てるためのお金を遺してあげたい」というような理由で、永代供養を選ぶ人も増えています。
永代供養の起源
永代供養墓の歴史

先程も述べたように、永代供養の原型となる仕組みは江戸時代頃には存在していましたが、檀家から外れるとお墓が撤去されるなど、現在の永代供養とは似ても似つかないものでした。
ここでは、現在の永代供養がどのようにして定着していくようになったのか説明していきます。
1985年に「久遠墓」が登場する
少子化問題で注目を集める
わが国では1997年に子どもの数が高齢者人口よりも少なくなり、いわゆる少子化問題の始まりとなりました。子どもの数が減少するということは、同時にお墓を管理してくれる人も減少するということです。
一人っ子の家庭が増え、お墓をどう維持していくのかなどの問題がある中、お墓の管理をする子孫がいなくなっても寺院などで供養してもらえる永代供養が注目を集めました。
出典|参照:第1部 少子社会の到来とその影響|内閣府
当時はまだネガティブなイメージが主流
しかしながら、久遠墓などの永代供養墓が始まった当時は、永代供養墓にはネガティブなイメージを持つ人が多くいました。
これまでの「先祖代々のお墓を維持していく」という意識が強く、永代供養墓は身内や後継者がいないなど、やむを得ない理由を持つ人が利用するお墓だというイメージが強かったためです。
現代的な永代供養墓が始まったばかりで制度などが安定せず、トラブルが起きることも多かったことがその原因の1つです。
1999年にお墓に関する法律が改正される
永代供養が広がるきっかけになったのが、墓地、埋葬等に関する法律の改正です。
まず、お墓から遺骨を取り出して別のところへ埋葬する改葬は、すぐにできるわけではありません。亡くなった人の氏名や本籍、改葬の理由などを記載した申請書を市町村長に提出して許可を得なければなりません。
これまで、改葬には、現在の手続きよりも様々な手続きが必要でした。改正後は大きく簡略化されて改葬しやすくなったため、後継者や身内がおらず、お墓の維持ができないという場合でも永代供養墓に改葬できるという選択肢が増えました。
2000年頃から本格的に永代供養が広まる
永代供養の人気が高まっている5つの理由
1:安心して利用できる場所が増えたから
2:外観がきれいなものが増えたから
普及当時はお墓の外観がだいたい同じで、中には無縁塔のようなものさえありました。
しかし、サービスを提供する寺院が増えたことで清掃が行き渡り、さらに洋型の墓石にできたり、墓標や塔婆が建てることも可能になったりするなど希望に合わせた外観にもできるようになっています。
3:次世代に手間をかけさせないで済むから
少子化や核家族化に伴い、これまでのように頻繁にお墓参りができない、お墓を継ぐ後継者がいない、お墓を建てるのにお金をかけたくないなど、一般的なお墓を持つという選択をしない人も増えてきています。
永代供養にしておけば、しっかりと遺骨の管理や供養を寺院や霊園がしてくれるため、次世代に手間をかけさせることはありません。
4:一般的なお墓に比べかかる費用が少ないから
お電話でも受け付けております


















