
お墓の生前購入で相続税や贈与税はどうなる?相続後の相続税との差額は?葬儀や戒名は?
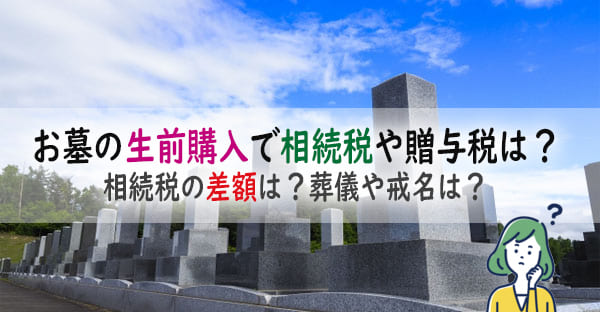
・お墓の生前購入で相続税は掛かるの?
・お墓の生前購入に贈与税はかかるの?
・相続後のお墓購入と比べて、相続税の差額は?
・葬儀費用や戒名料に相続税は掛かるの?
継承者を必要としない永代供養墓の登場により、生きているうちにお墓を購入する生前墓の契約が増えました。
お墓の生前購入により相続税が掛からないことも、生前墓が注目される理由です。
またお墓の生前購入で相続税は掛からないものの、お墓に彫刻する戒名料の相続税はどうなるのかも、気に掛かりますよね。
本記事を読むことで、お墓の生前購入による相続税や贈与税の扱い、それに伴う戒名料などについても、税金の扱いが分かります。
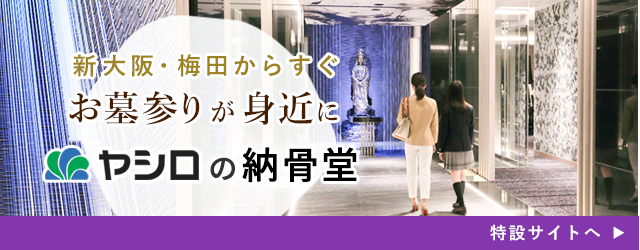
お墓に相続税が掛からないとは?

◇お墓に相続税が掛からない理由は、お墓が祭祀財産だからです
生きているうちにお墓を購入する「生前墓」は、しばしば相続税対策として購入されますよね。
これはお墓が相続税の掛からない「祭祀財産」と判断されるためです。
ただ法要・法事に掛かる費用は控除対象ではありません。
お墓に相続税が掛からず、納骨式は控除対象にならないとなれば、線引きが難しいと捉える人もいるでしょう。
では生前墓が相続税対策とされるのは、どのような理由があるのでしょうか。
| <生前墓が相続税対策になる理由> | |
| [相続後にお墓を建てる] | ①財産を相続 ②相続財産でお墓を建てる ③相続税の課税対象 |
| [生前にお墓を建てる] | ①財産からお墓を建てる ②お墓を「継承」 ③相続税が掛からない |
お墓が相続税対策となるのは、親が生きているうちに自分の財産でお墓を購入し、子どもにはお墓の形で継承されるためです。
ちなみにお墓は「継承」する祭祀財産で「相続」するものではありません。
相続税は相続する財産に対して課税されるため、お墓は課税対象外です。
生前墓が増えた背景:永代供養とは
◇「永代供養」とは、管理者が家族に代わり遺骨の管理や供養をすることです
永代供養とは、墓地や霊園・納骨堂などの施設管理者が代々継承すべき家族に代わり、永代に渡って遺骨の供養や管理を行うサービスを差します。
そのため永代供養をお墓に付けることで、継承者を立てる必要がありません。
けれどもあくまでも遺骨の管理や供養で、お墓が永代に渡り個別に残る訳ではないので注意をしましょう。
| <永代供養とは> | |
| ①お墓に永代供養を付ける | ・個別安置の期間を確認 |
| ②契約年数後、合祀墓に合祀 | ・契約更新により延長あり |
| ③合同で永代に渡り供養 |
|
永代供養では契約した5年や15年、33年などの一定年数後、契約更新がない限りは施設管理者の判断で、遺骨を取り出し合祀墓に合祀、他の遺骨とともに永代に渡り供養されます。
お墓は撤去される仕組みですが、遺族が契約年数内に更新をすることで、遺骨の個別安置(お墓を残す)ことも可能な墓地霊園が多いです。
お墓の相続税が掛からない「祭祀財産」とは?

◇「祭祀財産」とは、大まかに故人やご先祖様を供養するための財産です
お墓や仏壇、位牌や仏具など、故人やご先祖様を供養するために用いるものは「祭祀財産(さいしざいさん)」として継承されます。
「継承」とは子どもや孫、ひ孫と子々孫々に繋いでいく・受け継ぐもので祭祀財産に限らず、地位や身分なども「継承」です。
| <祭祀財産とは> ●供養・祭祀に用いる財産 |
|
| ●基本的に一人が継承する | ・お墓(墓地) ・仏壇(仏具) ・位牌 ・墓碑 ・家系図 …など。 |
親族間トラブルを避けるため、祭祀財産を継承する者は一人です。
相続財産のように相続権のある兄弟姉妹で等分する性質のものではありません。
日本の従来の慣習では長男が代々継承者とされましたが、現代は継承者がいない「継承者問題」などの事情から、風習は緩くなっています。
誰が継承者になるかは、その土地柄や家の風習によっても大きく変わるでしょう。
祭祀財産にならないもの
◇金銭的に価値のあるものは、財産としてカウントされます
お墓や仏壇仏具など供養に使う財産は全て「祭祀財産」相続税の非課税対象です。
けれども一部、金銭的のあるものと認められると課税対象になります。
・骨董品(御本尊など)
・高価な素材(金など)
なかには祭祀財産として相続税の非課税対象にしようと、金(ゴールド)で作られた御本尊や、価値が高い骨董品を生前に購入するケースなどもあるようです。
保険には相続税が掛からない?
◇生命保険や死亡退職金は、限度額内で相続税の非課税対象です
生命保険や死亡退職金も相続税の課税対象にはなりませんが、限度額があります。
「死亡退職金」は中小企業の経営者に多い制度で、死亡保険と同じく、故人亡き後に家族などに支払われる保険です。
いずれにしても限度額は「500万円×法定相続人の人数」となります。
| <生命保険・死亡退職金の相続税> ●限度額「500万円×法定相続人の人数」 |
|
|
[例] |
・9,000万円生命保険 ・子ども(法定相続人)が3人 ●非課税額は1,500万円まで |
| [非課税枠なし] | ・9,000万円の相続税…480万円 |
| [非課税枠あり] | ・9,000万円-1,500万円=7,500万円 ・7,500万円の相続税…270万円 |
| [差額] | ・480万円-270万円…210万円 |
このように死亡保険や死亡退職金は、現定額がありながらも相続税の非課税対象枠があることも、生前に積み立てておく人が昔から多い理由のひとつです。
・生命保険の死亡保険金に掛かる相続税の非課税枠とは?所得税や贈与税が掛かるケースは?
お墓の相続税・贈与税はどうなる?
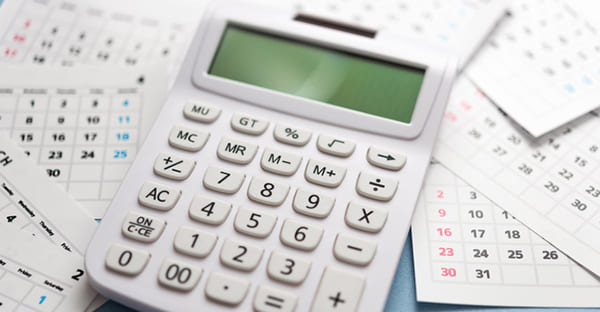
◇祭祀財産であるお墓は相続税・贈与税ともに掛かりません
このように祭祀財産であるお墓は相続税はもちろん、贈与税も掛かりません。 そのため子どもにお墓を購入する費用を贈与するよりも、本人が生前にお墓を建てる方が税金対策になります。
| <お墓の相続税・贈与税は?> | |
|
[相続税] |
・お墓を継承…相続税は掛からない ・購入費用を相続…相続税が掛かる |
| [贈与税] | ・お墓を贈与…贈与税は掛からない ・購入費用を贈与…贈与税が掛かる |
つまり、お墓は生前であっても本人が生前墓を購入してから、子どもに託した方が、税金(贈与税)が掛かりません。
いずれにしてもお墓に入る本人が生前墓を購入した方が節税対策となる訳です。
生前墓の固定資産税は?
◇墓地に税金は掛かりません
そもそも住宅は個人で家や土地を購入・所有するため財産として固定資産税が掛かりますが、墓地は個人が所有するものではありません。
| <生前墓の固定資産税は?> | |
|
[住宅] |
・固定資産税 ・都市計画税 |
| [お墓] (墓地を借りる) |
・年間管理料 (施設管理者へ支払い) |
住宅は土地も家も自分で所有するため固定資産税や都市計画税など、課せられた税金を国に支払う義務があります。
けれども墓地は永代に渡り使用する「永代使用権」を購入して、半永久的に借りているため、固定資産税も都市計画税も掛かりません。
お墓の相続税はどれくらい違う?

◇一例では200万円ほど、相続税の差額が出ました
では子ども1人が預貯金財産を9,000万円相続した事例で差額を計算してみましょう。
9,000万円の相続税を単純計算すると920万円です。
(両親の財産を相続したとします。)
このケースで子どもが800万円で、両親のお墓を購入するとどうなるでしょう。
(A)9,000万円-920万円(相続税)-800万円(建墓費用)=7,280万円
・相続財産の合計…7,280万円
一方、両親が9,000万円の預貯金財産から、生前に800万円のお墓を建てたとします。
子どもが受け取る預貯金財産8,200万円に対する相続税は、単純計算で720万円です。
(B)9,000万円-800万円(建墓費用)-720万円(相続税)=7,480万円
・相続財産の合計…7,480万円
9,000万円の預貯金財産、800万円のお墓を購入する場合、子どもが相続後にお墓を購入した(A)、両親が生前墓を購入した(B)の差額は、下記です。
●7,480万円(B)-7,280万円(A)=200万円
・相続税の差額…200万円
このケースはあくまでも一例ですが、このような事情から生前墓が相続税対策として注目されるようになりました。
お墓と葬儀費用は、相続税の扱いが違う?

◇お墓は相続税の非課税対象ですが、葬儀費用は故人の財産から捻出します
葬儀費用もお墓と同じく相続税が掛かりません。 けれども葬儀費用は故人の財産から捻出できる費用なので、お墓など非課税対象の祭祀財産とは扱いが違います。
| <お墓と葬儀費用:扱いの違い> | |
|
[葬儀費用] |
●亡き後に支払いができる ・故人の財産から捻出 ・相続前に差し引く |
| [祭祀財産(お墓)] |
●亡き後の支払いはできない ・相続税の非課税対象 ・継承(相続)は発生 |
このようなことから、お墓購入の費用は被相続人が亡くなってから支払うことはできません。
あくまでもお墓の形で「継承」することで相続税の非課税対象になります。
そのため被相続人が亡くなる前に、本人が購入する必要があるでしょう。
葬儀後の法事はどうなるの?
◇葬儀後の追善供養は、相続税控除の対象外です
家族が亡くなると遺族は何らかの方法で、故人を葬送しなければなりません。
そのため葬儀費用は、「債務控除」として非課税対象になり、故人の財産から支払うことができます。
・香典返し
・香典
・お墓購入の費用
・追善供養
(初七日以降の法要)
けれども初七日以降の法要は「追善供養」であり義務ではありません。
そのため初七日以降の追善供養は、遺族が支払う費用として、相続税控除の対象外となります。
お布施はどうなるの?
◇葬儀でお渡ししたお布施は「葬儀費用」です
お墓のように相続税の非課税対象がどこまでか、範囲がハッキリしない葬儀費用ですが、目安としては「葬儀当日に支払う費用」は、相続税控除の対象になります。
| <葬儀費用に含まれるもの> ●葬儀当日に支払う費用 |
|
|
[葬儀社への支払い] |
・葬儀費用 ・祭壇 ・棺 ・搬送費用 …など |
| ●僧侶・寺院への支払い | ・お布施(読経供養) ・御車代(僧侶の交通費) ・御膳料(僧侶の会食代) ・戒名料 ・葬儀と同日の法要 (繰り上げ初七日など) |
| [葬儀関係の支払い] |
・お手伝いへのお礼(寸志) ・会葬礼状 ・お土産代 |
初七日法要・四十九日法要などの追善供養は葬儀費用に含まれませんが、葬儀当日に払う繰り上げ初七日は葬儀費用として、非課税対象となります。
戒名を付けないケース
◇無宗教の人々は戒名が必ずしも必要ではありません
終活によるお墓の生前購入で相続税対策として、戒名も依頼して墓石に彫刻を済ませる人は多いですよね。
生前に墓石に彫刻する戒名や俗名は、朱色に塗られる「朱文字」です。
ただ「戒名」は仏様の弟子になった証、仏教の慣わしですので、宗旨宗派不問の民間霊園などにお墓を購入した場合、そもそも戒名が必要ないとも言えます。
| <戒名はどうする?> | |
|
[生前に戒名を依頼] |
・本人が財産から捻出 ・相続税は掛からない |
| [葬儀に合わせて依頼] | ・葬儀費用に含まれる ・相続税は掛からない |
| [法要に合わせて依頼] |
・遺族が戒名料を支払う ・相続税が掛かる |
| [戒名を付けない] (俗名を彫刻など) |
・戒名料が掛からない ・宗旨宗派不問の霊園 ・無宗教 |
葬儀費用に戒名料も含めるならば、生前に戒名を付けても、亡くなった後に付けても、相続税対策としては変わりません。
どちらにしても非課税対象ですが、墓じまいにより無宗教になる、宗旨宗派不問の民間霊園が増えた今、無宗教として戒名を付けない選択も増えました。
また「戒名は付けるが、僧侶に依頼しない」などのケースもあります。
| <戒名を付ける?付けない?> ●菩提寺がない家の選択 |
|
|
①生前の俗名を使う |
(戒名を付けない) |
| ②ネットで戒名を依頼 | (安い費用で戒名を付ける) |
| ③自分で戒名を付ける |
(無料で戒名を付ける) |
また驚く人も多くいますが、実は戒名は自分で名づけても問題はありません。
そこで家族や本人が戒名を名付けて、墓石や位牌に記載する事例も増えました。 このように菩提寺がない家では、戒名の判断は自由です。
まとめ:お墓の生前購入で相続税や贈与税は掛かりません

お墓や仏壇など、故人やご先祖様を供養するための財産は「祭祀財産」として相続ではなく「継承」をするので、相続税は掛かりません。
けれども故人から財産を相続した後、その相続財産でお墓を建立するならば、相続財産として計上しなければならず、相続税が掛かります。
お墓や仏壇などを非課税枠で継承したい場合、現物で継承しなければなりません。
けれども葬儀費用は相続税の非課税対象として、被相続人(故人)亡き後の支払いでも相続税の対象外です。
けれども葬儀費用は葬儀当日までに支払う費用を差し、葬儀後の初七日法要などに掛かる費用は、相続人(遺族)が支払う項目になるため、注意をしてください。
お電話でも受け付けております
















