
認知症になった親の口座が凍結!お金引き出しまでの流れ、事前にできる3つの対策も解説
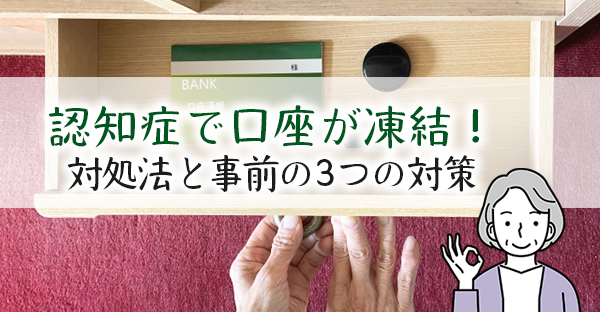
認知症になると、本人の預金口座が凍結しお金が引き出せなくなる可能性があります。
「ひとり暮らしの親が認知症になったものの、口座が凍結されていて、どう対処すれば良いか分からない!」などの相談も少なくありません。
親が認知症になり、すでに口座が凍結された場合には、法定後見人制度により、親の経済的な手助けができるでしょう。
また、このような認知症になった親の口座凍結を避けるためには、家族信託や任意後見人制度など、事前にできるいくつかの対策があります。
今回は、認知症による口座の凍結へ事前にできる3つの対策を、実際に凍結してしまった時の法定後見人制度とともにお伝えします。
認知症になった親の口座が凍結!お金引き出しまでの流れ、事前にできる3つの対策も解説

認知症になると口座が凍結される

最近では高齢者のひとり暮らし世帯が増え、家族や周囲は兆候や初期症状に気付かないまま、ある日突然認知症になるケースが増えています。
突然の認知症で問題になるのは、口座の凍結です。
ひとり暮らし世帯で認知症により、本人の口座が凍結されてしまうと、生活さえままなりません。
●認知症による判断力の低下や喪失により、認知症になった本人や家族などが資産を自由に動かせなくなることを、「資産凍結リスク」の可能性があります。
また、この問題は預貯金財産ばかりではありません。
不動産財産などの名義が親名義だったりすると、認知症になった後では、さまざまな問題が生じます。
・不動産(親名義)の名義変更
・定期預金の解約
・介護費用を算出したい
…認知症になった本人の意思が確認できないために、不動産の名義変更も、定期預金の解約も、全てが停滞することが問題です。
これらの資産が自由に動かせない分、家族が介護資金などを立て替える必要が出てきます。
認知症になる前にできる対策

認知症になると、初期段階から家計の管理が困難になる症例は多くあります。
認知症は脳が委縮するため、自分でコントロールが効かない状態でもあるので、例えば衝動買いの他、詐欺に引っ掛かってしまうケースも少なくありません。
ですから認知症の兆候が表れた時点で、周囲の人々が共に財産管理ができれば良いのですが、家計の管理は本人の自尊心にも掛かってきますから、家族間での充分な話し合いが必要です。
(1)家族信託
(2)任意後見制度
(3)日常生活自立支援事業
※生前贈与による財産の譲渡
本人の自尊心を大切にするため、認知症の症状もまだ初期症状であれば、社会福祉協議会で行っている日常生活自立支援事業を紹介するのも良いでしょう。
本人の意思により契約をするサービスですし、家族が介入しないため、家族信託よりも自尊心を保つことができます。
(1)家族信託
「家族信託」では、財産を持つ者が信用できる家族に、自分の財産の管理・処分を任せる仕組みです。
そのため事前に家族信託の契約をしておくと、認知症発症後に本人の口座が凍結されても、家族信託を受けた家族が預貯金口座の管理ができます。
家族信託では、委託者・受託者・受益者の3者によって成り立つ仕組みです。
・委託者…最初に財産について信託する人
・受託者…委託者から不動産などの名義を受け持つことや信託財産の管理・処分をする人
・受益者…信託財産から利益を得る人
この3者を予め決めておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
また家族信託のメリットのひとつとして、認知症になった後でも判断力が低下しないうちに手続きを進めることも可能です。
認知症になった本人の口座凍結問題が解決しやすい家族信託は、比較的新しい制度ですが、需要が高まり最も注目されています。
※家族信託について、詳しくは下記をご参照ください。
・家族信託とは?相談先やメリットとデメリット、手続きの進め方5つのステップまで解説!
(2)任意後見制度
「任意後見制度」とは、判断能力が不十分とされる認知症による口座凍結トラブルを事前に回避する手段です。
そのため本人の判断力があるうちに、予め決めて選んだ信頼できる代理人に、自分の生活や財産の管理に対する代理権を与える契約を差します。
●任意後見制度を利用するには、下記の手順を行います。
・公証人による公正証書の作成
・契約
ちなみに契約したからといってすぐに効力が発生するものばかりではなく、認知症や判断能力の低下により不十分になった状態にならないと効力は発揮しません。
ちなみに任意後見制度と似たような制度で、「法定後見制度」がありますが、これはすでに認知症になった時に利用する制度です。
・任意後見制度…現状は問題がないが、将来的に不安
・法定後見制度…現状すでに判断能力に症状がある
任意後見制度は、将来的に認知症による金銭の管理などに不安を感じている人が、事前に取る対策になります。
(3)日常生活自立支援事業
認知症による口座の凍結を防ぐため、本人が事前にできる対策が「日常生活自立支援事業」です。
家族信託も本人が契約する制度ですが、子どもなどの家族が財産を管理するため、親としてプライドが許さない…、などの事例も少なくありません。
このような場合に日常生活自立支援事業であれば、自治体が提供する月に一回の福祉サービスで、お金を払う(平均で約1,200円と、気軽に払う範囲)ため、本人も対策を進めやすいでしょう。
生前贈与による財産の譲渡
最後に、認知症や判断力の低下の前に、預金や不動産を贈与しておくのも一つの手です。
生前贈与をすることで、認知症による口座凍結のリスクを避けることもできます。
しかし、生前贈与は、贈与税が発生するため負担する注意が費用です。
贈与額によって贈与税も変化しますので、税理士に相談しながら進めると良いでしょう。
認知症で預金口座が凍結した時の対処法

周囲が本人の認知症発症に気付かず、突然口座が凍結した場合には、成年後見制度のなかでも任意後見制度ではなく、法定後見制度を利用することになるでしょう。
「成年後見制度」とは、認知症などで適切な判断能力がない成人に対する後見制度全般を差し、そのなかに任意後見制度、及び法定後見制度があります。
●「成年後見制度」とは、認知症や判断力が低下しその判断能力が不十分な人が生活する上で不利益が被らないように、本人の代わりに財産を管理契約の支援を行う制度です。
・法定後見制度…判断能力低下後
・任意後見制度…事前に本人が契約
※すでに認知症の症状があり、口座が凍結された場合には、法定後見制度により選任された家族が金銭の管理をします。
本人ももちろんできはしますが、すでに認知症の症状が出ているので、法定後見制度は家族(配偶者/四親等内の親族)や、検察官・市町村長などによる家庭裁判所への申立が始まりです。
ただし法定後見制度は、現状維持が原則です。
過度な投資や相続税対策・財産の組み替えなどはできません。
●また、あくまで財産の現状維持が目的です。
その点だけ理解をして、財産管理を進めてください。
最後に
以上が、親が認知症になって口座が凍結された時の対処法です。
ただ認知症になって口座を凍結された後では、家族やそれに相応する親族が、家庭裁判所に申立を行い、選任されなければなりません。
法定後見人に関しては3つの種類があり(後見/保佐/補助)、それぞれに権限が違うなど、また複雑です。
そのため認知症になる可能性は考えたくないものですが、元気なうちに任意後見人制度や家族信託など、家族が困らない対策を取っておくことをおすすめします。
※成年後見制度に関して、詳しくは下記記事でお伝えします。
・親が認知症になっても財産を守る「成年後見制度」とは?後見人ができること、できないこと
・任意後見制度で認知症になった親の財産を守る|手続き5つの手順と任意後見制度3つの種類
まとめ
認知症による口座の凍結、対策と対処法
●対策
・家族信託
・任意後見制度
・日常生活自立支援事業
※生前贈与
●対処法
・法定後見制度
(申立→家庭裁判所による選任)
お電話でも受け付けております















