
老々介護と認認知介護から抜け出すには?限界になる前6つの解決策、未然に防ぐ対策まで
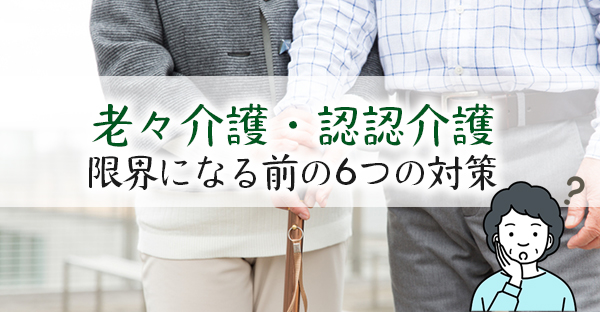
「老々介護」は高齢者が高齢者の介護をすることを差しますが、さらに近年では「認認介護」が問題になっていることはご存知でしょうか。
「認認介護」とは認知症の症状を持つ高齢者が、さらに重症な認知症の症状を持つ高齢者を介護する状況です。
パートナーがいて孤独死の不安が和らいでいるシニア夫婦も、この老々介護や認認介護への不安相談が増えました。
今回は老々介護や認認介護の現状を紐解きながら、最後に自分達でできる対策を6つお伝えします。
老々介護と認認知介護から抜け出すには?限界になる前6つの解決策、未然に防ぐ対策まで

老々介護とは?

「老々介護」とされる高齢者の年齢は、年金受給開始年齢の65歳以上が対象です。
例えば65歳の夫が体力が低下している妻70歳を介護する…、などのケースでは、老々介護になります。
また65歳以上であれば老々介護における高齢者の認識なので、例えば65歳の息子が88歳の母親を介護しているなど、夫婦に限らず息子が介護していることも対象です。
●「老々介護」とは、65歳以上の高齢者が、65歳以上の高齢者を介護する状態を差します。
家族がいない・お金がなく施設に入居できない点、と言った様々な理由から老々介護をしている世帯が急増しているのが現状です。
老々介護の実態

現段階の日本では老々介護の実態はどのようになっているのでしょうか。
下記は65歳以上の高齢者世帯の2001年~2016年度までの変遷です。
| 年次 | 60歳以上 | 65歳以上 | 75歳以上 |
| 2001年 | 54.4% | 40.6% | 18.7% |
| 2004年 | 58.1% | 41.1% | 19.6% |
| 2007年 | 58.9% | 47.65% | 24.9% |
| 2010年 | 62.7% | 45.9% | 25.5% |
| 2013年 | 69.0% | 51.2% | 29.0% |
| 2016年 | 70.3% | 54.7% | 30.2% |
※厚生労働省「国民生活基礎調査の概況IV.介護の状況 2019年度」より
このように2001年から2016年までで65歳以上の高齢者の世帯が右肩上がりになっているのがわかりますね。
現代の日本では深刻な問題と捉えてもいいのではないでしょうか。
これだけ高齢者が増えているのに対し、若い家族がいないことやお金がなく施設に入居できないことを考えると対策を打つ必要があるでしょう。
老々介護になる原因

老々介護になる原因は以下の3つです。
少子高齢化や核家族化による影響は、老々介護・認認介護ばかりではなく、高齢者世帯の孤独死にも影響しています。
現代では高齢者世帯の両親と、若い子ども達世帯が同居できない事情は分かりますが、何らかの形で外部との繋がりを保つことがポイントです。
(1)少子高齢化
(2)核家族化などの生活スタイル
(3)日本での介護保険制度
それでは、この3つの原因を深掘りしていきましょう。
社会的な背景を理解することで、より自分達でできる、適切な老々介護・認認介護への対策が見えてきます。
(1)少子高齢化
近年では少子高齢化問題が深刻化し、高齢者が高齢者を介護することが非常に増えてきているのが現実です。
・子供の数が減り、高齢者をサポートする存在も少なくなった。
・子ども達は夫婦共働き世帯が多いため、介護をする余裕がない。
現代の若い世帯は夫婦共働きが一般的になっています。
これは若い世帯の経済的な側面もあるでしょう。
このように子供がいるのにも関わらず、介護できない状態になる家庭も少なくありません。
少子高齢化の影響は、単純に「子どもがいない」だけではなく、さまざまな影響から、高齢者が高齢者の介護をせざるを得ない、老々介護・認認介護の現状があります。
(2)核家族化などの生活スタイル
前項でお伝えしたような、若い世帯の夫婦共働きや経済的状況も含めて、日本全体の生活スタイルが変化しているのも老々介護・認認介護に繋がっていることは否めません。
特に老々介護・認認介護に影響を及ぼしているのは、核家族化の加速ではないでしょうか。
・核家族化により日々の介護ができない
・親世帯と子ども世帯の住まいが距離的に離れている
・子育てと仕事の両立で、子ども世帯に親まで気遣う余裕がない
特に現代の40代50代世帯になると、子ども達も中学から高校、大学へと進学する時期です。
そのため、親の介護費用と子どもの教育費用がかさんで、経済的にも体力的にも苦しく、相談にくるケースが増えました。
子どもの教育費が掛からないうちは、介護ができない部分を民間の見守りサービスなどの利用で補填していたものの、「大学の進学費などで補填もできなくなった…」などの相談があります。
(3)日本での介護保険制度
そのため老々介護・認認介護の当事者である親世帯としては、自分達で介護の負担を補填しようと考えますが、現代の日本では、経済的な側面を助ける介護保険制度も充分ではないようです。
●現代の介護保険制度は、体力があり時間に余裕があることを想定しています。
・家事援助
・買い物代行
…などなどのサービスは介護保険に入りません。
近年、老々介護・認認介護世帯が急増する今、介護保険制度は現実の暮らしに達していないことが分かりはじめました。
このようなケースの現象に合わせて、これからの生活支援サービスや配食や見守りなどの介護者の負担を軽減する必要もあるのです。
老々介護・認認介護になる前の対策

以上が日本の老々介護・認認介護の現状ですが、自分達が将来的にこのような状況にならないために、「自分達で」できる対策にはどのようなものがあるでしょうか。
まずは最初の一歩として、下記3点を上げることができます。
老々介護・認認介護では、当事者である高齢者が自分の体力を過信している部分もありますが、前提として「周囲に迷惑は掛かる」可能性は想定の範疇に入れなければなりません。
その上で、いかに周囲の負担を最小限にするか…、を検討します。
そのためには、まず周囲の人々へ理解を求め、最小限の負担で済むよう介護知識を持ってもらうと良いでしょう。
(1)健康的な生活を送る
(2)家族と話し合う
(3)家族に介護知識を教える
(4)介護保険でサービスを利用する
(5)地域サークル、社会参加をする
(6)定期的に心身の健康チェックをする
以上6つが、老々介護で限界になることを避ける、そして老々介護から認認介護になり、キッチンを火の元とする火災など、思わぬ事故を起こさずに過ごすポイントです。
(1)健康的な生活を送る
本人はいつまでも若いと思いがちですが、高齢者になると本人には気付かない形で、徐々に身体的変化が起こります。
少しでも介護の必要のない健康的な生活を送るためには、ウォーキングなど適度な運動と健康的な食事もありますが、「日々の身体的変化を記録する」ことが効果的です。
・血圧/体温
・排泄周期
・睡眠時間
・食事内容と回数
・精神的な変化
朝起きたら血圧や体温をチェックして日記に記すなどの他、最近では健康管理を自動的にしてくれるスマートウォッチを活用する事例もあります。
ただ、これらの記録を自身で付けたい理由には、最後の「精神的な変化」を把握することもあるでしょう。
認知の始まりや老後うつにも対応
日々の記録とともに、一行でも良いので今日の気分や、怒った出来事などを記録します。
●加齢に伴う認知機能の低下により、本来の生活とは別に、怒りやすくなった、我慢ができなくなった、イライラしやすくなった…、などの症状は多いです。
また日々の気分など、精神的な変化の記録は、老後うつの早期発見にも繋がります。
高齢になるとなかなか自分のうつ症状を認められないこともありますが、文字にして表すことで、俯瞰的に自分を見ることができるでしょう。
(2)家族と話し合う
「つい先月まで元気に買い物も行っていたのに、ある日、転んで骨折をして入院をしたら、退院した後から寝たきりになってしまった…。」
などの体験談を聞いたことはないでしょうか。
高齢者が老々介護に陥る状況は、思った以上に突然訪れます。
事故や病気で突然の介護を突きつけられると、経験のない家族は困ってしまうでしょう。
●その点、さまざまな可能性を想定して家族と日々話し合うことで、家族も日ごろから「もしも」に対応できます。
・介護される本人の考え
・介護する側の家族の考え
…それぞれを日ごろか伝えておきましょう。
また、あまり考えたくないことですが、脳卒中や心筋梗塞など、その時になると本人の意思を伝えられないケースもあります。
話し合うとともに、エンディングノートなどに延命の有無や介護の希望を記しておくと安心です。
(3)家族に介護知識を教える
家族に介護知識を教えるのも対策の一つです。
介護をしたことがない家族は当然ながら「スキル」がない状態ではないでしょうか。
けれども前述したように、突然老々介護に陥った時、自分がどのような状況にあるのかは分かりません。
・どこで介護をするか(自宅/介護施設)
・誰が中心になるか(介護方針の決定など)
・介護を相談してくれる人や施設
・介護保険サービスの内容
・民間介護サービスの可能性
…具体的な連絡先や利用できるサービスなどをまとめておきます。
介護をする際に余計な身体的なストレスがかかったり、介護者とのコミニュケーションが上手くいかないという事態を軽減することができるでしょう。
老々介護に陥る前に、周囲の家族が最低限の負担のなかで介護保険サービスを利用しながらの協力体制ができるなど、介護を理解することで新しい方法も見つかりやすいです。
●特に老々介護で問題が起きやすいポイントは下記の3点が多いでしょう。
・移動
・排泄物
・おむつ交換
周囲もホームヘルパーなど、適切な介護保険サービスを利用するとともに、予め介護知識を身に着けることで、突然の事柄にも対応しやすくなります。
(4)介護保険でサービスを利用する
老々介護・認認介護に限らず、介護世帯では経済面での問題も少なくありません。
介護状態になってしまった場合、老々介護・認認介護を回避するためには、多かれ少なかれ子ども世帯の負担は掛かってきます。
けれども介護サービスをフル活用することで、経済的にも肉体的にも、その負担は大幅に軽減されるでしょう。
●要介護認定を受けたら、まず住む地域の地域包括支援センターでケアマネージャーに相談をしてください。(無料です)
老々介護(認認介護)になり得ること、子ども世帯は別居していることを伝えます。
・ホームヘルパー
・デイサービス
・短期入所
…などのあらゆる介護保険サービスを組み合わせて、介護保険内でスケジュールを組んでもらうことで、子ども世帯は経済的にも負担を少なくしながら、労力的にも対応できるほどになり、全くの老々介護を回避できるでしょう。
※介護保険で受けられるサービスについては、下記をご参照ください。
・【老後に破産しない資金計画】公的介護保険でどこまでできる?介護問題に備える5つの知識
(5)地域サークル、社会参加をする
以上、老々介護にはさまざまな対策がありますが、もしも夫婦で老々介護・認認介護の状況になった場合、介護うつに陥ることなく、楽しく毎日を乗り切るコツは、ひとりでも多く理解者、援助者を得ることです。
そのためには日ごろから、地域の人々とのコミュニケーションは欠かせません。
・町内会などの活動
・子育て支援ボランティア
・まちづくり/社会奉仕ボランティア
・生涯学習教室/サークル
・地域のお祭りなどの伝承活動
…などなど。
自治体では高齢者を対象としたあらゆるサークルなどを提供しているので、公民館などで調べて積極的に参加してみるのも良いでしょう。
(6)定期的に心身の健康チェックをする
老々介護ももちろん、介護うつなどの問題を引き起こす深刻な状況ですが、老々介護から認認介護へ切り替わることは、さらにさまざまなリスクを孕むことになるでしょう。
けれども老々介護から認認介護へ移行するリスクは、何よりも「本人が自覚していない」ことが多い点です。
そのため、本人も含め周囲の人々も、日ごろからチェックを行うようにしてください。
下記は認知症も含めた、老後/介護うつの可能性も含めたチェックです。
<チェック項目>
・以前より引きこもりがちになった
・同じ食品や商品ばかりが買いだめされている
・話の内容に違和感がある
・疲れている様子が見られる
・家事が億劫になっている様子(掃除や料理など)
・定期的な薬のチェックができていない
・金銭管理ができていない
…などなど。
老後うつや介護うつと認知症による症状の違いは、例えば家事ができていない状況だった場合、それを本人がどのように捉えているかによります。
・老後うつ/介護うつ…本人に焦りや罪悪感など、自覚症状がある
・認知症…本人に自覚症状がない
老後うつや介護うつだと周囲はひと安心してしまいがちですが、こちらも問題です。
近所の人々に声掛けや相談をしておく、自治体などに見回りサービスを相談するなど、遠くに住んでいてもできることはあります。
本人は自分が仕事をできないことがクローズアップされてしまいがちなので、周囲は話し相手やサポート体制を整える必要があるでしょう。
最後に
老々介護・認認介護は、個々の家庭ばかりではなく、今では社会問題になっています。
そのため国や自治体でも積極的に、さまざまな対策を取っているので、将来的な不安を感じた時には、まず、自治体へ相談してみるのも一案です。
老々介護にすでに陥ってしまった場合でも、介護サークルなど、介護者が相談しやすい環境を提供してくれる自治体もあるでしょう。
大切なポイントは、老々介護・認認介護で限界を迎えた時、本人は視野が狭くなってしまう点です。
そうなる前に「介護は一人ではできない」ことを自覚して、愚痴を聞いてもらえる場所など、自分の心身ケアも併せて、ひとつでも多く、SOSが出せる場所、受け止めてくれる場所を探しておくと良いでしょう。
※認知症による相続や経済面での対策として、家族信託もお伝えしています。
・家族信託とは?相談先やメリットとデメリット、手続きの進め方5つのステップまで解説!
まとめ
老々介護・認認介護、限界になる前6つの対策
(1)健康的な生活を送る
(2)家族と話し合う
(3)家族に介護知識を教える
(4)介護保険でサービスを利用する
(5)地域サークル、社会参加をする
(6)定期的に心身の健康チェックをする
お電話でも受け付けております















