
デジタル遺産とは?特徴や問題点・整理しておくべき理由も詳しく解説

「デジタル遺産ってなんのこと?」
「デジタル遺産は整理しておいた方が良いの?」
「具体的にどうやって整理すれば良いか知りたい」
スマートフォンやパソコンなどが普及した現在、デジタル遺産は注目されるようになっています。しかし、具体的にどのように扱えば良いのか、分からないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、デジタル遺産とは何か、問題点や整理しておくべき理由、具体的な整理方法、相続人になった際の手続きなどについて詳しく解説します。
この記事を読むことで、デジタル遺産とは何かを理解し、整理する際の参考にしていただけるでしょう。さらに理解を深めたい場合は、デジタル遺産に関する書籍を参考にしてみてください。
デジタル遺産とは?

デジタル遺産とは、パソコンやスマートフォンのようなデジタル機器を通じてインターネットに保管しているデジタル形式の財産です。
日本では法整備が進んでいないという現状もあり、きちんと準備しておかなければ、トラブルを招く恐れがあります。予期せぬ事態を防ぐためにも、デジタル遺産の種類を理解した上で整理することが大切です。
デジタル遺産に該当する財産
デジタル遺産は、現状では明確に定義されているわけではありません。インターネット上やデジタル機器に保存されているデータの中でも、財産価値を持つものと考えると分かりやすいでしょう。相続財産として相続人に相続されるという特徴があります。
デジタル遺産の主な種類としては、ネット証券口座や電子マネー、ネット銀行口座や暗号資産などです。中には利用規約によって相続できない場合があります。
現在はほとんどの人がパソコンやスマートフォンを持っているため、遺品を整理する時は忘れず確認しましょう。
デジタル遺産の現状は?
日本では、デジタル遺産の相続に関する法整備が進んでいないため、個人が備えておかなければならないという現状があります。
また、近年のスマートフォン普及率やインターネット利用状況によって、ますますデジタル遺産は増加していくでしょう。デジタル資産自体が発展中であることから、デジタル遺産の扱い方も変化していくであろうと予測されます。
デジタル遺品と何が違う?
デジタル遺品とは、お金に直接つながらないデジタルデータやメール、アカウントなどを指します。代表的なものに、動画や写真、ダウンロードした音楽データ、作成した文章などが挙げられるでしょう。
デジタル遺品を整理せずに保管していると、遺品整理に苦労する可能性があります。遺族が困らないよう、どのデータをどこに保管しているか、アクセスするために必要な情報は何かといったことをまとめておきましょう。
デジタル遺産が抱える3つの問題点

デジタル遺産は生前に対策を立てておかないと、トラブルが起きる可能性があります。相続対策として、デジタル遺産の整理をきちんとしておきましょう。
ここからは、デジタル遺産で起きるトラブルについて3点紹介します。
1:相続の手続きが混み入っていて分かりにくい
デジタル遺産の相続手続きは手間のかかる作業が多く、分かりにくいという点が問題です。分かりにくさには以下の理由があります。
まずはデジタル遺産の数が多く、すべての情報を確認する必要があるという理由です。一つずつ確認して相続財産に該当するかどうかを判別し、評価額を計算する必要があります。
また、デジタル遺産の窓口はほとんどがオンライン化されています。名義変更や解約などの手続きをする必要がある場合、インターネットに不慣れであると作業が難しいと感じることもあるでしょう。
2:被相続人しか分からない情報で管理されている
被相続人しか分からない情報で管理されていることが原因で、以下のような問題や、さまざまなトラブルが起きてしまいます。
デジタル遺産にアクセスするためには、IDやパスワードが必要です。もし、遺族がIDやパスワードを知らなければ、デジタル遺産にアクセスできません。ケースによっては、アカウントがロックされる可能性もあります。
しかし、相続人が被相続人が設定したアカウントやパスワードを知らず、デジタル遺産を把握できない場合でも、金銭的な価値があれば相続財産に含まれてしまいます。
また、音楽や動画のような定額課金サービスは、ユーザーから手続きをしなければ解約されません。遺族が契約状況を知らなかったり、アクセス方法が分からなかったりした場合、無駄な出費を続ける可能性があります。
3:相続時にデジタル遺産があるかどうか見つけづらい
従来のような紙の通帳であれば、部屋を探した時に見つかる可能性がありますが、デジタル遺産の場合は見つけるのが難しくなります。
ネット銀行やネット証券の口座などは、インターネット上の操作だけで取り引きを完結できることがほとんどです。実店舗がない場合もあり、通帳が発行されないため、本人以外の人が把握することが難しいことがあります。
さらに近年はSNSなどのサービスで収益を得ている人も増えているため、デジタル遺産を整理する際は注意して調べなければならないでしょう。
デジタル遺産を整理しておくべき7つの理由

ここまで解説してきた問題点からも分かるように、デジタル遺産を放置した結果、思わぬトラブルにつながってしまうことがあります。
ここでは、より具体的にデジタル遺産を整理しておくべき理由を7つ説明します。なぜ整理するべきかを理解しておくと、作業が円滑になるでしょう。
1:定期課金サービスの支払いを即時止めることができる
まず、定額課金サービスの契約の有無を確認することで、契約されていた場合は即時止めることができます。
定額課金サービスとは、動画配信サービスや音楽配信サービスなど、毎月定額料を払うことで得られるサービスです。
銀行口座やクレジットカードから毎月自動で引き落としの設定になっていることが多いため、契約者が亡くなった後も、気付かないまま支払い続けてしまうことがあります。
あらかじめ定額課金サービスを解約しておくと安心ですが、できる限りサービスを利用したいと考えている方は、遺族がすぐに見つけられるよう記録を残しましょう。
2:相続に対するトラブルを防ぐことができる
デジタル遺産を整理しておくことで、相続時の遺産分割協議のやり直しを防ぐことができます。遺産分割協議とは相続人全員で誰が何を取得するかを話し合うことです。通常の遺産分割協議が済んでからデジタル遺産の存在に気付いた場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
また、デジタル遺産の中でも財産価値が高いものを放置していた場合、相続税の申告漏れを指摘される可能性があります。デジタル遺産の価格によって、追徴課税額が変わるため注意が必要です。故意に申告しなかったと判断されてしまうと重加算税が課されることもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、デジタル遺産の整理をしておきましょう。
3:相続人が相続財産を全て把握できる
相続財産を相続人が全て把握できることは、トラブルを避ける点から見て重要です。前述のように遺産分割協議を再度行う手間も回避でき、デジタル遺産を放置していたことによる損失も防げます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10カ月以内です。あらかじめ相続財産を把握しておくことで、期限内に申告でき、申告漏れの心配もなくなります。
出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
4:遺族が交友関係を把握できる
デジタル遺産を整理しておけば、遺族が交友関係を把握することが容易になります。SNSや電話帳などに保存されている連絡先を確認すれば、葬儀の連絡をすべき相手がすぐに分かるでしょう。
スマートフォンやパソコンのロックが外せないと連絡先が分からないという事態になることもあります。特に、デジタル機器以外に連絡先の情報を保存していない場合は気をつけましょう。
5:SNSやブログのなりすまし防止になる
デジタル遺産を整理しておくことで、SNSやブログのなりすましや乗っ取りを防げます。
パソコンやスマートフォンのロック機能、SNSなどのアカウントのパスワードが分からず放置してしまうと、なりすましや乗っ取りに対処できません。乗っ取られたアカウントが悪用されることがあれば、第三者が被害に遭うことも考えられます。
SNSやブログといったサービスの退会が簡単にできるよう、整理しておくことが大切です。
6:データの流出防止になる
デジタル遺産を整理しておくことで、大切なデータの流出や紛失を防止できます。
個人的なデータに限らず、会社などの重要なデータをパソコンに保存していた場合、相続人が誤って消去してしまうこともあり得ます。このような場合は会社とのトラブルにまで発展してしまうリスクがあり、注意が必要です。
また、デジタル機器のデータ整理を個人で行う際は、データ消去が不十分になる可能性があります。確実に個人情報の流出を防ぐためには、専門業者へ依頼する方法もおすすめです。
トラブルを避けるためにも、パソコンやスマートフォンなどのデータを整理し、データ消去の方法なども検討しておく必要があります。
7:遺影を最新の画像にできる
スマートフォンなどで撮影し保存した写真データを整理しておくことで、最新の写真を遺影に使えます。
整理する際に、最新というだけでなく、魅力的な写真や笑顔の写真など、自分が残したいと思う写真を大切な人と共有しておくこともできるでしょう。
デジタル遺産の整理方法
ここでは、デジタル遺産の整理方法を具体的に解説します。デジタル遺産の整理方法には、不要なサービスを解約したりエンディングノートを作成したりする方法があります。
以下の手順を参考に、効果的に整理・管理していきましょう。
不要なサービスは解約する
利用しているサービスを定期的に見直し、使っていない不要なサービスは解約しておきましょう。多くの定額課金サービスは自動更新され、利用者が解約手続きをしない限り、支払いが継続してしまいます。
また、サービスの解約方法を相続人と共有しておけば、無駄な出費を抑えられるでしょう。
写真などのデータをクラウドに保存しておくサービスなどでは、解約する前に必要なデータをバックアップしておくこともできます。
契約しているサービスや金融関連の情報をスマートフォンで管理する
金融情報や各種サービス情報はデジタルデータにして、スマートフォンに保管しましょう。スマートフォンに保管しておけば、遺族も金融情報や各種サービス情報を発見しやすくなるだけでなく、読み間違いや記載ミスが発生することもありません。
ただし、スマートフォンのロック解除の方法を遺族に伝えておく必要があります。また、スマートフォンは誰が見ても分かりやすい場所に保管してください。
資産の内容を親族に伝えておく
デジタル遺産の金額がどれくらいになるか、遺族に伝えておきましょう。事前に遺産額を伝えておけば、トラブル防止にもつながります。
もし、生前に伝えることが難しければ、エンディングノートに書いておきましょう。エンディングノートとは、遺族が相続などの手続きをスムーズに行えるようにするためのものです。デジタル遺産の引継ぎに使うことができ、遺族が相続する時の判断材料になります。
デジタル遺産の目録を作る
デジタル遺産や遺品を記した目録があれば、遺産相続に関するトラブルを防ぐことが可能です。目録を作成する時は、利用しているインターネット上のサービス、デジタル機器に保存しているデータなどを洗い出して記載してください。
エンディングノートに必要な情報を記載しておく
エンディングノートを作成する時は、必要な情報を記載しておきましょう。遺族がデジタル遺産にアクセスできるよう、パスワードや登録用のメールアドレス、IDや電話番号などをまとめておきます。
また、パソコンやスマートフォンのロックを解除するためのパスコードも忘れずに記録してください。デジタル機器を使えなければ、データにアクセスできません。
セキュリティの面から、これらの情報が記載されたエンディングノートは、自宅の金庫など他人に見られない場所に保管する必要があります。それでも不安がある場合は、整理する際に、パスワードの使いまわしがあったら別のものに変えておきましょう。
さらに、ID・パスワードが記載されたノートとデジタル機器を同じ場所に置かないようにします。こうしておくことで、仮に窃盗に遭ったとしても、不正に端末がロック解除されるリスクが減るでしょう。
死後事務委任契約を結んでおく
死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務手続きを依頼する契約です。通常、役所への届け出や葬儀の手配、各種サービスの解約手続きなどを委任できますが、デジタル遺産の処理もここに含まれます。
誰に委任するかに関して制限はありませんが、手間のかかる手続きも多いため、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼するのがおすすめです。
出典|参照:死後事務委任|東京弁護士会
相続人がデジタル遺産を調べる方法
デジタル遺産が整理されていない場合、相続人がその存在を知ることが難しいことも多いです。しかし、放置しておいてトラブルに見舞われることもあるため、デジタル遺産があるかどうかしっかり調べましょう。どのように調べたらいいのか、具体的に解説します。
金融関連の明細書の取引内容を確かめる
まずは、すでに把握している金融関連の取引履歴があれば調べましょう。紙の通帳やクレジットカードの取引履歴、金融機関からの郵送物などです。これらの取引履歴や明細書には、デジタル遺産の情報が記載されていることがあります。
不定期の振り込みや入金がないか、公共料金などの自動引き落としの計算が合うかなどを調べてみましょう。このような手掛かりから、サブのネット銀行やネット証券の口座が見つかる可能性があります。
また、利用明細に取引があった可能性のある会社名などが見つかれば、デジタル遺産があるかどうか、問い合わせることで確認できるでしょう。
インストールされているアプリを確かめる
スマートフォンやパソコン、タブレットにインストールされているアプリには、デジタル遺産の情報が含まれている場合があります。ホーム画面やアプリ一覧、設定画面などから探してください。
例えば、ネット銀行や暗号資産(仮想通貨)取引所などの金融取引系アプリがインストールされていれば、デジタル遺産がある可能性が高いでしょう。
また、いわゆる○○ペイ(Pay)は、スマートフォンを用いたキャッシュレス決済サービスとして、急速に広まっています。これらのアプリを調べることで、連携口座の有無が分かります。チャージ型ペイサービスのアプリがあれば、残高の有無をチェックしましょう。
専門家へ依頼する
デジタル遺産を調査するためには、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器のロックを解除する必要があります。パスワードが分かっていれば問題ありませんが、パスワードが分からずロック解除できない場合は、専門知識が必要です。
近年は、遺品整理の専門業者がデジタル遺品整理にも対応している場合があります。業者のサイトをチェックし、パスワード解除など専門作業が可能かどうか確認しましょう。
メールを確かめる
デジタル遺産には、メールアカウントも含まれます。受信メールに、取引記録や重要な文書などが含まれる場合があるため、忘れずにチェックしましょう。メールを調べる際は、関連ワード(銀行や支払いなど)で検索すると便利です。
また、インターネットでよく閲覧されていたブックマークサイトを調べることで、デジタル遺産が見つかることもあります。
しかし、メールやブックマークを一つずつ調べていくのはかなりの労力が必要です。負担を軽減するには、どの程度まで調べるか、あらかじめ決めておくと良いでしょう。
もしデジタル遺産の相続人になったら?

デジタル遺産の整理方法や調べ方を見てきました。ここでは、相続人になった場合にどのような手続きが必要になるかご紹介します。トラブルを避けるためにも以下の2点を知っておきましょう。
相続税評価額を計算する
相続税評価額とは、財産の種類ごとに決められた評価方法によって計算された、財産の価額です。相続税はこの相続税評価額の合計額に基づいて決められます。相続税評価額を計算することで、相続税の支払いが必要か否か、必要な場合はいくらなのかが分かります。
評価方法は原則として相続発生時の時価で計算され、財産の種類によっては容易に評価できない場合もありますが、相続税の申告期限に間に合わせなければなりません。そういった場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
相続放棄も検討する
相続放棄は、相続人にとって選択肢の一つです。ネット証券や暗号資産取引では、プラスの財産となっているとは限りません。デジタル遺産を調査した結果、マイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を検討しましょう。
デジタル遺産に関して書かれているおすすめの書籍6選
デジタル遺産に関して、さらに詳しく理解したい場合は、以下の書籍を参考にしてみてください。デジタルに関するツールや発展状況は変化が速いため、できるだけ新しい情報を入手しましょう。
1:デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた
家族が亡くなった際のデジタル遺品の探し方や処理方法を中心に、どのように残すかについても解説されています。デジタル遺品について分かりやすさ・活用しやすさを重視した1冊です。
2:デジタル資産と電子取引の税務
近年急増している、デジタル資産とデジタル取引にまつわる税務について解説されています。NFTやインボイス制度などにも対応した内容です。また相談事例が豊富に掲載されています。
3:Q&Aで分かる!デジタル遺産の相続
デジタル遺産の相続について、金融や相続に知見のある弁護士がQ&A形式で解説しています。デジタル遺産の相続とは何か、相続手続き、相続に備えてできることなどが分かりやすくまとめられています。
4:スマホの中身も「遺品」です
SNSやネット銀行、サブスクサービスの浸透など、デジタル機器で取引され、金銭的価値を持つ遺品について解説されています。放置することの危険性や、現状の問題点などにも触れられている書籍です。
5:デジタル遺産の法務実務Q&A
仮想通貨やブロックチェーン、AI、IoTなど、近年の情報技術の視点から基本から応用まで解説されています。法律面からもデジタル遺産について、詳しくなりたい方向けです。
6:ここが知りたい! デジタル遺品
デジタル遺品とは何かという基本から解説されています。また遺族としてデジタル遺品との向き合い方についても書かれています。リスクや整理する方法、処理の仕方や相続の手続きまで、分かりやすくまとめられた書籍です。
デジタル遺産について理解しておきましょう
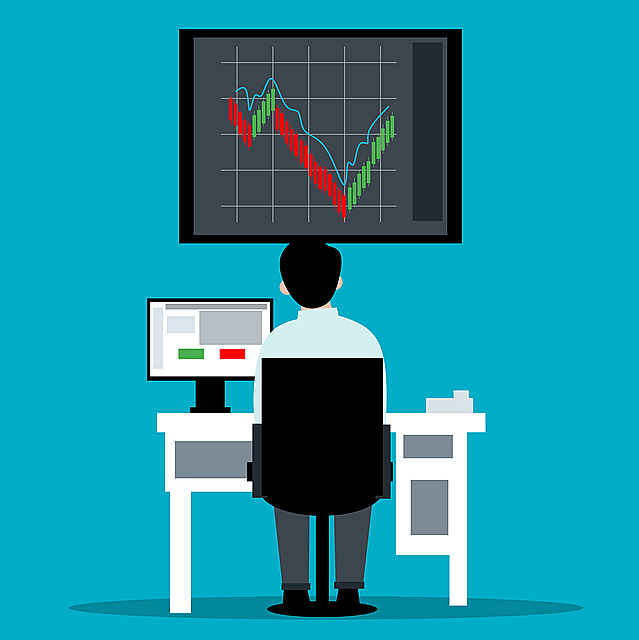
この記事では、デジタル遺産とは何かということから、放置した際の危険性、整理方法、相続手続きなどについて解説しました。
デジタル遺産の相続に関してはさまざまな課題があり、個人で備えておく必要もあるため、あらかじめ理解しておくと良いでしょう。
お電話でも受け付けております


















