
【老後に破産しない資金計画】共働き世帯と専業主婦世帯で、年金受給額はいくら違うの?

老後に破産しない資金計画は、これから定年退職を迎える世代にとって不可欠ですよね。
定年退職後、年金受給だけで暮らすと想定した場合、平均的なシニア夫婦世帯では毎月約5万5千円、30年間で約2000万円の不足額が生じると金融庁より発表され、話題にもなりました。
「老後2000万円問題」とも言われていまうが、このモデルケースは夫が40年間会社員として働き続け、妻が専業主婦だったシニア夫婦世帯です。
ただ今、老後に破産しない資金計画を立てている、これから定年退職を迎える世代では、共働き世帯が多いのではないでしょうか。
今回は、老後に破産しない資金計画を立てるうえで現実的な数字が見えるよう、共働き世帯と専業主婦世帯でどれくらい年金受給額が違うのか…、また50代からの対策についてもお伝えします。
※ 夫が家庭を守る専業主夫世帯もありますが、今回は性別役割分担が一般的だった典型的な昭和世帯と比較するに当たり、「専業主婦」として執筆しています、ご了承ください。
【老後に破産しない資金計画】共働き世帯と専業主婦世帯で、年金受給額はいくら違うの?

40代50代は共働き世代

1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月まで、51カ月間に渡り起こる日本のバブル景気を控えた1980年(昭和55年)の昭和世代では、まだまだ性別役割分担の考え方が広がっていました。
男性は外で働き、女性は家を守り子育てをする…、これが終身雇用制度と年功序列社会が当たり前だった時代の日本です。
人生の40年以上を真面目にひとつの会社で働いたら、そして女性は夫を支え立派に家事子育てを終えたなら、退職金と年金で豊かなシニアライフが待っている…、老後破産などごく一部の世帯と考えていたことでしょう。
けれども1990年代に日本のバブルがはじけると、次第に夫婦共働き世帯が急増します。
● そして1997年(平成9年)にはすでに、夫婦共働き世帯が専業主婦世帯を上回るようになりました。
→ 男女共同参画局による「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)をめぐる状況」では、2017年(平成29年)の共働き世帯は1188万世帯、対する専業主婦世帯が641万世帯です。
40代50代で老後に破産しない資金計画を立てる際、「老後2000万円問題」を気にするに当たり、理解しておきたいポイントは、この数字は「今シニアライフを送っている、専業主婦世帯」をモデルケースとしている点ではないでしょうか。
● 老後2000万円問題のモデルケースとなっているのは、夫が会社員として40年間働き、妻は専業主婦として暮らしていたシニア夫婦が、60歳で定年退職を迎えて、無職で30年間を暮らす想定です。
→ ですが現代の40代50代は、多くが夫婦共働き世帯となります。また年金受給開始年齢も65歳を基準に引き上げられるようになりました。
このように考えた時、どうも40代50代で一般的な共働き世帯が、老後破産しない資金計画としては、注意点がいくつかあるようです。
今後、年金受給額は年々少なくなる
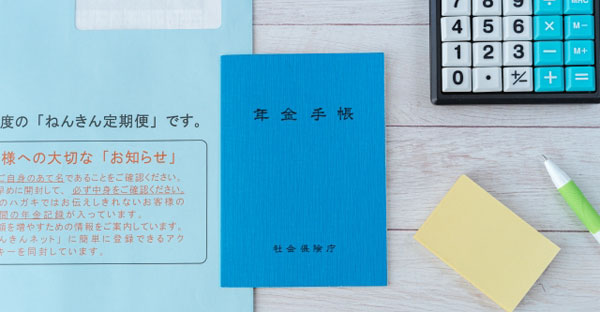
老後2000年問題でモデルケースとなった専業主婦世帯が、老後30年間(90歳まで生きたとして)赤字額を毎月5万5千円出しているように、そもそも専業主婦世帯では年金給付額だけでは、細々と暮らすとしてもムリが生じています。
昭和時代はこれを退職金給付制度で補ってきたことでしょう。
● けれども退職金給付制度を採用する企業自体が減少傾向にあることはご存知でしょうか。1992年に約9割だった採用企業数が2017年には約8割です。
→ さらに退職金給付制度を採用する企業でも、退職金は大幅に減額されています。
※ 1997年の退職金の平均額は約3千2百万円、対して2017年度の平均額は僅かながら2千万円を割っている現状を見ると、そもそも「夫婦共働きでなければ老後を安心して暮らせない」と考える40代50代が多いのではないでしょうか。
また老後に破産しない資金計画を立てるに当たり、専業主婦世帯を軸とした場合、年金受給額が年代によって減少することも心に留めておかなければなりません。
夫婦共に20代から年金受給年齢の65歳まで38年間働いたとして(平均月収を約38万円前後と想定)大まかに計算すると、40代専業主婦世帯では65歳からの年金受給額が約23万円/月、30代専業主婦世帯では約22万円/月でした。
月々は約1万円の差額ですが、年間では約12万円、30年間になると約360万円の差が出ます。
共働き世帯と専業主婦世帯、年金の差額は?

では具体的に、共働き世帯と専業主婦世帯の年金額はどれくらいの違いが出るのでしょうか?
年金制度は現役時代の収入によって金額も変わりますから一概には言えませんが、厚生労働省による「令和2年度の年金額についておしらせします」によると、月々9万442円、共働き世帯の年金額が増えるとされています。
● 共働き世帯と専業主婦世帯で年金の差額を求める際には、厚生年金(老齢厚生年金)に注目してください。
→ 専業主婦世帯では夫一人分の厚生年金が出るのに対し、共働き世帯では夫婦二人分の厚生年金が期待できます。
(1)専業主婦世帯(合計220,724円)
・国民年金(老齢基礎年金) … 130,282円(夫婦二人分として)
・厚生年金(老齢厚生年金) … 90,442円(夫一人分として)
(2)共働き世帯(合計311,166円)
・国民年金(老齢基礎年金) … 130,282円(夫婦二人分として)
・厚生年金(老齢厚生年金) … 180,884円(夫婦二人分として)
※平均的な収入があり、40年間就業した世帯をモデルケースとし、国民年金(老齢基礎年金)は満額、平均標準報酬額43.9万円(賞与を月割り)で算出した数字です。
…つまり妻の厚生年金が上乗せされるため、月間で90,442円、年間では1085,304円、共働き世帯の方が年金受給額が増える計算になります。
65歳~85歳まで受給したとして20年間で21706,080円と考えると、大きな数字ですね。
ただまだまだ現代の日本では、夫婦共働きを進めるに当たり妻の負担が大きくなる傾向があります。もしも今、妻が夫婦共働きで頑張ってる世帯なら、家族で話し合いながら意識改革をして、定年まで走り切るよう協力した方が良さそうです。
専業主婦世帯が今からできる対策とは

このように老後に破産しない資金計画を立てる場合、夫婦共働き世帯が有利であることは理解したものの、40代50代の専業主婦世帯では、「今から社員になるのも難しい…」と感じる方がほとんどですよね。
では今、専業主婦世帯で老後に破産しない資金計画を進めている家では、どのような対策が取られているのでしょうか。
● 「今からでも遅くない!」として、妻が働き始めて社会保険(厚生年金を含める)に加入する事例もありますが、この場合、月々の社会保険料の支払いに驚く声もあるでしょう。この他、下記のような方法が人気です。
(1)付加年金 … 国民年金プラス400円/月で、後々受け取る年金額を増やす方法です。ただし2万4千円の付加に対して1万2千円年金受給額がプラスできる仕組みなので、3年以上は払い続けなければなりません。
(2)繰り下げ受給 … 現在は65歳からの年金受給を基本として、60歳からの繰り上げ受給、65歳以上の繰り下げ受給の申請によって、年金の受給開始年齢を自分で決めます。
※ 65歳以上の繰り下げ受給を申請した場合、年金の受給金額は0.7%/月ずつ上がる仕組みです。
(3)任意加入 … 国民年金は基本的に40年間で満額です。けれども多くの人々がどこかで落としていて40年間を満たしている人は少ないため、任意加入で不足分を補うことで将来的に年金額を上げることができます。
…などなどの方法がありますが、最近老後に破産しない資金計画を立てている世帯では、独自の年金iDeCo(イデコ)や少額投資非課税制度のNISA(ニーサ)、積み立てNISAなどで補填を検討する方も多いです。
※ 老後の年金を増やす対策については別記事「【老後に破産しない資金計画】年金受給額や老後収入を上げるには?50代から5つの対策」でもお伝えしています。
いかがでしたでしょうか、今回は老後に破産しない資金計画を進めるうえで理解しておきたい、共働き世帯と専業主婦世帯での年金受給額の違いをお伝えしました。
会社員として働いていなくても、年収106万円を超えるなど一定の条件が整えば、社会保険の加入(厚生年金含めて)はできますが、今まで夫の扶養として保険料を支払っていた世帯では、「社会保険料が高い!」と感じるかもしれません。
最後に40代と30代では将来的な年金受給額が減少したことからも分かるように、今後は若い世代ほど老後破産をしないよう、現役時代から自分の財産を確保しなければならないでしょう。
そのため親世代は今、終活を通して墓じまいなどを進め、余計な負担を掛けないように生前整理を進める人々が増えました。永代供養によって今後の墓地管理料など墓守も必要ありません。
老後に破産しない資金計画を進めるとともに、早い段階でお墓事に関しても検討してみてはいかがでしょうか。
※墓じまいについては別記事「【大阪の墓じまい】行政手続きの手順。墓じまいと改葬(お墓の引っ越し)は何が違うの?」などでお伝えしています。
まとめ
共働き世帯と専業主婦世帯、年金受給額の違いは?
●専業主婦世帯(合計220,724円)
・国民年金(老齢基礎年金)130,282円
・厚生年金(老齢厚生年金)90,442円
●共働き世帯(合計311,166円)
・国民年金(老齢基礎年金)130,282円
・厚生年金(老齢厚生年金)180,884円
●専業主婦世帯の対策
・付加年金
・繰り下げ受給
・任意加入
お電話でも受け付けております















