
【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や役割など4つの基礎知識
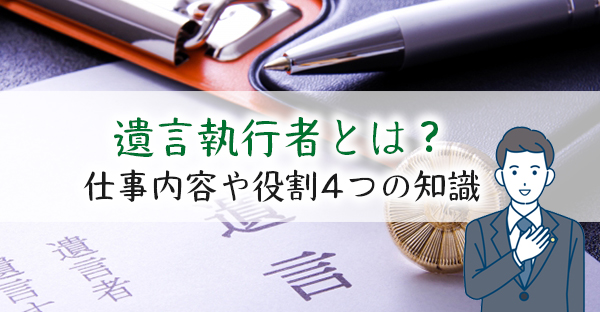
「遺言執行者」とは、遺言の内容を正確に実行するために必要な手続きを行う人です。
遺言を残しても、相続人の異議申し立てなどで無効になるケースが少なくありません。
そこで遺言執行者を指定することで、遺言者の死後、遺言内容が実行されるように問題を解決し、物事を進めてくれます。
この「遺言執行者」は、基本的には誰もがなれますが、多くの場合は、相続人のうち1人が遺言執行者になることが多いです。
場合によっては、銀行や税理士・弁護士・司法書士などがなることも可能でしょう。
【相続対策】遺言執行者を指定して安全性を高くする。仕事内容や役割など5つの基礎知識

遺言執行者とは?
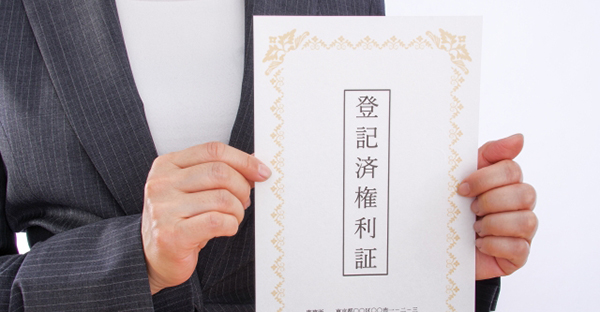
「遺言執行者」とは、遺言内容を正確に実行するために必要な手続きを行う人のことです。
簡略すると、相続人の代理人です。
遺言者(被相続人)としては自分亡き後も、より確実に遺言内容が実行されますし、相続人にとっても、相続に当たる手続きなどで頼りになります。
・相続財産目録を作成
・遺言内容の通りに相続人それぞれに分配
不動産の名義変更などを進める権限も持っているため、遺言者(被相続人)はもちろん、残された相続人にとっても助かるでしょう。
遺言執行者はなぜ必要なのか?
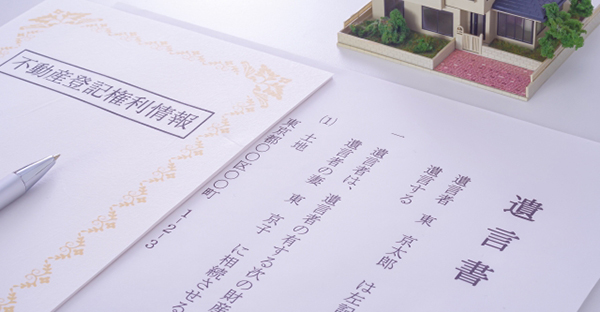
遺言執行者を指定することで、より確実に遺言を実行できますが、遺言書を作成したからと言って、必ず指定する訳ではありません。
けれども現実的に相続が発生した際、被相続人が遺言内容によっては、相続割合の指定や遺産分割自体ができないものもあります。
けれども、遺言を正しく実行するには通れない道です。
・隠し子の認知(認知届の手続き)
・相続人以外の第三者への遺贈
・不動産の相続登記
…などなど
そして複数の相続人がいた場合、法的には「相続人全員で手続き」を行いますが、具体的な作業は、複数の相続人のうち誰か一人が行わなければなりません。
この具体的な手続きは面倒な事柄が多いですから、「誰か一人」に誰がなるかで揉めることもありますが、遺言者(被相続人)が生前に遺言執行者を指定できます。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、相続人それぞれの代理人として、不動産の名義変更や、預貯金口座の解約を相続人にそれぞれに分配するなど、遺言内容を実現するための必要な手続きを行う役割です。
・遺贈
・預貯金の解約・名義変更手続き
・不動産の相続登記
・有価証券の名義変更
・貸金庫の開扉
…などなど。
遺言執行者はこれらの必要な手続きをして、遺言内容を執行します。
また、遺言執行者でなければできない相続手続きも多々あるでしょう。
遺言執行者は誰がなれるの?

法的に破産者や未成年者でなければ、誰でも遺言執行者になる資格はあります。
遺言者(被相続人)は、遺言を作成する過程で適切な遺言執行者を決めていきますが、自分亡き後に揉めることのないように配慮しなければなりません。
●長男など信頼できる相続人の一人か、財産や必要な手続きの内容によっては法の専門家である司法書士や弁護士などに依頼することになるでしょう。
※この他、遺言執行者として信託銀行に依頼する方法もあります。
さまざまな相続手続きをするため、基礎知識がない人が遺言執行者に指定されると、日々の暮らしのなかで、かなりの疲労が生じることにも配慮して決めてください。
初めてのことなので、相続財産の調査や戸籍謄本の収集に経験がなく、何からスタートしていいかわからないという方も多いです。
そのため身近に適任者がいない場合は、弁護士や司法書士などを遺言執行者に選定すると安心でしょう。
※遺言執行者を司法書士や弁護士などに依頼する場合は、下記もご参照ください。
・【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで
遺言執行者の選任の仕方
一般的に遺言執行者は、遺言者(被相続人)が遺言書により指定する他、遺言書に指定が明記されなかった場合や、遺言書自体がなかった場合には、家庭裁判所が決めることもできます。
<遺言執行者の選任>
・遺言書にて指定
・家庭裁判所が遺言執行者を決める
・遺言書にて「第三者による遺言執行者の選任」を依頼する
家庭裁判所が遺言執行者を決める場合、上記二つの他にも、遺言書で指定された遺言執行者が亡くなっていたケースにも有効です。
また遺言書による「第三者による遺言執行者の選任」依頼では、遺言者(被相続人)は、相続発生時に遺言執行者を選任してくれる第三者を指定できます。
遺言執行者になった人の仕事内容は?

遺言執行者になると、民法に基づき下記のような仕事をこなさなければなりません。
遺言執行者が仕事を怠った場合、相続人は家庭裁判所へ遺言執行者の解任を申し立てることが可能です。
※民法第1019条「遺言執行者の解任及び辞任」より
(1)遺言執行者就任の通知
(2)相続財産の調査
(3)相続人の範囲の確定
(4)財産目録の作成
(5)預貯金口座解約
(6)相続登記
(7)終了報告
遺言執行者の仕事に関しては、民法第1006条・第1007条・第1011条・1012条などで明記されています。
(1)遺言執行者就任の通知
遺言執行者になった場合、最初に行うべき事柄は、下記3点です。
・就任通知書作成と通達
・相続人の範囲の確定
・財産目録の作成
最初に行う就任通知書は、遺言書の写しとともに相続人全員に通達します。
ここから遺言執行者は(1)相続人全員の調査と戸籍などの取りまとめ、(2)相続財産の調査と財産目録の作成へと進まなければなりません。
※他の相続人とトラブルが発生したり、ひとりで進めるのが困難であれば、お金は掛かりますが司法書士や弁護士などに相談すると良いでしょう。
(2)相続財産の調査
ほとんどの遺言書には財産目録が添付されていますが、その場合でも財産目録に間違えがないか、漏れや変更がないかまでチェックが必要です。
相続分割のために相続財産の把握は必要不可欠ですが、相続放棄には期限があるため、特にマイナス財産には注意をして調査を進めてください。
●プラスの財産
・不動産
・預貯金
・現金
・有価証券
・価値のある遺品
…など
●マイナスの財産
・借金
・借金売掛金
…など
漏れのない相続財産の調査は、後々の相続税の計算や、節税対策を進める上で重要な作業になります。
(3)相続人の範囲の確定
誰が相続人になるかを特定する業務です。
遺言執行者は遺言者(被相続人)の出生~死亡まで、全ての戸籍を収集します。
勘違いする人も多いのですが、戸籍は最終的なひとつだけではありません。
●結婚などをきっかけにして、複数の自治体に戸籍が残っている人は多いです。
→これらの散らばった戸籍謄本を、出生~死亡までの経緯が分かるように揃えます。
遺言者(被相続人)の戸籍を集めて人生の流れを知ることで、相続人の範囲が確定されるでしょう。
戸籍の収集では、遺言執行者の身分証明書と遺言書が必要です。
(4)財産目録の作成
(2)相続財産の調査で相続財産のあらましが分かったら、これを財産目録にまとめ、相続人全員へ内容を送付します。
遺言執行者は財産目録の開示が義務付けられているため、この作業を怠るなどの問題が生じた場合、相続人から解任の申し立てを受けることもあるでしょう。
●また、財産目録により全ての相続財産が相続人全員に開示されるため、遺言書による遺産分割の内容などによっては、この時点で不満を持った相続人から遺留分請求(※)を受ける可能性もあります。
(※)遺留分とは、相続人それぞれが持つ、最低限の遺産分配です。
遺言書で指示する遺産分割内容が、この遺留分を侵害している場合、不満があれば相続人は遺留分請求を起こすことができます。
※財産目録の書き方については、下記に詳しいです。
・【相続対策】財産目録の書き方☆記載する5つの項目や注意点|書き進める5つのポイント
(5)預貯金口座解約
続いて行う具体的な事柄は、遺言者(被相続人)の預貯金口座を解約です。
・普通預金…解約後に解約金が相続人の口座に振り込まれる
・定期預金…名義変更をして満額まで継続させることも可能
遺言執行者はこれらの具体的な相続手続きを行う権利があり、遺贈者や全ての相続人は遺言執行者が手続きを進める際、必要書類などの依頼に協力する義務があります。
(6)相続登記
続いて相続登記です。
例えば土地や建物、車などの登記が必要な相続財産に関しては、名義変更を行います。
この手続きが「相続登記」です。
「特定財産継承遺言」が確認された場合、遺言執行者は単独で相続登記の手続きができます。
●「特定財産継承遺言」とは、ある財産を特定の相続人に継承させる旨を記した内容です。
※特に、相続人以外の第三者へ財産を譲る「遺贈」による相続登記は、遺言執行者にしか手続きができません。
また、遺言書に相続財産の処分が記されていた場合、これも遺言執行者が手続きを進めます。
ちなみに、全般的な相続の傾向として、一部で名義変更を後回しにしても法的に問題ないとして、名義変更を怠ったままのケースもありますが、今後は罰則を受けることになるので、早い段階で名義変更を行いましょう。
※相続財産の名義変更(相続登記)については下記に詳しいです。
・【不動産の相続】相続登記の義務化はいつから?相続登記を放置する3つのデメリットとは
・【不動産の相続】車や実家を相続した時の名義変更、必要書類と費用・手続き5つの手順とは
(7)終了報告
以上の相続登記や相続財産の処分まで、全ての業務が終了したら「業務報告書」の作成し、相続人全員に通知します。
最後に
以上が遺言執行者の指定(選任)と、業務内容です。
ここまで読み進めると分かるように、法的には遺言執行者は未成年や破産者出ない限り誰でも選任される可能性がありますが、専門的な作業や知識が必要であり、忙しい現代に日常生活のなかで、業務を遂行することは大変な労力を必要とします。
2019年度の法改正により、遺言執行者の業務内容、権限、立場が明瞭になったことで、一定の手順に添って進める必要性も出てきました。
また相続人が遺言執行者に選任された場合、他の相続人との感情的な対立、トラブルを招く可能性は充分にあり、後々まで遺恨を残しかねません。
このことから、現代の遺言執行者は報酬は掛かりますが、専門的な司法書士や弁護士などに依頼すると安心です。
※遺言執行者を専門家に依頼する場合の報酬などは、下記をご参照ください。
・【相続対策】遺言執行者は必要?報酬相場やメリットデメリット|依頼したい5つの事例まで
まとめ
遺言執行者の仕事内容
●遺言執行者の権限
・相続財産目録を作成、
・遺言内容の通りに相続人に分配
●遺言執行者の仕事
(1)遺言執行者就任の通知
(2)相続財産の調査
(3)相続人の範囲の確定
(4)財産目録の作成
(5)預貯金口座解約
(6)相続登記
(7)終了報告
お電話でも受け付けております















