
永代供養の費用について 費用の内訳・相場と失敗しない選び方も紹介

「永代供養の費用はいくらぐらいなの?」
「永代供養って追加費用は発生するのかしら?」
「永代供養ってお骨はどこに埋葬されるの?」
このように永代供養について疑問に思うことは多いのではないでしょうか。
この記事では、永代供養墓の種類や永代供養の費用の内訳について詳しく解説します。
この記事を読めば、永代供養がどのような供養方法でどのような人に向いているのか、永代供養にかかる基本的な費用や追加費用がかかるオプションの内容、相場などが把握できます。
また、永代供養についての基本情報がわかるため、数多くある永代供養を扱う寺院や霊園を調べる際に役立つでしょう。
そろそろ終活を考え始めている人、お墓のことで悩んでいる人は是非参考にしてください。
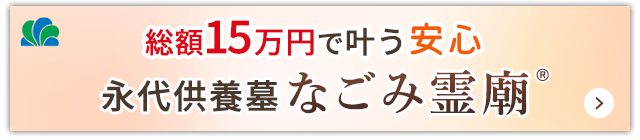
永代供養とはどのような供養方法か?

永代供養とは、お墓の管理や供養をお寺や霊園が家族に代わって行う供養方法のひとつです。
いつでも自由にお参りができ、たとえお参りに行けなくなったとしても、無縁仏や無縁墓になることはありません。そのため、後継者がいない人やお墓のことで家族に負担をかけたくない、生前にお墓を決めておきたいという人から選ばれています。
・【大阪の永代供養まとめ】勘違い「永代供養」はお墓じゃない?!最初に押さえる7つの記事
永代供養墓は永代供養つきのお墓
永代供養墓とは、お寺や霊園が永代にわたってお墓を管理、供養することを約束してくれる、永代供養がついたお墓のことです。
寺院や霊園が遺骨やお墓の管理だけでなく法要などを行うことで、お参りに来る遺族などがいなくなっても供養を行ってくれます。そのため、お墓を継承する家族がいない人や残された家族に面倒をかけたくないと思う人が、安心して利用できるお墓と言えるでしょう。
永代供養とは?費用・メリットについて
永代供養料と永代使用料は違う
永代供養料は永代供養をしてもらうために支払う費用のことで、永代使用料とは異なります。
永代使用料とは、お墓を建てたときに、霊園やお寺に支払う墓地の区画の使用料のことで、その区画を永代にわたって使用できる権利をいいます。
永代使用料はあくまでも「使用料」であるため、使用料を払ったとしても、その区画の土地の所有権が手に入るわけではないという点に注意しましょう。
永代供養についてわかりやすく紹介!費用や選び方なども詳しく説明
永代供養墓の種類・形式

永代供養墓の納骨方法には、いくつかの種類があります。
永代供養墓の種類や形式によってお墓参りの仕方などに違いがあるため、事前に親族などと話し合うと良いでしょう。
ここでは、主な永代供養墓の種類を4つ紹介します。
単独墓
単独墓はお墓を建てて、そこに遺骨を埋葬します。個別型と呼ばれることもあります。
ほかの人と同じお墓に入るのには抵抗がある、遺族がいるうちは自分のお墓に墓参りに来てほしいという人に選ばれやすいでしょう。
故人の戒名または名前が墓石やプレートなどに刻まれており、お線香やお花を供えることができます。
永代供養付きの単独墓は、通常13回忌や33回忌などの一定の期間が過ぎた後、墓じまいとなって合祀に移され、その後永代供養されます。
集合墓
集合墓とは、血縁のない複数の人の遺骨をまとめて納骨するお墓のことを言います。寺院や霊園によっては、これを永代供養墓と呼んでいる場所もあります。
骨壺や専用の袋などに入れられた遺骨は、集合墓に入り永代供養されます。
集合墓は石塔などで作られていて、お参りの時はお祈りのシンボルとして建てられた石仏やモニュメントの前で手を合わせます。
お墓を用意する必要がないため、単独墓と比べて比較的安価での埋葬が可能です。
合祀墓
合祀墓(ごうしぼ)は合葬墓とも呼ばれ、集合墓と同様に血縁のない複数の遺骨と一緒に埋葬します。遺骨は骨壺などから出されて、ほかの遺骨と合わせて埋葬します。
永代供養の遺骨は、最終的にこの合祀墓に埋葬されることが一般的です。お墓参りは集合墓と同様に、シンボルとなる石仏やモニュメントに手を合わせます。
合祀墓は、永代供養墓の中で特に費用を抑えて埋葬できる方法と言えるでしょう。
永代供養の合祀墓とは?合葬墓との違いやかかる費用、メリットもあわせて紹介
納骨堂
納骨堂は、建物の中で遺骨を保管してくれる施設のことです。寺院や霊園の中にあるものや、お墓参りの利便性のため、街中のビルの中にある場合もあります。
種類も豊富で、仏壇と遺骨安置場所が一緒になったものや、ひな壇に遺骨と位牌を並べたもの、遺骨を参拝スペースへ自動で運び出してくれるマンション型などがあります。
永代供養の場合は、期限後に合祀されるものや合祀されずにそのまま安置されるもの、安置方法の種類などで費用が変わります。
永代供養の費用の内訳と費用相場

次に、一般的な永代供養に含まれている費用の内訳とその費用の相場を紹介します。
永代供養墓のタイプや、お布施を含むか含まないかなどによって料金は変動するため、しっかりと確認していきましょう。
永代供養の費用相場は?メリット・デメリットや契約時に注意すべきことも紹介!
永代供養料
永代供養料には、お墓の管理や供養費用が含まれています。
そのため、普通のお墓を持つときに必要な年間管理料やお布施を支払う必要はありません。寺院や霊園にもよりますが、永代供養料は、一括で支払った後の費用はかからないことが多いです。
永代供養料の相場は、10万円~30万円ほどとなっています。特に気を付けたいのは、同じ価格でも供養の内容が違う場合です。含まれているサービスや供養祭の有無、納骨方法、なによりも手厚く供養できるかどうかを比較して検討しましょう。
永代供養で費用が高くなる場合は、樹木葬や一般墓の方が費用を抑えられる場合もあります。費用で迷ったときには、他の埋葬方法も検討するとよいでしょう。
納骨料
納骨料は、実際に僧侶に来てもらい、納骨法要を行う際にかかる費用のことです。納骨法要の費用の相場は5万円程度となっています。
僧侶に来てもらうため、お布施が必要になる場合があることに注意しましょう。また、別途開眼供養や年忌法要が必要な場合も、追加で費用がかかる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
プレート代・刻字料
単独墓の墓誌や集合墓、合祀墓などの礎(いしじ)に故人の戒名などを刻字してもらう際に、刻字やプレート代がかかる場合もあります。
単独墓などの墓石やプレートに刻字する場合は、石材業者を呼ぶ必要があるため、平均3万円~5万円程度の費用がかかるでしょう。集合墓や合祀墓などの礎に刻字する場合は、2万円程度になります。
永代供養に追加費用はあるのか

永代供養を決めたものの、自分が亡くなった後に親族に追加費用などの負担がかかるのではないかと、不安に思うこともあるでしょう。
ここからは永代供養に追加費用があるのか、あるとすれば、どのような場合に発生するのか解説していきます。
基本的に追加費用は発生しない
永代供養料にはお墓の永代使用や永代供養、管理料が含まれているため、基本的には初期費用以外の追加費用は発生しません。
ただし、寺院や霊園に特別な依頼をした場合は、追加費用がかかる場合もあるため、事前にどのくらいかかるのか確認すると良いでしょう。
永代供養の追加費用例
永代供養で追加費用が発生する場合、どういったところに費用がかかるのか気になる方もいるでしょう。
ここでは主な追加費用例を4つ、紹介します。
自分に必要なものか、節約できるものなのかを考えてみましょう。
お布施
お布施は読経や、戒名を授けてもらったりした際に、僧侶に謝礼として渡すお金のことです。
永代供養の場合、単独墓として建てたお墓の開眼供養や納骨の法要、7回忌や13回忌などの年忌法要で僧侶を呼んだ場合にお布施が必要になります。
また、仏様の弟子となるための名前である戒名を付けてもらった際も、戒名料と合わせてお布施が必要になるでしょう。
墓石代
合祀墓や集合墓などのお墓に入らずに、単独墓での埋葬を希望する場合は、一般のお墓と同様に墓石が必要になるため、追加の費用がかかります。
墓石は材質などによって値段が変わるほか、大きさや形は様々です。こだわりがない場合は、安価なものを選ぶことで、追加費用を抑えられるでしょう。
年間管理費・維持費
基本的に、年間管理費と維持費は永代供養料の初期費用に含まれる場合が多いですが、まれに追加費用として必要な場合があります。
また、生前に永代供養を契約した場合、契約者の生存中は維持管理費がかかる場合もあります。もともと年間管理費のかかるお墓に、永代供養をオプションとして加えた場合などにも、維持管理費がかかる場合があるため、注意しましょう。
永代供養でも管理費はかかるのか?支払うケースや支払う人について紹介!
会場使用料
納骨式の法要や年忌法要などで会場の法要室(斎場)を使う場合、追加で会場使用料がかかります。寺院などの菩提寺で法要を行う場合も、本堂使用料などがかかる場合があります。
自宅で法要を行えば会場使用料はかかりませんが、霊園や寺院で行う場合は、パッケージで葬儀から法要まで一括で行える場合もあります。
ただし、納骨式などの法要は必ず行う必要はないため、予算や労力などを考えて決めると良いでしょう。
永代供養のメリットとデメリット

永代供養が自分や遺族に合ったものなのかどうか、迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、永代供養のメリットとデメリットを紹介します。永代供養を選ぶ際の参考にしてください。
永代供養のメリット
永代供養のメリットは、「供養・管理をしてくれる」「費用が安い」「宗派・宗旨を問われない」という点があげられるでしょう。
寺院や霊園がお墓の管理や供養を行ってくれるため、後継者がいない人はもちろん、残された家族に負担がかかりません。また、合祀墓などのお墓に入れば墓石などの購入が不要のため、費用を抑えることが可能です。
永代供養の場合、宗派・宗旨を問わず受け入れてくれる寺院や霊園も多い点も、メリットと言えるでしょう。
永代供養のデメリット
永代供養のデメリットは「遺骨を取り出すことができない」「親族の理解を得にくい」などがあげられます。
特に合祀墓に埋葬された場合は、ほかの遺骨と混ざってしまうため、お墓を移したいと思っても遺骨を取り出すことは不可能です。
家族や親族の中には、一般的なお墓と違って遺骨を血縁のない人と一緒に埋葬することに、抵抗がある人も少なくないでしょう。事前に話し合いをして、自分の思いをしっかり理解してもらってから決断することが大切です。
永代供養墓の失敗しない選び方

永代供養墓を選ぶ際は、永代供養料の供養内容、管理内容をしっかりと確認しましょう。
永代供養は基本的に1遺骨のみの供養のため、墓じまいをして複数の遺骨を永代供養するときは、永代供養料が高額になる場合もあります。
中には夫婦で入れる永代供養墓や、3世代まで入れる永代供養墓などもあります。永代供養を行っている寺院や霊園によって、費用や管理内容は様々であるため、できるだけ多くの寺院や霊園のプランをリサーチすると良いでしょう。
永代供養は追加費用の有無なども確認して自分に合った方法を選ぼう
永代供養とはどういうものかをはじめ、永代供養の費用の内訳や追加費用について、詳しく解説してきました。
永代供養は、自分が亡くなった後に残された人に負担がかからないように、あらかじめ追加費用などを確認して、支払えるものは先に支払っておくことも可能です。
現在は様々な永代供養の選択ができるため、自分の希望に合った永代供養の方法を探しましょう。
お電話でも受け付けております















