
【2023年最新版】暦年贈与がなくなるとは?今後の生前贈与|名義預金とされない対策
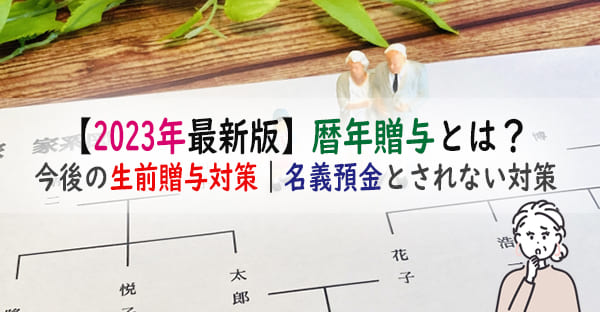
・暦年贈与とは?
・暦年贈与がなくなるって本当?
・2024年以降の税制改正で変わったことは?
・2024年以降の暦年贈与対策は?
・暦年贈与を名義預金と疑われない対策は?
「暦年贈与」とは、贈与税の非課税枠を利用して、毎年少しずつ財産を贈与する生前贈与です。
けれども2024年から施行される税制改正により、「暦年贈与は相続税対策の生前贈与にならない」と言われています。
本当でしょうか?
本記事を読むことで、暦年贈与とは何か?2024年以降の税制改正における暦年贈与対策や、以前から言われる「名義預金とされない」対策が分かります。

「暦年贈与」とは

◇「暦年贈与」とは、毎年控除される贈与税の非課税枠を利用して、少しずつ財産を贈与することです
2023年現在、贈与税の非課税枠は年間110万円(元旦~12月31日)と設定され、暦年贈与では毎年この非課税枠内で少しずつ財産を贈与します。
相続税対策の生前贈与として、相続発生時に相続財産を減らす、子どもや孫に財産を譲るための対策とされてきました。
| <暦年贈与の進め方> | |
| [生前] | ①受贈者名義の口座を新設 ②非課税枠内で毎年振り込み (贈与税が掛からない) |
| [相続発生後] | ③相続財産が軽減する (相続税額が軽減する) |
一般的な非課税枠を利用した生前贈与は、孫やひ孫への教育資金一括贈与、最大1,500万円までや、結婚・子育て一括贈与、最大1,000万円までの対策があります。
このように比較すると、暦年贈与は毎年少しずつ非課税枠で贈与を続ける、時間が掛かる生前贈与です。
・【2023年相続税】生前贈与のやり方とは?廃止になる?教育・子育て資金は延長する?
「暦年贈与がなくなる」とは?
◇2022年の税制改正で、暦年贈与の廃止は見送られました
2024年以降、暦年贈与がなくなると噂された理由は、2020年12月に発表された「税制改正大綱」の記述です。
国民の財産が平等に移行されるよう、中立的な相続税や贈与税の改正を検討すると書かれています。
2022年12月16日の「税制改正大綱」で見送られた理由は、想像ながら下記のような背景が想定できるでしょう。
・暦年贈与が国民に浸透している
・増税と勘違いする可能性
・不公平を感じる可能性
その昔から親や祖父母が子どもや孫名義の口座を作り、毎月地道に貯蓄を続ける習慣がありますよね。
けれども今後は、贈与税の非課税枠が廃止され、暦年贈与が相続税対策として意味を持たなくなる可能性は否めません。
・国税庁「令和5年度『相続税及び贈与税の税制改正のあらまし』」
2024年の税制改正で、暦年贈与の影響とは

◇2024年以降、生前贈与の持ち戻し期間が7年間に延長されます
2024年1月1日以降から施行される税制改正で、暦年贈与が最も影響を受ける改正は、「相続財産の持ち戻し」です。
正確には「生前贈与加算期間」と言います。
●相続人や遺贈者が生前贈与を受けていた場合、過去に遡って贈与を受けた財産を、相続財産に加算することを差します。
相続税対策の軸は、生前に財産を減らして相続財産に掛かる相続税を軽減するため、相続財産の持ち戻し期間が延長されることにより、相続税は高くなるでしょう。
特に暦年贈与で少しずつ生前贈与を続けてきたケースでは、3年分330万円の生前贈与の持ち戻しから、7年分770万円まで相続財産に加算される計算です。
2031年までは段階的に延長されます
◇生前贈与の持ち戻し対象期間は、2026年6月までは3年です
2024年1月1日より施行されるため、当面3年間にあたる2026年までは、実際的に生前贈与の持ち戻し期間は3年間となり、変わりません。
2027年6月以降、半年ずつ段階的に延長されていくでしょう。
| <段階的な生前贈与の持ち戻し期間> | |
| [年度] | [生前贈与の持ち戻し] |
| [2023年6月] | ・3年 |
| [2024年6月] | ・3年 |
| [2025年6月] | ・3年 |
| [2026年6月] | ・3年 |
| [2027年6月] | ・3年6ヶ月 |
| [2028年6月] | ・4年6ヶ月 |
| [2029年6月] | ・5年6ヶ月 |
| [2030年6月] | ・6年6ヶ月 |
| [2031年6月] | ・7年 |
2023年12月31日までに行った生前贈与に関しては、2024年1月1日以降の新税制法に適用しないため、2023年までは現行通りです。
2024年以降、暦年贈与を続けるには?
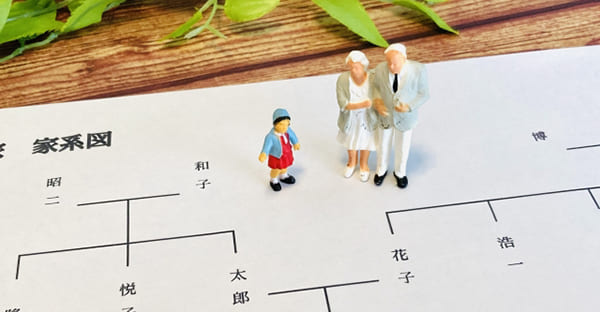
◇生前贈与の持ち戻し対象者は、相続や遺贈で相続財産を受けた人です
生前贈与の持ち戻しは、過去に遡り相続発生時に相続財産に加算するため、基本的に相続財産を受け取った人に適用します。
そのため、そもそも相続財産を受け取らない、法定相続人に当らない人々への贈与は、2024年以降の法改正の対象外です。
| <2024年以降の暦年贈与> ●相続財産を受け取らない人へ贈与する |
|
| [受贈者] | ・孫 ・嫁 ・婿 ・相続放棄した人 …など。 |
| [注意点] | ・生命保険の受け取り人ではない ・遺贈者ではない |
「受贈者」とは、暦年贈与を受けた人です。
相続財産を受け取っていない人に相続税は掛かりませんので、相続放棄をした人も、2024年以降の暦年贈与で、持ち戻し対象になりません。
ただし法定相続人ではなくても、生命保険の受け取り人や、遺言によって相続財産の一部を受け取った「遺贈者」は、生前贈与の持ち戻しが適用されます。
暦年贈与が名義預金と疑われる?

◇暦年贈与は受贈者名義の口座を開くため、名義預金と疑われることがあります
「名義預金」とは、口座の名義人とお金の主が異なる預金です。
前述したように、両親や祖父母が子ども名義で口座を作り、貯蓄をしていた場合には、名義預金と判断されます。
名義預金の申告漏れが起きた場合、「過少申告加算税」の支払い義務が生じます。
名義預金は時に故意の資産隠しとも判断されるため、追徴課税の負担は大きくなるリスクがあるでしょう。
| <名義預金の申告漏れと判断されたら?> | |
| [ペナルティーの種類] | [税率] |
| ①過少申告重加算税 (申告あり) |
…原則35% |
| ②無申告重加算税 (申告なし) |
…原則40% |
| ③延滞税 (法定納付期限の翌日以降) |
…2ヶ月まで7.3% (軽減税率あり) …2ヶ月以降14.6% (軽減税率なし) |
「過少申告加算税」もありますが、いずれにしても名義預金と判断され、相続財産の申告漏れと判断された場合には、重いペナルティーが掛かることが分かります。
親が子どもの名義預金で貯蓄した場合、親が亡くなると親の相続財産として申告をしなければなりません。

暦年贈与を名義預金とみなされないためには?
◇暦年贈与で利用する口座は、受贈者が管理をすることです
暦年贈与を受ける受贈者が新規口座を開設し、授与者は口座に振り込む形で、暦年贈与を行います。
税務署が悪質と判断した名義預金では、例えば北海道や沖縄など、居住区域ではない地方銀行に口座を新設し、多額の遺産を一度に預金するケースが多くありました。
当然、多くの名義預金の名義人は、口座の存在を知りません。
①名義人が預金口座を開設する
②名義人が通帳と印鑑を管理する
③暦年贈与は振り込みで行う
④贈与契約書を作成する
⑤贈与税の申告をする
暦年贈与を名義預金とみなされないためには、口座の管理を受贈者である名義人が行うことです。
名義預金は、そもそも名義人が口座の存在を知らないことも少なくありません。
受贈者本人が口座を管理し、贈与者と受贈者間で「贈与契約書」を交わしましょう。
暦年贈与を証明するポイント
◇暦年贈与の口座は、名義人がお金を出し入れすると良いでしょう
さらにお金の主が贈与者ではなく、受贈者である名義人であると証明するために、暦年贈与で使用する口座は、定期的にお金を出し入れして利用します。
| <暦年贈与を証明するポイント> | |
| ①口座を使う | …定期的に名義人がお金を出し入れする |
| ②贈与税を納税する | …敢えて贈与税の非課税枠110万円以上を贈与し、差額分の贈与税を支払う |
| ③暦年贈与を申告する | …名義預金と指摘を受ける前に、暦年贈与(受贈財産)と申告する |
敢えて贈与税を支払い、受贈財産であることを主張する方法は躊躇する人も少なくありません。
確かに非課税枠を利用しない限り、贈与税は相続税よりも高くなるでしょう。
けれども年間の贈与額合計が120万円であれば、非課税枠110万円との差額は10万円、子どもに適用する特例贈与の税率は、200万円以下で10%として、1万円前後です。
・【2023年相続税】生前贈与のやり方とは?廃止になる?教育・子育て資金は延長する?
まとめ:暦年贈与は名義預金ではありません

暦年贈与も受贈者名義の口座を新設し、贈与者が地道に振り込む形式を取るため、なかには「名義預金になるのでは?」と不安の声もあります。
けれども暦年贈与は、名義人が口座を管理し、適切な証明が成される限り、暦年贈与として相続財産に含まれません。
ただし2024年以降、生前贈与が相続財産に加算される「生前贈与の持ち戻し」期間が3年間~7年間に延長されます。
2024年以降に暦年贈与を検討するならば、法定相続人や遺贈者に当らず、財産を受け取らない孫や嫁、婿などを対象に行うと良いでしょう。
お電話でも受け付けております















