
お墓の継承とは?継承者の順位とは、誰がなるの?継承者の役割とは?継承の手続きや費用
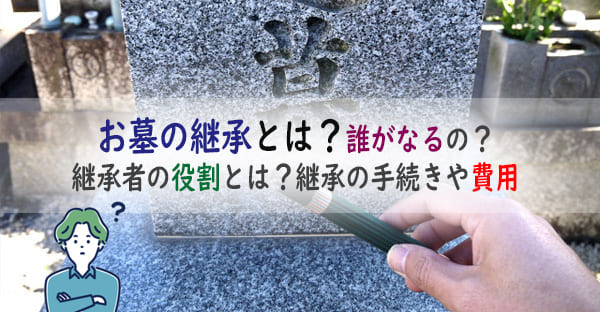
・お墓の継承とは?
・お墓の継承者は誰がなるの?順位とは?
・お墓を継承した時の役割は?
・お墓を継承する手続きは?
・お墓を継承すると掛かる費用は?
「お墓の継承」とは、祭祀継承者になることです。
家族が亡くなると相続問題もありますが、お墓や仏壇などの継承者問題も生じます。
本記事を読むことで、お墓の継承をする人は誰か?「順位」や、継承者4つの役割、経書の手続きや、お墓を継承したら掛かる費用をお伝えします。

お墓の継承とは

◇お墓を継承することは、祭祀財産全てを継承する「祭祀継承者」になることです
「祭祀財産(さいしざいさん)」とは、お墓や仏壇・家系図など、ご先祖様や故人の供養や管理にまつわる財産を差し、相続税は掛かりません。
お墓を含めた祭祀財産の一切は、一人が継承すると定められています。
| <お墓の継承|祭祀財産とは> | |
| [祭祀財産の種類] | [例] |
| ①墳墓 | ・お墓 ・墓地 ・墓碑 |
| ②祭具 | ・位牌 ・仏壇 ・神棚 ・御本尊(仏像) |
| ③系譜 | ・家系図 (血縁関係の図表) |
これらの祭祀財産を、お墓の継承者は全て引き継がなくてはなりません。
一方でお墓の継承をした「祭祀継承者」は、家のご先祖様や故人の供養について、決定権を持ちます。
お墓継承の特殊性
◇お墓など継承した祭祀財産は、相続とは関係がありません
お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産に含まれないため、お墓や仏壇を継承したからと言って、遺産を相続する取り分「遺留分」に影響がないでしょう。
一方で、お墓や仏壇を継承して負担が大きくなったからと言って、遺産が多く分けられる訳でもありません。
| <お墓継承の特殊性> | |
| ①遺産(相続財産)に影響しない (民法897条1項) |
・祭祀財産に該当 ・遺留分に影響しない ・相続放棄と関係がない |
| ②相続税が掛からない (相続税法12条1項2号) |
・祭祀財産は非課税枠 (骨董品的価値などあるものは除く) |
お墓を継承しても相続財産ではないので、当然相続税も掛かりません。
ただし相続放棄にも対応しない点は覚えておきましょう。
お墓の継承は、故人(被相続人)に指定されたら避けることができません。
けれどもお墓の継承後、墓じまいをするか、維持管理をするかの判断は自由です。
お墓の継承者は誰がなるの?

◇故人(被相続人)から指定があれば、その人はお墓の継承者です
お墓の継承者として、最も優先順位が高い人が故人(被相続人)から指名を受けた人となり、故人(被相続人)からの指名は遺言書でなくとも構いません。
例えば、エンディングノートや口頭での指名でも、同席し証明できる人がいれば成り立ちます。
①故人(被相続人)からの指名
②慣習に倣う
(親族間での話し合いで決める)
③家庭裁判所への調停裁判
前述したように故人(被相続人)によるお墓の継承者指名は絶対ですが、指名がなければ地域の慣習にならい決めるでしょう。
ただし遺産分割を法定相続人全員で決める「遺産分割協議」において、お墓の継承者が決まり全員が同意したならば、その人がお墓の継承者です。
①故人(被相続人)からの指名
◇遺言書やエンディングノートで指名されていることが多いです
生前にお墓の継承について、故人から打診がなければ、エンディングノートなどでお墓の扱いについて、何か補足があるのではないいでしょうか。
・お墓の継承は避けられない
・お墓の継承後、墓じまいは可
基本的に祭祀で揉めることのないよう、祭祀継承者は1人と定められていますが、再婚したケースなど、事情によっては複数の箇所にあるお墓の継承を、数人が担う判断もあります。
②慣習に倣う
◇故人(被相続人)から指名がない場合、地域の慣習に倣います
ただ法定相続人間全員で同意があれば、慣習に倣わずともお墓の継承者を決めることはできるでしょう。
地域や家によって慣習は違いますが、一般的には下記の順位でお墓を継承します。
①長男(嫡男)
②配偶者
③両親
④兄弟姉妹
⑤その他の親族
昔ながらの慣習では、長男(嫡男)がお墓を継承し、次男以降は家族を作ると新しくお墓を建てる仕組みです。
ただし独身の次男以降の兄弟姉妹など、お墓を継承した人が許可を出すならば、誰でもお墓に入ることができるでしょう。
③家庭裁判所への調停裁判
◇家族親族間でお墓の継承者を決めなければ、家庭裁判所が選びます
これは遺族による「祭祀継承者を定める審判申し立て」です。
また、家庭裁判所が適したお墓の継承者を決める時にも、一定の基準があります。
●家庭裁判所の判断基準
・故人(被相続人)との関係性
・祭祀主催者としての意思・能力
・生前に故人と交流していたか
・お墓から近いのか
・お墓や仏壇を継承する前の管理状況
(現在のお墓や仏壇の管理状況)
家庭裁判所によりお墓の継承者を決める時には、調停・審判の2つの選択肢があるでしょう。
ただしお墓の継承は遺骨の維持管理など負担も大きなものですが、家庭裁判所まで持ち込みは避け、相続人間で解決するのが理想的です。
お墓の継承者の役割は?

◇お墓を継承した祭祀継承者は法要の主催、施主としての役割があります
お墓を継承した人は必然的に、家の法要に関する全てを請け負うため、法要の施主としての役割の他、お墓の維持管理が伴います。
| <お墓の継承者の役割は?> | |
| [役割] | [内容] |
| ①お墓の維持管理 | ・お墓掃除 ・お墓の名義変更 ・年間管理料の支払い |
| ②施主(法要を執り行う) | ・法要の主催 ・僧侶をお呼びする ・親族へご案内する |
| ③遺骨やお墓の決定権 | ・墓じまい ・遺骨の行方 ・供養の仕方 |
以上3点です。
「遺骨やお墓の決定権」とは、例えば「墓じまいをして遺骨を取り出し、合祀墓に埋葬する」など、お墓や遺骨に関する最終的な決定権を持っていることです。
ただしお墓の継承者であっても、故人に対する思いはそれぞれですので、強行突破するのではなく、事前に家族や親族から同意を得ると良いでしょう。
年忌法要は必要?
◇年忌法要ではお布施やお斎代金が掛かります
ただ一方で御香典など、相互扶助があるでしょう。
僧侶へのお布施も1万円~3万円、会場代や御香典返し、お斎の手配などがあります。
| <年忌法要の進め方> | |
| ①僧侶の手配 | |
| [お布施] | |
| ・読経供養のお礼 | ・約1万円~3万円/1回 |
| ・御車代(出張の場合) | ・5千円ほど |
| ・御膳代(会食に欠席) | ・5千円ほど |
| ②会場 | ・3千円~1万円ほど |
| ③お斎 | ・千円~3千円/1人 |
| ④香典返し | ・千円~3千円/1人 |
| ⑤お供え物 | ・5千円~2万円 |
…などなどの費用が掛かります。
それぞれに法事の規模や弔問人数、地域によって費用目安には幅がありますので、ご了承ください。
減少する法要
◇高齢化により、法要を執り行う家も減少傾向です
超高齢化社会なので、80代・90代で亡くなると、その子どもも60代・70代です。
33回忌法要になると、本人も90代100歳以上と、亡くなっている方も多く、故人と近しい親族は少なくなりました。
| <お墓の継承|法要は減少傾向> | |
| [選択肢] | ・法要を執り行わない ・十三回忌・十七回忌に弔い上げ |
故人と思い出を共有する者が少なくなると、年忌法要に意味を見出せない方も少なくありません。
お墓を継承する手続きは?

◇墓地(霊園)管理者に報告し、名義変更を行います
お墓を継承する手続きは、お墓の名義変更です。
まず墓地(霊園管理者)に、名義人が亡くなったことを報告すると良いでしょう。
基本的には墓地(霊園)が主導して話を進めてくれるでしょう。
| <お墓を継承する手続き> | |
| [用意する書類] | ・名義変更届 ・墓地使用許可証 (永代使用許可証) ・継承者の住民票 ・継承者の戸籍謄本 ・故人の戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・遺言書、事由書 |
| [お墓継承の手続き] | ・墓地(霊園)に報告 ・必要書類の準備 ・必要書類の提出 (手数料) |
以上の流れです。
相続財産ではなく相続税も掛からないため、必要な手続きは簡単です。
ただし墓地(霊園)によっては、お墓を継承できる人を定めているので注意をしてください。

お墓を継承して掛かる費用は?
◇墓地(霊園)管理施設へ年間管理料を毎年支払います
公共部分は年間管理料によって、施設管理者が維持管理を行いますが、お墓の区画は、継承者が掃除やメンテナンスを自費で行うでしょう。
墓地内のお墓の数や施設の状態によって、年間管理料の金額幅は広いです。
| <お墓の継承で掛かる費用|年間管理料> | |
| [年間管理料の目安] | ・約3千円~2万円ほど |
| [特徴] | ・公営墓地では割安傾向 ・お墓の数が少ない墓地 (一人分負担が高い傾向) ・区画が広いほど割高 ・ガーデニング型墓地は割高 |
ガーデニング型墓地とは、近年お墓で人気のスタイルです。
墓地全体が花々が咲き誇る美しい庭園のように維持管理された墓地を差します。
ガーデニング型墓地では日々植物の植え替えやメンテナンスが必要なので、その分年間管理料も高くなる傾向です。
また寺院墓地でのお墓の継承は、説法を聴く「彼岸会」の集会に参加するなど、義務が生じたり、その度にお布施を支払う可能性もあります。
近年では宗旨宗派不問の民営墓地が広がっています。
対応するように寺院墓地の在り方も急速にかわっているでしょう。
年々と決まり事も緩くなってはいますが、予め確認をしておくと安心です。
お墓掃除の費用負担
◇お墓を継承すると、定期的なお墓の掃除やメンテナンスも必要です
特に遠方に住んでいる人がお墓を継承すると、「お墓参り(掃除)のために定期的に家族で帰省をしなければなりません。
・家族分の交通費
・家族分の宿泊費
遠方にお墓がある場合、「お墓参り代行サービス」も利用できます。
お墓を訪れお花を添えるなど、基本的なお参りであれば2万円/回ほどです。
お墓掃除も目的とした依頼では、オプション料金も提示されています。
| <お墓参り代行サービス> | |
| [基本のお墓参り] | ・約1万円~2万円 |
| ・献花やお供え物 | ・プラス3千円~5千円 |
| ・墓石クリーニング | ・プラス2万円ほど |
| ・墓石コーティング | ・プラス5万円ほど |
墓石コーティングはそんなに頻繁に依頼するものではありませんが、お墓参り代行ではお供えや献花も行って欲しいところですし、丁寧なクリーニングも依頼したいですよね。
そう考えると、遠方にあるお墓参りを代行してもらうとしても、それなりの費用になると言えます。
まとめ:お墓の継承をすると祭祀継承者になります

お墓や仏壇の継承は相続する遺産とは関係のない「祭祀財産」ですので、お墓を継承すると、ご先祖様の供養や遺骨の決定権を持つ、祭祀継承者となります。
祭祀継承者としてお墓の維持管理、遺骨の扱い、法要の主催などの責任を負うことになるでしょう。
ただ忙しい現代では、お墓の継承を負担に思う人も少なくありません。
お墓の継承は相続放棄をしてても逃れられませんが、継承後の墓じまいは可能です。
現代は「墓じまいパック」を提供する業者も多いため、賢く利用してはいかがでしょうか。
・墓じまいとは?やることは?「墓じまいパック」費用目安や納骨先、提供業者の種類とは?
お電話でも受け付けております















