
【大阪のお墓】建立者名は掘らなきゃダメ?複数の建立者を彫るなど、3つの疑問に回答!
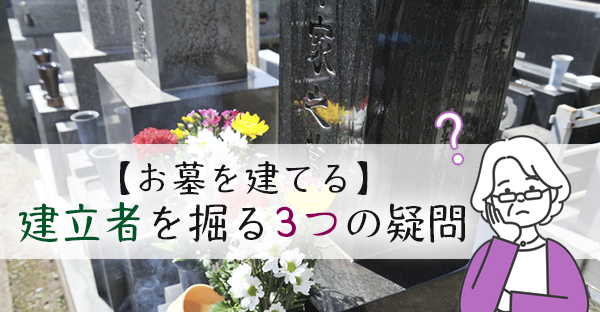
大阪ではお墓の建立者を墓石に掘りますが、なかには複数で建墓費用を出し合ったため戸惑ったり、「自分の名前なんて掘りたくない!」などの相談もあります。
ただ結論から言うと、必ず掘らなくてはならない訳でもありません。
特に大阪のお墓では兄弟が建立者であることが多く、迷う声が多い傾向です。
今回は、大阪のお墓で建立者名の彫刻に迷う人に役立つ、建立者名を必ずしも彫る必要がない理由と、建立者が複数人いた場合の対処法をお伝えします。
【大阪のお墓】建立者名は掘らなきゃダメ?複数の建立者を彫るなど、3つの疑問に回答!
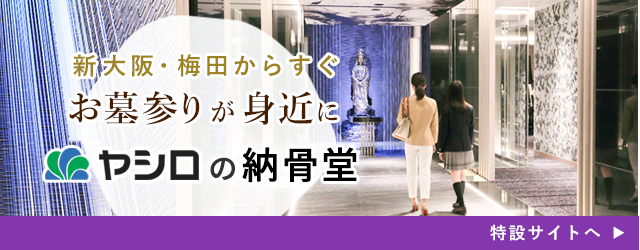
建立者とは?

大坂でお墓に掘る「建立者」とは仏教とは関係なく、お墓を建てた人の名前です。
大坂のお墓では、側面に建立者を建立した日付とともに彫刻します。
大坂のお墓ではこの「建立者」と「生前戒名」だけが、生きている人が掘られる名前です。
(1)生前戒名
・生前に戒名を与えられる
・仏教の教えでは仏門に入ったことになる
(2)建立者
・お墓を建てた人の名前
・仏教とは関係がない
今でこそ戒名は人が亡くなった時に授かりますが、もともとはその仏教の信徒になった時に授かる名前であり、仏様の弟子であることを表します。
そのため生前戒名は仏教と深い関わりがあり、お墓には名前を掘らなくてはならない、とされてきました。
けれども大阪のお墓で掘る「建立者」については仏教と関係がありません。
そのため、大阪でお墓を建てたものの、建立者として彫刻されるのは、何らかの事情で避けたい場合、名前を刻まなくても良いとされます。
あくまで個人の自由です。
事例としては「不気味だからお墓に自分の名前を掘りたくない」と、大阪ではお墓に建立者名を彫らない決断などがありました。
・【大阪のお墓】建墓で行う「建碑祝い」は改葬でも渡すの?改葬時のお祝い金3つのケース
建立者名は複数でも彫刻できるが…
大坂のお墓では建立者名の他、故人の戒名なども彫刻されますよね。
右側には故人の戒名・没年月日・享年が刻まれ、大阪のお墓で建立者は裏側です。
・お墓の正面…「○○家之墓」「南無阿弥陀仏」「絆」など
・向かって右側…故人の戒名・没年月日・享年
・お墓の裏側…建立者・設立年月日
前述したように基本的に仏教の教えと、大阪のお墓に建立者の名前を彫刻することは、何の関係もないため、その規則はほとんど自由です。
一基の墓石費用を兄弟で分割にした場合は、建立者名を連名することもあるでしょう。
けれども将来的な事柄を考えると、子々孫々の後世まで大阪のお墓では建立者名が残るため、お墓を継承する継承者一名の名前を彫ることをおすすめします。
お墓の継承トラブル事例も多い
日本の法律において、供養のトラブルを防ぐため、お墓やお仏壇など祭祀財産(さいしざいさん)の継承者は一人と定められてきました。
今、生きている兄弟は口約束でお互いに理解し合っていても、将来的な子や孫の代において、お墓の継承者で揉める可能性が出てくるためです。
実際にはお墓やお仏壇などのご先祖様の供養に用いる「祭祀財産(さいしざいさん)」は、相続ではなく「継承」です。
●現代の大阪では、メリットが少なく負担が多いとして、「お墓を継承したくない」と考えている人も少なくありません。
大阪のお墓で彫刻されている建立者が一名であれば、その家の者が代々継承し、お墓の維持管理への負担が大きくなった時には、墓じまいなどの選択もできる権限を持ちます。
けれども複数の建立者がいた場合、継承者が曖昧になるでしょう。
今は「お墓の譲り合い」トラブルが多い
ちなみに、ひと昔前の大阪では、お墓の建立者は家督全てを受け継ぐとされてきたため、お墓の取り合いが多くありました。
けれども最近では、法的に遺留分があるため、祭祀財産を継承したからと言って、相続する財産が増える訳ではありません。
そのため現代の大阪では、お墓の押し付け合いトラブルがほとんどです。
このような大阪のお墓トラブルを回避するために、事前に下記のような事柄を検討してください。
・お墓の管理はどうするのか?
・所有者が誰であるか
…そして、大阪のお墓を建てた時の「建立者」は、1名に絞って決めると良いでしょう。
・【大阪の終活】夫婦で入るお墓「夫婦墓」の費用相場☆継承者がいなくても建墓はできる?
建立者名に対する3つの質問に回答!

それでは現代、大阪のお墓で建立者を彫る際に多い相談や質問はどのようなものがあるでしょうか。
(1)必ず掘らなきゃいけないのか
(2)複数人の名前を掘ってもいいのか
(3)建立者名を掘る順番は決まっているのか
…それでは、それぞれ回答していきます。
(1)必ず掘らなきゃ行けないのか
必ず掘らなきゃ行けないということはありません。
一般的に大阪のお墓で建立者を彫刻する目的は、後々お墓を受け継いだ人が「このお墓は、いつ頃建ったお墓なのか?」を知るためです。
後々の墓主は、この建立年月日と建立者名を基に、お墓のリフォームを決めます。
(2)複数人名前を掘ってもいいのか
建立者の彫刻と仏教の教えとは関係性がないこと、法的にも建立者名を連名で掘っても問題はないことから、複数名の建立者を彫刻しても構いません。
●ただしお墓の名義人は1人と限られています。
家族内でよく話し合い、決めるようにすることが望ましいです。
実際にお墓は何十万、何百万とするため、兄弟で建墓費用を出し合い建立することが多く、複数の建立者名を彫っているお墓は多いでしょう。
心配事があれば、お寺や霊園に直接相談してください。
(3)建立者名を掘る順番は決まっているのか
大坂のお墓で建立者名を連名で彫刻する場合、一般的に名前を彫る順番は、相続する順番が多いです。
例えば父親が亡くなり、先祖代々墓を親族間でお金を出し合い建てた場合、下記の順番になるでしょう。
●父親が亡くなり、先祖代々墓を建てた場合、
(1)配偶者
(2)子
(3)直系尊属(祖父母)
(4)兄弟
…このようになり、結果的には年齢を重ねた人から順番に掘ることが多く、「亡くなる順番」と言うひともいます。
また大阪のお墓のなかには、建立者名を建墓費用を出した金額の順番で掘る家族もいますが、仏教的な意味合いは建立社名の彫刻にはないので、その順番でも構いません。
最後に
今回は、大阪のお墓で裏面に掘る建立者名について、多い相談や質問について回答しました。記事をまとめると、回答は下記になります。
・建立者名は掘らなくても良い
・建立者名は複数人掘っても良い
・建立者名の掘る順番は相続の順番
今では一定年数が過ぎると契約更新がない限り、墓じまいが行われ、ご遺骨は墓地内の合祀墓に埋葬される形式を持つ、永代供養墓も増えました。
そのため、継承者を必要としないお墓が広がったことで、必ずしも建墓時に建立年月日や建立者名を彫らないお墓も増えています。
菩提寺から離檀して無宗教になる家も増え、家や形式よりも、心の供養としてお墓が広がっているため、大阪のお墓では建立者名のないお墓も増えました。
・大阪でお墓を建てる予算はどれくらい?墓地代・墓石・年間使用料まで建墓費の内訳を解説
・お墓がない場合に選ぶ3つの葬送。建墓だけじゃない!予算で選ぶお墓を持たない葬送とは
まとめ
建立者名に多い質問に回答!
●連名で掘っても良いが、継承トラブルまで配慮する
・建立者名は掘らなくても良い
・建立者名は複数人掘っても良い
・建立者名の掘る順番は相続の順番
お電話でも受け付けております















