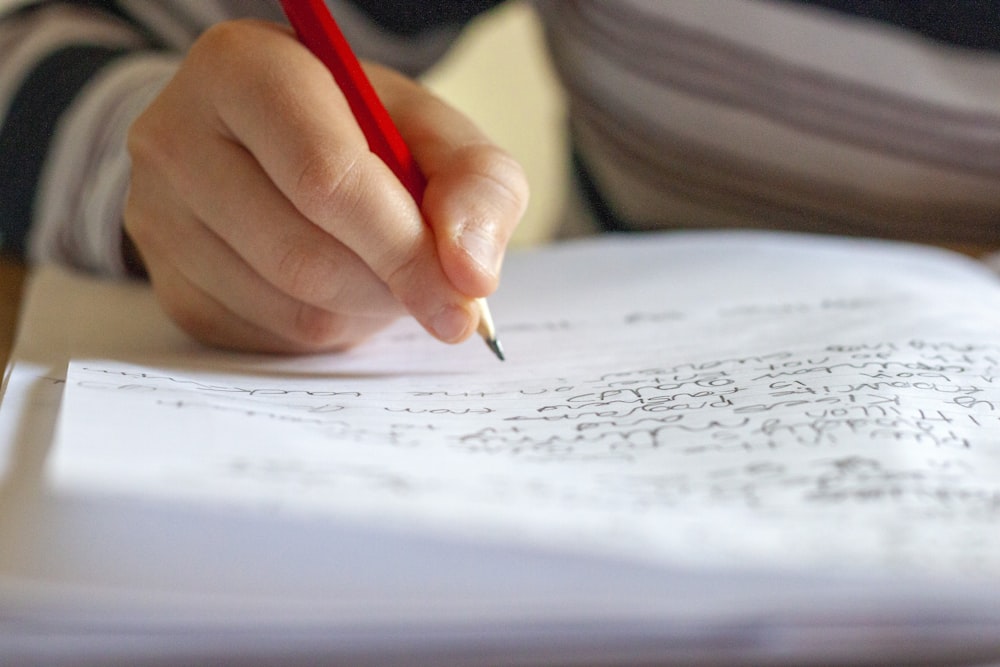子どもがいない夫婦の相続人は誰?遺言書や遺留分についての注意も解説

「子どもがいない夫婦の場合、相続ってどうすればいいの?」
「子どもがいない夫婦の法定相続人や法定相続分の割合が知りたい」
「起こりえるかもしれない相続トラブルや注意点、トラブル回避の方法を教えてほしい」
このように、子どもがいない夫婦の中には相続問題に対しての疑問や不安を抱えている人もいるのではないのでしょうか。
本記事では、子どもがいない夫婦の相続に関して法定相続人や法定相続分の割合を解説するとともに、起こりえるトラブルとその回避方法、遺言書や遺留分についての注意点を解説します。
この記事を読むことで、子どもがいない夫婦の相続に関する知識を身につけることが可能です。その知識を元に、実際に相続問題が発生した時にスムーズに対応することができるでしょう。
子どもがいない夫婦で相続に関する悩みを抱えている人は、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。
子どもがいない夫婦の相続はどうなる?

一般的に夫婦の相続は、残された配偶者と子どもがいる場合は子どもも対象となるケースが多いです。そのため子どもがいない場合、配偶者だけが全て相続できるのではないかと思われがちですが、実はその限りではありません。
これは亡くなった配偶者の両親または兄弟姉妹がいる場合は、彼らも相続人として遺産を受け取る権利が発生するからです。このような点から、子どもがいない夫婦の場合でも、配偶者以外に法定相続人がいるのであれば、全て配偶者が相続できない可能性が出てきます。
子どもがいない夫婦の法定相続人は誰になる?

子どもがいない夫婦の法定相続人は、存命している側の「配偶者」、亡くなった人の親や兄弟姉妹などの「血族相続人」の2種類になります。
基本的には配偶者が存命している場合、必ず配偶者は法定相続人として遺産を受け取ることができ、親や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥や姪が法定相続人となる可能性があります。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
配偶者
夫婦のどちらかが亡くなった際、配偶者が生きている場合は必ず相続人となります。基本的に法定相続人として第1に挙げられるのは子どもですが、子どもがいないとその次に法定相続人としての順位が上である配偶者が優先されるのです。
とはいえ、子どもがいる場合でも法定相続人ではあるので、配偶者は子どもの有無にかかわらず法定相続人として遺産を受け取れる立場にあります。
血族相続人
血族相続人とは、簡単に言えば亡くなった人と血のつながりがある相続人のことを指します。血族相続人には大きく分けて以下3つの種類があります。
・「直系卑属」 例、亡くなった人の子や孫などが含まれる
・「直系尊属」 例、親や祖父母など
・「傍系の血族」 例、兄弟姉妹や甥・姪など
子どもがいない夫婦の場合は、親や兄弟姉妹を基本として、祖父母や甥・姪などが血族相続人として相続対象に入る場合があります。
血族相続人には優先順位がある

子どもがいない夫婦の場合は、配偶者と亡くなった人の親・兄弟姉妹などの血族が法定相続人とされています。
ただ法定相続人には優先順位があり、配偶者が血族相続人よりも優先されるのと同じように、血族相続人の中でも優先順位が決まっているため、高い順位の人が亡くなっている・相続放棄した場合は、次の順位の人が相続人となります。
ここからは、血族相続人の中の相続の優先順位を解説しますので把握しておきましょう。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
第1順位:子ども
血族相続人の中で一番優先順位が高いのが、直系卑属である子どもです。これは実子はもちろん、養子縁組している子どもや籍を入れていなかったとしても認知している子も対象となります。
ちなみに子どもがすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫がいるのであればそちらが直系卑属として第1順位の相続人となる場合もあります。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
第2順位:直系尊属(父母など)
子どもがいないまたはすでに亡くなっている場合は、直系尊属が第2順位の相続人となります。直系尊属としては父母または祖父母が対象となっていますが、祖父母に関してはすでに父母が亡くなっている場合のみ対象となるため注意が必要です。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
第3順位:兄弟姉妹
血族相続人の中で最も下にあたる第3順位が、兄弟姉妹です。亡くなった人に子どもがおらず、父母や祖父母もなくなってしまっている場合、兄弟姉妹が相続人として遺産を受け取ることができます。
ちなみにすでに兄弟姉妹も亡くなってしまっている場合、兄弟姉妹に子ども(甥・姪)がいればそちらが代襲相続することが可能です。ただし、甥や姪の子どもは対象外となっています。
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
法定相続分の割合はどのくらい?

法定相続人や優先順位を理解したところで気になってくるのが、相続する遺産の割合です。基本的に法定相続分は、遺言書なども踏まえて、法定相続人で集まって遺産分割協議を行ったうえで、分割されるようになっています。
ただ法定相続人の種類によってある程度割合は決まっており、割合としては以下のように定められています。
・配偶者と父母の場合:配偶者が2/3、父母が1/3(父母が両方存命ならそれぞれ1/6)
・配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を人数分で分割)
出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
子どものいない夫婦に起こりえる相続トラブル

被相続人に子どもがいなかった場合、相続が発生した際に問題が起こることがあります。以下では、子どもがいない場合に起こりうる相続の問題点について紹介します。
これらの問題に直面するのは、被相続人の配偶者です。子どもがいない場合、夫婦のどちらかが亡くなった際に配偶者がどのような問題に直面する可能性があるのか、今のうちから知っておいた方がよいでしょう。
配偶者と血族相続人の仲が悪く話がまとまらない
子どもがいなかった場合、被相続人が亡くなった後に相続を話し合うのは被相続人の配偶者と血族相続人であるため、元々お互いの仲が悪かった場合には、話がうまくまとまらなくなる可能性があります。
子どもがいない夫婦では、配偶者とともに被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続人となります。お互いに仲が良ければよいのですが、元から話もしない間柄であった場合、相続問題を話し合うどころか連絡を取り合うことすら難しい状況におちいる可能性があるでしょう。
不動産などの分割で揉める
現金などの金銭であれば分割しやすいですが、不動産や土地などの分割しにくい遺産は揉めやすい傾向が見受けられます。
不動産そのものを物理的に分割できないうえ、土地に関しては細かく分けてしまうと相続する土地が小さくなるだけではなく、その価値が下がってしまうというリスクがあるためです。
このような場合は不動産や土地を売却して金銭に変える方法もありますが、相続人全員が同意しなければ実践できないなど、トラブルになった際の解決方法で揉めることもあります。
出典|参照:不動産の所有者が亡くなった|法務局
相続人の中に認知症の人がいて遺産分割協議を進められない
子どもがいない夫婦の法定相続人は、配偶者のほかに父母や兄弟姉妹など、どうしても高齢になりやすい傾向が見受けられます。そうなると、相続人の中に認知症の人が出てくる場合もあるでしょう。
相続人が認知症になってしまうと、正常な判断ができないとして、遺産分割協議が進まない・できなくなってしまう可能性が出てきます。成年後見制度の利用も可能ですが使いづらい側面もあるなど、スムーズに遺産相続ができなくなる点は大きな問題でしょう。
相続人の人数が多くなかなか連絡が取れない
法定相続人として、兄弟姉妹が選ばれた場合に起きやすい問題が、相続人の数の多さゆえに、連絡が取れないという点です。また、相続人との関係が疎遠だと連絡先が分からないこともあります。
相続を進めるためには法定相続人が全員集まり、遺産分割協議をしなければいけません。ただ相続人の人数が多いとなかなか連絡が取りにくく、協議するための日程調整が難しくなりがちです。
子どものいない夫婦が相続トラブルを回避するためのポイント
夫婦の間に子どもがいなかった場合、相続が発生した際に残された配偶者が相続問題に悩まされる可能性がおおいにあります。そこで、ここからは子どもがいない場合にしておくと良い相続対策を紹介します。
遺産相続は遺産争族と呼ばれるほどに、親族間でも争いが起こりやすいとされています。問題が起こらないよう、早いうちから手を打っておくとよいでしょう。
・遺言書を作成する
・生前に財産を配偶者に贈与する
・生命保険の受取人を配偶者にしておく
遺言書を作成する
遺産相続に関するトラブルを回避するために欠かせないのが、遺言書の作成です。遺言書を作成すれば誰にどの程度の遺産を相続させるのかを決めることができるうえ、法定相続よりも優先されます。
ただあまりに偏った遺産相続をさせてしまうと、配偶者や直系尊属から遺留分を請求される可能性があるため注意が必要です。
また遺言書の作成には定められた条件や注意点があるため、弁護士などの専門家に作成を依頼し、遺言執行者を選任して遺産相続時のやり取りをスムーズにできるように配慮しましょう。
生前に財産を配偶者に贈与する
仮に配偶者に全ての遺産を相続させたとしても、その配偶者が亡くなった際には、最終的に配偶者の両親や兄弟姉妹に被相続人の財産が渡ることを覚えておきましょう。
子どもがいないため、財産を相続した配偶者が亡くなった際には、その配偶者の親族に財産が渡ることになります。結果的に、被相続人とは血の繋がりがない人に全ての財産がいくというケースもあるでしょう。
最終的に自分の親族に財産を渡したい場合は家族信託を利用し、配偶者が亡くなった後は自分の親族を受益者とする対策方法があります。
生命保険の受取人を配偶者にしておく
意外なことかもしれませんが、生命保険金は相続財産とは基本的にみなされないため、特定の人に財産を残したい場合には生命保険に入り、受取人をその人に指定しておくとよいでしょう。生命保険金が相続財産とみなされなかった場合、遺留分の対象にもなりません。
ただ、被相続人が生命保険の保険料を負担し、その負担によって相続財産が著しく減ってしまった場合は注意が必要です。生命保険金の受取人も相続人で、その他の相続人と差がつきすぎて不公平であると判断された場合は、生命保険金が遺留分の対象となることもあるでしょう。
遺言書を作成する場合の注意点

遺言書は法定相続よりも優先されることから、相続させたい内容や相手を限定したい人にとってはトラブル回避の有効な手段として用いられています。特に子どもがいない夫婦の場合は法定相続人が増える可能性があるため、作成しておくことがおすすめです。
ただきちんと決まりを守って作成しないと無効になるほか、いくつか注意しておかなければいけない点があります。
ここからは、遺言書を作成する場合に意識しておきたい注意点を2つほど解説します。
遺留分に気をつける
どんなに遺言書で相続人や相続分の割合を決めたとしても、相続人には遺留分を請求する権利があります。
子どものいない夫婦の場合、相続分に対して遺留分を請求できるのは配偶者または亡くなった人の父母もしくは祖父母です。このため、配偶者に遺言書で遺産を全て相続させたとしても、亡くなった人の父母もしくは祖父母が遺留分を請求するリスクがあります。
請求できる期間は、相続開始前の1年間または、相続人相手の生前贈与であれば10年間までさかのぼることが可能です。
出典|参照:遺留分侵害額の請求調停 | 裁判所
万が一に備えて予備的遺言を遺す
夫婦でそれぞれ遺言書を作成していたとしても、場合によっては遺言書が無効になってしまうケースがあります。
分かりやすい事例としては、夫婦それぞれがお互いに全財産を相続させるという遺言書を作成していたとします。その状態で片方が先に亡くなると、相続させる相手が亡くなってしまったということで生きている配偶者側の遺言書が無効化されてしまうのです。
このため、想定できる事態や万が一の事態に備えて、「自分より先に夫(妻)が亡くなっている場合は、〇〇に全財産を相続させる。」などの予備的遺言を書いておくことで有効になります。
子どもがいない夫婦は相続問題に備えて準備をしておこう

子どもがいない夫婦の場合、配偶者以外の相続人が複雑になりやすく、遺留分などをはじめとした問題から相続トラブルが起きやすい傾向があります。
このため子どもがいない夫婦は特に相続トラブルを回避するための対策を講じておくことが大切で、同時に相続人となりえる血族相続人を把握しておくようにしましょう。
今回解説した記事の内容を参考に、いずれくるだろう遺産相続に備えてみてはいかがでしょうか。
お電話でも受け付けております