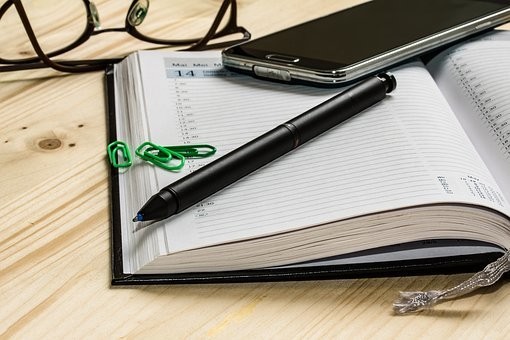位牌堂の特徴とは?納骨堂との違いや利用手順・費用についても解説

位牌堂という言葉をご存知でしょうか。納骨堂と同じようなものだと考えている人も多いでしょうが、納骨堂と位牌堂は異なるものです。
本記事では位牌堂の特徴や位牌堂を利用する手順、位牌堂へ安置を検討する際の注意点などについて解説します。
記事を読むことで位牌堂と納骨堂の違いや、どのようにして位牌堂に位牌を安置するのかを知ることができるでしょう。また、位牌堂にかかる費用なども併せて解説しているため、位牌堂へ位牌を安置するにはどのような費用がかかるのかも知ることができます。
位牌は故人を供養する大切なものです。記事を読むことで位牌堂とは何か、位牌堂を利用するのにどれくらいの費用が必要になるのかを知り、位牌を供養する際の参考にしてみてください。
位牌堂とは
位牌堂と納骨堂の違い

位牌堂と納骨堂の違いは、納骨堂が遺骨を安置するお堂であるのに対し、位牌堂は位牌を安置するお堂であるという点です。
納骨堂には位牌堂と同様の棚式のものから、ロッカー式や仏壇式、墓石式、倉庫式などさまざまな種類のものがあり、中には位牌と遺骨を一緒に安置できるものもあります。
納骨堂の場合は種類によっては位牌と遺骨を一緒に安置することができますが、位牌堂に遺骨を安置することはできません。
位牌堂へ位牌を安置するパターン

位牌は基本的に自宅の仏壇で供養するものですが、さまざまな理由から位牌堂へ位牌を安置する人も多いです。位牌堂へ位牌を安置するのには2つのパターンがあります。
遺族の方針により、どちらにするか選ぶことができますが、菩提寺の方針や地域の習慣で決められている場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
ここでは位牌堂へ位牌を安置する2つのパターンについて、それぞれ見ていきます。
位牌堂のみへの安置
自宅に仏壇がなく、位牌を安置しておく場所がないという場合には、位牌を位牌堂にだけ安置するという方法があります。
なかなか自宅へ帰れなかったり、さまざまな理由で毎日自宅でお勤めするのが難しかったりするという理由から、位牌堂へ安置する人も多いです。
自宅と位牌堂への安置
位牌を自宅と位牌堂の2カ所で安置するという方法もあります。この方法の場合、位牌を2カ所に分けて安置するため良くないのではと思う人もいるでしょう。
しかし、位牌の役割はこの世の私たちとあの世の故人を繋げることで、位牌に魂は宿っておらず、位牌を2カ所に安置したからといって故人の魂が別れるということはないため心配はいりません。
位牌堂に安置する位牌のことを寺位牌と呼び、自宅に安置する位牌よりひと回り小さいものを準備します。
位牌堂を利用する際の手順
1:寺院探し
菩提寺に位牌堂があれば、菩提寺に位牌堂の利用について相談をしましょう。菩提寺がない場合や、菩提寺はあるけれど菩提寺に位牌堂がない場合には、位牌堂がある寺院を探すことが必要です。
インターネットなどを利用して、位牌堂がある寺院を検索してみてください。
2:寺院への檀家が必要かの問い合わせ
位牌堂がある寺院を見つけても、寺院によっては寺院の檀家でなければ位牌を受け入れてもらえない場合があります。
そのため、寺院の檀家になることが必要かどうかを問い合わせましょう。寺院の檀家になるためには入檀料が必要となります。
一般的な入檀料は10~30万円程と言われていますが、寺院や寺格によっても入檀料が異なるため確認が必要です。檀家になることが必要な場合、入檀料と位牌堂の利用料などがかかるため出費が多くなります。
また、檀家になるのが難しい場合には、檀家ではなくても位牌堂を利用できる寺院を探しましょう。
3:入檀条件を確認
寺院の檀家になる必要がある場合、入檀料を支払えば誰でも入檀できるわけではなく、入檀条件をクリアしなければなりません。
入檀するためには、寺院の宗派と家の宗派が同じであることが前提となります。もし宗派が異なるなら宗旨を変える必要がありますが、そうなれば家族だけでなく親族も関わる問題となるため、親族ともよく話し合うことが必要になるでしょう。
また、既に他の寺院の檀家である場合には、その檀家を離れてからでないと入檀することができません。入檀条件を確認し、親族などとよく話し合ってから入檀するようにしましょう。
4:位牌の安置
上述した条件などをクリアすることができれば、位牌の管理料や永代供養料などの必要な費用を納めることで位牌を位牌堂へ安置することができます。
位牌堂に位牌を安置する費用については後述しますが、お寺によって費用が異なるため事前に確認しておくようにしましょう。
位牌堂への安置を検討する際の注意点

位牌を位牌堂へ安置することを検討する場合には、注意すべき点がいくつかあります。ここでは位牌堂への安置を検討する際の注意点について解説するため、参考にしてみてください。
位牌を納めた場合「永代供養」の期間
位牌を永代供養すると言っても永久に位牌が安置されるわけではなく、契約期間の間は安置して供養してもらえますが、契約期間が過ぎれば終了となります。
安置期間については、ほとんどの寺院が17回忌、33回忌、50回忌などの区切りまでとしており、33回忌を区切りに契約終了とする寺院が多いと言えます。
しかし、中には50回忌まで安置してくれる寺院もあるため、契約時に確認しましょう。
お供えはできない
位牌堂は棚に位牌を並べて安置する棚式の形式を採用しているところがほとんどです。そのため、それぞれの位牌のためにお供えをすることはできません。
また、お供えができないだけでなく、位牌の前でお参りすることもできない場合があります。位牌堂に安置した位牌は遺族が供養するのではなく、基本的に寺院が供養するものだと考える方が良いでしょう。
位牌堂にかかる費用
入檀料
位牌堂へ位牌を安置するために檀家になる必要がある場合には、上述したように檀家になるための入檀料を支払う必要があります。入檀料は寺院によって異なりますが、一般的な相場は10~30万円程です。
入檀料に位牌の預け入れ費用が含まれている場合と、位牌の預け入れ費用とは別に入檀料が必要になる場合がありますが、どちらのパターンなのかは寺院によって異なるため事前に確認をしておきましょう。
入檀料は毎年払うものではなく、一度支払えば離檀するまで費用が発生することはありません。
管理費
檀家になると檀家になった寺院や、檀家が共同で利用する墓地などを維持するために管理費を支払う必要があります。
管理費は自分のお墓を清掃するために使われるのではなく、檀家が共同で使用する墓地の水くみ場などの施設を維持するために使われるものです。管理費を支払えばお墓の掃除はしなくても良いと誤解されがちなため、きちんと理解しておきましょう。
管理費は毎年支払うもので、一般的には年に1~2万円程の相場です。
位牌を納める費用
位牌堂に位牌を納める費用は寺院によって異なりますが、一般的には1基の位牌につき10万円程の相場です。
ただし、先祖位牌や回出位牌、夫婦位牌などのように、1基の位牌が複数の霊魂の依り代となっている場合には、料金が変わるケースもあるため注意しましょう。
位牌堂に位牌を納めるときに慌てることがないよう、事前に確認しておくのがおすすめです。
回忌法要・盆施餓鬼・お彼岸などの依頼費用
寺院の檀家になると三回忌などの回忌法要や、盆施餓鬼、お彼岸などの定期法要に際して、個人や先祖の供養を寺院に依頼します。
これらの法要に際して支払う費用については、依頼する法要の種類や寺格などによって異なるため、それぞれの法要を依頼する際に確認するようにしましょう。
新しい戒名に必要なお布施
寺院施設の修繕や増設費用
檀家になるとその寺院の本堂など、寺院施設の修繕や新たに施設を増設する際にお布施を頼まれることがあります。
寺院施設の修繕や増設に関するお布施は、管理費などのように必ず支払わなくてはならないというものではありませんが、檀家となることでそのようなお布施をお願いされる場合もあるということを知っておきましょう。
位牌堂の特徴や費用を把握しておきましょう

位牌堂の特徴や位牌堂を利用する手順、また、位牌堂への安置を検討する際の注意点などについて紹介しました。
位牌堂は位牌だけを安置して供養する施設であり、納骨堂とは異なるものです。
位牌堂に位牌を安置するためにはさまざまな条件をクリアする必要があり、場合によってはその寺院の檀家になることが必要なケースもあります。親族間のトラブルを防ぐためにも位牌堂へ位牌を安置する場合には、家族だけでなく親戚ともよく話し合うようにしましょう。
また、位牌堂に位牌を納める際や納めた後にも費用がかかることにも注意が必要です。位牌堂に位牌を安置しようと思う場合には、紹介した内容を参考に位牌堂の特徴や費用を把握しておいてください。
お電話でも受け付けております