
電話加入権は相続財産となる?相続・放棄の手続きや必要書類等について解説
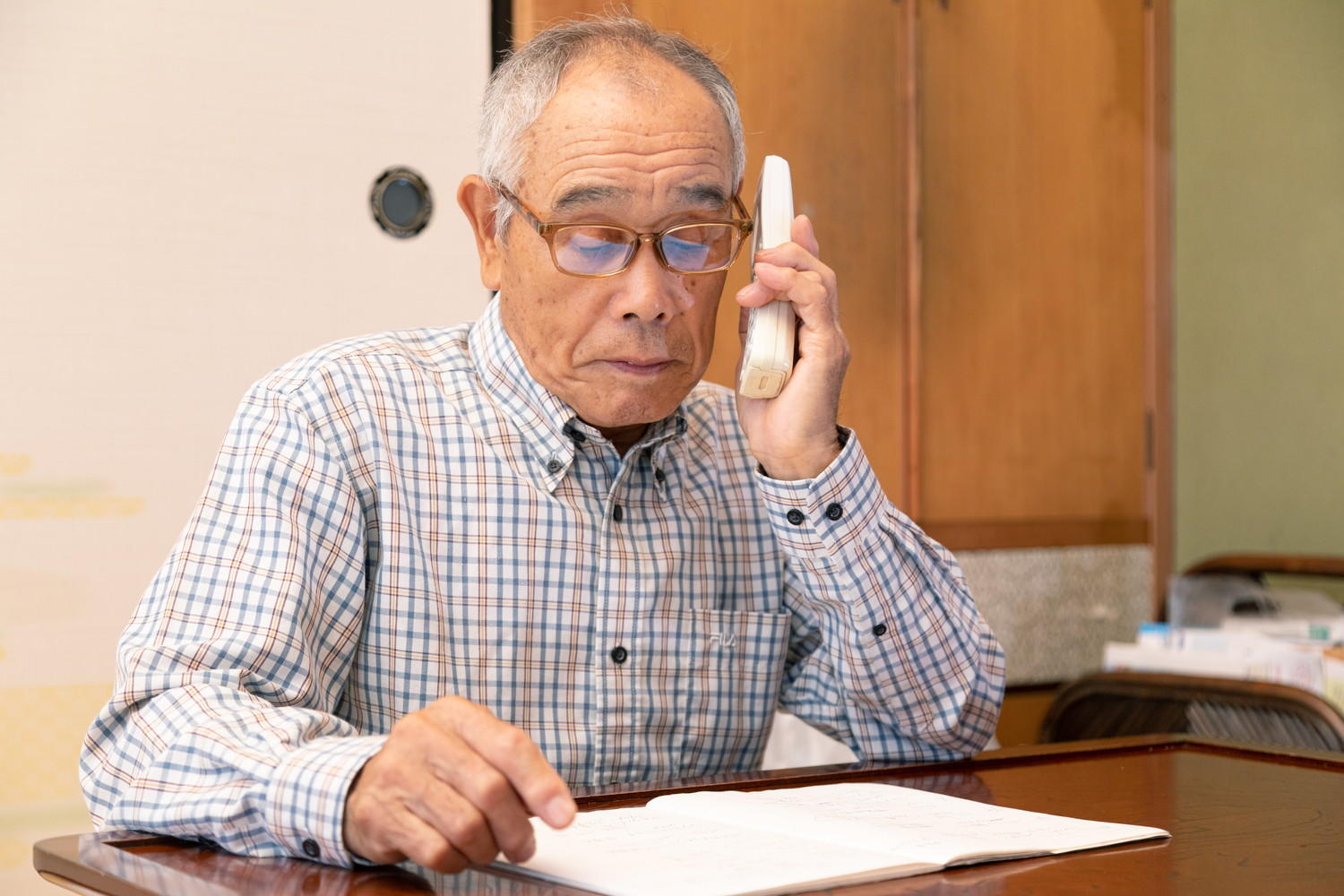
「電話加入権ってなに?」
「電話加入権は一時的に中断できるの?」
など、電話加入権についての疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。
例えば、親に万が一のことがあった場合、電話加入権も相続財産になります。しかし、相続しても使わないのであれば、解約や一時的な中断が必要になる場合もあるでしょう。
この記事では、電話加入権の基本的な情報をはじめ、相続や放棄の手続きおよび相続時に保有を確認する方法などについて詳しく紹介しています。この記事を読むことで、電話加入権の様々な手続きの方法が理解できるでしょう。
近年ではスマートフォンや携帯電話での連絡手段が主流であるため、固定電話はあまり使用しなくなりました。しかし、電話加入権の相続にはメリットも存在します。
電話加入権のメリットや手続きが気になる人は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
電話加入権について

以前は固定電話が設置してある家庭が一般的でしたが、個人で持つ携帯電話が普及した現在では固定電話がない家庭も増えています。
電話加入権は、家庭に固定電話を設置しようとする際に必要になってくる権利とされ、NTT西日本もしくはNTT東日本に契約を申し込み、施設設置負担金を支払うことで得られます。
固定電話を設置したい時は他人の不要な電話加入権の譲渡を受けるという方法を利用すれば、初期費用である施設設置負担金を抑えることができるのがメリットです。
電話加入権の保有を確認する方法

電話加入権の保有は、局番無しの「116」に電話をかけることで確認できます。電話加入権を保有しているかを知りたい人はもちろん、いつ頃解約しているかなども確認することが可能です。
電話加入権の解約は、「116」やインターネットのサイト上から申し込みできますが、申し込むとNTT東日本・西日本の担当から確認の電話が入ります。この際、解約ではなく、休止を勧められることがほとんどでしょう。
つまり、解約していると思っていても、実は一時的な休止状態であり、電話回線は止まっていても電話加入権は手元に残っているという状況もあり得るということです。
電話加入権の有無や、現時点で休止状態か否かはきちんと確認しましょう。
電話加入権の評価額について

電話加入権の評価額は、1952年頃の34,000円程度から始まり、1960年頃には10,000円程度になったとされています。その数年後には30,000円程度となり、1971年頃には50,000円程度になりました。
特に、1976年頃が電話加入権が高かった時期で、費用は80,000円程度とされていましたが、2005年頃に36,000円程度になってからは変わっていないとされています。
1952年頃から現在と価格があまり変わっていないことから、電話加入権はとても高価な権利だったことがわかるでしょう。
電話加入権は相続財産として扱われる

電話加入権は相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。そのため、財産評価は必須です。相続財産とはなりますが、少額であることがほとんどでしょう。
しかし、相続税の納税額への影響がほとんどないとはいえ、立派な財産であることに変わりありません。たとえ数千円でも必ず申告書に記載し、引き継ぐ際は名義変更の手続きも忘れずに行いましょう。
相続に関係する電話加入権の手続きと必要書類等

電話加入権を相続した場合、今後の利用状況などの見通しに合わせて様々な手続きを選択することが可能です。
しかし、中には注意しなければならない点や、二度と同じ番号を使用できなくなる手続きなどもあるため、慎重に検討しましょう。
ここでは、それぞれの手続きに必要な書類や、手数料の有無などを紹介しています。どれを選択するか検討する際は、ぜひ参考にしてください。
承継する場合
親の死に伴い、電話加入権を相続した場合は名義変更が必要になります。この名義変更は「承継」という項目で手続きを進めましょう。承継に手数料はかかりません。必要な書類を用意し、NTT東日本・西日本から承認を得ることで承継は成立します。
手続きには、新しい契約者の名前や生年月日、住所がわかる書類と現契約者の死亡を確認できる書類が必要になります。さらに、「加入継続申込書」の必要事項を記入してから申し込みを行いましょう。
譲渡する場合
電話加入権は資産であるため、他人に譲渡することが可能です。その際は、少しでも金額の戻りがあるように相場を調べて、買取業者などへ売却することがほとんどでしょう。
売却する際には、まず「休止手続」を完了させておきましょう。この時に発行される「電話利用休止表」は、譲渡の際に必要になる書類です。
売却の際には、「電話加入権譲渡承認請求書」と「印鑑証明書」に加え、上述の「電話利用休止表」を用意してください。
なお、電話回線の休止には工事費用がかかるため、事前に工事費用と売却代金の比較を行いましょう。
買取価格によっては工事費用の方が高い場合もあり、売却してもマイナスになってしまうケースがあります。売却によって利益が出るのかをしっかりと把握してから、譲渡するようにしましょう。
解約する場合
電話加入権を解約する場合の手続きはNTTのサイトからすることができます。電話加入権の解約に伴う工事費もかかりません。
契約者が亡くなられている場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が必要になります。その場合は手続きを行う方の本人確認書類も必要になります。
利用停止する場合
利用中の電話回線今は使わないけれどまた使う予定があるという場合は利用中止という手続きもあります。サイトから手続きをすることが可能です。
約10年間継続して利用中止することができるとされていますが、再利用時には電話番号が変わります。また、電話を止める時と再開時それぞれ工事費がかかります。今は使う予定がないけれどまたいつか使いたいという時に再開できるのがメリットです。
一時中断する場合
一時的に中断したい時は、無期限で中断することができます。ただし、中断期間中でも月々の月額利用料は発生します。また、中断手数料も発生するため、注意が必要です。
しかし、前述の利用停止と違って、再開する時に電話番号を変更する必要はありません。電話番号をそのまま使用し続ける場合は、一時中断を選択すると良いでしょう。
手続きにおける注意点
電話加入権は様々な手続きを選択できますが、必ず今後の見通しを立ててから手続きに進みましょう。特に、休止や解約を選んでしまうと同じ番号は使えなくなります。
今後少しでも同じ番号を使用する可能性はないか、よく考えてから選択してください。
また、休止中も更新手続きを行わなければ、電話加入権が消滅してしまうため注意が必要です。存続期間は最大10年ですが、5年ごとに更新手続きが必要になることを忘れないようにしましょう。
消滅してしまった電話加入権は新たに購入しなければならないため、更新手続きを怠らないように気を付けてください。
電話加入権は相続するべきか

電話加入権を相続することには、「同じ電話番号を使用できる」というメリットがあります。例えば、勤務先や病院などの緊急連絡先として登録されていたり、親のお店を引き継いだりした場合などは相続を検討してみると良いでしょう。
もう一つは、災害時の通信手段として使用できるメリットがあります。スマートフォンや携帯電話はネット回線であるため、停電してしまうと利用できなくなってしまいます。
しかし、ISDN回線やアナログ回線は、条件にもよりますが停電時でも使用することが可能です。相続する際には、災害時にも使用できるかを確認してみると良いでしょう。
電話加入権の相続税評価について

電話加入権は、相続税の課税対象になるため相続財産になります。現在は、ほぼ資産価値がないとされていますが、国税庁で電話加入権の評価方法が定められています。
国税庁による電話加入権の評価方法は、売買の実例に基づく価額や専門家の意見を専門家の意見により評価額を算出します。
2020年頃に相続した分についての標準価額は、1,500円程度とされていますが、覚えやすい電話番号や嫌われる電話番号といった特殊な番号の場合は、専門家の意見により評価額を算出されるといわれています。
出典|参照:電話加入権の評価|国税庁
電話加入権は「家庭用財産」の評価に含まれる

家庭用財産は一単価あたり50,000円以下の場合、ひとまとめに「家財一式」として評価します。
電話加入権は「家庭用財産」の評価に含まれるため、家具や家電、衣服などと扱いは同じです。そのことを踏まえ、家庭用財産の家財一式を評価・計上する際は忘れずに電話加入権も含めましょう。
ちなみに、車や宝石など、50,000円を超える家庭用財産は家財一式に含めません。財産ごとの評価が必要になるため、財産を評価・計上する際は50,000円の基準を忘れないようにしましょう。
国税庁へ提出する相続税申告書の記載例
家庭用財産に含まれる電話加入権は、相続税申告書の第11表に「家財一式」として計上しましょう。
その際、50,000円以下の家庭用財産はひとまとめにしているため、「数量」と「単価」の欄は記載する必要はありません。空欄で提出してください。
電話加入権が相続財産であることを覚えておこう

電話加入権の手続きはそれほど難しくはありません。もし電話回線を相続したいと思った時は忘れずに手続きをしておきましょう。
万が一契約者が亡くなってしまった場合、そのままにしておくと基本料金を払い続けることとなってしまいます。
書類を準備したりなどの手間はありますが電話加入権はいざという時のためにも譲渡する準備をしておくと安心でしょう。
お電話でも受け付けております















