
分骨の永代供養とは?かかる費用や手元供養・樹木葬についても紹介

「お骨を分けることは可能なの?」
「分骨したお骨の供養方法が知りたい」
「分骨する際はどんなことに気をつけたらいいの?」
お墓が自宅から遠いため、近くで供養したいと考えて分骨を希望される方もいます。しかし、分骨に関して正しい知識や注意点を知らない方もいるでしょう。
本記事では、分骨の意味と分骨後の永代供養を紹介しています。また、分骨に必要な手続きや手順、分骨にかかる費用など、分骨するときに知っておきたいポイントも紹介しています。
本記事を読めば、分骨の方法や考え方の理解が深まるだけでなく、分骨後のお骨の供養の仕方が分かるでしょう。
分骨を考えているけれど供養方法がよく分からず困っている方や、分骨の手順や考え方を理解したいと思っている方は、ぜひ読んでみてください。
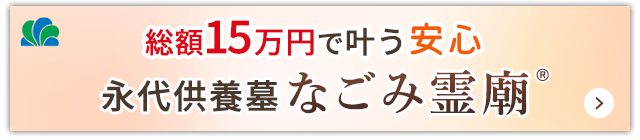
分骨の意味とお骨を分ける理由

分骨とは、2カ所以上の場所にお骨を分けて納骨することをいいます。お骨を分ける理由は、「家族それぞれでお墓を持ち供養したいから」や「お墓が遠いためお骨の一部を手元に置きたいから」、「お骨の一部を宗派の総本山に納めたいから」などさまざまです。
分骨したお骨の「永代供養」とは?

永代供養とは、遺族に代わり寺院や霊園が供養や管理をしてくれる方法です。分骨後、お墓をもう1つ用意するのは費用の面でも管理の面でも大変でしょう。
しかし、分骨したお骨を永代供養にすれば一般供養よりも費用が抑えられ、お墓の管理も楽になります。
分骨の永代供養の利点
永代供養は、最初に永代供養費を支払えばお墓の管理や法要をしてくれるため、分骨を永代供養にすると、新しくお墓を建てるよりも費用も手間もかからないといった利点があります。
また、お骨を納めた寺院の檀家になる必要がないのも、永代供養のメリットといえるでしょう。
永代供養の注意点
永代供養では個別供養をしてくれる場合でも、一定期間をすぎると合祀されてしまうパターンが多くあります。1度合祀されてしまうと、お骨を取り出すのは不可能となってしまうため注意が必要です。
永代供養墓を利用するときは、「お線香やお供えができない」ことや「いろいろな宗教や宗派の方が利用するため配慮した対応が必要になる」ことにも注意します。分骨を永代供養する場合は、管理先のルールを確かめて納得してから利用しましょう。
・永代供養墓をわかりやすく解説!何年供養できる?選ぶポイントは?
永代供養以外の分骨の供養方法

分骨後の供養方法は、永代供養以外にもいくつかあります。埋葬ではなくお骨を収納する納骨堂を利用する方法や、いくつかのお骨を合わせて埋葬する合祀なども分骨後の供養です。故人や分骨先の希望にあった供養方法を選びましょう。
手元に置いておく「手元供養」
手元供養とは、分骨堂やお墓に納骨せずにお骨を自宅へ持ち帰り、手元に置いて供養する方法で、自宅供養ともいわれます。
手元供養のメリットは、ライフスタイルに合わせた供養ができることです。祀り方も自宅の広さに合わせて、ミニ仏壇やミニ骨壺などを選ぶことができます。
常に故人と一緒にいたいと願う方には、手元供養が向いているでしょう。手元供養では、お骨をペンダントや指輪にして持ち歩くことが可能です。
・手元供養とはどんな方法?選ばれる理由やメリット・デメリットも紹介
樹木が墓石の代わりとなる「樹木葬」
樹木葬とは、樹木を墓石の代わりにシンボルとして、お骨を埋葬する方法です。樹木葬であっても納骨できる場所は法律で決まっているため、樹木がある場所ならどこでも自由に納骨してよいわけではありません。
樹木葬を考えている方は、お骨を埋める前に自治体へ問い合わせて、墓地として正式に許可がある場所かどうか確かめましょう。
海に散骨する「海洋散骨」
海洋散骨とは、お骨をお墓や納骨堂に納骨せず海に散骨する埋葬方法です。海洋散骨するときは、お骨を粉骨にする必要があります。
海洋散骨を禁止する規定はありませんが、自治体により散骨できる場所が決まっているため注意が必要です。散骨するときは、遺族のみで勝手に海へ散骨せず、葬儀社や自治体に事前に相談しましょう。
・永代供養をする時期はいつ?適しているタイミングや手順を詳しく解説
分骨をする際の手順

分骨の方法は2つあります。1つは、納骨する前の火葬場で分骨する方法、もう1つは納骨済みのお骨を分ける方法です。
2つの方法は手順やかかる費用が違います。それぞれどのような手順になるのか、確かめていきましょう。
納骨をする前の場合
まずは、納骨する前の火葬場で分骨するときの手順です。分骨する数の分だけ、骨壺を用意します。そして、火葬場に分骨する数の分の火葬証明書、もしくは分骨証明書を発行してもらいましょう。
お骨を拾うときには、準備した骨壺それぞれにお骨を入れてください。お骨の用意ができたら、分骨先の管理者全員に火葬証明書、もしくは分骨証明書を渡します。後は、分骨先の管理者がそれぞれの供養方法で納骨するか持ち帰ります。
すでに納骨されている場合
お墓や納骨堂へすでに納骨されているお骨を分骨する場合は、一度お墓や納骨堂からお骨を取り出す必要があります。お骨を取り出すには、お墓や納骨堂を管理している人や管理会社へ分骨の連絡が必要です。連絡して分骨証明書を発行してもらったら、お骨を取り出す日程を決めます。
納骨済みのお骨を取り出す前には、閉眼供養が必要です。その後、依頼した石材店や寺院がお骨を取り出します。お骨の分骨が済んだら、元のお墓や納骨堂にお骨を戻し開眼供養をしてください。分骨先の管理者へ分骨証明書とお骨を渡して、分骨先で開眼供養をすれば終了です。
・自分で分骨することはできる?タイミングと方法・粉骨や手元供養も説明
分骨に必要な手続き

ここからは、火葬場で分骨するときに必要な手続きを説明します。火葬場で分骨するときは、分骨する数の火葬証明書もしくは分骨証明書を発行してもらいましょう。このとき、火葬証明書は火葬許可証とは違うため注意が必要です。
火葬場によっては、当日にならないと証明書が発行できないことがあります。葬儀社を通さず自分で依頼する場合は、このことにも注意しましょう。
次に、お骨がすでに埋葬されているときの、分骨に必要な手続きを説明します。まず、お骨が埋葬されているお墓を管理している寺院、もしくは管理会社へ分骨証明書の発行依頼をしてください。
お墓を開けてまた閉めるため、石材店へ墓石を動かす手配と、閉眼供養や開眼供養の依頼も忘れずにしましょう。
分骨にかかる費用

火葬場で分骨する場合は、分骨数の骨壺の料金と火葬証明書か分骨証明書の発行手数料がかかります。証明書の発行手数料は自治体により違いますが、1通おおよそ300円です。
お墓に納めてあるお骨を分骨する場合は、墓石の移動におおよそ2~3万円、分骨証明書の発行代金に1通おおよそ100円かかります。開眼供養や閉眼供養の代金は、おおよそ1~3万円です。
分骨後の供養にかかる費用は、供養方法により違います。たとえば、手元供養では骨壺やペンダントなどの料金、永代供養を依頼する場合は永代供養の料金がかかることを覚えておきましょう。
知っておくと安心な分骨のポイント

分骨は、残された人が希望する以外に故人が希望する場合もあります。分骨に対する考え方は、人それぞれです。それゆえ、故人が希望した場合でも、分骨後に残された親族間で揉める可能性があります。
こうしたトラブルを回避するためにも、知っておくと安心な分骨のポイントを押さえておきましょう。
法要は通常通り行う
分骨しても、法要は通常通りに行ってください。法要は、代々のお墓で行っても分骨したときに新しく建てたお墓で行っても、両方で重ねて法要しても構いません。
法要は、故人を偲び遺族が冥福を祈るための儀式です。遺族の意向に合わせた方法で供養するのがよいでしょう。
手元供養の場合でも証明書は取得しておく
分骨証明書は手元供養では必要としませんが、気が変わり後で納骨したくなったときには必要になります。そのため、手元供養する場合でも分骨証明書を取得しておきましょう。
手元供養のため分骨証明書を取得していなかったけれど、後から必要になった場合は分骨前のお墓がある自治体で再発行できます。再発行には、「故人の氏名」や「亡くなった年月日付」、「火葬日」が必要です。
分骨証明書の再発行手続きが必要になったときのために、故人の亡くなった日や火葬日などはメモで残しておきましょう。
分骨をする際には事前にしっかり話し合っておく
家族といえども分骨に対する考え方は違うため、お骨を分骨するかどうかは、家族や親族などでよく話し合って決めましょう。
また、ひとりの考えで勝手に分骨を決めてしまうと、トラブルの元となってしまうことも考えられます。そのため、分骨については供養にかかわる人たちでよく話し合い、全員の了解を得られてから手続きに移りましょう。
分骨についての考え方

仏教の教えによる考え方では、分骨すると魂が2つに分かれてしまうと考えられているため、分骨するのは良くない、縁起が悪いといわれています。
このように、分骨は良くないとされている面もありますが、残された人にとってお骨が手元にあることで生きる励みや支えとなっていることもあり、古くから行われてきている習慣でもあります。
残された人の気持ちを考えるならば、分骨は縁起が良くないと捉えるよりも、むしろ尊い行為であると捉える方が自然でしょう。
分骨の手順や供養方法について理解しよう
分骨については考え方がひとそれぞれであるため、家族や親族間でよく話し合って決める必要があります。また、分骨したお骨を永代供養する際の方法もしっかり理解し話し合うことで、関係する全員が納得できる供養を行うことができるでしょう。
分骨する前には、手順や供養方法をよく理解しておきましょう。
お電話でも受け付けております















