
2026年の節分はいつ?2月3日(火) 恵方・豆まき・柊イワシなど行事を解説
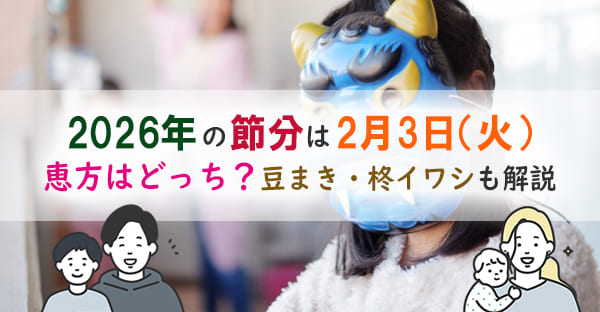
◇2026年の節分は、2月3日(火)です。
節分は、季節の変わり目に邪気を払い、無病息災を願う日本の伝統行事で、豆まきや恵方巻、柊イワシなどの風習が知られています。
本記事では、2026年の節分の日程をはじめ、その意味や由来、2026年の恵方、正しい豆まきの仕方、柊イワシなど節分の行事や豆知識について分かりやすく解説します。
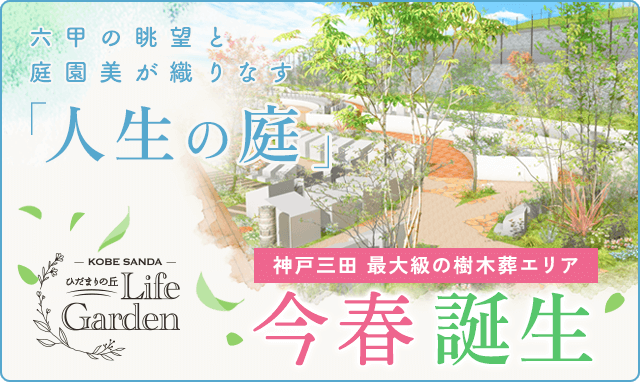
そもそも「節分」とは

◇「節分」は本来、立春・立夏・立秋・立冬の前日です
今年の節分は2026年2月3日(火)です!
中国から伝わる二十四節気は、実際の日本の季節感とは合わないため、二十四節気に合わせて日本の季節を捉えるための「雑節(ざっせつ)」を設けました。
そこで「季節の変わり目には邪気が入る」として、四季の始まりを表す四つの節気、立春・立夏・立秋・立冬の前に節分を設けたのです。
| <そもそも節分とは?> | |
| ・立春の前日 | (冬→春へ) |
| ・立夏の前日 | (春→夏へ) |
| ・立秋の前日 | (夏→秋へ) |
| ・立冬の前日 | (秋→冬へ) |
そこで現代まで残った節分が、立春の前日に行う2月3日(2月2日)の豆まきになりました。
陰暦(旧暦)だった時代には、旧正月が立春にあたり、より厳かな気持ちで一年の邪気祓いや無病息災祈願として、行わてきたのではないでしょうか。
(陰暦(旧暦)時代の名残りとして、年賀状には「立春」や「迎春」などの言葉がありますね。)
節分はどのように始まった?
◇陰暦(旧暦)時代、節分は立春の前日であり大晦日でした
もともとは中国の風習で、日本に入ってきたのは室町時代と言われています。
その昔、季節の変わり目には邪気が入ると言われ、平安時代には追儺(ついな)と呼ばれる、邪気祓い・約祓い行事が行われていました。
・新年の無病息災を祈願する
・季節変わりの邪気を祓う
・人の心にすくう鬼を退治する
・年取りの日
・心構えを新たにする
現在でも平安神宮(京都)では追儺(ついな)の名残りとして、ついな式「大儺之儀」が節分会(せつぶんえ)に行われていますが、この「追儺(ついな)」の儀礼に登場する、「方相氏(ほうそうし)」が、恐ろしい面を付けていたのだと言います。
ただ追儺(ついな)で登場する方相氏は、専ら鬼を祓う役割で鬼ではありません。
けれどもその恐ろしい面が先行して、庶民へ広がるにあたり「恐ろしい面の鬼」が邪気へと変化したのでしょう。
節分に祓う「鬼」とは?
◇節分の鬼は「五色の鬼」、人間の5つの煩悩を表します
節分の鬼と言えば赤鬼ですが、節分には「五色の鬼」がいるとされました。
これは仏教で瞑想時に邪魔をする、5つの人間の煩悩「五蓋(ごがい)」です。
| <節分の五色の鬼> | |
| ①赤鬼 | ●貪欲(とんよく) ・欲望 ・渇望 |
| ②青鬼 | ●瞋恚(しんに) ・悪意 ・憎悪 ・怒り |
| ③緑鬼 | ●惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん) ・倦怠 ・眠気 ・不健康 |
| ④黒鬼 | ●掉挙(じょうこ)・悪作(おさ) ・頭に血が上る ・平常心を失う ・過去の行いを悔いる、後悔 |
| ⑤黄鬼(白鬼) | ●疑惑(ぎわく) ・愚痴 ・疑う心 |
本来、節分で豆まきは窓や玄関に向かって豆を投げますが、しばしば鬼に扮した人に向かい投げますよね。
この場合は人にすくう五色の鬼を、その人の体や心から追い出し、穏やかな心を失ったがために起こる厄を祓う意味合いがあります。
節分でやることは?

◇節分では豆まきをしたり、恵方巻をいただきます
また厄や邪気が家に侵入することを防ぎ追い払うため、家の軒先や玄関に柊とイワシの頭を飾る「柊イワシ(ひいらぎいわし)」の風習もありますね。
大阪の節分では、焼いたイワシの頭を飾るため「やいかがし(焼臭)」や「やっかがし」などとも言うでしょう。
[1]豆まき
[2]年取り豆
[3]恵方巻(えほうまき)
[4]柊鰯(ひいらぎいわし)
大阪で節分の「鬼(おに)」は、陰陽師の「陰・隠(おん)」から来たとも言われます。
「隠」は「隠れる(かくれる)」意味合いがありますね。
大阪の節分で行う鬼祓いは、目には見えない隠れた疫病や心の鬼、知らない間に迫りくる災害などの厄を祓うための行事です。
節分にやること[1]豆まき
![節分にやること[1]豆まき](https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/wp-content/uploads/2023/01/pixta_85468236_S-1.jpg)
◇豆まきは、魔を滅する「豆(まめ=魔滅)」を鬼にぶつけて祓います
かつて節分の日に鬼になる人は、その年の干支生まれにあたる「年男」が良いとされてきました。(地域によっては年男・年女は厄年とも言われますよね。)
年男(年女)がいない家では、家長が鬼になることが多いでしょう。
ただ鬼になった誰かへ向かって豆を投げる儀礼は、本来の仕方ではありません。
| <豆まきの仕方> ●落花生を撒くこともあります |
|
| [1]豆まき用の豆を炒る ・豆を「炒る(いる)」=鬼を「射る(いる)」 ・後で豆から芽が出ないように |
|
| [2]豆を、枡に入れてお供えする ・神棚 ・お仏壇 ・玄関 …など |
|
| [3]窓から豆を投げる ●奥の部屋の窓から玄関へ向かう ・玄関から外へ向かって豆を投げる「鬼は外!」 ・玄関から内へ向かって豆を投げる「福は内!」 |
|
| [4]玄関から豆を投げる ・玄関から外へ向かって豆を投げる「鬼は外!」 ・玄関から内へ向かって豆を投げる「福は内!」 |
|
| [5]「年齢+1個」の豆(福)を拾って食べる ・「福は内!」で家内に入った豆 ※幼児は食べないように注意をします。 |
|
邪気(鬼)自体は暗闇に紛れて夜にやって来ると言われるため、日中に豆(魔滅)を炒ったら(射る)、枡などに入れてお供えをして待ちましょう。
お仏壇や神棚がなければ、玄関先でも問題はありません。
夜になったら、玄関より最も遠い奥の部屋から始めます。
●豆まき自体は下から投げる「下投げ」が良いとも言われてきました
最後に年齢分+1個の豆をいただきますが、拾う豆は「福は内!」で入ってきた豆です。
現代では、拾わずに別の豆をいただく家庭も多いでしょう。
節分にやること[2]年取り豆
![節分にやること[2]年取り豆](https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/wp-content/uploads/2023/01/pixta_13478244_S-1.jpg)
◇「年取り豆」とは、年齢+1個の豆(福豆)を拾っていただくことです
豆まきの最後で、「福は内!」で家内に投げた豆(福豆)を「自分の年齢分+1個」拾っていただく行事を「年取り豆」と言います。
ただ子どもであれば容易いことですが、大人になると「そんなに多くは食べられない!」と言う人も多いのではないでしょうか。
また高齢になると、歯の調子などから豆を食べられない事情もありますよね。
このような時には、「福茶(ふくちゃ)」としていただきます。
「福茶」とは?
◇「福茶」とは、福豆にお茶を注いでいただくものです
もともとは新年最初に井戸から汲んだお水「初水」で立てたお茶を差しましたが、近年では、邪気を祓う縁起の良いお茶「福茶(ふくちゃ)」として親しまれています。
「福は内!」で拾った福豆にお茶を注いでいただけば良いのですが、さらに縁起が良く、美味しい「福茶」のいただき方が親しまれているでしょう。
| <福茶のいただき方> | |
| ●材料 | ・福豆 ・塩昆布 ・梅干し ・緑茶 |
| ●いただき方 | ①湯呑に、福豆・塩昆布・梅干しを入れる ②熱い緑茶を注ぐ |
…とても簡単ですね。
福豆が多い場合には、急須(きゅうす)に入れて作っても良いでしょう。
数粒であれば、湯呑に直接作っていただくと簡単です。
昆布茶のような美味しく味わい深い福茶ができあがります♪
六波羅蜜寺の「皇福茶(おうぶくちゃ)」
節分にやること[3]恵方巻
![節分にやること[3]恵方巻](https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/wp-content/uploads/2024/12/26934855-1.png)
◇「恵方巻」は節分にいただく巻き寿司です
・2026年は恵方巻を食べながら、南南東を向きます。
恵方巻は、その年の恵方(2026年は南南東)を向き、無言でいただくと良い、とされる、縁起の良い数字である七種の具材が入った巻き寿司です。
| <恵方巻> | |
| [1]恵方巻のルール | ・その年の恵方を向いていただく (2026年は南南東) ・無言でいただく ・切らずにいただく |
| [2]恵方巻7種の具 | ・アナゴや鰻 ・玉子 ・かんぴょう ・椎茸 ・でんぶ ・だて巻きや高野豆腐 ・きゅうり |
恵方巻の七種の具は、基本的には上記七種ですが、数字の「七」が奇数の縁起の良い数ともされるので、今ではあらゆる具材で親しまれています。
えびやまぐろなどの寿司類、チーズなど洋風の恵方巻も人気がありますよね。
「恵方」はどうやって決まるの?
◇「恵方」は、年神様がいらっしゃる方角です
年神様は「歳徳神(としとくじん)」とも言い、鏡餅やしめ縄も、年末年始に年神様を家にお迎え入れしてもてなし、果報を授かるためにあります。
年神様のいらっしゃる方角「恵方」は、十干(じっかん)に基づいて割り出されますが、大まかには西暦で下一桁の数字により判断できるでしょう。
| <西暦下一桁で見る「恵方」> | |
| ①南南東 | …1、3、6、8 |
| ②北北東 | …2、7 |
| ③東北東 | …4、9 |
| ④西南西 | …0、5 |
今では全国的に広がる恵方巻ですが、もともとは大阪の花街で節分に商売繁盛を願い、広まった行事です。
・丸かぶり寿司
・太巻き寿司
芸子や商人などの間で御縁を繋げる、断ち切らない関係を祈願し、「今年一年も御縁を断ち切らず、良い関係性でありますように」と願い事とともにいただきました。
[4]柊鰯(ひいらぎいわし)
![[4]柊鰯(ひいらぎいわし)](https://www.yasiro.co.jp/eitaikuyo/media/wp-content/uploads/2023/01/pixta_19831933_S.jpg)
●「柊イワシ」は魔除けです
鬼は柊の尖った刃先と、イワシの生臭い臭いが嫌いだとされ、家に入ってこないように結界を作る意味合いで、家の玄関の軒先などに飾りました。
・焼嗅(やいかがし)
・やっかがし
・やいくさし
・やきさし
などなど、地域によって呼び名はさまざまです。
「家に侵入しないように」飾るものなので、家の内ではなく家の外、玄関先や軒先に飾るようにしてください。
門松とは違うので、ひとつ飾れば問題はありません。
| <柊イワシ> | |
| ①飾る時期 (地域で違う) | ・2月3日夜~2月4日まで ・2月3日夜~2月いっぱい ・小正月(1月15日)~2月3日夜まで …など |
| ②処分の仕方 | ・神社でお焚き上げ ・塩とお酒を掛け、白い紙に包んで捨てる |
現在の柊鰯は作り物を飾る家が多いのですが、本物を飾る時には生もので臭いもキツイため、近隣住民や猫などへの配慮も必要です。
まとめ:2026年の節分、恵方は東北東です

節分は本来「立春の前日」2026年こそ2月3日(火)ですが、本来は毎年2月3日とは限りません。
2026年以降、2月3日以外で節分が訪れる年度は2029年、2033年(いずれも2月2日が節分)などがあるでしょう。
2026年2月3日(火)の節分の恵方は南南東、近年ではエビやまぐろ、サーモンなどを入れた美味しい恵方巻もたくさん販売されていますので、今年は「御縁を繋げたい」人々で集まり、恵方巻をいただいてみてはいかがでしょうか。
まとめ
節分に行うこととは?
[1]豆まき
・豆を炒る
・夜までお供えをする
・奥の部屋の窓から行う
・外と内に撒く
※鬼に扮する人は年男(女)や家長
[2]年取り豆
・「福は内!」の福豆を拾う
・年齢+1個をいただく
・食べきれないなら福茶も良い
[3]恵方巻
・2026年の恵方は南南東
・無言でいただく
・恵方を向いていただく
・切らずにいただく
・始まりは大阪の花街
[4]柊イワシ
・柊とイワシを家の軒先に飾る
・鬼を家に侵入させない
お電話でも受け付けております
















