
自分で分骨することはできる?タイミングと方法・粉骨や手元供養も説明

「自分で分骨を行うことはできるの?」
「自分で分骨することのメリットやデメリットって?」
「自分で分骨を行う場合、何か注意点はある?」
このように、自分で分骨を行いたいと考えている人の中には、分骨できるのかどうか不安を抱いているという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、自分で分骨をするタイミングや分骨方法、自分で分骨するメリットやデメリットなどを紹介しています。本記事を読むことで、どのようにして納骨を行えばよいのか把握することができるでしょう。
また、自分で分骨を行う際の注意点や分骨後の手元供養の方法なども紹介するため、実際に自分で分骨する予定の人も参考にできます。
自分で分骨することはできるのかどうか知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
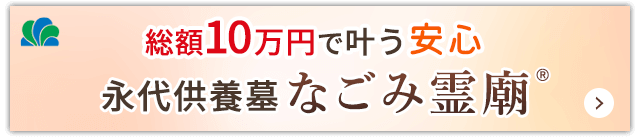
「分骨」とは?

分骨とは、亡くなった人一人の遺骨を分けて、2か所以上の場所に埋葬、あるいは保管することを指します。一般的に、故人の供養と言うと、遺骨をお墓に埋葬することを想像する人が多いでしょう。
しかし分骨の場合、お墓に埋葬する以外に、手元に置いて供養を行うケースもあります。そのため、分骨を行いたい場合、どのようにすればよいのかわからず悩むという人も少なからずいます。
また、分骨に対してあまり良くない印象を持っているという人もいるでしょう。
自分で分骨することはできる?
故人の遺骨を自分で分骨したいと考えている人もいるでしょう。結論から述べると、自分で分骨を行うことは可能です。
ただし、分骨のタイミングによっては手続きや墓地埋葬法の改葬に該当して許可が必要になります。たとえば、火葬のタイミングであれば火葬場で遺骨を分けることは可能ですが、すでに埋葬されている遺骨を分骨する場合はさまざまな手続きを行わなければいけません。
詳しくは、この後説明していきます。
分骨をするタイミングとその方法

自分で分骨を行う場合のタイミングとしては、故人が亡くなり火葬を行うタイミング、納骨前のタイミング、納骨済みの遺骨を分骨するなどさまざまなパターンがあります。
分骨を行うタイミングによっては、前述のとおり、寺院や霊園の管理者に確認を取り、必要書類による手続きを行わなければいけなくなります。ここでは自分で分骨をするタイミングと分骨方法について解説していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
火葬後に分骨する
故人の遺骨を分骨するタイミングとしては、火葬直後に分骨するというケースがあります。火葬場で火葬が行われた際の分骨であれば、問題なくスムーズに分骨を行うことができるでしょう。
火葬の際に分骨を行う場合、あらかじめ葬儀会社や火葬場の職員に対して分骨を行いたいという旨を伝えておきましょう。また、事前に分骨のための骨壺を用意しておくだけで、その他の手続きをする必要なく、そのまま分骨することが可能です。
納骨前の自宅安置中に分骨する
故人を火葬して遺骨を一旦骨壺に納めておき、納骨前のタイミングで分骨を行うというケースもあるでしょう。このような場合は自宅に安置している間に分骨することになるため、分骨用の骨壺を用意しておけば、特に許可を得る必要なく分骨を行うことができます。
基本的に納骨を行う前のタイミングであれば、寺院や霊園など墓地の管理者などに許可を取る必要はありません。
お墓に納骨した遺骨を分骨する
すでに墓地に納骨されている遺骨を改めて分骨したいというケースもあるでしょう。すでに埋葬されている場合でも、分骨することは可能です。
ただし、遺骨がすでに埋葬済みである場合は、墓地の管理者に許可を取る必要があります。寺院や霊園など墓地の管理者に許可を取り、分骨証明書を発行してもらいましょう。
また、お墓を動かしたり蓋を開けたりすることは素人には難しいため、お墓の構造によっては石材店に依頼して開けてもらう方が良いでしょう。
・分骨をする2つのタイミングとメリットデメリット|分骨手続きの流れや費用の目安を解説
自分で分骨するメリットとデメリット

ひと口に自分で分骨を行うと言っても、さまざまな事情があります。自分で分骨を行うことにはメリットもデメリットもあるため、具体的にどのようなメリット、デメリットがあるのか把握しておきましょう。
ここでは、自分で分骨するメリットとデメリットについて解説していきます。
自分で分骨するメリット
分骨を行う際には、墓地の管理者や石材店に作業を依頼することになります。その点、自分で分骨をする場合、業者への費用の支払いを行う必要がないため、コストや手間を削減することが可能です。
そのため、自分で作業が行える場合は、メリットが多いと言えるでしょう。
自分で分骨するデメリット
前述のとおり、自分で分骨を行える場合は業者に作業を依頼するコストや手間を省くことが可能です。しかし分骨に関する知識がない場合、作業の段取りに手間取る可能性があります。
また、納骨済みの遺骨を分骨する場合、お墓の蓋を開けて遺骨を取り出す必要がありますが、素人がこのような作業を行うのは難しいです。事故につながる可能性もあるため、自分で分骨を行うのであれば、手続きや納骨の仕方、お墓の構造などをよく調べておく必要があるでしょう。
自分で分骨を行う際の注意点

前述のとおり、埋葬済みの遺骨を自分で分骨する場合、必要な手続きを済ませる必要があります。また、事前に親族に確認を取り、同意を得ておかなければ、後々トラブルに発展する可能性もあります。
それでは、自分で分骨を行う場合には具体的にどのような注意点があるのでしょうか。ここでは自分で分骨を行う際の注意点を紹介していくため、参考にしてみてください。
喪主や親族の同意を得ておく
前述のとおり、故人の遺骨を別々の場所に埋葬するということに嫌悪感を抱く人も存在しています。親族の中にも、信仰心が強く、故人の遺骨の管理に対してこだわりを持っている人がいる可能性もあるでしょう。
また、故人の遺骨は親族が管理しているケースがほとんどであるため、分骨を行う際には分骨を行う理由をきちんと説明し、喪主や親族から同意を得ておく必要があります。間違っても、一方的に分骨を行うことを伝えるだけに留まらないようにしましょう。
分骨証明書が必要
分骨した遺骨を埋葬する場合、分骨証明書と呼ばれる書類が必要になります。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」の第5条では、遺骨を埋葬する場合は墓地の管理者に分骨証明書を提出しなければならないとされています。
なお、分骨証明書は火葬場で分骨する場合は火葬場に依頼、墓地に埋葬済みの遺骨を分骨する場合は墓地管理者に発行を依頼することで、入手することができるでしょう。
出典|参照:昭和二十三年厚生省令第二十四号 墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-eov 法令検索
・分骨証明書とは?入手する方法や埋葬時など必要となるシーンを解説
カビが発生しないように取扱いや保管に注意する
遺骨は湿気に弱いです。たとえば遺骨を素手で触ってしまった場合、触れた場所からカビが発生する可能性もあります。
そのため、遺骨には素手で触れないように保管には気をつける必要があります。自分で分骨を行う場合も、箸を使ったりゴム手袋を使ったりして、そのまま直接遺骨に触れないようにして取り扱うようにしましょう。
分骨した遺骨を粉骨しても良いの?

自分で分骨をしたいと考えている人の中には、遺骨を粉骨したいと考えている人もいるでしょう。それでは、分骨した遺骨を自分で粉骨しても良いのでしょうか。
ここでは粉骨するメリットや粉骨する方法などを紹介していきます。
粉骨するメリット
遺骨を粉骨することにより、故人の意向に沿って遺骨を散骨することもできるようになります。散骨とは、海や山など自然の中に遺骨を適切な方法で散布することです。
また、粉骨することで、故人の遺骨をペンダントといった装飾品に加工することもできるようになります。
粉骨する方法
自分で粉骨をする場合、手袋、マスク、すり鉢、金槌、ミルなどの道具を揃える必要があります。まずは、手袋やマスクを着用しましょう。
木槌や金槌で遺骨を砕いてすり鉢ですり潰すことで、遺骨を粉末状にすることができます。手作業で粉末にするのは手間がかかりますが、電動のミルがあれば簡単に粉骨することが可能です。
分骨した後の手元供養の方法

手元供養とは、遺骨の一部を自宅に安置したり、ペンダントなどの装飾品として携帯したりすることで、供養を行う方法です。手元供養用のアイテムとしては、ミニ骨壺やミニ仏壇、遺骨アクセサリーや遺骨プレートなどがあります。
このように手元供養にはさまざまな方法がありますが、手元供養を行うことで、遺骨を埋葬するよりも故人を身近に感じることができるでしょう。
自分で分骨する際の注意点を確認しよう
自分で分骨を行うことは可能ですが、分骨のタイミングによっては墓地の管理者に許可を取る必要があります。
ぜひ本記事で紹介した自分で分骨をするタイミングや分骨方法、自分で分骨するメリット、デメリットなどを参考に、自分で分骨を行う方法について理解を深めてみてはいかがでしょうか。
お電話でも受け付けております















