
【定年後の過ごし方】子ども家族や親族とは距離感!楽に生きる4つのコツ|永代供養ナビ

定年後くらい、楽に生きる過ごし方を満喫したいですよね。
けれども気が付けば、子ども世帯のサポートや孫の世話などで、疲弊してしまう人も少なくありません。
今の60歳以上の人々は、さまざまな人間関係のなかで我慢して、仕事でも家庭でも「断ることは悪!」と考え、体力の限界を超えても日々頑張ってきた人も多い世代です。
けれども人生の最終ステージとも言える定年後の過ごし方ですから、好きな時間や趣味の時間を楽しんで、ゆとりある時間を過ごしたいですよね。
今回は、定年後に楽に生きる過ごし方、特に子どもや家族、親族との適切な距離感を見つける、4つのポイントをお伝えします。

(1)断ることは、悪いことではない!

親族関係の悪化はよくよく元を辿ると、「嫌な気持ちでムリをしてお付き合いをするから」と言うケースは少なくありません。
こちらは良かれと思ってムリをしているのですが、辛い思いをしてイヤイヤ引き受けるからこそ、現れてしまうトラブルも少なくありません。
遅かれ早かれ、義両親や親族関係でムリをしていると、相手にも嫌な気持ちが伝わります。
自分と会うことを無意識にも嫌がられるのは良い気持ちがしないためです。
・皮肉や嫌味となって現れる
・無理をして引き受けているのに、感謝もされない
・悪口を言われている
例えば「孫の顔が見たい!」と言うのでムリをして会いに行っているのに、「ありがとう」と言われるどころか、「皮肉や嫌味ばかり!」なんて後悔も見受けます。
また親族が「会っている時は普通だったのに、いない時に悪口を言っていることを知り、ショックを受けた…」などの体験談もありました。
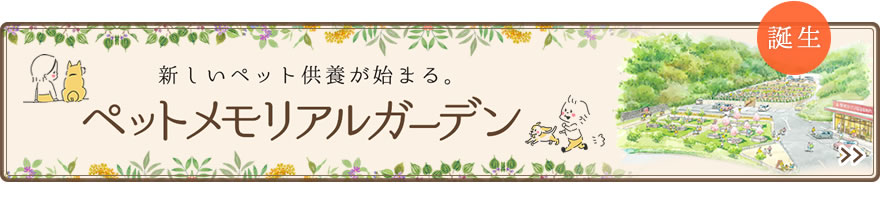
まず、断ってみる
定年を超えると体力的にもムリが生じますよね。
そのため「やってられないよ!」と言う人もいますが、断ってしまえば良いのです。
また60歳を超えたご夫婦は、子ども達も充分な大人であることが多く、仮に義両親が「孫に会いたい!」と言っても、子どもだけを義実家へ行かせることもできます。
●60歳以上で多い傾向にある考え方に「断ることは悪い事」と言うものがありますが、まずは一度、断ってみてはいかがでしょうか。
[親族]法事や会食を思い切って欠席する
[孫]要望の多いお年玉やプレゼントを廃止
[子ども]子守りは本心に従って答える
[親]介護施設への入居をサポート
「…しなければ愛がない」の考え方は60歳を過ぎたら、もう必要ありません。
いやいや受けてつい文句が出てしまっては、返って関係は悪化するばかりです。
自分を労わり、自分の本心を聴いて対応することこそ、家族や親族との関係性も良くなると信じて、「まず断る」「断ることはホントに悪い事?」と検討すると良いでしょう。
それはあくまでも相手の問題で、自分の問題ではないのです。
自分も若い頃のようにムリは利かないので、「できる範囲での」サポートを心掛けてください。
定年後の穏やかな夫婦の過ごし方については、下記でご提案しています。
・【定年後の過ごし方】人生終盤!夫婦関係を見直して伸び伸び生きる4つのコツ|永代供養ナビ
(2)同居ってホントに良い選択?

定年後の自由な過ごし方を検討しているならば、イメージ先行で決めてしまうと危険な選択が、同居の有無です。
よく子ども世代が親との同居で悩む話題が聞こえますが、これは親世代にとっても同じことではないでしょうか。
●下記のような点で不便を感じた体験談が多いです。
・定年後も家族の家事を担う生活が辛かった
・孫の送り迎えや世話が体力的にしんどくなった
・価値観の違い
・生活時間が違い、気遣いが多かった
・友人との旅行や食事に行きにくい
特に親世帯は子ども世帯に家を提供したり、二世帯住宅の資金援助をするため、いざ不協和音が産まれた時に「逃げ場」に困ります。
同居から「逃げ出した」体験談
山田花子さん(仮名)75歳は、夫を亡くして数年後、息子夫婦から同居を提案されました。
家を建て直して、そこに息子夫婦と同居する計画で、全てではなかったものの建て直し資金の8割を援助しています。
当時、夫を亡くして気を落とす花子さんを気遣い、旧友達が定期的にカラオケ会を開いたり、年に2回の旅行に誘ってくれていて、これが定番行事となっていました。
ところが家事育児と仕事の両立で疲弊していたお嫁さんから、度々苦言を言われるようになってしまいます。
・出掛けてばかりで、家のことをしてくれない
・可愛いはずの孫の面倒を見てくれない
・(ハロウィンなど)家族のイベントに参加しない
…などなどです。
最後の「家族のイベントに参加しない」は世代間によるギャップもあるかもしれません。
花子さんは
「クリスマスや年末年始、お彼岸やお盆などは年中行事として控えているものの、ハロウィンやバレンタインなど、家族で外食をしたり、家でパーティーをする生活習慣がなかった」
…と言います。

アパートを借りて同居を解消
夫を亡くして意気消沈はしていたものの、徐々に元気を取り戻して自由を謳歌していた花子さんは、これからの定年後の過ごし方を真剣に考えました。
そこで「残された時間、息子家族へ気遣いながら暮らすよりも、自由な時間を過ごしたい!」が結論です。
けれども、今まで住んできたマイホームは改装され、すでに息子夫婦の家になっています。
●それでも自由な時間を取るために、花子さんはアパートを借りて、息子夫婦と暮らす家を出ました。
1Kの質素な部屋ですが掃除などの手間暇もなく、一人で暮らすには丁度良い空間です。
長年住み慣れてきた家を出ることは抵抗があったものの、同居を解消して良かったと、回想しています。
●自分で生活ができるなら、まだ同居の選択は残しておいても良いのかもしれません。
(3)孫のお世話はムリをしない!

山本典子さん(仮名)72歳は、働き始めた娘から孫の世話を頼まれていました。
夕方17時に終わる保育園に迎えに行き、数時間孫を預かると、仕事を終えた娘が、孫を迎えに来る毎日です。
●そして心なしか、娘の迎え時間が1時間、また1時間と遅れるようになりました。
孫が熱を出して保育圏に登園できない時は、一日中、孫の世話をしています。
孫も3歳になり、だんだんと活発になってきた頃の事件です。
●ある日、孫のトイレの世話をしようとしゃがんだ瞬間、フラッとしたまま倒れ込んでしまい、朦朧としてきたため救急車を呼びました。
幸い貧血と極度の疲れで倒れただけでしたが、倒れた拍子に足を痛めてしまい、そのまま数カ月の入院となります。
子どもを預かる「命」の責任
そこで典子さんは、退院後は孫の世話を断ることにしました。
典子さんにとって孫は可愛い存在、もちろん娘も可愛い存在ですが、だからこそ悲しい事件が起きないよう、熟考した結果です。
・乳幼児の誤飲への配慮…視力に不安
・怪我への配慮…体力に不安
・部屋にある危険なものを片付ける日々がしんどい
・休む日、時間が必要
・自分の自由な時間を持って、心の余裕が必要
…などなどの考えが積み重なり、思い切って孫のお世話を辞退しました。
その後、娘は夫と協力をしながら、延長保育も取り入れて子育てをしています。
(4)親の法事は辞める

還暦も過ぎると親族であっても、法事くらいしかお互いに会う機会はなくなりますよね。
だからこそ長男夫婦である塚田康夫さん(仮名)75歳は、法事を続けてきたのですが、母の15回忌をきっかけに、両親の法事を取りやめることにしました。
法事に参列するだけならともかく、施主として取り仕切る立場としては、菩提寺のご住職とのスケジュール調整や会食の手配など、なにかと大変です。
主に裏方の仕事を担ってきた妻が、還暦を越えて体力的にムリが生じてきたため、施主として両親の法事を執り行うことを辞めています。
●辞めたきっかけ
・親族がたまにしか会わないため、気を使い合うだけ
・お酒が入り、相続で揉めたので辞めた
・施主以外、会食や片付けなどの手伝いがなく負担が大きい
●辞めた後の対応
・日ごろから仲の良い親族だけで、偲ぶ会を開いている
・それぞれの家族で供養をしている
・供養をしたい人だけ、弔問に来る
「両親を偲ぶ気持ちを大切に、形式にこだわらない」と形式を変える家が増えました。
…とは言え、なかには「キチンと供養したい」と言う親族もいるので、それぞれ自由に家族単位で法要を行ったり、お墓参りへ行く家が増えたようです。

最後に
今回は、定年後に楽に生きる過ごし方のコツとして、思い切って断る、やめることでスッキリとした体験談が多い、4つの事柄をお伝えしました。
定年後に快適な過ごし方を見つけるポイントは、現役時代とは違う、今の体力と時間を自覚することです。
そして一日、一カ月、三カ月、半年、一年の単位で、自分がどれだけ活動的に動くことができるのかを見極めます。
そのうえで、自分が本心からやりたいこと、過ごしたい時間を優先して、優先できない事柄は思い切ってお断りすることで、自然に相手とのムリのない距離感を見つけるでしょう。
これは家族や夫婦、親族であっても同じです。
また定年後の過ごし方だからこそ「断捨離してしまってスッキリ!」した生活習慣なども多くありました。詳しくは下記をご参照ください。
・【定年後の過ごし方】健康管理は必要?残る人生、体を解放する5つの断捨離|永代供養ナビ
まとめ
家族や親族との楽な距離感を作る4つのポイント
(1)気が乗らないことは、まず断ってみる
(2)自分で生活できるなら同居は控える
(3)孫のお世話はムリをしない!
(4)親の法事は辞める
お電話でも受け付けております















