
相続放棄をしても管理義務はなくならない?いつまで義務を負うかについても解説

「相続を放棄したら、両親が残した田舎の家の管理から逃れられるのかな」
「親が残した家の手入れが大変だから、相続を放棄してしまいたい」
親が残した住宅や土地の相続に関して、管理の大変さから相続を放棄したいと思う人は少なくないでしょう。
本記事では相続放棄について詳しく解説するとともに、相続放棄によって管理義務がどのようになるかについて解説します。
この記事を読むことで、相続放棄をするときに注意しなければならないこと、管理義務を怠った場合にどのようなリスクがあるかの知識が得られるでしょう。その知識を元に、相続放棄をしたあとの管理義務に関して注意ができます。
相続放棄後の管理義務について気になる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
そもそも相続放棄とは?

被相続人(相続する財産を持つ人)が亡くなると相続が始まりますが、相続人は相続の形式を選ぶ必要があります。
ひとつは単純承認で、相続人が土地や財産を引き継ぐとともに、借金等の義務も全て負うというものです。
他には、被相続人の権利や義務の全てを引き継がない相続放棄、相続する財産の範囲で借金等の義務も追う限定承認というものがあります。
相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申し出る必要があり、相続放棄により相続する財産を管理する義務を負う必要から逃れられるでしょう。
ただし、相続人は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続についてどうするかを決める必要があります。
出典:相続の放棄の申述|裁判所
出典:民法|e-Gov法令検索
相続放棄をしても管理義務はなくならない
 民法940条では、相続を放棄しても不動産等の管理義務はなくならないと規定されています。相続を放棄しても、その放棄によって相続人となったものが財産を管理し始めるまでは、自分の財産と同一の注意を持って管理しなければならないとしているためです。
民法940条では、相続を放棄しても不動産等の管理義務はなくならないと規定されています。相続を放棄しても、その放棄によって相続人となったものが財産を管理し始めるまでは、自分の財産と同一の注意を持って管理しなければならないとしているためです。
相続人が一人で他に相続人がいない場合や、相続人が複数いてもその全員が相続を放棄した場合は、最後に相続放棄をした人が財産を管理する義務が生じます。
出典:民法|e-Gov法令検索
相続放棄をしたあと管理義務を怠ったときのリスク

相続により居住地から遠い実家の家や山林、田畑などを相続することになり、これらを相続放棄して適切に管理しなかった場合、どのようなリスクがあるでしょうか。
民法940条では、自己の財産と同一の注意を持って、財産を管理するように規定されています。ここからは、相続放棄をしたあと管理義務を怠ったときのリスクについて解説していきます。
出典:民法|e-Gov法令検索
事件や犯罪に巻き込まれる可能性がある
誰も住まなくなった家を放置することで、その建物を犯罪者のアジトに使われるケースや、違法薬物の原料となる植物の栽培に使われるケースといった、犯罪に巻き込まれるリスクがあります。
また、放火などの事件に巻き込まれる可能性もあります。事件や犯罪に巻き込まれてしまった場合、相続放棄をしていたとしても管理義務を負うものとして責任を問われることになるでしょう。
損害賠償を請求される可能性がある
例えば古くなった瓦が強風で飛んで通行人にケガをさせた場合は、相続を放棄していたとしても、管理責任者として損害賠償を請求される可能性があります。
また、遺品や農地などをきちんと管理しなかったことで資産の価値がなくなり、債権者が債権回収ができなかった場合も、損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
特定空き家に指定される可能性がある
相続を放棄していたとしても、管理の責任がある空き家が特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家とはそのまま放置すれば倒壊する、あるいは危険である、衛生上問題があるとみなされた空き家のことを指します。
平成26年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第14条では、市町村長は特定空き家の所有者に対し、特定空き家の除却、修繕、立木竹の伐採等を助言、指導できるとしています。
そのため、特定空き家に指定されてしまうと空き家の除却、修繕をする必要が出てきてしまうでしょう。
相続放棄ができなくなる場合がある
相続放棄をした状態でも、他に管理者がいないことから管理をせずに売却などの処分をしたくなることもあるでしょう。
しかし、売却といった行為は相続の単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることにつながります。単純承認の場合は負債も含めての相続のため、金銭的なマイナスとなる場合もあり注意が必要です。
相続放棄の管理義務を負う期間はいつまで?
 相続放棄をした状態でも管理義務がなくならないということは、いつまで管理義務を負わなければならないのでしょうか。
相続放棄をした状態でも管理義務がなくならないということは、いつまで管理義務を負わなければならないのでしょうか。
相続放棄をした人が管理義務を逃れるには次順位の相続人に引き継ぐか、選出した相続財産管理人に引き渡すという方法が考えられます。詳しく解説していきましょう。
次順位の相続人が管理を始めるまで
自分の次の順位の相続者、被相続人の配偶者や子が相続を放棄した場合は、被相続人の兄弟がそれにあたります。次順位の相続者が管理を始めるまでは、相続放棄していても管理義務がある状態となるので注意が必要です。
出典:民法|e-Gov法令検索
選出した相続財産管理人に引き渡すまで
相続人にあたる人、兄弟や孫までが全て相続放棄をした場合など、相続する人が不明の場合については相続財産は法人とすると規定されています。
相続人が明らかでない場合は利害関係者、つまり相続を放棄したものの管理義務がある人が家庭裁判所に請求して、相続財産の管理人を選定してもらうこととなるでしょう。
ここで選定してもらった管理人に財産を引き渡せば、相続放棄した財産の管理義務はなくなります。
なお令和5年4月1日の民法改正により「相続放棄のときに、相続財産を現に占有している」人に管理義務があると明確になるため、相続する土地や建物と離れて暮らしている場合は、相続放棄後の管理義務に悩むことはなくなるでしょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
相続放棄をしたあとも管理義務に気をつけよう
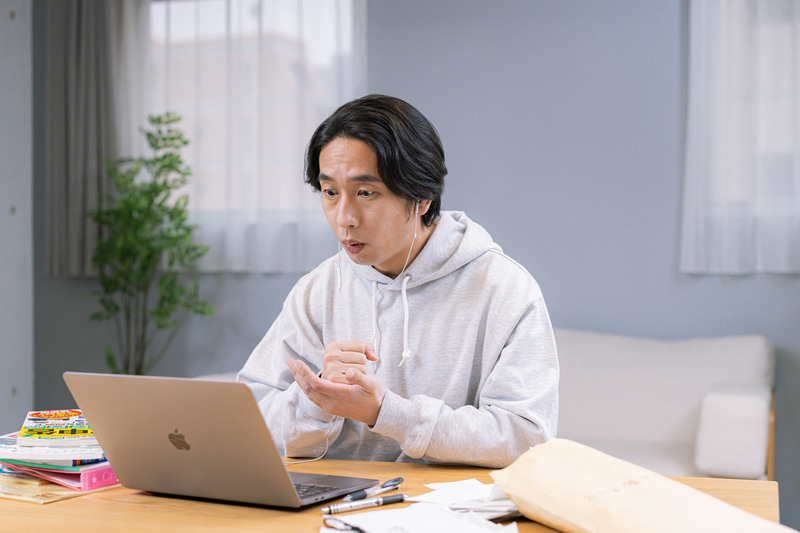
両親が住んでいた田舎の家や土地、山林などの管理をしたくない場合、相続放棄をすると管理義務から逃れられそうですが、子供が全員相続放棄をしてしまった場合などは、管理義務がなくならないので注意しましょう。
なお、令和5年4月1日の民法改正により「相続放棄のときに、相続財産を現に占有している」人に管理義務があると明確になるため、相続する土地や建物と離れて暮らしている場合は、相続放棄後の管理義務に悩むことはなくなるでしょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
お電話でも受け付けております















