
【お墓Q&A】墓地の権利はどんな仕組みになっているの?「永代使用権」はどんな権利?
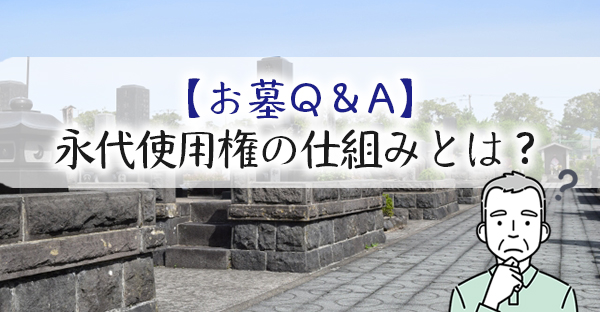
霊園でお墓を建てる際、墓地を使用する権利として「永代使用権」を購入します。
この墓地を使用する権利ですが、一般的な戸建て住宅などでは土地の所有権を購入するため、「永代使用権って何?」と、墓地の権利関係に関する仕組みに戸惑う声も多いです。
そこで今回は、墓地についての権利関係が、法律上どうなっているのか、「永代使用権」について詳しく解説します。
【お墓Q&A】墓地の権利はどんな仕組みになっているの?「永代使用権」はどんな権利?
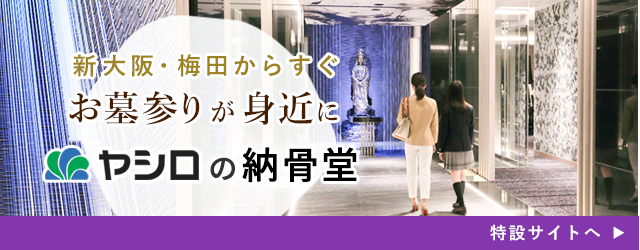
墓地の権利「永代使用権」

霊園でお墓を建てる際、墓地の権利は「永代使用権」を購入します。
永代使用権は永代に渡り購入した区画を使用できる権利で、個々の所有権ではありません。
●「永代使用権」とは、永代に渡り購入した区画を使用できる権利です。
また一般的に霊園では年間管理料を毎年支払いますが、一定期間、年間管理料を支払わなかった場合は、墓地の権利である永代使用権も失われます。
※詳しくは「永代使用権が失われる時」で後述しますので、コチラをご参照ください。
「永代使用権」は法律用語ではない
ただし墓地の権利とされる「永代使用権」は法律で定められた用語ではありません。
墓地の権利は特殊で、寺院墓地が責任を持って代々お墓を管理してきた歴史から、昔からの風習として「永代使用権」と呼ばれるようになりました。
●墓地は都道府県の知事の許可が必要ですので現実的ではありませんが、もしも許可が下りるならば、個人の所有地に墓地があってはならない法律はありません。
実際に現代でも昔からあるお墓のなかには、裏山など個人所有の土地を墓地としてお墓を建てている様子も見受けます。
ただ昔からの風習として、墓地の権利が「永代使用権」とされるようになったの背景には、宗教施設である寺院墓地を分譲できない背景から産まれました。
現代の民間霊園は?

ただ現代の民間企業が運営する、いわゆる民間霊園においても墓地の権利は「永代使用権」としています。
●民間霊園でも墓地全体を管理する必要性から、基本的に「永代使用権」が一般的です。
→個々の所有にしてしまい自由に墓地区画を譲渡されたり、貸し借りされることで、墓地全体としての管理維持が難しくなります。
また墓地の区画は小さく大量に分譲されますから、大変なこともあるでしょう。
このようなことから、墓地の権利自体を購入してしまうことは、霊園管理上で現実的ではありません。
民法としてはどうなるの?
そこで墓地の権利関係の仕組みは、昔から伝わる風習から特殊な権利の仕組みと言えますが、民法としては下記のような権利とも考えられます。
・地上権(物権)
・貸借権
・使用貸借権
ただ昔からの風習的な墓地の権利の仕組みですが、行政上の許可においても「永代使用権」に倣っているでしょう。
永代使用権は所有権ではない
このようなことから、墓地の権利は所有権ではなく永代使用権なので、マイホームを建てる時に購入する土地のように、下記のような事柄はできない霊園がほとんどです。
・第三者に墓地の権利を譲渡する
・霊園に墓地の権利を買い戻してもらう
ただ墓地には昔から続く古い墓地もあれば、新しく作られた霊園もあり、法的にどのような扱いになっているのか、グレーな部分も多いです。
民間霊園など新しいシステムの霊園であれば、契約時に交わされる契約書や使用規約に、永代使用権について明記されているでしょう。
一方、昔ながらの寺院墓地などの場合は、その寺院や土地の歴史、昔ながらの風習によって判断することもあります。
寺院墓地の場合

また新しい民間霊園は宗旨宗派を問わない施設が多いですが、昔ながらの寺院墓地の場合は、宗教施設です。
そのため宗教上の決まり事にも左右されるでしょう。
<寺院墓地は宗教施設>
・檀家になる必要がある
・宗派に倣ったお墓を建てる
※この他、それぞれの寺院の決まり事に倣う
寺院墓地から宗旨宗派を問わない民間霊園へ改葬(お墓の引っ越し)をしたい場合、まずは寺院墓地のご住職へ相談をして、許可を得なければなりません。
この際、檀家から離れる選択も多いですが、檀家から離れる料金として「離檀料」を支払うことも多いです。
目安としては約5万円~20万円ほどですが、そもそも「離檀料」も昔ならの風習のひとつですから、決まり事はありません。
寺院によって離檀料の金額もさまざまで、そのために離檀料トラブルもごく稀にですが起こります。
寺院墓地と霊園
ここまで寺院墓地と民間霊園に分けてお伝えしてきましたが、お寺の境内にある墓地が寺院墓地です。
●一方「民間霊園」「霊園」と呼ばれる墓地は共同墓地であり、寺院に付属したものではありません。
民間霊園の墓地所有権は霊園を経営する企業であり、特定の宗旨宗派で供養行事を行うことはあっても、寺院の所有ではないことで、宗旨宗派不問の霊園が多くなります。
ただいずれにしても霊園の管理や維持の必要性から、寺院墓地や民間霊園でお墓を建てても、墓地の権利は「永代使用権」であることが多く、第三者への譲渡や貸し借りはできません。
永代使用権が失われる時

お墓を建てる時に墓地それぞれに使用規約があり、そのなかに墓地の権利である永代使用権や、その取り消しについても明記してあるはずです。
・年間管理料について
・墓地使用者の資格
・墓地使用の規定
・墓石や設備の規定
・墓地施設使用の規定
・墓地の継承
・(寺院墓地など)宗旨宗派の規定
…など。
契約時にはこの使用規約を確認してから契約を交わします。
この使用規約に基づき、下記のような事柄で永代使用権が失われる可能性があるでしょう。
・一定年数、年間管理料が滞納された
・一定年数、墓主と連絡が取れない
・一定年数、継承者がいないまま放置された
・契約時に偽りがあった
・(寺院墓地の場合)墓主の改宗
・(寺院墓地の場合)規定の宗旨宗派以外での法要
…などなど。
この他、墓地の譲渡や貸し借り、お墓以外の目的で使用されたなど、使用規約から逸脱した行為があった場合に、永代使用権は失われます。
永代使用料は返還されない
また墓地使用の権利である永代使用権が失われた場合、そのお墓は撤去され、埋葬していた遺骨は無縁仏として供養塔などに合祀埋葬される流れになるでしょう。
この時、戸建て住宅の住宅地のように売却する訳でないので、永代使用料は返還されません。
最後に
以上が墓地の権利である「永代使用権」についてです。
墓地を購入すると、永代に渡り使用する権利である「永代使用権」を得ることができますが、所有権ではないため、墓地の譲渡や貸し借りはできません。
また所有権を購入して売却する訳ではないので、永代使用権が失われた時にも、今まで支払ってきた永代使用料は返還されない点も、予め理解して契約を進めてください。
永代使用権が失われるケースで最も多い原因は、
・継承者の不在
・年間管理料の未納
年間管理料が未納になるのも、継承者が不在だからでしょう。
実際にお墓と共に家督を継ぐ時代ではない現代、相続において負担の大きいお墓の継承は、相続人の揉め事の原因にもなっています。
近年では無縁仏にならない解決策として、家族に代わり霊園が永代に渡り遺骨の供養をする「永代供養」が注目されるようになりました。
永代供養は形のないサービスなので、お墓にも付加できますし、納骨堂や合祀墓でも永代供養は可能です。
※永代供養については下記記事をご参照ください。
・永代供養は合祀墓だけじゃない!納骨堂や集合墓、個別スペースが確保される5つの永代供養
まとめ
墓地の権利「永代使用権」とは
●永代使用権とは
・永代に渡り購入した区画を使用できる権利
・法律上の言葉ではない
・第三者に譲渡や貸し借りはできない
・永代使用権の買い戻しはできない
●永代使用権が失われることもある
・年間管理料の未納
・使用規約に反する行為
・継承者の不在
●永代使用権が失われると
・お墓は撤去
・遺骨は無縁仏として供養塔に
お電話でも受け付けております















