
【おひとりさま老後生活】孤独死を避ける6つの対策|孤独死が起きやすい8つの環境とは
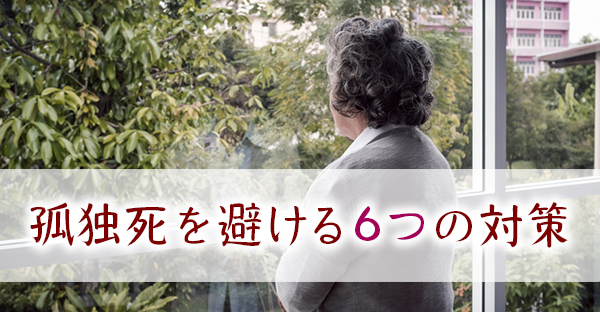
おひとりさま老後では孤独死への対策を充分にして、安心して過ごしたい人が多いですよね。
近年では少子化高齢化が問題となり、単身高齢者世帯の孤独死ケースが増えています。
孤独死への対策をしていないと、(1)発見までが遅れる可能性、(2)家族への迷惑、などの恐れを持ったままの暮らしになりがちです。
心配や不安を抱えたままの老後生活は、趣味を見つけて充実しにくい傾向もあるので、これからお伝えする孤独死への6つの対策を試してみてはいかがでしょうか。
【おひとりさま老後生活】孤独死を避ける6つの対策|孤独死が起きやすい8つの環境とは

家庭内別居でも孤独死はある

孤独死への対策を検討する前に、そもそも「孤独死」がどのようなものか…、理解しておくと良いでしょう。
「孤独死=高齢世帯」と考えられがちですが、例え若くても孤独死はあり得ます。
●孤独死とは、高齢者のみならず若い世代でも同じく、ひとり暮らしやそれに近い生活をしているなかで、何らかの病気で亡くなることを言います。
ですから孤独死への対策は、自分亡き後に早い段階で誰かに見つけてもらうこと、そして死後の対処を進めてもらう方法です。
…では、具体的にどのような環境や状況下で孤独死が起きたのでしょうか。
実は家庭内別居などでも、孤独死が起きています。
孤独死が起きやすい8つの環境
高齢者のひとりくらし世帯が孤独死対策を進めるためには、まずどのような環境・状況下で孤独死が起きやすいのかを理解し、回避する考え方があります。
孤独死対策では、孤独死が起きやすい環境を何らかの方法で解消する、考え方が最も近道です。
ここでは孤独死が起きやすい8つの環境と、その反対になり得る対策をお伝えします。
| <孤独死が起きやすい8つの環境> | ||
| (1) | ひとり暮らし世帯 | 老人専用住宅などの検討 |
| (2) | 仕事をしていない | 定期的な活動の場を見つける |
| (3) | 親族の付き合いがない | 定期的な電話・挨拶状 |
| (4) | 持病のある | 訪問医などを検討する |
| (5) | 隣人付き合いがない | 自治会などに参加する |
| (6) | 男性高齢者のひとり世帯 | 男性高齢者の特性を理解する |
| (7) | パートナーがいない | お茶友達などを広げる |
| (8) | ひきこもりがち | 定期的に外に出て挨拶をする |
男性の高齢者に多い特性とは、女性の高齢者よりも比較的ひきこもりがちになることです。
1日10分でも良いので、庭いじりなど外に出るだけでも、意外と近隣の人々は見ています。
「あれ、おかしいな?」「どうしたのかな?」
そう思ってもらえる生活をすることで、自然と孤独死対策に繋がるでしょう。
孤独死の具体的な事例

ひとつの事例として、ひとり暮らしをご紹介しましたが、家庭内別居でも孤独死が起きるとお伝えしたように、(1)早くに発見されない(2)看取りがない、死を孤独死と表現する人が多いです。
・ひとり暮らし
・誰にも看取られなかった
・当人の自宅
・ひとり暮らしなかでの突然の疾患などにより死亡すること
孤独死の対策はどの世代でも必要ではありますが、若い世代は働いている人が多いため、毎日職場の人々と関わりがあります。
そのため、日ごろ真面目に勤めている人が無断欠勤をすることで、異変を感じる職場の人々も少なくありません。
●一方、高齢世帯は定年退職により、世間との密な関わりが薄れているひとり暮らし世帯が多いです。
そこで高齢者のひとり暮らし世帯で、特に孤独死への対策が注目されています。
また、突然の疾患などで数日間遅れて発見されるということも十分にあり得ます。
日々の連絡が途絶えて心配なら、一度、ご自宅を訪問するようにしましょう。
孤独死への対策が必要な理由
では、なぜ現代において孤独死を避ける対策が不可欠とされているのか、その理由をお伝えします。
まず、孤独死をすることで残された周囲のものに問題が発生ことを覚えておきましょう。
問題が発生するのは以下のものです。
・不動産価値の下落
・遺族、または、行政が行う死亡人の処理
・遺族に負担が発生する
問題を見ると、残された者の都合のようにも思えますが、当人にとっては孤独死への対策を取ることで、外とのコミュニケーションが産まれて、より充実したシニアライフのきっかけになることもあります。
孤独死への対策を進めたことで、薄れていた子どもや親族との繋がりが復活する事例も多くありました。
「孤独死をしてしまっては仕方がない!」と思うかも知れませんが、事前に孤独死への対策取ることで、急な事態でも遺族が対応できるのもメリットです。
孤独死を回避する6つの対策

当人にとっては孤独死への対策を取ることで、ただ死を待つような時間を過ごす日々から払拭されます。
現実的な部分では、身内(家族)と一緒に暮らすのが1番の対策方法でしょう。
けれども現代の日本では、場所や家族構成などから叶わない人も少なくありません。
では、自ら対処できる孤独死を避ける対策には、どのようなものがあるでしょうか。
(1)訪問サービスを利用する
(2)見守りカメラなどを使う
(3)ご近所の方々との交流を持つ
(4)毎日の健康的な食生活を心がける
(5)snsで交流する
(6)通所サービスを利用する
近年では、各市町村で高齢者世帯への孤独死対策が行われています。
各市町村の孤独死対策
孤独死対策は、市町村だけではなく、国全体で考えられています。
・住んでいる地域の各自治体
・ボランティア
・NPO団体
…など。
ボランティアやNPO団体などを利用する場合も、住んでいる地域の自治体などで相談してみると、身近なところで紹介してくれるケースは多いです。
各市町村の自治体でどのような孤独死対策が行われているのかを確認し利用しつつ、民間のサービスと上手に組み合わせ、検討してみてはいかがでしょうか。
訪問サービスを利用する
訪問サービスと言うと介護目的のイメージが強いですが、各種訪問サービスを利用することで、死後に発見が遅れるリスクを防ぐメリットがあります。
・毎週月曜日に宅配サービスがくる
・毎週月曜日~金曜日はヘルパーさんが来る
…などなど。
定期的に訪問サービスが来ることで、何かあった時にも発見してもらえるため心強いです。
見守りカメラなどを使う

一方、要支援や要介護にも当たらない元気なシニア世帯では、見守りカメラを導入する方法もあるでしょう。
子どもが定期的に親の家を訪問する孤独死対策もありますが、今では産まれた地域にずっと住む人も少なくなりました。
遠くに住む、高齢者に定期的に連絡を取るのは簡単なことではありません。
見守りカメラは月々契約のプランから、個人で設置するものなど、価格帯までさまざまです。
毎日、電話やメールでやり取りできるのが1番の理想ですが、現代では、様々な理由から、連絡を取る手段が少なくなっています。
そんなときは、見守りカメラを活用するのも一つの手です。
外出時でもアプリを開くだけで、家の中を確認できたり、防犯上の役割も果たしてくれるでしょう。
ご近所の方々との交流を持つ
高齢者のひとり世帯が自分でできる孤独死対策では、日ごろから挨拶を交わすほどで良いので、ご近所との交流を保つ方法です。
今では定時に外出して近所との交流を計るために、ペットを飼うケースも増えました。
●毎日定時に顔を合わせ挨拶をしているなど、ご近所との交流があれば「今日は〇〇さんいないみたい」という話になるでしょう。
→ 毎日、家の前の掃除をしているのに、突然と掃除をしなくなって家の中にこもっているという事態になると、「大丈夫かな?」と思いますよね。
周囲の人の交流があることで、万が一の事態に対応できると考えられます。
また、女性よりも男性の方が孤独死にする件数が多く、男性は周囲の人との関わりを持たず、一人でこもりやすい傾向にあることも、ぜひ意識をしてください。
● 自分から地域のイベントなど、積極的に参加することや、近所の人と交流を持つことで、孤独死対策だけではなく、充実したシニアライフにも繋がります。
毎日の食生活を心がける

毎日の食生活を正すことも重要です。
実は最近では、毎日健康的な食事を配達してくれるサービスも見受けるようになりました。
健康的な食事をしながら、定期的な訪問が期待できるため、孤独死対策に重宝されています。
・元気な時の体力を維持する
・バランスの取れた食事
・夜ふかししない
・早起き
・適度な運動
・身体に異常が見られたらすぐに病院に行く
食事宅配の見守りサービス
前述した食事の宅配サービスでは、高齢者のひとり世帯に向けて、安否確認など見守りサービスを実践している業者も増えました。
| <見守りサービスがある宅配サービス業者> | |||
| (1) | ヤクルトの宅配見守りサービス | 週1回 | 500円~1000円/7本 |
| (2) | コープのお弁当宅配 | 1日1回 | 530円~700円/1食 |
| (3) | シルバーライフグループふれ愛 | 1日1回~2回 | 486円~540円/1食 |
| (4) | 宅配クック123 | 1日1回~2回 | 540円~594円/1食 |
| (5) | ワタミ、まごころスタッフ | 1日1回~2回 | 390円~580円/1食 |
業者によっては手渡しでの宅配としていたり、宅配の度に声掛けをして安否確認をしてくれるサービスもあります。
ただ反対に、毎回の声掛けや手渡しをおっくうに感じる人もいるでしょう。
それぞれの希望に合わせて選んでください。
SNSで交流する

孤独死をしないためにも、SNSを活用するのも一つの手です。
自分と同じ境遇の方や同一な趣味を持つ方は、SNS上にたくさんいます。
常にひとりでいるという認識を無くして、繋がりを絶やさないことも大切です。
上記一例では、NPO法人エンリッチを通したコミュニティでしたが、FaceBookやInstagramなどのSNS上では、高齢者向けのコミニュティもあるので、検討してみてはいかがでしょうか。
通所サービスを利用する

見守りカメラだけでは不安という人は、通所サービスを利用すると良いでしょう。
要支援や要介護認定を受けている場合は、ケアマネージャーに無料でケアプランを作成してもらうことで、自己負担もほぼなく、孤独死対策も可能です。
●「通所サービス」とは、デイサービスやデイケアのを差します。
ただ心も体も元気なシニアにとっては、ディサービスの内容に不満を感じる人が多い点も否めません。
大切なポイントは定期的に活動する場を持つことなので、地域のサークルなどでも良いでしょう。
元気な高齢者の定期的な活動
通所サービスに抵抗を覚えるのであれば、反対に今までの経験を生かして、子ども達などへ教える活動もできるかもしれません。
その他、元気な高齢者は自分が介護ボランティアを行う選択も一案です。
●自治体によって、元気な高齢者が介護ボランティアを行うと、ポイントが貯まる制度も見られます。
ポイントの使い方は自治体によって違いますが、現金や商品への交換などの一例があります。
孤独死対策だけではなく介護予防にもなるうえにポイントが貯まり、一石二鳥、三鳥ではないでしょうか。
どのような形でも定期的に通う場所を作っておけば、万が一の事態でも対応してくれるのでオススメです。
最後に
以上がおひとりさま老後に役立つ、孤独死対策6つの対策です。
ただ高齢者のおひとりさま世帯が最も安心できる孤独死対策は、誰かと共に住むことでしょう。
けれども一緒に住む人々は、必ずしも家族や配偶者である必要はありません。
例えば、元気な高齢者の人々専用の高齢者住宅では、フロントに看護師が常駐し、部屋からコールができる仕組みの住宅もあります。
また、レクレーションルームやトレーニングルーム、カラオケ設備など、高齢者の充実した暮らしを支援する設備が充実した高齢者住宅もありました。
もちろん、老人ホームや介護施設の他、高齢者同士のシェアハウスなども見受けます。
孤独死対策を早めに済ませて不安を払拭し、充実したシニアライフを満喫してみてはいかがでしょうか。
まとめ
孤独死が起きやすい8つの環境、孤独死6つの対策
●孤独死が起きやすい8つの環境
(1)ひとり暮らし世帯
(2)仕事をしていない
(3)親族の付き合いがない
(4)持病のある人
(5)隣人付き合いがない
(6)特に男性の高齢者
(7)配偶者と離別/死別/未婚
(8)ひきこもりがち
●孤独死6つの対策
(1)訪問サービスを利用する
(2)見守りカメラなどを使う
(3)ご近所の方々との交流を持つ
(4)毎日の食生活を心がける
(5)snsで交流する
(6)通所サービスを利用する
お電話でも受け付けております















