
檀家をやめるにはどうしたらいい?方法や費用とポイントもあわせて紹介

「檀家をやめたいけど、自由にやめることってできるの?」
「檀家をやめるときの手順や手続き、かかる費用が知りたい」
「檀家をやめた後の仏事が心配」
檀家をやめることを考えている場合、多くの人が離檀に対する疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では離檀に必要な手続きや費用などの基礎知識に加え、菩提寺への離檀の伝え方や気を付けたいポイントを紹介しています。また、離檀後の葬儀や法事・法要といった仏事についても紹介しているため、あわせて確認できます。
離檀に必要な知識を身に付けることで、家族や親族、菩提寺と良好な関係で檀家をやめられるでしょう。
檀家をやめる「離檀」について詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
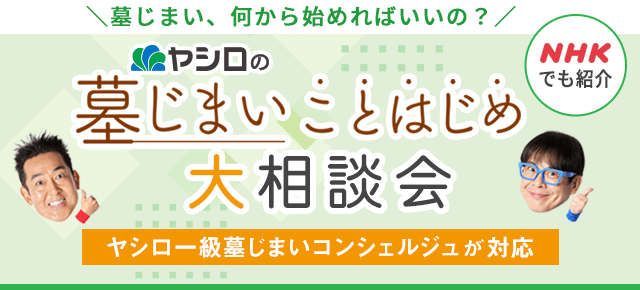
檀家をやめることはできるの?

檀家をやめることは可能です。ただし、檀家をやめる前にいくつかの手順や手続きを踏まなくてはなりません。また、檀家をやめるための費用が発生することが多いため、お金の準備も必要になります。
スムーズに檀家をやめるためにも、事前に準備しておくことが大切と言えるでしょう。
檀家をやめたい人の主な理由

江戸時代の寺請制度に由来する檀家制度により、日本では全ての世帯が檀家になっていました。しかし時代が移り変わり、様々な理由や事情などから檀家をやめたいと考えている人が増えています。
檀家をやめる主な理由としては、転居や継承者の不在、経済的負担、また宗教観の変化が挙げられます。たとえば、檀家となっているお寺(菩提寺)から遠く離れた場所に転居することにより、お葬式や法要などが物理的に困難となってしまうなどです。
檀家をやめる「離檀」の流れ

檀家をやめる「離檀」には様々な準備や手続きが必要になり、一足飛びでいかないのが現状となっています。
ここからは、スムーズに離檀を進められるよう基本的な流れを紹介していきます。離檀を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
お寺に相談・離壇の旨を伝える
離檀することを決めた場合、まずお墓がある菩提寺に相談し檀家をやめることを伝えましょう。
伝える際はいきなり離檀したいというのではなく、檀家をやめる考えに至った経緯や理由について住職に伝え、きちんと納得してもらえるように話をすることが大切です。また、離檀については早めに菩提寺に相談しておきましょう。
菩提寺に改葬許可証が必要かを確認する
檀家をやめる場合、遺骨を他の場所に移す「改葬」が必要です。改葬を行う際には、現在のお墓がある自治体から改葬許可証を発行してもらわなくてはいけません。
この改葬許可証が必要になるのは、他の墳墓や納骨堂に移す場合であるため、自宅で遺骨を保管するときには原則、改葬許可証は必要ありません。
ただし、自治体によっては、遺骨を自宅で安置する場合でも改葬許可を取らなければいけないことがあるため、事前にお墓がある市町村に確認しておきましょう。
新しいお墓から受入証明書・菩提寺から埋蔵証明を受け取る
改葬許可証を発行してもらうためには、新しいお墓の受入証明書と現在のお墓の埋蔵証明書が必要です。
受入証明書は、遺骨の移動先である墓地の管理者に作成してもらいます。一方、埋蔵証明書は、今あるお墓に誰の遺骨が埋蔵されているのかを証明するものであるため、お墓の管理者である菩提寺に作成してもらう必要があります。
自治体の諸手続きを行う
一般的な改葬の主な流れと手続きは、以下の通りです。
1.移動(改葬)先の墳墓、納骨堂を決める
2.改葬許可申請書の取得、現在のお墓の管理者から埋蔵証明書を受取る
3.改葬許可の申請および改葬許可証の受取り
4.遺骨の取り出し
5.改葬先へ遺骨の埋蔵・収蔵
先述した改葬許可証の「申請書」の受取り、改葬許可の申請、改葬許可証の受取りについては、現在のお墓がある市町村役場で行います。
また、遺骨を取り出す際は、市から発行された改葬許可証を菩提寺に提示する必要があります。そのため、事前に準備しておくことを忘れないようにしましょう。
閉眼供養を行う
離檀とともに菩提寺のお墓をしめる場合には、閉眼供養してもらいます。閉眼供養とは、お魂抜きや性根抜きとも呼ばれており、お墓に宿った故人の魂を鎮めて抜き取る供養のことを言います。
閉眼供養は遺骨を取り出す日か、お墓を撤去する前にお寺の住職によって行われます。
墓石を撤去する
閉眼供養まで済ませた後は、いよいよお墓の撤去になります。お墓を撤去するためには、石材店に作業を依頼しなくてはいけません。
このとき注意したいのが、寺院によっては石材店を指定しているケースがあることです。檀家をやめるときに、石材店についても寺院に相談しておくとよいでしょう。
墓じまいをした後の供養の選択肢

墓じまいをした後の選択肢としては永代供養墓や合祀墓に移したり、あるいは海や山といった自然に散骨したりすることが挙げられます。
ここからは、墓じまい後の供養の選択肢について紹介していきます。
永代供養墓に遺骨を移す
永代供養墓とは、納骨後の供養や管理を寺院や霊園などが永代に渡り行ってくれるお墓のことを言います。
また、ひと口に永代供養墓といっても様々な種類があり、墓石の代わりに樹木や花壇をシンボルとする樹木葬、納骨堂などが挙げられます。このように、故人や家族の意思に応じて選べることも魅力の1つと言えるでしょう。
永代供養墓の「永代」は永遠・永久という意味ではないため、寺院や霊園によっては永代を一定期間と定めていたり、施設が存続している限りとしていたりするケースがあります。契約前に期間をよく確認するようにしましょう。
合祀墓に遺骨を移す
合祀とは、故人の遺骨を骨壺から取り出し、血縁関係に関わらず他の遺骨と一緒に埋葬し合同で祀ることを言います。
合祀されるまでには2パターンあります。1つ目は、葬儀後に個別で安置する期間がなく最初から合祀するパターン、2つ目は一定期間、個別に骨壺で安置し供養され、その後他の遺骨と一緒にされ合祀するパターンです。
合祀墓では他人の遺骨と一緒に埋葬するため、合祀するタイミングについては家族や親族ときちんと話し合って決めるようにしましょう。
散骨をする
散骨とは、故人の遺骨を粉状に加工し、海や山などに撒く供養の仕方です。この散骨には大きく分けて3つの方法があり、海洋散骨、山林散骨、その他の散骨になります。
ただし、いずれの方法でも散骨を行う際には、専門の業者に依頼することをおすすめします。理由としては、散骨するためのガイドラインの存在や、山林所有者や近隣住民などとのトラブルを防ぐためです。
たとえば、海洋散骨の場合では日本海洋散骨協会のガイドラインにより、加盟業者は指定された海域のみで散骨可能とされています。
檀家をやめる際のポイント

先祖代々のお墓がある場合、檀家をやめることは一個人や家族だけの問題ではありません。そのため、檀家をやめる際にはしっかりと主な親族や菩提寺とも相談する必要があります。
ここでは、檀家をやめる際に気を付けたいポイントを詳しく紹介していきます。円満な離檀に向けて、ぜひ参考にしてみてください。
- 親族にきちんと相談する
- お寺には相談する姿勢で連絡する
- お寺に出向いて挨拶をする
- 離壇しないと無縁仏になってしまう可能性について伝える
- しっかりと感謝の気持ちを伝える
親族にきちんと相談する
檀家をやめることは、先祖代々のお墓や菩提寺との関係に関わるため、家族だけではなく親族ともきちんと相談しておくことが大切です。
遺骨を永代供養墓に移す場合は、親族からの同意がなければ改葬した後にトラブルを引き起こしてしまう恐れがあります。檀家をやめる際には、檀家をやめた後についても十分に話し合っておくようにしましょう。
お寺には相談する姿勢で連絡する
親族の話し合いの後には、お墓がある菩提寺に連絡しましょう。ただし、檀家と菩提寺との関係を良好な形で終わりにするためにも、離檀するという結論から一方的に話し始めないように注意してください。
あくまで相談する姿勢で、離檀についての話をするようにしましょう。
お寺に出向いて挨拶をする
離檀することが決まった場合、お寺に出向いて離檀の挨拶を行いましょう。葬儀や法要、お墓の管理など長くお世話になったことに対して、直接挨拶するのがマナーと言えます。
ただし、怪我や病気などやむを得ない事情により、お寺に行けない場合には御礼状を送りましょう。礼状の文例としては以下の通りです。
「長年に渡り、菩提寺としてご先祖様をお守りいただきまして心より御礼申し上げます。このたび、新たな霊園にて永代供養をしていただくこととなりました。お墓は変わりますが、今後とも変わらずご先祖を供養していただければ幸いに存じます。」
離壇しないと無縁仏になってしまう可能性について伝える
檀家をやめる理由として、無縁仏となってしまう可能性を示唆することも大切です。無縁仏になってしまうと、寺院にとっては大きなデメリットしかありません。
具体的にはお墓の管理やメンテナンス、最終的なお墓の撤去・解体費などの負担です。また、お墓の縁故者を探す手間や時間も取られてしまい、さらに寺院にかかる負担が大きくなります。
こうした寺院側にかかる将来的な負担を防ぎ、無縁仏とならないために離檀する必要があることを伝えましょう。
しっかりと感謝の気持ちを伝える
離檀することになった場合、菩提寺にはしっかりと長年お世話になった感謝の気持ちを伝えましょう。
菩提寺は、先祖代々のお墓を守り、葬儀や法要の際には遺族の気持ちに寄り添い支えてきてくれた存在です。菩提寺に対して感謝の気持ちを伝えることで、良好な形で関係を終わりにできます。
檀家をやめる際にかかる費用の種類と目安

檀家をやめる際には改葬の手続きだけではなく、離檀料や閉眼・開眼供養料、お墓の撤去・解体費用など様々な費用が必要になります。
離檀にかかる費用の中で、菩提寺に払う離檀料は長年お世話になった感謝の気持ちを込めたお布施の一種です。ここからは離檀料をはじめ、離檀にかかる費用の種類と目安についてく詳しく紹介していきます。
離壇料
離檀料とは檀家をやめる際に、菩提寺に渡すお布施のことです。この離檀料は法律的な支払い義務はなく、あくまで今までお世話になった感謝の気持ちを込めたものとなります。
また、所属する寺院によっても離檀料に違いがあります。一般的に、離檀料は5万~20万円程度と言われているため、この範囲内で用意するとよいでしょう。
閉眼供養・開眼供養のお布施
離檀にかかる費用には、閉眼供養や開眼供養へのお布施も挙げられます。それぞれの供養に伴うお布施は、一般的に2万~5万円程度と言われています。
閉眼供養と開眼供養の両方を行う場合には、10万円程度と見積もっておくとよいでしょう。
墓石を撤去する費用
墓じまいは墓石を撤去するだけでなく、墓石があった場所を更地にし返還しなくてはいけません。墓石を撤去する費用は、一般的に1㎡につき5万~15万円程度と言われており、お墓一基ごとの場合には20万円程度が相場とされています。
ただし、お墓が建っている土地の大きさや形状によっても費用が変わってしまうため、事前に石材店に見積もりをお願いしてみるとよいでしょう。
新しいお墓にかかる費用
檀家をやめた場合、お墓の移設先は別の霊園などに新たなお墓を建てるケースと、今までお世話になっていた菩提寺の敷地内にある永代供養塔に合祀するケースなどに分けられます。
たとえば、霊園などに新しくお墓を建てる場合は、土地の使用料や墓石の建立費用が発生します。また、新しく建てたお墓が永代供養墓であれば、永代供養料も必要になるでしょう。
改葬にかかる全体の費用は、100万~300万円程度が相場とされています。ただし、新しい供養先やお墓の立地などによって費用が変わってくるため、事前に確認しておくことが大切です。
永代供養にかかる費用
離檀後のお墓の移設先として、霊園などの永代供養墓を選ぶ人もいるでしょう。永代供養墓の場合、発生する費用はいつから合祀するかで大きな差があります。
最初から遺骨を合祀するケースでは10万~30万円程度、一定期間の安置後に合祀するケースでは100万円程度が相場です。
離壇を相談してからやめるまでにどのくらいの時間がかかる?

離檀にかかる時間は、平均で2か月~6か月程度となっています。しかし、改葬先が決まらなかったり、菩提寺から離檀に対して難色を示されたりすると改葬の手続きが進まなくなります。
スムーズな離檀を行うためにも、菩提寺への離檀の伝え方や改葬先の選定などをしっかりと準備しておくことが大切です。
檀家をやめたら葬儀や法事はどうすればいい?

最近では、檀家でなくても行える無宗教葬(自由葬)や偲ぶ会として葬儀などを行えるようになっています。また、お墓で営む法要のときにのみ決まった寺院で行う、墓檀家と呼ばれるシステムもあります。
離檀後の葬儀や法事・法要の仕方については様々なものがあるため、家族や親族と相談しながら決めていきましょう。
檀家をやめる際にお寺とのトラブルを避けるためにするべきこと

離檀する理由や伝え方、また離檀料などによっては菩提寺とのトラブルにつながってしまうことがあります。ここからは菩提寺とのトラブルを避け、円満な離檀を行うために注意すべきポイントを紹介していきます。
本当に檀家をやめるべきかをよく検討する
離檀の相談を菩提寺に伝える前に、本当に檀家をやめるべきかどうかを検討しましょう。檀家であるデメリットだけでなく、檀家であることのメリットも合わせて考えておくことが大切です。
また、遠方への引っ越しが理由で離檀する場合には、菩提寺にその旨を相談してみましょう。寺院によっては、遠方でも葬儀や法事に来てくれることがあります。さらに、最近ではオンラインでの法事や供養もあるため、引っ越しをしたとしても檀家を続けることは可能です。
金額で折り合いが付かない場合は宗派の本山に相談する
檀家をやめる際に、菩提寺から離檀料を請求されることがあります。場合によっては高額になってしまうケースもあり、菩提寺と金額の折り合いが付かなくなってしまうこともあるでしょう。
菩提寺との話し合いで解決しない場合には、宗派の本山に相談してみてください。
離壇にかかる費用と内訳を事前に確認しておく
檀家をやめる場合、離檀にかかる費用と内訳を事前に確認しておきましょう。離檀するためには菩提寺にあるお墓の改葬が必要になり、それにかかる費用も発生します。寺院によっては、離檀料の中にお墓の撤去・解体費用や、閉眼・開眼供養料も含んでいるケースがあります。
菩提寺とのトラブルを防ぐためにも、檀家をやめる意向を伝えたら離檀にかかる費用についても尋ねてみてください。
檀家をやめる方法や費用などについて知っておこう

本記事では、檀家をやめる「離檀」の流れや費用、また離檀する際のポイントなどについて詳しく紹介してきました。
長い間お世話になった菩提寺に対して感謝の気持ちと、誠意をもって離檀への意向を伝えることで、お互いにとって円満な形で離檀できるでしょう。
檀家をやめることを考えている場合には、本記事を参考にトラブルなく離檀できるようにしましょう。
お電話でも受け付けております















