
永代供養のその後とは?初盆や法要にかかる費用やお墓参りについて解説

「永代供養した後はどのようにすれば良いの?」
「初盆や法要にかかる費用の相場はいくら?」
「お墓参りについてはどのようにすれば良い?」
このように永代供養したその後、どのような手順を踏めば良いのか悩んでいる方はいませんか。
本記事では、永代供養したその後の一般的な供養方法や遺骨をどうすれば良いのか、初盆や法要にかかる相場とその内訳、お墓参りの方法などを解説しています。
この記事を読むことで、永代供養したその後の大まかな流れや必要な手続きなどが、理解できるでしょう。また、一般的な法要の手順やお墓参りで気を付けるべきなども紹介しているため、スムーズに進められるでしょう。
永代供養したその後の流れについて知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
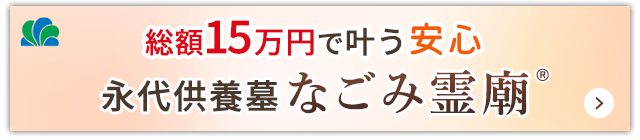
永代供養した後に行われる一般的な供養方法

まず「永代供養」とは、霊園などが代行して供養を行うことです。永代供養すると、お墓に関する管理は寺院や霊園がすべて行ってくれます。
ここでは、永代供養した後に行われる一般的な供養方法を主に5つに分けて、解説していきます。
春・秋のお彼岸に行う供養
永代供養での代表的な法要の時期は、春と秋のお彼岸に行われる法要です。
春のお彼岸は春分の日を挟んで前後3日間で、秋のお彼岸は秋分の日を挟んで前後3日間をいいます。春と秋のお彼岸の法要は、この7日間のどこかで行われるのが一般的です。
年忌法要
年忌法要とは、仏教上で定められた七回忌や十三回忌などの命日に行う法要のことです。永代供養がされた寺院や霊園によって、年忌法要をするタイミングは異なってきます。
寺院の行事にあわせて、行事が行われる年度内の故人の戒名をまとめて読み上げてもらう方法と、個別に法要の開催日を選んで遺族側から依頼して、年忌法要をしてもらう方法があります。
寺院や霊園の行事にあわせて行う場合は、寺院や霊園のやり方にすべてを委ねるため、遺族が施設先に足を運んだり、法要を仕切ったりする必要がありません。もちろん、費用もかかりません。
その代わりに、法要を開催する日を寺院や霊園が決める日に従わなければなりません。また、個別の法要はできませんので注意しましょう。
・永代供養での三回忌などの年忌法要は可能か?服装や費用・お墓参りの仕方も解説
祥月命日の供養
祥月命日とは、一般的に命日といわれる、故人が亡くなった月日と同じ日のことです。一周忌以降の月日を指す言葉として使います。9月13日に亡くなった人の場合の祥月命日は、次の年からの9月13日です。
永代供養の法要は、寺院や霊園によっては、故人の祥月命日に合わせて行われるところもあります。
月命日の供養
月命日とは、故人が亡くなった日のことで、祥月命日の月以外は、毎月あります。
例えば、亡くなった日が9月13日の場合は、9月を除く毎月13日が月命日です。つまり月命日は1年に11回あることになります。
定期的に法要を行いたい場合は、月命日に法要を行う寺院や霊園を選ぶとよいでしょう。
毎月1回の供養
毎月1回の法要とは、月命日とは違い、毎月1回決められた日に合同で行われる法要です。
永代供養の手続きを終えたその後も、きめ細やかな法要を受けられるようにしたいと考える人は、毎月1回法要を行ってくれたり、毎日読経をしてくれたりするような寺院や霊園を探してみると良いでしょう。
・故人さまと逢える大切なひととき、ヤシロが真心こめて永代供養いたします。
永代供養後の遺骨は?

では、永代供養をした後の遺骨は、どのように処理するべきなのでしょうか。生前に家族内で相談して決めている場合もあれば、代々伝わってきた方法をとる場合などがあります。
一般的に遺骨は、識別できるように個別安置をするか合祀墓で合葬するかの2つです。以下では、それぞれの方法について詳しく解説していきます。
個別安置後に合葬
永代供養したその後、すぐには合葬せずに決められた一定期間、個別安置する場合があります。この場合は、期間内であれば遺骨が骨壺に埋葬されているため、他の遺骨と混ざることはありません。一定の期間が過ぎると、合葬されます。
一般的な個別安置の期間は、三十三回忌まででしょう。初めから合葬する場合よりも、費用がかかる点には注意しましょう。
いつから個別安置期間が始まる?
個別安置期間は施設によって異なりますが、永代供養が終了した後から始まり、一般的には三十三回忌までです。なかには、十七回忌や五十五回忌に設定している寺院などもあります。
合祀墓で合葬
合祀墓とは、遺骨を家族や他の人などと識別せずに埋葬するお墓を指します。そのためこの場合には、遺骨を識別せずに1つにまとめた後、一度に供養するのです。
他の遺骨と混ざってしまいますが、費用は個別安置する場合に比べて安く済ませることが可能です。
合葬されると遺骨は返還できない
合葬する際の注意点として、合葬した後、遺骨は返還できなくなってしまいます。これはすべての遺骨を混ぜることで、識別がつかない状態になってしまうためです。
よって、合葬した後は、遺骨を他の場所へ移すことができなくなります。人によっては散骨などを望む方もいるため、確認をしてから判断しましょう。
・永代供養はどこに納骨される?
永代供養後の初盆や法要

永代供養した場合、故人の冥福を祈り、親族が集まる場を設けたいと考える方も少なくないでしょう。その際には、初盆や法要を行うという選択をすることも可能です。
初盆や法要については、永代供養の際に契約に含まれることもあるため、必要であれば契約する前に伝えておきましょう。
ここでは、永代供養後に遺族が行う法事や供養にはどのような例があるかを解説します。あくまでも一般的な目安になるため、参考にしてみてください。
初盆や法要を行う意味
初盆(新盆)とは、故人が亡くなったその後、初めて迎えるお盆に行う追善法要です。もし、お盆の前に亡くなった故人はその年のお盆に、またお盆が過ぎてから亡くなった故人は次の年のお盆が初盆になります。
この時期は家族や親族が集まりやすいため、永代供養であっても初盆に法要を行う方も多いでしょう。
何回忌まで法要を行うか
年忌法要や回忌法要は、必ずしもしなければならないという決まりはありません。一般的な目安だと、三回忌までは法要を行っても問題ありません。
遺族によっては、三十三回忌や五十五回忌まで行う場合もあります。確実に何回忌までと決められてはいないため、代々受け継がれているしきたりに合わせたり、相談しあったりして決めるのが良いでしょう。
永代供養にしたその後の法要の手順

永代供養を選んだけれど供養を行いたい場合には、どのような手順をとれば良いのでしょうか。また、一般的な法要と異なる点はあるのでしょうか。
ここでは、永代供養した後の法要の大まかな手順を解説します。
家族や親族に日程の相談
まずは、家族や親族など故人と親しい間柄であった人に、法要について相談しましょう。法要の連絡は突然してしまうと都合がつかない場合もあるため、日程が抑えやすい数か月前に伝えておくことがおすすめです。
喪主や遺族だけで決定してしまうと、親族の間柄でトラブルが起きてしまう可能性もあります。トラブルが起きないようにするためにも、計画性を持ちながら早めに日程は相談しておきましょう。
納骨先に法要の相談・依頼
法要の相談をした後は、永代供養を依頼している納骨先に法要の相談をしておきましょう。この時に、決定した法要の日程や参加人数などを明確にして、一緒に伝えます。
永代供養では、永代にわたり第三者がお墓を管理し、供養する方法であるため、契約上では3回忌法要までを執り行ってくれる場合もあります。
ただし、施設によっては個人の法要ができない場合もあるので、法要ができるのかを事前に確認することを怠らないようにしてください。
法要当日
法要当日は、参列しに来た方々や僧侶などに丁寧なあいさつや気配りを忘れないようにしましょう。喪主は法要がスムーズに進むように、その日の流れを頭に入れておくようにします。
法要が終了したら、お墓参りをします。この際に線香や献花に加えて、故人が生前に好きなものや大切にしていたものなどを持ち合わせておくのがおすすめです。
ただし、施設によってはお供えものができないこともあります。事前に施設のルールを確認しておきましょう。
法要でかかる費用とは

永代供養をしたその後に法要を行う場合、かかる費用には場所代、お布施、お線香やお花・お供え物、会食代、御膳料・御車代があります。
挙げた5つの費用はどれぐらいが相場でしょうか。見ていきましょう。
お布施
法要をする時にお布施を用意しますが、永代供養をした後に、年忌法要を行う場合のお布施は、最初に永代供養を契約した時の契約料に含まれていることが多いため、そういう場合は用意する必要はありません。
しかし、契約内容で別とされている法要の場合は、お布施の用意が必要になるため、前もって確認しておきましょう。
お布施の相場は、およそ3万円~5万円とされていますが、寺院や地域によって相場は変わってくるため、寺院に確認をすることをおすすめします。お布施はいくらですか、といった聞き方ではなく、他の方はいくら包んでいますかと聞きましょう。
場所代
永代供養をしたその後の法要を自宅で行う場合は費用はかかりませんが、寺院やセレモニーホールで行う場合は、場所代がかかります。
場所代の相場は、寺院で法要を行うとだいたい3千円~2万円程度といわれています。また、セレモニーホールを利用する場合は3万円程度をみておけば良いでしょう。
中には、永代供養先の寺院で法要を行う場合に、最初の契約の時に支払う費用の中にすでに法要にかかる費用が含まれている場合もあるため、契約する時にしっかり確認しておきましょう。
会食代
法要が終わった後、必ず行うものではありませんが、大抵行われるのが会食です。
法要を行った寺院やその近くの食事処などで法要に参加した人で食事をする訳ですが、どんな場所で会食を行うかによって相場は変わってきます。だいたい1人あたり3千円~5千円を目安にすれば良いでしょう。
御膳料
御膳料も御車代も、法要にかかわってくれた僧侶にお渡しするお金です。
法要の後に会食を行ったけれど、僧侶が参加しなかった場合に、御膳料としてその会食の代わりにお金を渡します。相場は5千円~1万円程度です。
御車代
自宅やセレモニーホールなどで法要を行う場合、僧侶にわざわざ足を運んでもらったと考えて、そのお礼の御車代を渡します。こちらは3千円~1万円程度を用意しておけば良いでしょう。
・永代供養の費用について 費用の内訳・相場と失敗しない選び方も紹介
永代供養したその後のお墓参りの方法

永代供養の後にお墓参りをする方法は、永代供養がどのような種類で行われているかで変わってきます。
ここからは、それぞれの種類によって違ってくるお墓参りの方法を詳しく見ていきます。
集合安置型の場合
集合安置型の場合は、遺骨を1カ所にまとめて安置します。そのため、個別で故人が眠る場所を特定するのは不可能です。
全体を見渡せる場所に、大きな香炉や供花台が設置されている場合が多く、お参りはその前で行います。そこで、お線香を焚いて花を供え、手を合わせましょう。
集合安置型のタイプの中には、お供え物は置けないこともあるため、事前に確認することが必要です。
個別安置型の場合
個別安置型の場合はその名の通り、故人がどこで眠っているかが、墓石や故人名が刻印されたプレートなどではっきりとわかります。そのため、お参りの際も、故人が特定できる墓石やプレートの前で手を合わすお参りができます。
大抵の場合、それぞれの場所にお線香やお花を置くところが作られており、そういう場所があればお線香やお花を持参しても良いでしょう。それらの場所があるかないかは、お参りに行く前に必ず確認する必要があります。
納骨堂の場合
納骨堂は、主に建物の中などに遺骨を納められる施設です。最近では、機械が遺骨を運んできて専用の空間で遺骨と対面できるなど、様々なタイプのものがあります。
納骨されている場所に個別にお線香やお供え物が置ける場合はそこでお参りが可能です。納骨堂全体の共同の香炉や供花台が設置されている場合もあります。
それぞれの状況に合わせてお参りする方法も変わってくるため、前もって確認してからお参りに行きましょう。
樹木葬の場合
樹木葬の場合は、墓石の代わりに樹木を墓標とします。樹木にプレートなどがかけられているため、故人が眠る場所ははっきりわかります。そのため、その樹木の前でお参りしましょう。
ただし、お線香が山火事を引き起こしてはいけないからと、焚くことが禁止されていたり、お供え物にも制限があったりと、室外ならではのルールがあります。お参りに行く前に必ず確認をとって、ルール違反にならないよう心がけましょう。
・永代供養のお墓参りの流れとは?お供え物などの注意点や法事についても解説
永代供養後の供養方法やお墓参りについて理解しよう

永代供養にしたその後、遺骨を個別に安置しておく期間や法要・お墓参りについては、永代供養の契約を結ぶ前に家族や親族で検討しましょう。そして、希望通りにできるかしっかり確認することが大事です。
お電話でも受け付けております















