
「終活」とは?何歳で何から始める?終活を進める5つのステップとメリット・デメリット
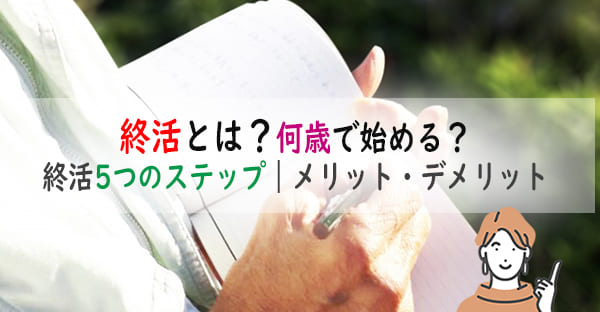
・「終活」とは?
・終活は何歳で、何から始めるといい?
・終活を進めるステップは?
・終活のメリットとは?
・終活にデメリットはある?
「終活」とは自分の人生の終末を見据えて、生きている時間を充実させ、より納得できる最期を迎えるために、生きているうちから準備をする活動です。
2009年に「終活」との造語が発表され、14年の時を経て瞬く間に広がりました。
充実した人生はもちろん、「残される家族に負担を掛けたくない」と考える人が増えています。
本記事を読むことで「終活」とは何か?終活を進める5つのステップとメリット・デメリット、終活を始める年齢やデメリットへの対策が分かります。

終活とは

◇「終活」とは、人生の終わりに向けて考え、活動をすることです
「終活(しゅうかつ)」の始まりは2009年、「現代終活事情」のタイトルで記載された週刊朝日の記事です。
翌年2010年「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされると、映画「エンディングノート」も公開され、広く認知されるようになりました。
| <終活とは> ●人生の終末に向けた活動 |
|
| [具体的な内容] | ・身辺整理(遺品整理) ・相続対策 ・葬儀の手配(遺影準備) ・お墓の手配 ・自分史の作成 ・エンディングノートの作成 …など |
終活の歴史からも分かるように比較的新しい活動で、「終活」ももともと就職活動の「就活」を文字って作られた造語とされます。
2009年頃に終活が広がり初めてから14年、現代はエンディングノートなど、終活を誘導するツールが数多く登場するものの、決まり事はありません。
終活の目的
◇終活の目的は、より良い・納得できる最期に辿り着くためです
終活の目的は本人の意思や希望、家庭環境によっても異なってくるでしょう。
けれども誰しもに言えることは、納得できる最期を迎えるためにあります。
「人生の最期に後悔したくない」
終活を始めるに至ったさまざまな経験から、それぞれに目的を持って進める事柄が終活です。
・残された人生の時間を充実させる
・最期に後悔ないよう準備をする
・家族への気掛かりを解消する
・残された家族の負担を減らす
・自分の理想の最期へ向けて準備をする
そのため「終活でやること」のガイドラインはありますが、重点を置く項目は、個々で違います。
なかには「(充実して)生きるため」に始め、やりたいこと・やるべきことをリストアップし、残された時間でこなす「終活」事例もありました。
終活のメリットとは

◇終活のメリットは、残された人生の時間が充実することです
終活にはさまざまな目的があり、目的によってメリットも異なりますが、共通して言えることは、自分の限られた時間や最期を意識して過ごすことで、充実した今を生きます。
| <終活のメリットとは> | |
| [自分] | ①残された人生が充実する ②自分の気持ちが整理される ③より納得できる最期を迎える |
| [家族] | ④残された家族に遺志が伝わる ⑤残された家族の負担が軽減される |
では親が終活をすることで子どもにどのようなメリットがあるかと言えば、経済的負担もありますが、親の遺志を本人の口から聞くことができる点です。
親が存命する男女400人に向けた子ども世代へのアンケートでは、約65%以上の人々が、終活で使う「エンディングノート」を残して欲しいと答えました。
| <エンディングノートを残して欲しいか?> | |
| ①残して欲しい | …29% |
| ②まだ早いが、いずれ残して欲しい | …約35.5% |
| ③残す必要はない | …34.5% |
| ④すでにある | …1% |
ただしアンケート結果でエンディングノートが「すでにある」と答えたのは僅か1%、終活の認知度に比べて、実際に動き出している人々が少ないことが分かります。
・エンディングノートの書き方まとめ☆欠かせない7つの項目と残された家族に役立つポイント
・ライフメディアリサーチバンク(2014年)
終活のデメリットはある?
◇終活のデメリットとして、親子の意見の相違があります
終活のデメリットが際立つケースのほとんどは、子どもから親へ終活を勧めたケースです。
現代の日本で終活は広く認知されてきてはいるものの、まだまだ高齢の世代からは「生きているうちに死後の話をするなんて!」と考える人も多いでしょう。
| <終活のデメリットとは> | |
| [デメリット] | [対策] |
| ①親子間の意見の相違 | ・寄り添う声掛け |
| ②親族の反対 | ・話し合いの場 |
| ③詐欺にはまる | ・親子で進める |
| ④不安が増強する | ・無理なく進める |
| ⑤知らない生前契約 | ・親子で進める |
良い終活ができるポイントは、親子・家族で進めることです。
子どもから勧める終活であれば、急がず親の気持ちに寄り添い、ゆっくりと話し合いを進めましょう。
また親が終活を勇むあまりに、一人で生前契約をしたため、子どもが葬儀やお墓の生前契約の存在を知らず、葬儀・納骨を済ませてしまった事例があります。
お互いに終活の活動を報告し合い理解し合うことで、デメリットは避けることも充分に可能です。
終活を進める5つのステップ

◇終活は、終末期も含めた老後の準備と、死後の準備に分かれます
終活で進める事柄は、老後の充実した暮らしから、日々衰えて行く心身への対策、終末期と、自分の死期を想定して進めるものです。
そのため人生5つのステップを想定して、下記の手順を進めます。
進めやすいツールとして、エンディングノートを使用すると良いでしょう。
| <終活を進める5つのステップ> | |
| ①老後の準備 | [やりたいことリストを作成] ・交友関係の整理 (リストの作成) |
| ②生前整理 | ・断捨離 |
| ③終末期の準備 (医療の意思表示) |
[終末医療の意思表示] ・延命措置 ・臓器提供など [認知症などの対策] ・家族信託 ・任意後見人 …などの検討 [介護方針の希望] |
| ④死後の準備 | [死後の供養] ・葬儀 ・お墓(遺骨の供養) [死後の手続き] ・死後事務委任契約の検討 |
| ⑤相続の準備 | ・遺言書を完成 ・財産リストを作成 ・相続税対策 |
難しいポイントが専門的知識を必要とする終活です。
例えば認知症対策の家族信託契約や任意後見人契約の他、相続の準備なども専門的知識が必要になるでしょう。
自分で調べて充分に対策できるものもありますが、複雑で進まないようならば、税理士や行政書士など、専門的な第三者に並走してもらうのも一案です。
・【大阪の終活】生前に気になる相続問題の対策とは。知っておくと便利な8つの記事を紹介
終活は何歳から始める?
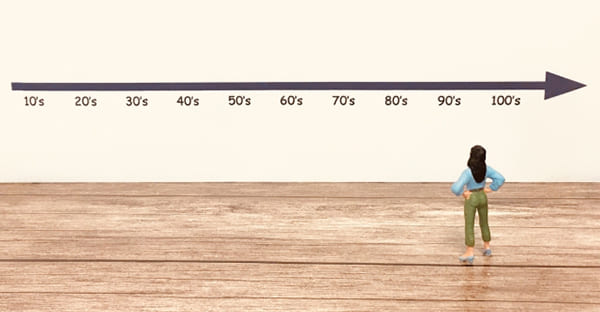
◇一般的に終活を始める年齢は、65歳が多いとされます
終活は、いつから始めても良い活動ですが、まだ動ける50代・60代から始めると後悔しません。
前述したエンディングノートのアンケートでは、親が存命する男女400人から65%以上の子どもが「エンディングノートを残してほしい」と答えています。
一方でエンディングノートが「すでにある」と答えた子どもは僅か1%、「終活をいつかしたい」と想いながら、「まだ時間はある」と終活を後回しにしてしまう現状が垣間見えるでしょう。
けれども体力・気力が衰え始める老後から進める終活は、本人の負担が大きいです。
| <終活は何歳から始める?> ●理想は50代・60代には始めます。 |
|
| [体力・気力がある時代] | ・日常生活に問題がない ・金銭管理ができる ・財産管理ができる (不動産など) |
| [判断能力の不安] | ・日常生活は問題がない (多少のサポートで良い) ・金銭管理に不安 ・財産管理に不安 |
| [判断能力の低下] | ・日常生活にサポートが必要 ・金銭管理を任せる ・財産管理を任せる ・共に行動する人が必要 (通院など) |
| [終末期] | ・終末医療の判断 ・相続の発生 ・葬儀 ・遺骨の供養(納骨) |
終活は自分の最期を意識する、目を向ける作業です。
そのため本人が終活を望まなければ、家族が無理に先導することで、死への不安から気が滅入ってしまうこともあります。
50代・60代の気力体力があるうちから、本人の希望で進める終活が理想です。
・要支援と要介護の違いとは?要介護認定だった兄が、頑張って要支援になった結果は退所!
終活を始めたきっかけ
◇終活を始めるきっかけは、人生の節目が多いです
いつからでも始めて良い終活は、30代・40代の若い世代でも見受けます。
若い世代から終活を始める人々の多くは、葬儀やお墓など葬送の仕事の関わる人々の他、がんと診断されて死を目の当たりにした人などです。
ただそればかりではなく「子どもが産まれた」「結婚した」など、人生の節目で、責任を感じた時に終活を始める若い世代も多くいます。
| <終活を始めたきっかけ> | |
| [50代以上] | ・定年退職 ・還暦を迎えて ・認知症への不安 ・身近な人の死 ・配偶者の死 ・親の死 |
| [若い世代] | ・余命告知(病気) ・身近な人の死 ・結婚 ・子どもができた |
いずれにしても何らかの事情で死を目の当たりにした時、現実的に残された人々が困らないよう、また充実した生きる時間を過ごすよう、終活を始めた人が少なくありません。
まとめ:「終活」とは残された人生を充実させることです

2009年に週刊朝日で「就活」になぞらえ、「終活」の造語を産み出した人は「現代終活事情」コラムを連載した、葬儀相談員さんでした。
葬儀相談員である彼女の言葉を借りると、「エンディングを考えることを通して、これからの人生を生き生きとしたものにする」活動が終活とされます。
自分の最期を想定しながら進める「終活」は時に、自分の体力・気力の衰えや、終末に向けた体力の変化を見据えなければなりません。
けれどもだからこそ、儚い人生を改めて実感し、残された時間をいかに「満足できる最期に向けて充実させるか」に集中させてくれます。
お電話でも受け付けております















