
浄土真宗の納骨式は他の宗派と違うの?手順や気を付けることを解説

「浄土真宗の納骨式は他の宗派と違う?」
「浄土真宗の特徴って?」
「浄土真宗の納骨式で気を付けなければいけないことはある?」
このように、浄土真宗の納骨式について詳しく知りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、浄土真宗の納骨式と他の宗派との違いや、浄土真宗の特徴、浄土真宗の納骨式で気を付けることなどについて紹介しています。この記事を読むことで、浄土真宗の納骨式について理解を深めることができるでしょう。
また、大谷本廟や大谷祖廟に納骨する方法についても紹介しているため、分骨の方法について知りたい人も参考にできます。
浄土真宗の納骨式と他の宗派との違いについて詳しく知りたい人は、この記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
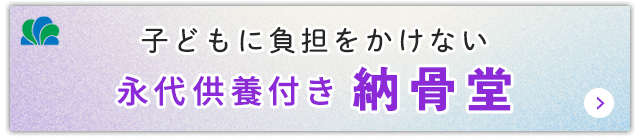
浄土真宗の納骨式は他の宗派と違うの?

浄土真宗で納骨式を開くタイミング自体は、他の宗派と同じです。しかし他の宗派の場合、遺骨を入れる骨壺は一つですが、浄土真宗の場合は骨壺を二つ使用する場合がある点が特徴的です。
たとえば浄土真宗本願寺派の場合、大きな骨壺に喉仏以外のすべての骨を納め、胴骨としてお墓に納めます。また、もう一つの骨壺には喉仏を納め、分骨として大谷本廟に納めることになります。
浄土真宗東本願寺派の場合も分骨しますが、大谷祖廟にすべての遺骨を納めることが可能です。
浄土真宗の特徴とは?

浄土真宗の納骨式が他の宗派と違う点を紹介しましたが、浄土真宗は考え方なども特徴的です。浄土真宗と他の宗派の違いを理解する上では、浄土真宗の独自性を知っておくことが重要だと言えるでしょう。
ここでは浄土真宗の特徴について解説していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
浄土真宗の考え方
浄土真宗には、「悪人正機(あくにんしょうき)」という思想があります。この「悪人正機」は、浄土真宗の教えの中でも最も重要なものです。
悪人正機を簡単に解説すると、良い人間が救われるのは当然として、本当に救いたいのは悪い人間であるということです。つまり、浄土真宗の思想とは、「救いの本質とは悪い人間を救うことにある」というものになります。
阿弥陀仏が救済を目指すものは衆生であり、すべての衆生は末法濁世を生きている悪人であるという考え方です。
納骨のやり方
前述のとおり、浄土真宗の特徴は骨壺を二つ用意して分骨する点です。
浄土真宗において喉仏の骨は特別な骨とされるため、浄土真宗本願寺派では喉仏の骨を分骨して親鸞の廟所である京都の大谷本廟に納めます。
また、浄土真宗東本願寺派の場合は、親鸞のお墓である大谷祖廟に納めることが可能です。喉仏の骨はお釈迦様が座禅を組む姿に見えることから、他の宗派でも最後に骨壺に納めるなど、大切に扱われます。
浄土真宗の納骨式を行う時期

浄土真宗の納骨時期は基本的には決まっていません。僧侶によっても違いがあり、四十九日が終わればいつでも問題ないという人もいれば、100日を過ぎてから行うという人もいます。
また、納骨式の期限もないため、僧侶と相談して決めると良いでしょう。一般的には一周忌や三回忌法要と併せて行うケースが多く見られます。
浄土真宗の納骨式を行う手順

浄土真宗では、一般的なお墓に納骨を行う場合に、他の宗派とは異なる点があります。ここでは浄土真宗の納骨式を行う手順を紹介していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
建碑法要をする
建碑法要(建碑式)とは、浄土真宗で新しくお墓を建てた際に行われる法要です。他の宗派の場合、納骨式では新しいお墓に故人の魂を入れる入魂式を行いますが、浄土真宗には魂を入れるという概念が存在しません。
そのため、入魂式の代わりに建碑法要を行うことになります。建碑法要では、納骨式の際にお墓に白い布をかぶせて、お経をあげてもらいます。この建碑法要を終えることで、新しいお墓が正式なお墓になります。
お墓に土をかける
建碑法要を行った後、納骨を行います。納骨を行う際、他の宗派では親族や友人など故人との縁の深い人々が、順番に焼香を行っていきます。
一方、浄土真宗の納骨法要の場合は、焼香や合掌と共に遺骨を埋めたお墓に土をかけるという点が特徴的です。
なお、納骨の際の土入れに際しての具体的な指示はありません。そのため、初めて参列する際にはやり方がわからず動揺することもあるでしょうが、そのような場合は、他の人の動作を真似して堂々と行えば問題ありません。
納骨式のお供え物に決まりはあるの?

浄土真宗は他の宗派と違った独自性を持っているため、お供え物にも違いがあるのではないかと考えている人もいるのではないでしょうか。
お供え物に関しては、浄土真宗だからと言って特別な決まりはありません。
他の宗派と同様に、故人が生前好きだったものなどをお供えして問題ありません。お花や果物、お酒など、故人に合わせてお供えすると良いでしょう。
浄土真宗の納骨式で気を付けること

浄土真宗の納骨式を行う場合、何らかの注意点があるのではないかと心配している人もいるでしょう。たとえば、経済的な問題などによって大谷本廟や大谷祖廟に納骨することが難しいケースもあります。
ここでは浄土真宗の納骨式で気を付けることを紹介していくため、参考にしてみてください。
法名に格や位は存在しない
浄土真宗では、誰もが平等に救われるという考え方が基本です。そのため、法名に格や位はありません。
さらに、お布施の金額も関係ないため、高額なお布施を渡したからと言って格や位が上がるという訳でもありません。浄土真宗では法名をいただく際のお布施も不要と言われていますが、一般的には3万円~10万円程度のお布施を渡すケースが多いでしょう。
本尊納骨ができない場合は旦那寺に相談する
本尊納骨とは、故人の喉仏を大谷本廟や大谷祖廟に納骨することを指します。本尊納骨ができない場合は、地元にある浄土真宗の旦那寺などに埋葬することも可能です。
経済的な問題などによって本尊納骨ができない場合は、一度相談してみると良いでしょう。
浄土真宗の大谷本廟や大谷祖廟に納骨するにはどうすればいいの?

浄土真宗には「大谷本廟」と「大谷祖廟」という紛らわしい名前が出てきますが、大谷本廟は親鸞の娘である覚信尼が作った親鸞の廟所、大谷祖廟は親鸞の遺骨が納められたお墓です。
喉仏以外の骨はお墓に埋葬しますが、喉仏の骨は大谷本廟もしくは大谷祖廟に納骨します。分骨方法は、親鸞の墓所近くに納骨する祖壇納骨と、大谷本廟の納骨堂に納める無量寿堂納骨の2種類です。
祖壇納骨を行う場合、事前に手続きを行い、お勤めが行われた後、喉仏の骨が入った骨壺を境内にある明著堂へ移動し、合掌、礼拝するという流れになります。
無量寿堂納骨を行う場合は、大谷本廟の受付で手続きをし、納骨所で読経を行ってもらい、納骨します。
浄土真宗の納骨式を行う手順について知っておこう

浄土真宗の納骨式は他の宗派と違い、喉仏を分骨して大谷本廟や大谷祖廟に納骨することになります。また、個人のお墓に納骨する際にも他の宗派との違いがあります。
この記事では、浄土真宗の納骨式について詳しく紹介しました。他の宗派との違いや浄土真宗の特徴などを参考に、浄土真宗の納骨式をスムーズに行えるようにしておきましょう。
お電話でも受け付けております















