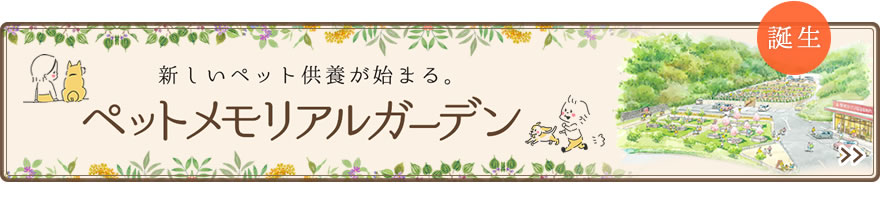次男は本家のお墓には入れないってホント?次男が選ぶお墓、3つの対処法|永代供養ナビ
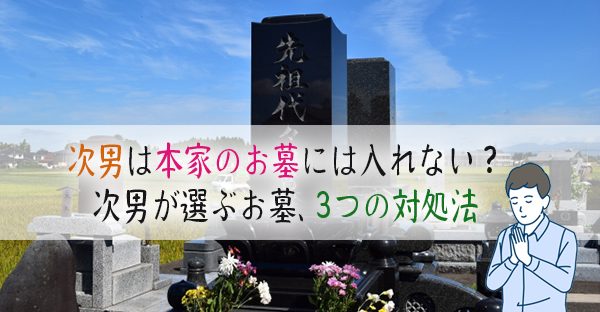
「次男ですが本家のお墓に入れますか?」との質問が多いですが、現代の法律では次男もお墓に入ることは可能です。
けれどもお墓の名義人である墓主が、お墓に入ることを許可しないならば、それは長男次男に限らず、入ることはできないでしょう。
・墓主から許可が下りない
・墓地管理者から許可が下りない
今もしばしば聞く「次男がお墓に入れない」理由は、昔の日本で根付いていた家制度です。
今回は現代において、次男が本家のお墓に入れる/入れないケース、入れない時3つの対処法をお伝えします。
※次男以降、三男・四男や娘もお墓に入れないことがありますが、今回は次男として解説しますので、ご了承ください。

「次男がお墓に入れない」理由とは

●昔の日本では、代々長男がお墓を引き継ぐ「家制度」があったためです
日本でお墓は先祖代々から受け継がれ、本家のお墓は長男が継承してきました。
そこで本家以外の家族が一緒にお墓に入ると、お墓の継承者や決まり事が複雑化してしまいます。
日本で昔にあった家制度の元、仮に次男が本家のお墓に入った場合、下記のようなトラブルの可能性が考えられるでしょう。
①次男の子どもも継承を望む
②関係者が多すぎる
③次男はお墓を建てて独立する
またその昔には、長男がお墓の継承とともに家の財産を全て相続する「家督制度」もあったため、次男がお墓に入り、その子どもや孫が継承していくことになると、長男と次男で争いが勃発する不安もあったでしょう。
けれども現代では、相続人それぞれが均等に財産を相続する「遺留分」と言う権利があるため、その限りではありません。
・【相続対策】遺言書を残しても遺留分は請求される?生前できる3つの遺留分侵害額請求対策
①次男の子どもも継承を望む
●子どもや家族のいる次男が本家のお墓に入った場合、その子孫は代々人数が増えます
長男一家だけであれば、代々長男が引き継ぐことで継承者が明瞭です。
けれども子どもや家族のある次男が本家のお墓に入った場合、継承者が曖昧になります。
・次男の子ども
今の墓主(長男)と次男の間で分かり合いトラブルがなかったとしても、子どもの代でどうなるかは分かりません。
昔のようにお墓の継承者を争うケースは少ないですが、反対にお墓の維持管理を押し付け合うトラブルが起きる可能性もあります。
②関係者が多すぎる
●次男やその家族がお墓に入ることで、関係者が増えてお墓ことが進みにくいです
「お墓はただ放置しておけば良い」と言う訳ではありません。
墓石であっても経年劣化が進むため、定期的なメンテナンスや建て替え、時には墓じまいやお墓の引っ越し「改葬(かいそう)」が必要な時もあるでしょう。
・墓じまい(お墓を廃棄)
などなど、大きなお墓事を進めたいものの、お墓関係者の人数が増えすぎて、全員に連絡を取るのが困難になってしまう可能性があります。
そのため「お墓1基に1家族」と考える風習があるでしょう。
③次男はお墓を建てて独立する
次男が本家のお墓に入るケース

●ただし法律上では、次男が本家のお墓に入る事は可能です
(お墓の継承に関しては、民法で定められています。)
お墓の名義人である墓主が許可する限り、次男は本家のお墓に入れますが、一般的に次男が本家のお墓に入る時、下記のようなケースが多いでしょう。
①次男が独身
②子どもがいない
③墓主が許可する
ただし寺院墓地など、現代でも稀に次男以降の兄弟姉妹がお墓に入ることを規約で禁止する墓地もあります。
現代では宗旨宗派を問わない民間霊園も増え、墓地管理者が次男の入墓を禁止するトラブルは少なくなりましたが、検討をしているなら確認をしてみても良いでしょう。
①次男が独身
●次男が独身のため、本家の墓に入るケースは多いです
次男が独り身の場合、次男以外の家族がお墓に入ること、使うことがありません。
そのため、お墓の継承問題やお墓事に関する関係者が複雑化する心配もないでしょう。
次男が本家のお墓に入ることを希望する他、例えば独り身の次男が突然亡くなり、入るお墓も準備していないため、四十九日法要に間に合わせる形で、次男を本家のお墓に入れる判断も多いです。
②子どもがいない
●結婚していても子どもがいない次男も、本家のお墓に入る事例があります
また結婚していても夫婦に子どもがいなかった次男は、夫婦ともども本家のお墓に入る判断も多いです。
・新しくお墓を建てても次男夫婦に継承者がいない
次男夫婦に子どもがいない場合、新しくお墓を建てても継承者がいないばかりか、残された配偶者(妻)がお墓を建てる経済的負担がのしかかるためです。
※この場合、配偶者方のお墓に入る判断もありますが、次男夫婦が本家のお墓に入る判断もあるでしょう。
③墓主が許可する
次男が本家のお墓に入れないケース
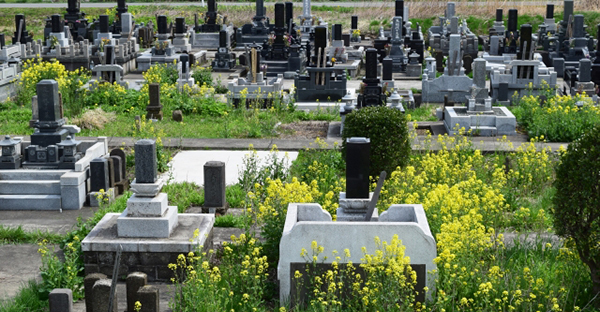
一方、次男としては本家のお墓に入りたいものの、墓主の許可が下りないなど、さまざまな理由で入墓できないケースもあります。
①結婚して子どもがいる
②墓主との関係性が薄い
③墓地の利用規約で禁止
ただし前述したように、基本的に現代の法律では、墓主が許可すれば次男に限らずお墓に入ることが可能です。
そのため例えば「結婚して子どもがいる」全ての次男に当てはまるものではありません。
①結婚して子どもがいる
●次男に子どもがいると、後々お墓の関係者が複雑になりがちです
そのため基本的には、あまり次男家族がお墓に入ることを良しとしない家は多いでしょう。
一方、次男としては子どもが次男のお墓を代々継承できるため、新しくお墓を建てやすくなります。
・長男が遠方に住み、継承者を譲りたい
・長男が配偶者方の養子に入っている
・遺言で次男のお墓継承を指定された
・長男が宗教的にお墓を継承できない
…などなど何らかの事情で長男が継承者を放棄した場合、稀に次男が本家のお墓を継承し、結果的に次男家族が本家のお墓に入るケースもありました。
②墓主との関係性が薄い
●そもそも次男がお墓に入ることを、墓主に相談できないケースもあります
これは兄弟間では少ないケースですが、例えば前妻と後妻など異母兄弟の場合や、すでに世代継承が進み、甥っ子が本家のお墓を継承しているなどです。
③墓地の利用規約で禁止
●墓地の利用規約に「本家の家族しか入墓できない」と定められているケースです
ただし、これはあくまでも墓地の利用規約であり、民法では次男が本家のお墓に入ることを禁止していないため、墓主が次男の入墓を許可している場合、墓地管理者との話し合いで次男がお墓に入るケースもあります。
①三親等まで
②六親等まで
ここで「三親等までって、どこまで?」との質問も多いですが、墓主の兄弟姉妹であれば三親等内には入ります。
・二親等…祖父母/孫/兄弟姉妹
・三親等…祖祖父/ひ孫/叔父叔母/伯父伯母/姪っ子/甥っ子
…このようになるため、一般的な墓地では断られることはありませんが、稀に「お墓に入れるのは本家の家族のみ」と規約に定める墓地もあるため、寺院墓地などで気なる時には確認をしてください。
次男が本家のお墓に入れない時、3つの対処法
②お墓のない葬送
●「お墓のない葬送」は合祀墓や納骨堂などです
最初から他の遺骨とともに合祀埋葬しても抵抗がない場合には、合祀墓を選ぶと葬送費用を安く抑えられますが、個別に遺骨を安置したいのであれば、納骨堂などが良いでしょう。
・合祀墓…約10万円~30万円
・納骨堂…約20万円~150万円
・手元供養…約3万円~100万円
次男が本家のお墓へ入らないとして、配偶者が残っている場合には、配偶者が遺骨を自宅で祀る手元供養の選択も多いです。
残された配偶者が生前に合祀墓や自然葬など、希望の葬送を生前契約し、一緒に葬送する事例も増えました。
・大阪で「お墓はいらない」人の遺骨はどうする?その背景と問題を解決する5つの供養方法
③自然葬
●お墓のない葬送のひとつとして、自然葬を選ぶ人が増えました
「自然葬」は土や海、空などに遺骨を還す葬送を差します。
パウダー状に粉骨した遺骨を海や空に撒く散骨はもちろん、土に埋める樹木葬でも、最終的には土に還るため、お墓の必要はありません。
・樹木葬(個別型/シンボルツリー型/公園型)
・散骨(海/山林/空/宇宙など)
今では故人の遺骨から作り出したダイヤモンドを肌身離さず持ち歩く「ダイヤモンド葬」などもありますが、一般的な自然葬は上記2つの自然葬です。
・【自然葬の種類】自然葬の種類と特徴。個別の墓標を残す自然葬もあるの?|永代供養ナビ
最後に
今回は次男が本家のお墓に入れるかどうか…、それぞれのケースと、入れない時に選択できる3つの対処法をお伝えしました。
次男が本家のお墓に入りたい時、日本の昔ながらの「家制度」と呼ばれる慣習から、家族や親族の反対に合うことは、今でも確かにあります。
もちろん話し合いの元、家族や親族の合意を得て埋葬されるに越したことはありません。
けれども法的には、お墓の名義人である墓主が許可を出せば、次男もお墓に入ることができます。
(本文でお伝えしたように、墓地によっては規約で禁止する管理者もいるでしょう。)
特に後々、誰かがお墓参りに訪れる、供養を続けるならば、納骨トラブルを俯瞰して検討し、後々まで気持ち良くお参りができるための選択をすることをおすすめします。
まとめ
次男は本家のお墓に入れるの?
●お墓に入れないとされる理由
①次男の子どもも継承を望む
②関係者が多すぎる
③次男はお墓を建てて独立する
●お墓に入りやすいケース
①次男が独身
②子どもがいない
③墓主が許可する
●お墓に入りにくいケース
①結婚して子どもがいる
②墓主との関係性が薄い
③墓地の利用規約で禁止
●お墓に入れない時の対処法
①新しくお墓を建てる
②お墓のない葬送
③自然葬
お電話でも受け付けております