
相続欠格になる場合とは?相続廃除との違いや代襲相続についても解説
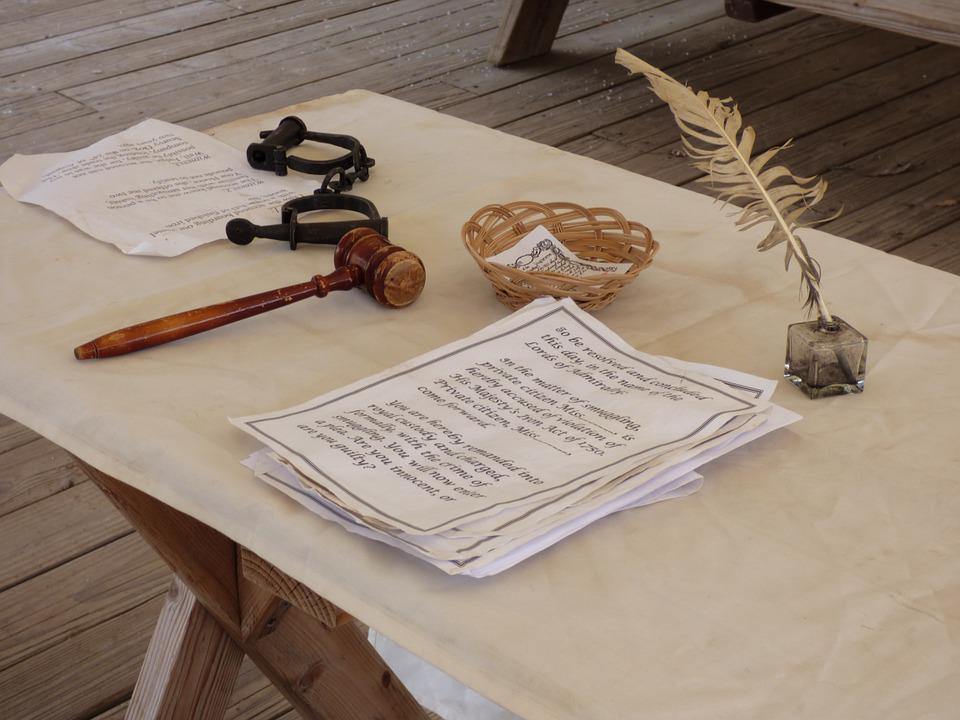
「相続欠格ってどんなもの?」
「相続欠格になる理由にはどんなものがある?」
「相続欠格の効力が適応されるタイミングとは?」
このように、相続欠格になる理由について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、相続欠格の概要や相続欠格になる理由、相続欠格の効力が適応されるタイミングなどを紹介しています。この記事を読むことで、相続欠格とはどのような場合に適応されるのか把握することができるでしょう。
また、遺言書がある場合でも相続欠格は適応されるのかどうかや代襲相続についても紹介するため、相続欠格について理解を深めることができます。
相続欠格について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
相続欠格とは

相続欠格とは、重大な非行を行った場合に、相続人として遺産を相続する権利を失う制度のことです。民法891条で相続人の欠格事由が定められています。
相続人の欠格事由に該当する場合、相続する権利を失うだけでなく、最低限の財産の取り分である遺留分についても得られる権利をはく奪されることになります。
出典|参照:民法 第八百九十一条 (相続人の欠格事由)| e-Gov法令検索
相続欠格になる5つの理由

相続欠格は、特定の「重大な非行」を行った場合に相続する権利を失うという制度です。ここでは、相続欠格になる5つの理由を紹介していくため、どのようなケースで相続欠格になるのか参考にしてみてください。
出典|参照:民法 第八百九十一条| e-Gov法令検索
1:故意に被相続人や同順位または先順位にある相続人を死亡または死亡させようとして刑に処せられた
故意に被相続人や自分と同順位以上の相続人を殺害した場合や、殺害しようとして刑に処された場合、相続欠格に該当します。たとえば、被相続人を殺害して実刑判決が出た場合、相続欠格となります。
ただし、執行猶予が付きその期間が満了している場合や、過失によって被相続人を死亡させてしまった場合は、この欠格事由には該当しません。
出典|参照:民法 第八百九十一条| e-Gov法令検索
2:被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴や告発を行わなかった
被相続人が殺害されたことを知っており、そのことを告発しなかった場合には相続欠格に該当します。被相続人が殺されたことを黙認している場合も欠格事由となり、相続欠格となります。
ただし、黙認していた相続人が未成年者である場合や、殺害した人が自身の配偶者だった場合、殺害の事実が発覚して捜査が行われている場合は、この欠格事由には該当しません。
3:被相続人の遺言を偽装や変造または破棄隠ぺいなどの行為をした
被相続人の遺言書を偽装、改変、破棄、隠匿した人は、相続欠格になります。
遺言書は被相続人のみ作成、変更、破棄することが可能です。遺言書に相続人が不利になるような内容が書かれていた場合でも、不正を働くと相続欠落になり相続権を失います。
4:詐欺または脅迫によって被相続人の遺言を取り消しまたは遺言の変更を妨げた
詐欺や脅迫を行うなどして被相続人の遺言の変更などを妨げた場合、相続欠格に該当します。被相続人が遺言を作ることや、遺言を変更すること、取り消すことなどを妨害した場合は相続欠格となります。
5:詐欺や脅迫によって被相続人に遺言の作成や変更または撤回や取り消しを行わせた
詐欺や脅迫を行うなどして被相続人の遺言を取り消させた場合、相続欠格に該当します。前述の事由と同じように、詐欺や脅迫によって、被相続に遺言を用意させたり、不利な遺言の内容に変更させたりした場合は相続欠格となります。
相続欠格と相続廃除の違いとは

相続欠格と同じように、相続人に遺産を相続させないようにする制度として「相続廃除」があります。
両者は混同されるケースも多いですが、相続欠格が被相続人の意思に関係なく相続する権利をはく奪されるものであるのに対して、相続廃除は被相続人の意思によって相続人の相続権を喪失させるものという違いがあります。
また、相続欠格の場合は法的に権利がはく奪されるため取り消すことができませんが、相続喪失の場合は取り消すことが可能です。
相続欠格となる場合の遺留分の取り扱い

遺留分とは、一定の相続人に対して認められた、最低限の遺産を相続する権利を指します。遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子供、父母などです。
相続欠格となった場合、遺留分についても認められなくなります。そのため、たとえ遺留分が貰えなくても、遺留分侵害額請求を行っても遺留分を取り戻すことはできません。
出典|参照:相続欠格とは。相続人に重大な非行があると遺産を相続できない |税理士法人チェスター
相続欠格の効力が適応されるタイミング

相続欠格での対応は、相続欠格事由に該当するタイミングによって異なるため注意が必要です。相続が発生する前に相続欠格事由に該当した場合は、その時点で相続欠格になります。
一方、相続発生後に相続欠格事由に該当した場合は、相続が発生した時点にさかのぼり、相続欠格になります。ここでは相続欠格の効力が適応されるタイミングについて解説していくため、参考にしてみてください。
遺産分割前に相続欠格となった場合
遺言書がない場合、遺産分割協議を行い遺産を分割します。遺産分割協議が成立する前に相続欠格事由に該当するケースがあります。このようなケースでは、相続が発生した時点にさかのぼって、相続欠格になります。
この相続欠格者の相続については、他の相続人のものになります。
遺産分割後に相続欠格となった場合
遺産分割協議が成立後、相続欠格事由に該当する場合もあります。
この場合、既に遺産分割は完了していますが、相続欠格になるタイミングは相続が発生した時点です。そのため、他の相続人が相続回復請求を行い、相続欠格者が取得した相続分を取り戻すという流れになります。
遺言書がある場合でも相続欠格は適応される?
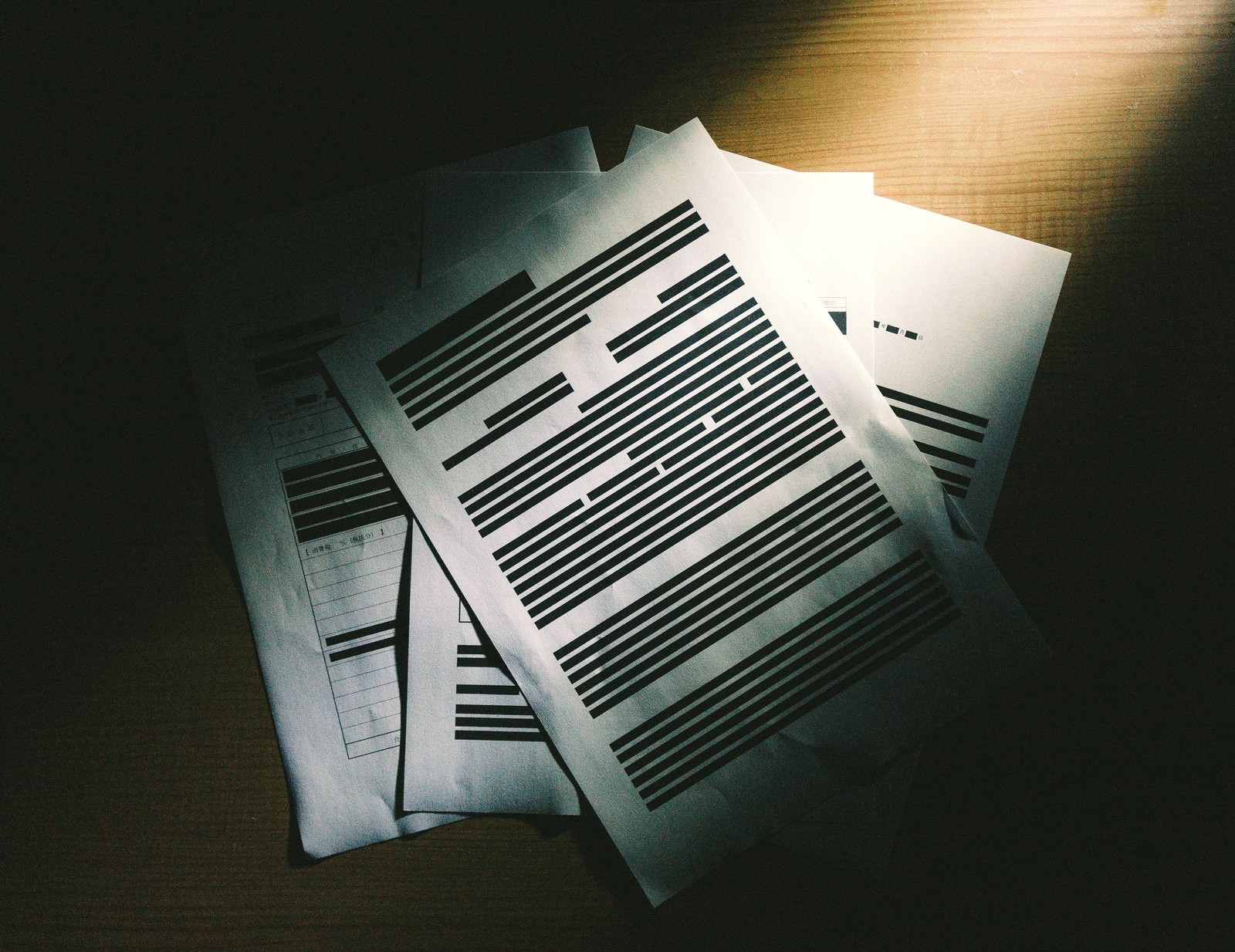
被相続人の遺言書がある場合でも、相続欠格事由に該当すれば、相続欠格となります。
遺言書に相続人以外で遺産を受け取る人が指定されているケースもあるでしょう。このような人のことを受遺者と呼びますが、受遺者が相続欠格事由に該当している場合も、遺産を受け取ることはできなくなります。
相続欠格となった場合の代襲相続

代襲相続とは、相続人が死亡するなどして相続権を失った場合、その相続人の子供が相続することです。
相続欠格事由に該当した人の相続分ははく奪されますが、子供がいる場合、その子供が代襲相続することが可能です。また、代襲相続の場合は相続人と同様の相続権があるため、遺留分に関しても認められます。
出典|参照:民法 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|e-Gov 法令検索
相続手続きの際には相続欠格の証明が必要

相続欠格事由に該当した場合、相続する権利を失います。しかしその事実は戸籍などに記載されるわけではないため、相続手続きの際には相続欠格の証明が必要です。
したがって、相続欠格を明らかにする証明書を相続欠格者自身に用意してもらうことになります。
相続欠格者がいる場合はトラブルに発展するケースがある

被相続人を殺害したケースだけでなく、被相続人に無理に遺言書を書かせた場合も相続欠格事由に該当します。
しかし相続手続きの際に相続欠格として相続権をはく奪するためには、相続欠格者である本人が証明書を作成する必要があるため、トラブルに発展するケースも多いでしょう。
このようなケースでは、相続に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。
相続欠格になる理由について理解しよう

相続欠格事由に該当する場合、相続する権利がはく奪されるため、遺留分についても受け取ることはできなくなります。
ぜひ本記事で紹介した相続欠格になる理由や相続欠格の効力が適応されるタイミングなどを参考に、相続欠格になる事由について理解を深めてみてはいかがでしょうか。
お電話でも受け付けております















