
家族信託とは?相談先やメリットとデメリット、手続きの進め方5つのステップまで解説!
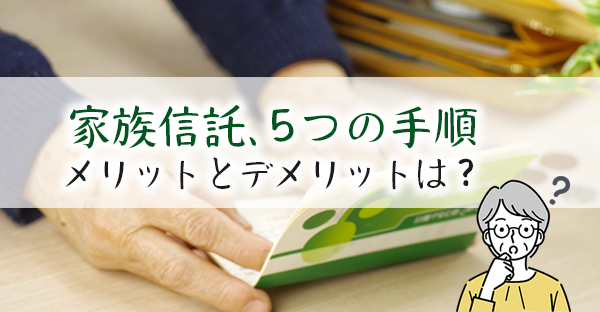
「家族信託」とは、認知症など判断能力の低下により自分で財産管理ができなくなった人が、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。
比較的新しくできた制度ですが、認知症への不安を持つ高齢者を中心に、元気なうちに信頼できる子どもと契約を交わそうと、注目されています。
信託には他にもいくつかの方法がありますが、家族信託は家族に財産を委ねるため、信託銀行の利用などと比べて割安で、遺言機能も備える点がメリットです。
ただし家族信託も万能ではありません。
今回は、家族信託の仕組みやメリット・デメリット、手続きの進め方を5つのステップに整理してお伝えします。
家族信託とは?相談先やメリットとデメリット、手続きの進め方5つのステップまで解説!

家族信託とは?

「家族信託」とは、認知症による判断能力の低下や、自分が亡くなった時などに、信頼する家族に財産管理ができる権限を与える契約です。
「信託」は「信じて託す」と書きますから、そのまま、家族を信じて財産を託すことになります。
この他の信託としては、遺言信託や信託銀行などがありますよね。
家族信託によって財産管理できる家族は、そのまま所持しても構いませんし、処分することも可能です。
●仮に、家族信託で契約した財産に不動産があったとします。
受託者(家族信託で財産管理を担った家族)は、下記のような権限があるでしょう。
・財産管理
・不動産の売却
・第三者へ管理を委託
…例えば賃貸アパートを家族信託で請け負った受託者は、その権限を利用して、賃貸アパートの管理を第三者へ委託する契約ができます。
このように家族信託を利用することで、より融通の利く財産管理が実現するでしょう。
家族信託の仕組み

信託銀行などで行う信託は、契約者が亡くなったり、認知症などにより判断能力が低下した時、銀行がそれぞれの専門家に依頼して、財産管理や(遺言信託であれば)遺言執行を行います。
一方、家族信託の契約は家族同士である三者が行う契約です。
(1)委託者…財産管理をお願いする人
(2)受託者…財産管理を請け負う人
(3)受益者…財産の恩恵を受ける人
認知症による家族信託の発動では、受益者が分かりにくいとの声もありますが、例えば相続が発生した時に、相続を受け取る人は受益者になります。
ちなみに認知症による家族信託の発動では、例えば口座の凍結で権限を発揮するでしょう。
認知症による判断能力の著しい低下が認められると、本人の口座は凍結されますが、家族信託を予め契約していた場合、家族信託の権限により、本人の口座からお金を引き出すことが可能です。
※認知症による口座の凍結については、下記に詳しいです。
・認知症になった親の口座が凍結!お金引き出しまでの流れ、事前にできる3つの対策も解説
(1)委託者とは?
「委託者」とは、財産管理をお願いする人です。
●高齢の親が家族信託を利用して、子どもに財産管理を依頼する場合、親が委託者になります。
財産・遺産を管理すること方法以外にも、処分などを予め決めておく権限を持っている人のことで、受託者を選ぶことや解任する権限も持っているのです。
(2)受託者とは?
「受託者」とは、委託者から任された財産を管理する人のことを言います。
●高齢の親が家族信託を利用して、子どもに財産管理を依頼する場合、子どもが受託者です。
受託者は、委託者より多くの権限を任されている一方で、さまざまな責任が生じます。
複数の相続人がいた場合、家族信託の受託者になることで他の相続人から異議を唱えられるかもしれません。
・善管注意義務…善良な管理者の注意義務の略、常識的な注意を払う義務
・忠実義務…忠実な財産管理を遂行する義務
・分別管理義務…それぞれの財産を分離して管理を行う義務
このような事柄から、家族信託は受託者の負担は大きい側面もあります。
そのため不安を感じたら弁護士など、専門的な第三者への信託を検討するのも良いでしょう。
※一般社団法人信託協会では、個人/法人/団体までさまざまな人を対象に信託を紹介しています。
受益者とは?
「受益者」とは、財産管理により収益が発生する金銭を受け取る人です。
信託契約によって定められた場合、個人や法人に関わらず受益者になり得ます。
・個人(受託者/相続人など)
・企業、法人、組合、団体、社団(権利能力なし)
・将来の子ども
…などなど。
利益を得る受益者は、受託者に対していくつかの権限も持っています。
特に受託者を監視する役割も持ち、受託者の解任や選任の権限もあるでしょう。
家族信託のメリット

家族信託は相続対策の他、認知症に備えた財産管理の委託や、将来的に親が住む実家を売却したい場合などにも利用されます。
前述したような、利益が生じる賃貸アパートなどの管理でも、高齢になった親が子どもに任せたいとして、家族信託を契約するケースもあるでしょう。
(1)親の財産が容易に管理できる
(2)遺言書の効力と同じ効果を持つ
(3)費用を安く抑えられる
また家族信託を行うことで二次相続まで想定できることも選ばれる理由です。
この他、障害のある子どもに実家を残したい、と言った事例もありました。
(1)親の財産が容易に管理できる
高齢者の親の財産管理を容易にできることがメリットです。
高齢者になると、いつ亡くなってもおかしくはない状態になりますよね。
元気なうちに財産の名義変更を行い、受け継がれる方が受託者として家族信託をしておくことで、老後の資産管理も自由にできることです。
(2)遺言書の効力と同じ効果を持つ
被相続人から財産を受け継ぐとなると、遺言書を作成するのが一般的で、専門知識も必要となる場合があります。
その場合、家族信託を利用することで、遺言書の作成をしなくても面倒な手続きは必要なく、自分が亡くなった時に発生した相続について財産を継承することができます。
(3)費用を安く抑えられる
自分で家族信託の手続きをすることで、安い費用で契約できることも、メリットのひとつです。
専門家に依頼すると、依頼料なども含めて割高な利用料が請求されることもあるでしょう。
割高な利用料を避けるためにも、自分で家族信託を利用する手続きをすると、無駄な出費を減らすことができます。
家族信託のデメリット

一方で家族信託は、受益者(相続人)のひとりである家族が受託者となり、相続財産を管理すること、家族の多くが専門的な知識を持ち合わせていないことから、デメリットも多く指摘されてきました。
(1)受託者の選任が決まりにくい
(2)節税効果は期待できない(小さい)
(3)贈与税が発生する可能性
また家族信託は、基本的に家族を信頼して財産を託すと言う、信頼関係の上で契約を交わしますから、時には受託者が財産を使い込む…、などの可能性も否めません。
(1)受託者の選任が決まりにくい
家族信託を利用する際には、受託者の決定で揉めることがあります。
冷静に財産の管理や処分ができる、委託者だけではなく家族や関係者全員が信頼できるだけの家族がいるか、が問題です。
●家族信託は、委託者が判断できるうちに利用出来るのが最大のメリットですが、「なぜ私が受託者じゃないんだ」と疑問にもつ方もいる可能性があります。
これらの管理や処分が正しく行えなかった場合、相続人の中から不満の声が上がり、トラブルにも発展する可能性もあるので注意しましょう。
(2)節税効果は期待できない
家族信託を利用したことで、節税効果が期待できるわけではないでしょう。
委託者→受託者に継承されることで、財産を取得したという扱いです。
その場合は税金的に受託者にとって、相当の負担が掛かる可能性があります。
(3)贈与税が発生する可能性
自分で家族信託の信託契約書を作成することで、本来であったら払う必要がない贈与税が発生する場合があります。
●家族信託にしろ相続にしろ、一度専門家に相談すると安心です。
家族信託の手続きの流れ

家族間で行う家族信託契約は自分達で進めることもできますが、後々まで安心できる契約書の作成や、トラブル回避のためにも、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼し、契約を進めると安心です。
(1)家族信託について内容を話し合う
(2)信託契約
(3)信託用口座を開設
(4)信託登記
(5)家族信託運用
家族信託はより契約書として効力が高い公正証書として作成するケースが多いです。
公正証書の作成は公証役場で公証人により行われます。
扱う財産の金額に応じて手数料などは変わりますが、一般的には約1万円~5万円が、公正証書作成の目安になるでしょう。
(1)家族信託について内容を話し合う
まずは、家族信託について家族同士で内容を理解し話し合うことから始まります。
話し合いの前に委託者は信託する財産を整理しておくとスムーズです。
預貯金財産の他にも不動産財産は評価額などを出しておくと良いですし、株式や有価証券などもあります。
・委託者
・受託者
・受益者
…の役割を家族内で決める。
それぞれの役割が違うので、どの役割を担うかにより、後から財産相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
ちなみに家族信託で管理を任せる財産は、価値のあるものでなければなりません。
負債などはもちろん、年金受給権なども任せることはできないので、注意をしてください。
(2)信託契約
次に信託契約です。先程ご紹介した3者の役割の内容を取り決めます。
また受託者はひとりでなくても構いません。
そのため受託者を2人など、複数人選任することで、お互いの業務をお互いにチェックできるメリットがありおススメです。
・財産の範囲
・誰が財産の管理をするのか
・信託の目的
・受益者は誰にするか
…などについて信託契約を行います。
また、家族信託は身内のみで行う契約なので、受託者が業務をきちんと遂行しているかを受益者に代わり監督する、第三者である「信託監督人」を設置する方法も検討してみてはいかがでしょうか。
(3)信託用口座を開設
次に家族信託を利用するにあたり信託管理する「信託用口座」を開設しましょう。
この「信託用口座」は預金や財産収入などの利益を得る際に利用します。
(4)信託登記
家族信託の中で不動産がある場合は、委託者から受託者への名義変更手続きが必要です。
これを「信託登記」と言います。
信託登記は法務局で行い、自分で登記をするのではなく、司法書士に依頼するようにしましょう。
(5)家族信託運用
それぞれの準備が完了次第、受託者による財産管理がスタートします。
最後に
いかがでしたでしょうか、今回は家族信託のメリットとデメリット、手続きの進め方をトラブルを未然に防ぐいくつかのポイントとともにお伝えしました。
家族信託は、例えば子どもが親の財産を管理するなど、家族が財産管理ができるので、あらゆる事態に対応できる融通性が何よりのメリットです。
けれどもその分、ひとりの受託者に任せると、負担が大きすぎて適切な業務の遂行ができなくなったり、兄弟間で後々まで悔恨の残るトラブルの種にもなり兼ねません。
本文中でお伝えしたように、受託者を複数設けたり、専門的な第三者である弁護士や司法書士などのサポートを仰ぐ、などの方法を取り入れることで、デメリットに対する不安は解消されるでしょう。
認知症による判断能力低下に対しても、家族が預貯金を引き出せることは介護において助かるので、元気なうちに早め早めの対策がおすすめです。
まとめ
家族信託のメリットデメリット、手続き5つの手順
●メリット
(1)親の財産が容易に管理できる
(2)遺言書の効力と同じ効果を持つ
(3)費用を安く抑えられる
●デメリット
(1)受託者の選任が決まりにくい
(2)節税効果は期待できない(小さい)
(3)贈与税が発生する可能性
●手続き5つの手順
(1)家族信託について内容を話し合う
(2)信託契約
(3)信託用口座を開設
(4)信託登記
(5)家族信託運用
お電話でも受け付けております















