
【不動産の相続】確定申告で揃える書類や手続きの仕方。命日で違う申告期限も詳しく解説
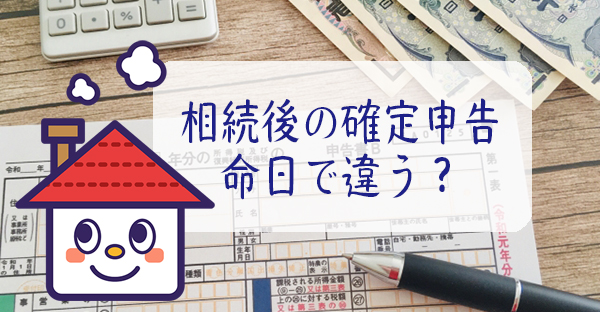
相続した不動産によって収入があった場合、相続人は確定申告を行います。
賃貸アパートや駐車場など、家賃収入が伴う不動産はもちろん、相続した不動産を売却して譲渡益(利益)が生じた場合でも、相続人は確定申告を行う必要があるでしょう。
基本的には通常の確定申告と手続きは同じなのですが、相続による確定申告の場合、申告期限が一般的な確定申告とは異なるため注意が必要です。
【不動産の相続】確定申告で揃える書類や手続きの仕方。命日で違う申告期限も詳しく解説

相続で確定申告が必要な5つのケース

相続により確定申告が必要になるのは、収入(所得)が生じたケースですが、一部相続した不動産などを寄付した場合、確定申告により還付金が返ってくる可能性があるでしょう。
また賃貸アパートなど、毎月の収入を伴う不動産相続の場合、相続人自身の確定申告とともに、亡くなって自分で申告ができない被相続人の確定申告を代理で行います。
これを「準確定申告」と言い、一般的に相続人全員で4ヶ月以内に全ての手続きを済ませなければなりません。
(1)相続した遺産を売却した
(2)収入を伴う不動産の相続
(3)相続した遺産を寄付
(4)遺産を現金化し分割
(5)支給年金・死亡保険を受け取った場合
ただし今回は、相続人が自身の確定申告を行う手続きについて、より詳しくお伝えします。
準確定申告の進め方や書類、手続きについては、下記記事をご参照ください。
相続した遺産を売却した
相続した土地や建物、株式や有価証券などを売却すると、所得が発生したと見なされます。年内に発生した収入(所得)に対して、確定申告が必要です。
ですから相続された遺産を売却して利益が出た場合は、確定申告を行います。
利益が生じていないならば、それに必要はありません。
遺産を売却した場合の確定申告は、利益に対してのみ計算されます。
収入を伴う不動産の相続
収入を伴う不動産とは、賃貸アパートや駐車場などを差します。
相続した場合、被相続人の命日を境に、それ以前が被相続人の収入、命日以後が相続人の収入です。
●確定申告は毎年1月1日~12月31日、1年間の区切りで申告します。
(1)1月1日~被相続人の命日以前 → 準確定申告(被相続人の収入)
(2)被相続人の命日以後~12月31日 → 確定申告(相続人の収入)
もちろん賃貸アパートや駐車場の相続により、今後も収入を得るならば、毎年確定申告を続けるでしょう。
ただ最初の年以後は、通常の確定申告と同じです。
そのため翌年からは一般的な確定申告と同じく、2月16日~3月15日までを受け付けとしています。
相続した遺産を寄付
相続した遺産を寄付した場合も確定申告を行う家が多いです。
厳密に言ってしまうと、相続した遺産を寄付しても、確定申告は義務ではありせん。
ただ節税になり、金額によっては還付金の戻りが期待できることもあるので、もし遺産を寄付するときには申告をして損はありません。
※国税庁 「一定の寄付金を支払ったとき(寄付金控除)」
遺産を現金化し分割
遺産を売却し、それぞれ相続人同士で現金を分割する方法を換価分割といいます。
この換価分割を行うことで収入が発生したとみなされるため、相続人全員の確定申告が必要です。
未支給年金・死亡保険を受け取った場合
未支給年金や死亡保険を受け取る際にも確定申告が必要になります。これらは一時所得として取り扱われるためです。
ただし、一時所得は50万円の特別控除が設けられているため、未支給年金を含めた年の一時所得が50万円以下であれば確定申告を行わなくてもOKです。
確定申告には2種類ある「白色申告と青色申告」

相続後に確定申告で提出する書類には主に2種類があり、基本的には相続人の年間収入によって確定申告の種類が変わるでしょう。
(被相続人の代理で行う準確定申告の場合、被相続人が生前に行っていた確定申告の種類に準じます。)
・白色申告…年間所得300万円以下
・青色申告…年間所得300万円以上
白色申告とは、個人事業主を始めて間もない人、年間所得が300万円以下の人が行う確定申告です。
一方、青色申告では年間所得が300万円以上の人が届ける確定申告の種類で、控除利用により10万円〜65万円の控除を受けることができます。
相続人が会社員などの場合、多くの人が「年間所得が300万円以上」に当てはまるため、相続後の確定申告では、一般的には青色申告をすることになるでしょう。
種類で違う、相続後の確定申告期限
ここで注意をしたい点が、相続後の確定申告においては、白色申告と青色申告で申告期限が異なる点です。
被相続人が青色申告を行なっていた場合、被相続人の命日によって確定申告を提出する期限が異なってきます。
また白色申告であっても、被相続人が亡くなった年に開業届を出していた場合には、注意が必要です。
●白色申告
(1)被相続人が亡くなった年の1月16日以降に開業届を提出→命日から2ヶ月以内
(2)それ以外の白色申告→通常の確定申告と同じ(毎年の2月16日~3月15日)
●青色申告
(1)被相続人が1月1日~8月31日に亡くなった場合→命日から4ヶ月以内
(2)被相続人が9月1日~10月31日に亡くなった場合→同年の12月31日まで
(3)被相続人が11月1日~12月31日に亡くなった場合→翌年2月15日まで
白色申告は承認手続きは必要なく、決算書の種類も収支内訳書で行います。(青色申告は青色申告決算書)
確定申告の進め方
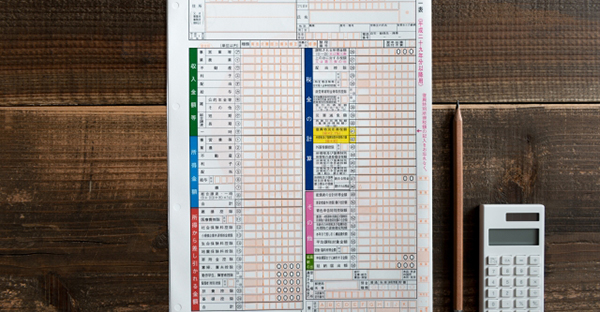
確定申告には、申告書A・申告書Bの2種類があります。
申告書Aは申告書Bの簡易版的な存在で、主にサラリーマン(年収2,000万円を超えた場合など)や、アルバイトやパート、医療費控除や住宅ローン控除など、簡易的な確定申告を進める場合に用います。
一方、申告書Bは凡用版なので、基本的には申告書Bを用いることになるでしょう。
また、令和5年1月からは申告書Aの廃止が決まりました。以降は申告書Bのみです。
確定申告6つの手順
確定申告の申告書をはじめとする申告書は、国税庁の「確定申告特集」からダウンロードができます。(国税庁 申告書B様式 )
(1)住所、氏名などを記入する
(2)収入金額等、所得金額を計算する
(3)所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
(4)税金の計算をする
(5)その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入する
(6)住民税に関する事項を記入する
ネットで繋がるならば、国税庁が提供する「確定申告書作成コーナー」を利用すると便利です。
確定申告で必要な書類
相続後の確定申告は、相続人が住む所轄の税務署で行います。
賃貸アパートの相続などで、準確定申告の手続きを行う場合、準確定申告に限っては、被相続人が生前に住んでいた所轄の税務署で済ませなければなりません。
(1)確定申告書B
(2)マイナンバーカード
(3)印鑑
(4)収入に関する書類
マイナンバーがない場合は、マイナンバーが記載されている住民票か通知カードに、保険証・自動車免許証・パスポートのいずれかを併せて提出します。
現物を提出する訳ではなく、コピーを確定申告書の添付欄に貼り付けての提出です。
確定申告の申告先
通常の確定申告時期(毎年2月16日~3月15日)に行うのであれば、住まい所轄の税務署で相談窓口などを設けるため、このような窓口を利用するのも良いでしょう。
前述したように、確定申告は申告者の住まいを所轄する税務署で手続きを行います。(国税庁 「税務署の所在地を知りたい方」)
また「e-tax」を利用したネットで完結する確定申告も便利です。
ただしe-taxを利用する場合、マイナンバーカードが必要になりますが、作成までに数週間を要する自治体が多いでしょう。
相続後の確定申告には期限もありますから、相続発生後、早々にマイナンバーカードを取得することをおすすめします。
※国税電子申告・納税システム「e-Tax」
まとめ
相続後の確定申告は、相続税手続きとともに税理士や行政書士、司法書士などの専門家へ依頼することも多いです。
相続後の確定申告のみを依頼するのであれば、税理士に依頼することが多いでしょう。
通常の確定申告でも税理士に依頼する人はいますが、費用目安は一般的に年収に応じた報酬になる契約が多く、例えば年収500万円の人が確定申告のみを依頼した場合、報酬相場は約7万円~8万円と言われています。
ただ相続後の確定申告では、賃貸アパートなどの定期収入がないケースであれば、報酬相場から見ると格安ですが、3万円前後から受け付ける税理士事務所も見受けるので、複数探してみてはいかがでしょうか。
金銭的に余裕もなく、ひとりで相続後の確定申告を進められない場合には、所轄の税務署で相談することも可能です。
まとめ
相続後に行う確定申告の手続き
・年収300万円以上なら青色申告
・相続後の確定申告は期限に注意
・申告書様式はBを使う
●確定申告6つの手順
・住所、氏名などを記入
・収入金額等、所得金額を計算
・所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算
・税金の計算
・その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入
・住民税に関する事項を記入
●申告先
・住まい所轄の税務署
・e-Taxでネット申告も可
・税理士などに依頼する方法もある
・税務署で相談もできる
お電話でも受け付けております















