
【不動産の相続】故人の代理で行う「準確定申告」。手続きの進め方や必要書類、期限まで
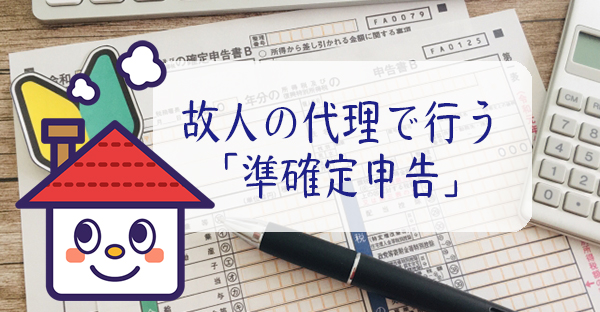
準確定申告とは故人の生前の所得についての確定申告のことです。
相続人全員が共同で確定申告を行いますが、申告期限と命日による納付期限があり、申告では確定申告書の他に添付書類も必要ですので、準確定申告が必要だった場合は、早々に手続きを進めると良いでしょう。
通常の確定申告と同様に、生前の所得によっては、納付か還付が確定し、納付の場合は相続人に納付義務が発生します。
【不動産の相続】故人の代理で行う「準確定申告」。手続きの進め方や必要書類、期限まで

準確定申告と確定申告の違い

準確定申告は故人の確定申告ですので、手続きの流れのほとんどは確定申告に倣いますが、いくつかの違いも理解して、申告をすると安心です。
・期限がある
・申告者が違う
特に準確定申告の期限は、相続発生からたった4ヶ月です。一般的な確定申告は、毎年2月16日~3月15日ですが、4月に故人が亡くなった場合などタイミングによって、しっかり理解して進めておかなければ、加算税が課される可能性も否めません。
期限がある
通常の確定申告の場合、暦年1年間の所得税を翌年2月16日~3月15日の間に申告すれば対象となります。
一方、準確定申告の場合は、相続が発生してから4ヶ月以内に申告しなければならないため、書類の準備等は早めに着手することが大切です。
仮に、期限内に準確定申告を提出できなかった場合は、加算税が課せられてしまうので、注意しましょう。
申告者が違う
確定申告は個人で行うものですが、相続発生により故人の財産は法定相続人の全員が後々相続します。
そのため通常の確定申告は本人が一人で手続きを行いますが、準確定申告では法定相続人全員が準確定申告の手続きを進めなければなりません。
準確定申告の手続き

準確定申告を行うケースは、被相続人(故人)がフリーランスや自由業などで、所得税の天引きや年末調整のない仕事や収入がある場合、毎年確定申告を行っていたなどです。
自営業やフリーランスの他、家賃収入があるケースもあるでしょう。
● 被相続人が生前に確定申告を行っていた場合
・自営業者
・フリーランス
・家賃収入
・副業で給与所得があった
・給与所得以外に20万円を超える収入があった
・公的年金などで20万円以上の所得があった
・不動産を売却した年
・生命保険などで満期金や一時金を受け取った
・株や有価証券を売却して、源泉徴収をしていない
※会社員であっても年収が2,000万円を超えている
…などなど
このようなケースでは被相続人が亡くなった年の元旦~命日まで、準確定申告を行います。
例えば、被相続人が2021年9月15日に亡くなったとしたら、準確定申告を行う期間は2021年1月1日~2021年9月15日となる訳です。
前年の確定申告をせずに亡くなった場合
毎年一般的な確定申告は、2月16日~3月15日の申告です。
そのため例えば2月30日に亡くなり、被相続人が前年度の確定申告を済ませていない場合もあるでしょう。
●この場合には、前年度の確定申告も「準確定申告」として、代理で行います。
→ 2021年2月30日に被相続人が亡くなっており、2020年度の確定申告を済ませていない場合、法定相続人は共同で、下記の準確定申告を行わなければなりません。
・2020年度1月1日~12月31日
・2021年度1月1日~2月30日
そして準確定申告は4ヶ月の期限がありますので、被相続人が2月30日に亡くなった上記のケースでは、6月30日までに2020年度と2021年度命日までの準確定申告を行うことになるでしょう。
準確定申告で揃える書類

準確定申告に必要な書類は、以下の6つです。
基本的に申告ができない被相続人の代わりに、法定相続人が確定申告を行うと考えると良いでしょう。
・確定申告書
・被相続人の源泉徴収票
・被相続人の控除証明書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
・被相続人の医療費の領収書
・委任状
通常の確定申告と大きく違う書類は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」です。
基本的には準確定申告は代表を設けて手続きを進めますが、この確定申告書付表を作成するには相続人全員の情報が不可欠となり、手続きが遅れる事例もあります。
昔のように相続人全員の署名捺印の必要はなくなりましたが、4ヶ月の期限内に情報を揃えるためにも早めの作業がポイントです。(詳しくは後述します。)
確定申告書
準確定申告の際には、通常の確定申告と同様に申告書を提出します。
また、申告書には2種類あり、被相続人の職業や収入で異なるので注意をしてください。
家賃収入など、以前から被相続人が毎年確定申告をしていたのであれば、どちらの申告書を提出しているか、確認してみると良いでしょう。
※ 国税庁「確定申告書の記載例」
申告書A
準確定申告の書類の一つは、「被相続人が会社員または、パート」などの給与所得者など、年金受給者の場合に必要とする書類になります。
※ 国税庁「確定申告書A様式」
申告書B
準確定申告の書類2つ目は、「被相続人の不動産や事業所得がある場合に必要とします。申告書1よりも記入欄が多く所得の控除を幅広くカバーしています。
※ 国税庁「確定申告書B様式」
被相続人の源泉徴収票
準確定申告をする際に被相続人の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票には3種類あるのでご紹介します。
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・企業年金の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票
被相続人の準確定申告を行う際は、被相続人の給与所得があった場合に、給与の支払者(会社など)から交付された「給与所得の源泉徴収票」を提出します。
※国税庁「給与所得の源泉徴収票」
公的年金の源泉徴収票
被相続人が年金受給者の場合、日本年金機構から死亡届けを提出した方に準確定申告用の年金源泉徴収票が送られてきます。
年金の源泉徴収票が実際に手元に届くまでの期間は、年金を受給受け取り停止から約2ヶ月〜3ヶ月とされています。
準確定申告は、4ヶ月以内の申告期限なので、早急に受給受け取りの停止の手続きを行いましょう。
※国税庁 「公的年金の源泉徴収票」
企業年金の源泉徴収票
お勤め先の企業の年金基金に加入している場合は、亡くなられた後に受給停止の手続きを行い、源泉徴収票が送付されます。
それぞれ送付期間が決まっているため早めに手続きをしましょう。
※国税庁 「企業年金の収入がある場合」
被相続人の控除証明書
準確定申告では、被相続人が生前支払っていた保険料は所得控除の対象となります。所得控除の対象となる保険料は以下の4つです。
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
控除を受ける際には、被相続人が加入していた保険会社に控除証明書の発行手続きを行います。(問い合わせて発行してもらってください。)
●注意点として、控除証明書の発行も各保険会社によって発行時期が異なります。
早めに保険会社に問い合わせましょう。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
準確定申告を行う際に、複数の法定相続人がいる場合は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を提出する必要があります。
●相続人全員のマイナンバーや、本人確認書の添付も必要なので、ここで相続人全員の足並みが揃わないと、手続きが遅れて期限が迫る事例も少なくありません。
準確定申告を行うことが分かり次第、相続人に周知しておくことが対策です。また、準備できるものは早めに手配しましょう。
※国税庁 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」
被相続人の医療費の領収書
被相続人の医療費の控除をする際に領収書が必要です。
医療機関にかかった領収書をあらかじめ準備してください。
委任状
所得税を払い過ぎてしまった場合に、還付金を受け取れます。
準確定申告の手続きを3ステップで解説
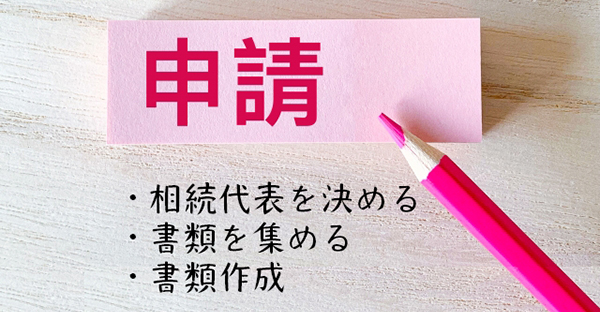
書類を揃えてしまえば、準確定申告は3ステップで手続きが済みます。ただし、何度も言うようですが、準確定申告に限っては期限が4ヶ月と短いため、それだけは注意をしてください。
・相続代表を決める
・書類を集める
・準備確定申告の準備及び書類作成
特に3人以上の法定相続人がいる場合、まずは相続代表を決めてから進めるか、相続人それぞれが準確定申告を進めるのか、相続人全員で決めてください。
<STEP1>相続代表を決める
法定相続人が複数いる場合に、申告する方法が2パターンあります。
・まとめて準確定申告を提出する
・各相続人個人が準確定申告を作成して提出する
まとめて準確定申告をする場合、相続人の代表を決めることになります。
相続人の代表となる方は、税務署から送付される書類や問い合わせの対応をしなくてはなりません。
<STEP2>書類を集める
準確定申告を行う前に、どんどん必要な書類を集めましょう。
上記でも解説しましたが、6つの書類は以下です。
・確定申告書
・被相続人の源泉徴収票
・被相続人の控除証明書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
・被相続人の医療費の領収書
・委任状
準確定申告
上記6つの書類を揃えたら、被相続人が住んでいた所轄の税務署で準確定申告の手続きを行います。
全国の税務署は、下記国税庁の検索サイトで探してください。
※国税庁 「税務署の所在地を知りたい方」
まとめ
以上が準確定申告の手続きですが、令和2年度以降からネットによる申告「e-tax」が準確定申告にも適用されています。
ただしe-taxによる確定申告は、マイナンバーカードの取得をしなければなりません。
※国税庁 「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」
一般的には単発での依頼は少ないですが、行政書士や税理士などの専門家へ、準確定申告のみを依頼するケースもあります。
相続手続き全般では、一般的な費用相場が遺産の1%ほどと言われていますが、準確定申告を単発で依頼する場合、料金目安は数万円ほどでしょう。
ただそれほど複雑ではないので、相続人が自分で手続きを進めることも充分に可能です。
まとめ
準確定申告の進め方
●準確定申告の3ステップ
・相続代表を決める
・書類を集める
・準備確定申告の準備及び書類作成
●準確定申告、6つの書類
・確定申告書
・被相続人の源泉徴収票
・被相続人の控除証明書
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
・被相続人の医療費の領収書
・委任状
お電話でも受け付けております















