
遺贈寄付って何?種類・メリットや注意すべきことを詳しく解説!

「遺贈寄付をする人が増えているって聞くけれど、遺贈寄付って何?」
「遺贈寄付をすると節税効果があるって本当?」
「遺贈寄付をする際に注意すべきことってある?」
遺贈寄付に関心があるものの、遺贈寄付について詳しく知らないという人もいるのではないでしょうか。
本記事では遺贈寄付の種類やメリット、遺贈寄付をする際に注意すべきことなどについて詳しく解説しています。
記事を読むことで遺贈寄付とは何か、遺贈寄付をすることでどのようなメリットがあるのか、また手続きの具体的な流れや注意すべき点などについて知ることができるでしょう。
遺贈寄付に関心がある人や、実際に遺贈寄付を検討している人はぜひこの記事を参考にしてみてください。
遺贈寄付とは何か

遺贈寄付は、個人が遺言により、遺産を全てもしくは一部を親族ではなく、公益法人やNPO法人、学校法人、国立大学法人などの団体や機関へ寄付することを指します。場合によっては、寄贈するよりも相続する方がメリットがあります。
また、遺贈する場合は特定の団体に限らず法定相続人以外の人にも可能です。そして、遺贈する側は「遺贈者」、遺贈する相手を「受贈者」と呼びます。
遺贈寄付の種類

遺贈寄付の意味については理解できたでしょうか。ここでは遺贈寄付の種類について解説します。
遺贈寄付には、大きく分けて2つの方法があります。それぞれの遺贈寄付の特徴、注意点などをしっかりと押さえておきましょう。そしてどちらがより適するかの判断材料にしてください。
特定遺贈
特定遺贈は、事前に遺産のうち特定のものを指定し、与える遺贈のことを指します。例としては、「Aさんには土地を、Bさんには株式を、Cの団体には現金を与える」と遺言書に記載されます。
受贈者が法定相続人ではない場合、遺産分割協議に参加する必要がなく、遺産はすぐに受け取り可能です。さらに特定遺贈の場合、負債を相続しないという利点もあります。
注意点として法定相続人以外の方が、不動産の特定遺贈を受ける場合、不動産取得税がかかる可能性があります。
出典|参照:遺贈(寄付)の注意点|大曽根行政書士事務所
包括遺贈
包括遺贈は、遺産の具体的な内容を特定せずに、全てまたは遺産全体の何割というように割合を決定し、与える遺贈を指します。例として、「Aさんに自分の資産の3割を譲る」と遺言書に記載されます。
ただし、遺産には土地などの資産だけでなく、借金や負債などのマイナス面も含まれます。受贈者は受け取る際に全て確認し、借金などの資産がないか注意しましょう。
また、割合のみが指定されるため、具体的な財産が決まりません。そのため、受贈者は遺産分割協議に参加する必要があり、遺産をどれだけ相続するかの決定を話し合わなければなりません。
出典|参照:遺贈(寄付)の注意点|大曽根行政書士事務所
遺贈寄付をする人が増えているのは何故?

遺贈寄付をする人が増えている理由として生涯を独身で過ごし、財産の相続人がいない人が増えていることが挙げられます。
またそれだけではなくコロナなどによる社会問題への関心が高まったことも、遺贈寄付をする人が増えた原因と言えるでしょう。
さまざまな社会課題がある現代において、遺贈寄付は自分も社会のために何かしたいという思いを叶えられる手段の一つであるため、関心が高まっているのです。
遺贈寄付のメリット

遺贈寄付をする人が増えているのはおひとりさまの増加や社会問題への関心の高まりという理由だけでなく、さまざまなメリットもあるからとも言えます。
ここでは遺贈寄付にはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
● 節税になる
● 財産の承継先を見つけられる
● 寄付金控除を受けられる
● 社会貢献になる
節税になる
基本的に相続させる財産が基礎控除額を超えた場合には相続税を支払う必要があります。しかし遺贈寄付を行った財産は課税の対象にならないため、相続税を節税することが可能です。
なお、相続人が財産を相続した後に寄付を行った場合には原則として課税の対象となりますが、相続税の申告期限まで寄付する、財産をそのままの形で寄付をする、国に認められている団体に寄付するなどの要件を満たした場合は課税対象から外すこともできます。
出典|参照:相続税は誰が払う?いつ?どうやって?よくある疑問も解消します!|税理士法人チェスター
財産の承継先を見つけられる
財産の相続人がいない人の財産は、原則として本人が亡くなると国庫に帰属することになります。遺贈寄付を行えば、自分自身で自分の財産の継承先を決めることが可能です。
自分が関心のあることや、応援したいこと、また自分にゆかりがある団体などに自分の財産を使ってもらうことができれば満足感を得ることができるでしょう。
寄付金控除を受けられる
故人が生前自営業を営むなどして確定申告をしていた場合、相続人が財産を相続してから4カ月以内に故人に代わって確定申告を行う必要があります。
故人の収入がある程度あった場合には所得税が課せられますが、遺贈寄付をした場合には一定の要件を満たすことで遺贈寄付をした金額について、寄付金控除を受けることが可能です。
寄付金控除を受けられれば、所得税の課税額を少なくすることができ、相続する財産を実質的に増やすことができます。
社会貢献になる
遺贈寄付をすることで社会貢献になるというのもメリットの一つです。日ごろから誰かの役に立ちたいと思っている人も多いでしょう。
遺贈寄付を行うことで自分の財産を社会のために役立てることができ、満足感を得ることができます。
生きている間は自分自身の生活があるため、なかなか寄付をするのは難しくても遺産の中からなら寄付をすることができるという場合もあるでしょう。
少額の遺贈寄付でも受け付けている団体はあるため、財産が多くなくても社会貢献ができるでしょう。
遺贈寄付の手続きの流れ

それでは実際にどのような流れで遺贈寄付を行う必要があるのでしょうか。遺贈寄付の手続きだけでも相応の時間や手間がかかります。そのため、何をこれからするのか流れを把握していきましょう。
ここでは遺贈寄付の手続きに必要な点、大まかな流れについて解説していきます。
専門家に相談
専門家に相談することで、法律面や遺贈する際の注意点を含め、検討してくれます。これによって事前にトラブルを防ぐことができるでしょう。また、遺贈予定の団体自身で、寄付の準備等を相談できる場所もあります。
寄付先を選ぶ
自身の財産をどのような割合で、どの人や団体に遺贈するのかを決める必要があります。その判断は自身で決定することができます。その際に、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら決定すると良いでしょう。
遺言執行者を依頼する
遺贈者の意思を確実に実現するため、事前に遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行には相応の時間と手間、知識が必要なため弁護士や司法書士などの専門家を指定すると、問題が起こりにくいです。
また、遺言執行者を指定する場合、遺言者の逝去の報を執行者に伝えるための通知人を決めておきましょう。この逝去の知らせを受けた後に、遺言書の内容が実現できます。ここでの通知人は、家族や近所の方、施設や病院スタッフなどです。
遺言書の作成
遺言書を作成する場合、誰に、どの財産を遺贈するかを明記し、遺贈先の正式名称と住所を記入しましょう。また、法的に有効な遺言書にするために専門家に相談しながら作成し、ミスがないように記載しましょう。
遺言書は、手書きで文を書く自筆証書遺言、公証役場にいき作成する公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は、費用や手間がかからない点が特徴です。ただし無効になる可能性があるため、不備の無いよう作成する必要があります。公正証書遺言は、専門家と相談し作成するため不備が生じにくい特徴がありますが、一方で費用や手間は生じてしまいやすいです。
遺言書作成後は、しっかりと保管しましょう。保管方法は、自宅で保管するか遺言執行者がいる場合は、遺言書を預けておくのも良いでしょう。
寄付の実行
最後に遺言執行から引き渡しまでの流れです。遺言者が逝去された場合、遺言執行者は遺言書の内容に従い、手続きを開始します。
ただし遺言書の開封は、遺言書の方式によって異なるため十分注意しましょう。公正証書遺言の場合は、手続きが必要ありません。しかし、自筆証書遺言は法務局で保管されていない場合、家庭裁判所の兼任を受けなければなりません。
そして遺言書に記された遺贈先に、遺言書の写しが送付され、財産を受け取るかの意思を確認します。これが完了すれば、遺言執行者に従い、遺贈先に財産を引き渡します。
遺贈寄付を行う際に注意すべきこと
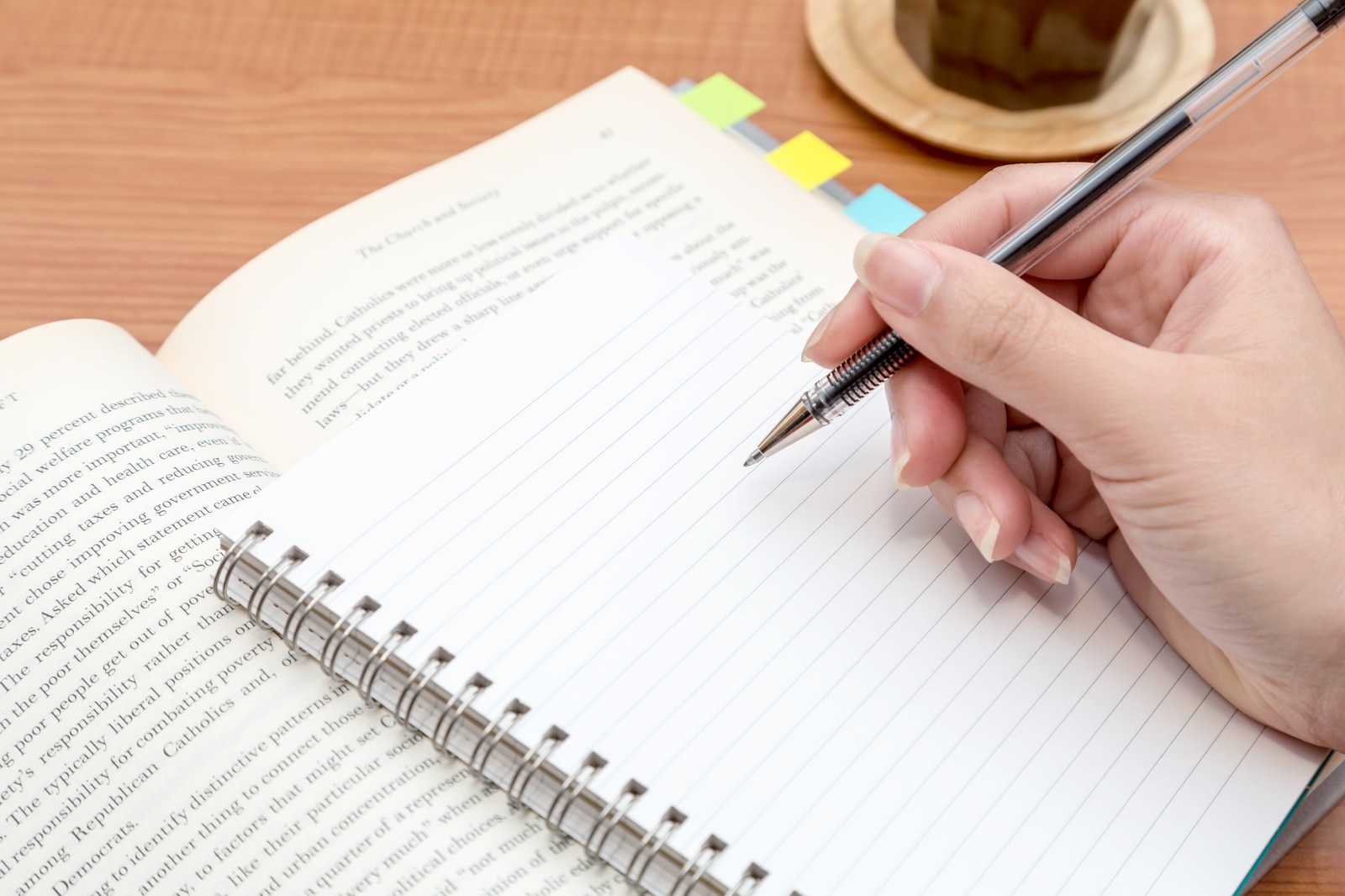
遺贈寄付を行うことで節税になる場合がある一方、相続税が増税される場合もあるなど、遺贈寄付を行う際には注意すべき点がいくつかあります。
ここでは遺贈寄付を行う際に注意すべきことについて解説しますので、遺贈寄付を行う際の参考にしてみてください。
納税が免除になるケースがある
相続税や所得税の控除など、納税が免除になるケースはどこへ寄付をするのかによっても変わります。国が指定している組織・団体へ遺贈寄付を行った場合、控除となりますが、それ以外の団体や個人などに寄付した場合には控除されないでしょう。
また、慈善事業を行っていても、認可を受けていない宗教法人やNPO法人などに寄付した場合、納税が免除にならないため注意しましょう。
相続人の遺留分は寄付金から除外しておく
遺贈寄付を行う場合には相続人の遺留分に注意することが必要です。配偶者や子、父母、祖父母には遺留分(相続人に保証されている最低限の遺産の取り分)があります。
遺留分は遺言よりも強い力を持っているため、遺留分まで寄付してしまうと相続人が寄付先に遺留分を取り戻す請求を行う可能性があります。
そうなると寄付先に迷惑をかけてしまうため、遺贈寄付する際には相続人の遺留分を寄付金から除外しておくようにしましょう。
出典|参照:遺留分放棄の許可 | 裁判所
特定遺贈を選択する
遺贈寄付の方法には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈は不動産や現金など特定の財産を選んで遺贈しますが、包括遺贈の場合は財産の割合を決めて遺贈する方法であるため、借金などのマイナスの財産があれば、寄付先はマイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。
また包括遺贈を受けると相続人と同等の権利義務を負うため、寄付先が相続人と遺産分割協議を行わなくてはならない場合もあるでしょう。遺贈寄付を行う場合には寄付先への配慮として特定遺贈を選択するのが好ましいです。
出典・参照: 遺贈について |弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
相続税が増税されるケースがある
相続や遺贈の贈与で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合、その人の相続税額に対して、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
対象となる人物は大きく分けていずれかの要件に当てはまる場合です。
まずは、被相続人から相続や遺贈により財産を取得し、被相続人の配偶者、父母、子ではない場合です。これは例として、被相続人の兄弟や姉妹、おいなどです。
次に、被相続人の養子として相続人となった人で、被相続人の孫でもあり、代襲相続人になっていない人です。
ただし、被相続人の養子は一親等の法定血族であるため、相続税の2割加算は対象外となりますが、被相続人の養子となる被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象になります。
出典|参照:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁
不動産を寄付する場合は清算型遺贈を選ぶ
不動産を寄付する場合には、相続後に遺言執行者が不動産を現金化して遺贈する、清算型遺贈を選ぶようにしましょう。
不動産のまま寄付をすると時価で不動産を譲渡したと見なされ、含み益に譲渡所得税が課せられます。そうなると相続人が確定申告を行って納税しなければならなくなるため、注意が必要です。
寄付先に確認をとってから手続きをする
寄付先によって遺贈寄付を受け入れる条件が決まっており、不動産や有価証券などは現物のまま受け取ってもらえない場合もあるでしょう。
またトラブルに巻き込まれたくない観点から、遺贈寄付を受け入れていない団体もあります。そのため、必ず寄付先に確認をとってから手続きをするようにしてください。
遺贈寄付の種類をしっかり理解しておこう

遺贈寄付の種類やメリット、手続きの流れ、注意すべきことなどについて詳しく解説しました。
遺贈寄付は、遺言書などにより特定の個人や団体に、遺産を寄付することが可能です。ただし、時間や手間がかかるからといって、専門家などの意見を聞かずに行うのはおすすめできません。不明な点は近くの専門家に相談したり、税金に関しては各都道府県に確認したりしましょう。
この記事の内容を参考に遺贈寄付の種類や注意点をしっかり理解した上で、ご自分の思いを実現してください。
お電話でも受け付けております















