
永代供養での三回忌などの年忌法要は可能か?服装や費用・お墓参りの仕方も解説

「永代供養でも年忌法要は必要なの?」
「そもそも年忌法要のときの服装や費用は?」
年忌法要とは、故人の命日を迎える節目でおこなう法要をさしますが、法要についてあまり経験のない方は疑問や悩み事があるでしょう。
この記事では、永代供養における年忌法要を中心に紹介していきます。遺族ができること、法要、三回忌法要の流れや法要の際の注意点などについて詳しく解説していきます。
記事を読み終わる頃には、法要に関する知識の幅が広がり、万が一のときにも慌てずに対処することができるでしょう。もし、家族や友人に法要について質問された場合でも、しっかりとしたアドバイスができるようになります。紹介する内容を活かして、故人を偲ぶ大切な時間を過ごしてください。
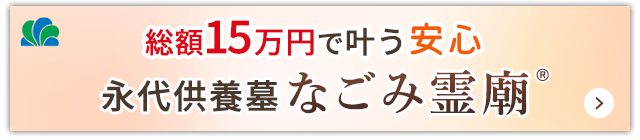
永代供養で三回忌法要は可能?

永代供養とは、霊園に遺骨を管理・供養してもらうことです。永代供養を選択した場合、故人の供養はお墓を管理している寺院や霊園がおこなっているため、あらためて遺族が法要をとりおこなう必要は原則ありません。
しかし、永代供養であっても法要をおこなって問題ないため、三回忌法要をとりおこなうことは可能です。
そもそも法要は、年忌や忌日をきっかけに家族や親族で故人を思い偲ぶひとときです。永代供養にこだわらず、法要を通して故人の冥福を祈って追善供養をしてあげましょう。
年忌法要・回忌法要は追善供養です
年忌法要・回忌法要は、故人が亡くなった祥月命日に、一回忌、三回忌のように特定の節目の年ごとに行われる仏教の追善供養(ついぜんくよう)を指します。永代供養を選択すると、霊園・寺院が年忌法要・回忌法要をおこなっているケースがあるため、もし供養をするならば、「追善供養」という形でおこなうとよいでしょう。
「追善供養」とは、遺族が故人の冥福を祈っておこなう供養のことです。故人のために善を積むことで、故人が良い世界へと輪廻転生できるよう祈りを捧げると共に、その善が自分自身にも戻ってくると考えられています。
ちなみに、浄土真宗では、人は亡くなると阿弥陀如来のちからで成仏すると考えられているため、「追善供養」という言葉は使用しません。
法要を行うことで親族の関係も密になる
法要をおこなうと、なかなか顔をあわせる機会の少ない親族同士が、故人を通して集まるきっかけにもなります。法要で共に故人を偲び、その後、食事をしながら近況報告をすることで、親族の関係も密になるでしょう。
亡くなった故人が永代供養を選択していたとしても、このような場を設けることで多くの人とのつながりを感じることに意味があります。
・永代供養墓をわかりやすく解説!何年供養できる?選ぶポイントは?
寺院・霊園がおこなう永代供養の主なタイミング

永代供養を選択した場合、寺院や霊園が日頃から供養をおこなってくれます。それでは、具体的にどのようなタイミングで供養をしてくれるのでしょうか。ここでは、寺院・霊園がおこなう永代供養の主なタイミングを紹介します。
なお、永代供養の契約によっては法要の種類が異なる場合があります。一般的におこなわれる法要として認識しておきましょう。
春・秋のお彼岸
春分・秋分の日の前後3日をあわせた7日間を「春彼岸」「秋彼岸」といいますが、この時期にお彼岸の供養がおこなわれます。各お彼岸は、代表的な法事でもあるため、僧侶によって懇ろな法要をしてくれるところが多いでしょう。
一周忌・三回忌などの年忌法要・回忌法要
仏教上で定められた、一周忌や三回忌といった故人の命日にも供養をすることが多いでしょう。法要をおこなう年数として、「満1年目が一周忌」「満2年目が三回忌」「満6年目が七回忌」という流れでおこなうのが一般的とされています。
そして、三十三回忌や五十回忌を弔い上げ(最後の法事)とするのが通例です。
月命日
故人が亡くなった月を除く、それ以外の月命日にも法要をとりおこなってくれる場合があるでしょう。たとえば、1月22日に亡くなった故人の場合、1月を除いた2月から12月の毎月22日に供養をおこない、1年で合計11回の月命日の法要がおこなわれます。
永代供養で遺族がおこなう法事・供養例

永代供養を選んだとしても、故人の冥福を祈り、また親族が集まる場を設けたいという方もいるでしょう。遺族がおこなうことができる法事・供養にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、永代供養でも遺族がおこなうことができる法事・供養例について紹介していきます。
四十九日
四十九日は、命日から数えて49日目におこなう追善法要です。仏教では人が亡くなると7日ごとに極楽浄土に行けるかの裁判がおこなわれるとされています。その最後の裁判が49日目になるため四十九日に法要をおこない、故人を偲び供養をおこないます。
四十九日は「忌明け」とされ、ご遺族にとって大切な節目の日です。たとえ永代供養を選ばれた場合でも、この日にあらためて法要を営むことで、気持ちに区切りをつけ、故人を偲ぶひとときを持つことができます。
・納骨式や四十九日法要のお布施の相場は?お寺へ渡す金額やかかる費用を解説
初盆
初盆(新盆)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆におこなう追善法要です。もし、お盆の前に亡くなった故人はその年のお盆に、またお盆がすぎてから亡くなった故人は次の年のお盆が初盆になります。
初盆の供養は永代供養の契約内に入っていないことが多いため、霊魂としての初めての里帰りを、家族や親族で迎えてあげるとよろこばれるでしょう。また、家族や親族が集まりやすい時期でもあるため、永代供養であっても初盆に法要をおこなう方が多いとされています。
・初盆の法要とは?流れ・準備・お布施・服装まで|初めてでも安心できる基礎知識
三回忌までの年忌法要・回忌法要
年忌法要・回忌法要は、永代供養でもおこなってくれる場合があるため、必ずしも必要ではありませんが、目安として三回忌くらいまでの法要はとりおこなうとよいでしょう。
一般的に、三十三回忌や五十回忌が「弔い上げ」とされることが多く、ここで一連の年忌法要を締めくくるケースが見られます。ただし、どこまで法要を営むかはご遺族のご判断に委ねられ、三十三回忌でも五十回忌でも差し支えありません。
永代供養でおこなう三回忌法要の流れ

永代供養を選んでいて、三回忌供養をおこないたいという場合、どのような手順で進めるのがよいのでしょう。一般的な法要とは異なるのでしょうか。
ここでは、永代供養でおこなう三回忌法要の大まかな流れについて紹介します。
親族と日程調整
まずは、家族や親族に法要について相談しておきましょう。急に法要の連絡をしても都合がつかない可能性があるためです。法要をおこなう数カ月前には伝えておくとよいでしょう。
喪主の都合で慌てて進めようとしても、親族間でいざこざが起きてしまうケースもあります。問題なく、心をこめて故人を供養するためにも、計画的に準備しましょう。
永代供養を依頼している寺院・霊園に相談
家族や親族に法要の相談をしたら、永代供養を依頼している寺院・霊園にも相談しておきましょう。 その際には、法要の日程や参加予定人数も含めて具体的に伝えるとよいでしょう。
永代供養は、永代にわたって第三者が遺骨を管理・供養する埋葬方法であるため、契約によって三回忌法要をおこなう場合もあります。三回忌法要が契約に含まれていない場合には、しっかりと事前に法要の相談をするようにしてください。
また、施設によってはさまざまな規則で個人での法要がおこなえない場合もあるため、前もって確認しておくことを忘れないようにしてください。
寺院や僧侶に法要を依頼
次に、寺院や僧侶に法要を依頼しましょう。この段階で日程もきちんと決めて、具体的な内容で依頼してください。
もし、宗派による決まりごとやお布施の金額など、分からないことがあれば、あわせて確認しておくと安心でしょう。
寺院の場合は、僧侶に依頼することもできますが、僧侶が所属していない霊園などの場合には、各自で手配することになります。近頃は僧侶の派遣サービスというのもあります。上手に利用するとスムーズに依頼ができるでしょう。
当日の法要
当日は、参列してくださったご親族や、わざわざお越しいただいた僧侶の方々への感謝の気持ちを込めて、丁寧なご挨拶と細やかな心配りを忘れないようにしましょう。
また、喪主として問題なく三回忌がおこなわれるよう、読経や焼香といった段取りは事前によく確認しておきましょう。できれば、親族にも手順の情報を共有しておくのもよいでしょう。
お墓参り
法要後は、お墓参りをおこないます。お線香や献花、故人が生前好きだったものなど、手をあわせるときに必要なものはあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
ただし、永代供養のお墓の場合、お供えものが一切できないケースもあるため注意が必要です。墓地の規則を確認し、その規則に従うようにしましょう。
これに関しては「永代供養での三回忌法要の5つの注意点」でより詳しく解説しています。
・永代供養のお墓参りの流れとは?お供え物などの注意点や法事についても解説
会食
お墓参りが終わったら、他のご遺族の希望をふまえて規模や予算を確認し、一般の法要と同じく、会食をおこなうとよいでしょう。
冒頭でも述べたように、永代供養を選んでも、このような場を設けることでなかなか会えない親族との大切な交流の場となります。可能ならば、多くの人とのつながりを感じるためにも会食をおこなうとよいでしょう。
永代供養での法要の費用

法要ではお布施やお車代、御膳料など何かとお金がかかる場面がありますが、永代供養はどこにどのような費用がかかるのでしょうか。ここでは、永代供養の場合の法要の費用について詳しく見ていきます。
なお、費用については地域や寺院・霊園によっても異なります。あくまでも目安として参考にしてください。
お布施・お車代・御膳料
一般的にお布施の額は、30,000円~50,000円ほどであるとされています。これは地域によっても異なるため、疑問や不安があれば依頼した僧侶にあらかじめ聞いてみてください。なお、僧侶を派遣するサービスであれば、明確なお布施額が提示されやすいでしょう。
御車代は、僧侶にきていただいたお礼です。セレモニーホールや自宅など、別の場所へ足を運んでもらう場合には支払うようにしましょう。御車代の平均相場は、3,000円~10,000円ほどです。
御膳料は、会食する場合、僧侶が辞退して参加しなかったときに支払うおもてなし料です。5,000円~10,000円ほどが平均相場となります。
会場代
当然、どこで法要をおこなうかによって会場代は異なりますが、以下の内容は参考になるでしょう。
菩提寺として利用する場合は、会場代はかからない場合もありますが、永代供養の法要としてお寺を使用する場合には、3,000円~20,000円ほどが目安です。
自宅でおこなう際は、費用はかかりませんが、準備に手間がかかる場合があります。
セレモニーホールの会場代は一般的に30,000円ほどかかりますが、自宅でおこなう場合よりも準備や片付けの手間がかかりにくいのがポイントの一つです。参加する人数で料金が変動するため、利用時は確認しましょう。
線香やお供え物代
お墓参りするときに持参するお線香や献花、法要時に渡すお供え物などの費用は想定しておくとよいでしょう。人にもよりますが、数千円~10,000円ほどあれば十分でしょう。
永代供養墓によっては、お供え物ができないケースもあるため、事前に確認をしましょう。
会食費
会食代の目安は、一人当たり3,000円~5,000円ほどを目安にしておきましょう。10人参加する場合は、30,000円~50,000円ほどかかります。
法要をおこなう場合には、参列者はお金を包んでいることもあるため、実質かかる負担はこれより少なくて済むでしょう。
永代供養での三回忌法要の5つの注意点

ここまで、永代供養の場合の法要の流れや費用について見てきましたが、気をつける点がいくつかあります。最後に、永代供養で三回忌法要をおこなう際の注意点を5つピックアップして紹介していきます。
1:家族とあらかじめ日程調整する
家族とあらかじめ日程調整を密におこなっておきましょう。連絡の行き違いで些細なトラブルが起きる場合もあるため、注意が必要です。日程が決まったら、参列予定の方にも早めの連絡をしましょう。
また、日程もそうですが、あわせて法要当日の流れも全員が共有できているとよいでしょう。そうすることで、日程決めから法要の最後まで、スムーズかつ安心して当日を終えることができます。
2:寺院・霊園への連絡は早めに
寺院・霊園への連絡は早めにするようにしましょう。特にお盆は、一年のうちで忙しくなる時期です。初盆に法要が決まったら、相手方のことを考えてできるだけ早めに連絡を入れましょう。
3:お墓参りの服装は普段着でよい
法要と同様に、お墓参りの服装にも明確な決まりはありません。スーツなどのフォーマルな装いだけでなく、落ち着いた印象のある普段着でお参りしても問題ありません。
ただし、節度ある身だしなみを心がけることが大切です。だらしない服装や汚れた衣服は避け、清潔感のある装いで故人を偲びましょう。
4:永代供養墓によってはお花を置けない
お墓参りに行くときは、手ぶらでもよいでしょう。お供え物を持って行っても問題ありませんが、施設によってはお供え物に制限があるため規定を事前に確認しておきましょう。
たとえば、樹木葬では食べ物の持ち込み・お焼香が禁止の場合があったり、納骨堂では火気厳禁や生花の持ち込みが禁止の場合があったりします。そのほかに、永代供養墓のタイプによっては、お供えスペースがない場合もあります。
あくまでも、永代供養を依頼している施設の規定と永代供養墓のタイプを考慮して対応するようにしましょう。
5:お布施はなくてもよい
法要では、お布施が求められますが、お墓参りでは必ずしも必要というわけではありません。しかしながら、お墓参りで僧侶に読経をお願いする場合は、お礼として3,000円~10,000円程度の「供養料」を包むのが一般的とされています。
永代供養で三回忌をすることは意味がある

いかがでしたでしょうか。この記事では、永代供養でおこなう法事について詳しく紹介してきました。永代供養を選んだとしても、故人を偲び、また遺族が集まるきっかけにもなる法要は価値のあることでしょう。
永代供養では、墓地を管理する寺院や霊園が、お彼岸や年忌法要、月命日などにあわせて合同供養を実施していることがあります。
一方で、四十九日や初盆といった節目の法要は、ご遺族があらためて個別に営んでも問題ありません。
また、三回忌までの年忌法要についても、ご希望があれば執り行うことができます。
永代供養を選ばれた場合でも、こうした節目に手を合わせることで、いつまでも故人に心を寄せ続けることができるでしょう。
お電話でも受け付けております















