
2人のための夫婦墓とは?選べる種類と費用相場・利点や欠点も併せて紹介

「夫婦墓にはどんな種類がある?」
「2人とも亡くなった後、最後に納骨するのは誰?」
夫婦墓に関してはまだよく分からない点がある方もいるのではないでしょうか。
少子高齢化に伴いお墓に対する考え方は段々と変わってきています。先祖代々のお墓を維持していくには継承者が必要ですが、先々のことを考え夫婦だけで入る夫婦墓を希望する方もいるでしょう。
この記事では永代供養つきの夫婦墓を選ぶメリット、デメリットを始め、最後の納骨、墓じまいまで夫婦墓に関わることを解説していきます。この記事を読むことで、理想的な夫婦墓の形が見えてくるでしょう。
夫婦墓が自分たちに向いているか分からず決めかねている方はぜひ参考にしてみてください。
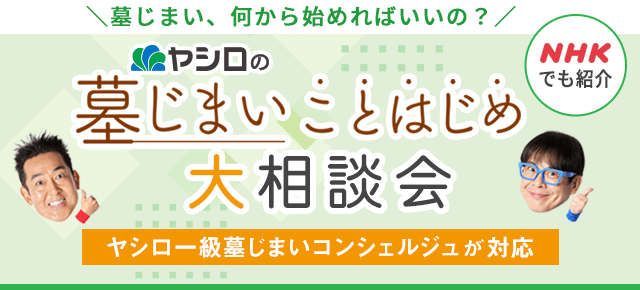
夫婦のための夫婦墓とは?

夫と妻の2人だけで入れるお墓を夫婦墓(めおとばか、ふうふばか)と言います。夫婦だけでの使用を前提としたお墓のため、特別なケースを除きほかの人を一緒に納骨することはないでしょう。
墓石を建てる場合は一般的なお墓とは名前の刻み方が違い、2人の戒名もしくは俗名を並べるケースが多く見られます。
子どもがいない、先祖代々の墓とは別に準備したい、お墓の継承を望まないなど夫婦墓を選ぶ理由はさまざまです。
夫婦墓の種類と必要な費用の相場について

夫婦墓の種類は大まかに分けると一般的な個別墓、納骨堂、樹木葬の3つがあります。かかる費用は選ぶ種類や埋葬方法などにより違いますが、お墓にかかる料金のほか、永代使用料や年間管理料が含まれているのが一般的です。
ここからは、夫婦墓の種類とその費用相場について紹介します。希望する種類の夫婦墓が予算内で納まるかチェックしてみましょう。
個別墓の場合
屋外の墓所に墓石や墓標を個々に建て埋葬するのが一般的な個別墓です。契約により一定期間が過ぎると同じお墓を使い続けられないケースが多く、取り出された遺骨は複数人が眠る場所へ移され、その後も供養されます。
個別墓はほかの種類に比べて費用が高めで、納める墓所が都心部に近いほど費用がかかる傾向が見られます。夫婦墓の費用相場は安価な施設で約80万円~と考えておくといいでしょう。
出典|参照:価格から探す|霊園・墓石のヤシロ
納骨堂の場合
建物の中にあるスペースに遺骨を納めるのが納骨堂です。納骨堂には、納骨壇式、ロッカー式、自動搬送式などのタイプがあります。納骨堂も個別墓と同様、安置期間が過ぎると合葬されます。
タイプや地域、施設で価格は違いますが、夫婦で使用する場合の相場は約60万円~です。自動搬送式はほかのタイプより高く、個別墓と同じくらいの相場です。
出典|参照:価格から探す|霊園・墓石のヤシロ
樹木葬の場合
樹木や草花の周囲へ遺骨を埋葬するのが樹木葬です。シンボルツリーを共有し個別の墓碑に納めるタイプや、遺骨を埋葬した場所に植樹するタイプなどがあります。
個々にスペースを確保する方法は約100万円近くかかる場合もあり、複数人が一緒に納められる合葬タイプを選ぶと相場は約40万円です。費用は抑えられますが、2人で使う夫婦墓のイメージとは少し異なってしまうでしょう。
出典|参照:価格から探す|霊園・墓石のヤシロ
夫婦墓はどんな人におすすめ?

基本的には夫婦以外の人が入ることがない夫婦墓は、その性質から向いている人と向いていない人がいます。
ここからは、夫婦墓がどのような人におすすめか具体的に紹介します。参考にしてみてください。
親と一緒の墓が嫌な人
先祖代々受け継いでいる墓があるけれど、親と一緒に入ることが嫌な人は夫婦墓がおすすめです。
例えば、親と疎遠になっている夫婦や、遠方に住んでいて納骨やお参りが難しい人もいるでしょう。そのような夫婦にとっては、夫婦墓を立ててそこに入るほうが後の管理も楽になります。
また、単に自分で墓を立てたいからという理由で夫婦墓を選択するのも良いでしょう。後の管理のことを考えた上で夫婦墓を選択してみてはいかがでしょうか。
跡継ぎがいない夫婦
夫婦墓は、跡継ぎがいない夫婦におすすめです。
子どもがいない、もしくは墓の跡継ぎをする意志がない家庭の場合は夫婦墓にしておくと、死後の管理が楽になります。永代供養付きの夫婦墓なら、普段の掃除やその後の管理なども一任できるでしょう。
死後の管理費などに悩むことがないため、跡継ぎがいない夫婦は夫婦墓を検討してみてはいかがでしょうか。
夫婦墓には永代供養墓がおすすめ

永代供養は墓地を所有している施設で管理され、同じ場所に眠る人々と一緒に供養されます。
夫婦墓の種類により途中で埋葬場所が移る場合もあるため、2人が永遠に一緒の場所で眠れるかどうかは選び方次第で変わるでしょう。
その後の管理費などに悩まずにすむため、夫婦墓は永代供養墓がおすすめです。
・【大阪の終活】夫婦で生前契約する永代供養は?家族やペット、大切な人と入る7つの記事
夫婦墓を建てる利点

永代供養つき夫婦墓は個人の希望を優先して建てることも可能です。亡くなった後、お墓を受け継ぐ心配もせずにすむでしょう。
ここからは夫婦墓を建てる利点について紹介します。選ぶ決め手となる良い面を見つけてみましょう。
子どもや孫への負担がなくなる
従来のお墓はきれいに保つために掃除や植えてある樹木の手入れなどのメンテナンスが必要です。お墓の一部が壊れた場合には修理の手配もしなければならないでしょう。
永代供養のついた夫婦墓は、金銭的な面も含め子どもや孫の負担はほとんどなくなります。離れた場所に住んでいて頻繁に足を運べなかったとしても、施設側がきちんと管理してくれるためお墓のことを気にせずにすむでしょう。
継承してくれる人がいなくても利用できる
永代供養の場合、管理や供養は遺骨を納めている施設が行うため、継承者がいなくても利用できます。通常のお墓は所有権を持っている人が亡くなると相続財産として扱われ、継承する人物が必要です。
亡くなった後の心配がいらない永代供養つきの夫婦墓は、継承してくれる子どものいない夫婦でも申し込みやすいでしょう。
夫婦2人でデザインや場所を決められる
夫婦墓は自分たちに合う埋葬場所や埋葬方法、スタイルを決められます。納める施設によっては自由度が高い場合もあり、墓石、墓標のデザインを2人の好みに合わせ自分たちらしさを表現することも可能です。
形にこだわったオリジナルのモニュメントを建てる、夫婦で大切にしてきた言葉を刻むなど普通のお墓では難しいことも叶えられる可能性があります。
建墓費用を抑えられる
永代供養つき夫婦墓は一般的なお墓よりも安い費用で建てられます。通常、お墓を建てる際は墓地、墓石、そのほかの付属品が必要です。すべて入れて計算すると高額になるケースもあります。
個別の契約期間終了後に埋葬場所を移すタイプの夫婦墓は価格の設定が低めです。お墓の場所や種類、埋葬方法の選び方によっては建墓費用をかなり安く抑えられるでしょう。
夫婦墓を建てる欠点

夫婦墓は利点ばかりではなく、気づかずに契約してしまうと後悔するような欠点も存在します。良い面ばかりでなく不都合な点も理解しておくことで、自分たちに合うスタイルかどうかを正しく判断できるでしょう。
ここからは、夫婦墓の欠点について紹介します。
子どものお墓参りの手間が増える
受け継がれている先祖代々の墓がある場合、夫婦だけのお墓を建ててしまうと残された子どもは両方を気に掛けなければなりません。
永代供養の夫婦墓は、お墓の管理や法要の準備で子どもの手を煩わせることはありませんが、元々あるお墓の維持管理や法要は変わらず必要です。
お墓参りに出かける場所も2ヵ所になり、その分時間もとられてしまうというデメリットがあります。
最後は合葬されてしまう
永代供養のついた夫婦墓の多くは安置可能な年数が決められており、最後は合葬されます。夫婦墓から取り出された遺骨は合葬墓や供養塔などへ移されます。
合葬されると使用していた墓石は撤去され、遺骨を取り出した後に残る骨壷も処分されるでしょう。2人だけのお墓ではなくなってしまうため、夫婦墓のイメージとは離れてしまいます。
後から遺骨を移すことができない
夫婦墓から合葬へ移された遺骨は個別に管理されないため、後から取り出したり、移動したりはさせられません。
残った家族や親戚が訪れやすい場所へ移したいと考えても、合葬されてしまっていると希望を叶えられないでしょう。遠くても故人が眠っている場所まで出かけないとお墓参りができなくなります。
子どもがいる場合は決める際によく話し合い、永代供養つきの夫婦墓を選ぶときは合葬されるまでの期間を伝えておきましょう。
夫婦墓の契約から納骨までの3つの流れ

支払いや納骨は夫婦墓を用意する上で理解しておきたいポイントです。料金の支払い方、実際の納骨を誰が行うかはケースによって異なります。
ここからは、夫婦墓を契約した後の具体的な流れについて説明します。
1:最初に料金を一括で支払う
契約する施設により料金の支払い方は違います。契約時と一人目の方が亡くなった後に分けて支払うケースも見られますが、永代供養つきの夫婦墓では最初に料金を一括で支払う場合が多いでしょう。
料金にはお墓を建てる費用、合葬に移す際にかかる費用などが含まれています。年間管理費は契約内容により支払い続けていく場合もあるため、必ずしも含まれているとは限りません。
2:先に旅立った故人を遺された配偶者が納骨する
2人のうちのどちらかが亡くなった際に納骨を行うのは遺された配偶者です。つまり夫が先に亡くなった場合は妻が、妻が先に亡くなったときは夫が遺骨を納めることになります。
この時点で注意しておきたいのが料金の支払いについてです。契約時に全額の支払いがすんでいるか確認し、分割して支払う予定になっていたときは忘れずに残りの金額を支払いましょう。
3:2人目は子どもか死後事務執行者が納骨する
2人目の納骨は子どもまたは死後事務の執行者の手で行います。子どもがいる場合は生前に納骨する施設への支払いや契約に関する書類を渡し、お墓のことでトラブルが起きないようにしておきましょう。
身近に納骨をお願いできる人がいない場合は司法書士や弁護士などの専門家と死後事務委任契約を結んでおくと安心です。死後事務委任契約を結ぶと、亡くなった後の手続きや納骨などを任せられます。
・永代供養で起こりうるトラブルとは?問題が起きないためのポイントを解説
墓じまいをする際の4つの手順

前述したように、永代供養の夫婦墓以外に先祖のお墓が残っていれば、遺された人に負担を背負わせてしまうでしょう。先祖のお墓が残っている場合は、自分たち以外に受け継ぐ家族、親族がいなければ無縁仏となってしまう可能性もあります。
お墓を維持していくのが難しい場合は墓じまいするのも方法の1つです。ここでは、墓じまいの手順を解説します。
1:墓地管理者に契約を終了したい旨を伝える
墓じまいすることを決めた後は、お墓のある墓地の管理者へ連絡を入れ、契約を終了したい旨を伝えます。供養をお願いしていた菩提寺にお墓がある場合は、お寺との間でトラブルが起こらないよう丁寧な対応を心掛けましょう。
檀家を辞める際、お布施として菩提寺へ離壇料を支払うことがあります。契約書に記載されていなければ支払う義務はありませんが、お礼の気持ちとして納めるケースが多いでしょう。
2:改葬手続きをする
埋葬していた遺骨を別のお墓に移す際は改葬手続きが必要です。まずは、埋葬中のお墓のある自治体から改葬許可申請書を受け取りましょう。申請書は自治体の窓口のほかホームページからダウンロードすることも可能です。
必要事項を記入後、使用している墓地の管理者に埋葬中であることを証明するための署名、捺印をお願いし、書き終えた申請書を自治体へ提出すると改装許可証が交付されます。
出典|参照:改葬の手続き|宮崎市
3:先祖の遺骨を供養してもらう
墓じまいするときは供養してから先祖の遺骨を取り出しましょう。
墓じまいの際は遺骨を移して撤去する前に、墓石から先祖の魂を抜く供養が必要です。墓じまいの供養は教えの異なる一部の宗派を除き、閉眼供養や御魂抜き、性根抜きなどと呼ばれています。
4:墓石を撤去し更地にする
埋葬していた遺骨を取り出した後に残った墓石は撤去し、更地の状態で墓地管理者へ返します。墓地により撤去を依頼する石材店が指定されている場合と、自由に選べる場合があるため確認してみましょう。
業者を探して手配する際は見積もりを取って依頼先を決定し、撤去作業の日時を決めます。お墓の場所によっては、撤去に使用する重機の運び込みが困難で手作業で撤去する場合は費用が高めになる可能性があるでしょう。
2人のための夫婦墓を準備しよう

永代供養つきの夫婦墓は子どもがいない場合や、子どもへの負担をなくしたいと考えている方にとっては良い点が多く、自分たちの死後に関する心配事も減らせるでしょう。
しかし、よく把握した上で申し込まなければ、後に家族や親族に迷惑がかかるおそれもあります。
永代供養つき夫婦墓の場合も、死後の手続きを託す人は必要です。記事内で紹介した夫婦墓の種類や費用相場、契約後の流れに関する理解を深め、円滑に準備を進めていきましょう。
お電話でも受け付けております















