
【種類別】永代供養墓の利点と注意点とは?選ぶポイントもあわせて紹介

「よく聞くけど永代供養とはなんですか?」
「永代供養墓ってたくさん種類があるけどどれを選べばいいの?」
「どれくらい費用がかかるの?」
お墓を探している方や終活している方の中には、このような疑問や悩みを持つ場合も少なくありません。
本記事では、永代供養墓の種類や自分に合った永代供養墓を選ぶためのポイント、注意点を紹介しています。
この記事を読むことで、永代供養の仕組みや永代供養方法の種類ごとの特徴、永代供養墓を選ぶ際に気を付けたいことを把握できます。その知識をもとに、自分の希望に合った永代供養墓を選択できるようになるでしょう。
永代供養墓を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
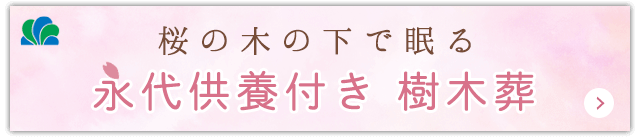
永代供養ってなに?

終活について色々調べていくうちに、永代供養という言葉を耳にする機会が多くなるでしょう。
永代供養とは故人を供養する方法の1つですが、お墓の継承者がいない方が増えている現代において注目が高まっています。
以下では、永代供養の意味や特徴について解説していきます。
永代の意味
永代とは長い年月を意味し、永世と同様の意味を持っています。また、永久という意味で用いられることもある言葉です。
永代供養は長い年月供養してくれるということに間違いはありませんが、未来永劫に渡って個別納骨されるものではありません。
永代供養は、一定期間を過ぎると合祀されて共通の永代供養墓に埋葬されることがほとんどです。
お墓の管理や維持の負担を減らせる
永代供養は寺院や霊園が管理してくれるため、子孫がお墓を継承する必要がありません。
近年は、子供や孫にお墓の継承について負担をかけたくないという思いから、永代供養を選ぶ方も多くなっています。
また、一般的なお墓と比較すると、永代供養は少ない費用で維持できるタイプもある点がメリットといえるでしょう。
家族に代わって霊園や寺院が供養を行う
縁故者がいなくなり、誰にも供養されず放置されたお墓はいずれ無縁墓になってしまいます。先祖や自分たちのお墓が荒れた無縁墓になってしまうのは避けたいものです。
永代供養は、家族や親族に代わって寺院・霊園が供養してくれるため、継承者がいなくても無縁墓になる心配がありません。
お墓の継承が難しい方や、子どもや孫に負担をかけたくないと考える方は、永代供養を検討してみましょう。
・永代供養についてわかりやすく紹介!費用や選び方なども詳しく説明
永代供養墓の寺院と霊園の種類

永代供養墓を探していると、寺院か霊園で迷う方も多くいます。
永代供養を申し込みしてから後悔することのないように、寺院と霊園の永代供養では、どのような違いがあるのか事前に確認しておきましょう。
以下では、寺院・霊園それぞれの永代供養墓の特徴についてお話しをしていきます。
寺院の場合
一般的なお墓を建てる場合と異なり、永代供養は宗派を問わない供養方法とされています。寺院の永代供養も、宗旨・宗派を問わないところがほとんどです。
一方で、永代供養墓の申し込み条件が檀家になることという寺院も少なからずあるため、きちんと確認しておきましょう。
寺院の場合は、お墓や仏事に精通する僧侶に相談できるのがメリットです。また、僧侶直々に供養してもらえる点も寺院の永代供養の特徴といえます。
霊園の場合
霊園は、公営霊園と民間霊園の2種類があります。
公営霊園は、都道府県や市町村が運営・管理している霊園のことです。宗教に関係なく利用できますが、申し込み条件があることも多く、応募者多数の場合は抽選になるため必ずお墓に入れるとは限りません。
後者の民間霊園は、民間企業や財団法人などが運営しています。施設面が充実していたり、送迎バスなど独自のサービスに力を入れていたりするところが多いのが特徴です。
・永代供養の相談はどこにする?押さえておくポイントや改葬に必要な手続きも解説
永代供養墓の安置場所の種類

永代供養墓は、たくさんの種類や形式があります。ここでは、永代供養墓の安置場所の種類について説明していきます。
屋内型と屋外型、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在しているため、しっかりと認識することが大切です。
屋内の場合
都市部を中心に増えている屋内型は、建物の中にお骨を安置するお墓のことです。
駅から徒歩で行ける立地にあることも多く、車を持っていない方や足の悪い方にも優しいお墓といえるでしょう。また、天気を気にせずお参りできるのも屋内型の特徴です。
しかし、屋内型は限られたスペースの中に遺骨を安置しているため、お盆やお彼岸といったお墓参りシーズンになると人が集中して混雑する恐れがあります。
屋外の場合
屋外型の永代供養墓は、広い敷地であることが多く落ち着いてお参りできます。一般的なお墓に近い墓石を用いたタイプもあるため、従来のお墓にこだわる方にも受け入れやすい点がメリットといえるでしょう。
屋外型の場合、山の近くや郊外にあることも多く、交通アクセスが悪い可能性があります。また天気の影響を受けやすく、雨や雪の時は傘が必要になったり、濡れてしまったりという点がデメリットです。
・永代供養墓はどんなお墓かわかりやすく解説!何年供養してくれる?選び方のポイントは?
永代供養墓の安置方法の4つの種類

永代供養墓には、遺骨を合同で埋葬する方法と個別で埋葬する方法があります。
ここでは、4つの種類の安置方法について紹介します。
それぞれの種類別に、特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していきましょう
1:合祀型タイプ
合祀型タイプは、1つのスペースに他の人の遺骨と一緒に埋葬する方法です。永代供養墓の中でも費用が安く、お墓にかかる費用をなるべく抑えたいという方からニーズが高まっています。
しかし、合祀型タイプに埋葬されてしまうと、他の人の遺骨と一緒になっているため、特定の遺骨だけ取り出すことはできません。
このことが原因で、家族や親族とトラブルになってしまうことも少なからずあるため、事前にしっかりと話し合いをするようにしましょう。
2:集合安置型タイプ
遺骨を納めた骨壺を1つの場所にまとめて安置する方法です。
すぐに合葬する合祀型タイプと違い、集合安置型タイプは一定期間個別に骨壺を安置してもらえます。契約期間内であれば改葬や分骨に対応してくれるところもあるため、気になる方は確認しておきましょう。
また、合祀型タイプより費用は割高になりますが、後で紹介する個別安置型タイプに比べると費用を安く抑えられます。
3:個別安置型タイプ
個別安置型タイプは遺骨を個別に埋葬するため、故人をより身近に感じられます。
施設によって、故人専用の場所に安置したり、個別の参拝スペースでお参りできたりなど種類も様々です。そして一定期間が過ぎた後は、合祀型の永代供養墓に埋葬されるのが一般的とされています。
デメリットは、合祀型タイプや集合安置型タイプに比べると遺骨を個別に管理するため、維持や管理に手間がかかる分費用が割高になる点です。
4:墓石安置型タイプ
一般的な個別墓と同じようにお墓を建て遺骨を埋葬するのが、墓石安置型タイプです。
墓石代やスペース代がかかる分費用が割高になってしまうことは否めませんが、通常のお墓と同じように個別にお参りして供養できるのがメリットです。
しかし、契約内容によっては一定期間経ってから共同墓所に合祀されることもあります。また、墓石を撤去する際に撤去料金を支払うケースもあるため、契約内容はしっかりと確認しましょう。
・継承者のいない永代供養でも個別に安置できる?
永代供養墓に関連するお墓の5つの違い

永代供養について調べていると、その他の供養方法とはどのように違うのか疑問に思う方もいるでしょう。
以下では、永代供養墓に関連するお墓の5つの違いについて解説していきます。
1:一般のお墓との違い
一般のお墓と永代供養墓の大きな違いですが、一般のお墓は家族や親族が管理・継承するのに対して、永代供養墓は寺院や霊園が遺骨を管理・供養してくれることでしょう。
永代供養をすると、寺院や霊園が永代に渡って管理・供養してくれるため、子孫がお墓を継承する必要はありません。
2:納骨堂との違い
永代供養と納骨堂の違いですが、そもそも意味合いが異なります。
納骨堂とは、お墓の形式の1つで屋内に遺骨を安置することです。一方永代供養の意味は、お墓の管理形態のことで、寺院や霊園が遺族に代わって遺骨を管理・供養することを指しています。
納骨堂の中には永代供養サービスをしているところも多いため、納骨堂と永代供養墓を混同して考える方も少なくありません。
3:永代供養の位牌
位牌とは、故人の戒名や没年月日などを記した木の札のことです。故人を想って供養している時に、故人の魂が戻ってくる依代とされています。
永代供養にする場合、位牌はどうすればいいのか悩んでしまう方もいるでしょう。位牌の取り扱い方ですが、遺骨と一緒に永代供養をしたり、寺院に一時的に預けたりという方法もあります。
永代供養先の寺院や霊園に相談してみるのもいいでしょう。
4:永代使用との違い
永代供養と似た言葉に永代使用があります。一見同じことを指しているようですが、実は全く意味が違う言葉です。
永代使用とは、お墓の土地を永代に渡って使用する権利のことで、お墓を建てる時に土地の使用料として永代使用料を支払います。
お墓の継承者がいる間は永代使用権を代々受け継いでいけますが、継承者がいなくなった場合は永代使用権を返還しなくてはなりません。
5:お布施の必要性
お布施とは、葬儀や法要の際に読経してくれた僧侶への謝礼として金品を渡すことです。
永代供養であっても、納骨や法要の際に僧侶を読んで読経してもらう場合はお布施が必要になります。
しかし、寺院や霊園によっては永代供養料にお布施代が含まれていることがあるため、事前に確認してください。
【種類別】永代供養墓の9つの利点と注意点

自分に合った永代供養墓を選ぶためには、お墓の形や遺骨の安置方法など、それぞれの永代供養墓の特徴を理解しておくことが重要です。
ここでは、9種類の永代供養墓の利点と注意点を紹介していきます。
1:永代供養墓タイプ
一般的なお墓に永代供養が加わったタイプで、継承者がいなくなった場合でもお寺や霊園が供養・管理してくれます。個別に管理・供養し、墓石代やスペース代もかかるため、永代供養の中では費用が高いのが特徴です。
契約期間中は個人の墓で供養を行い、契約期間が過ぎたら合祀して共同のお墓に埋葬されます。一般的に弔い上げとなる三十三回忌を目途とする場合が多いでしょう。
2:屋内の霊廟タイプ
霊廟は「れいびょう」と読み、亡くなった方の霊を祀る建造物のことを指しています。
霊廟タイプは、故人ごとにスペースが設けられ仏壇を安置する場合が多いです。上下2段に分かれていて、主に上の段に仏壇を設置し、下の段に骨壺を納めるのが一般的とされています。
ただし、あらかじめ埋葬できる遺骨が限られているプランが多く、追加で遺骨を埋葬するにはスペースを新たに契約しなければならないケースもあり注意が必要です。
3:屋内のロッカータイプ
コインロッカーのように前面に扉が付いた同じ大きさの壇がズラリと並んでいて、その中に骨壺を納めるタイプのお墓です。
ロッカーと聞くと質素なものを想像しがちですが、最近は扉に装飾が施されてきらびやかなものや、シックで高級感があるものなどデザインや種類が豊富なタイプが増えています。
注意点としては、多くの場合でいずれ合祀になることや納骨できる数に制限があることが挙げられるでしょう。
4:屋内の合祀タイプ
不特定多数の遺骨と一緒に共通のお墓に埋葬されるのが合祀タイプです。お墓の継承者がいなくても永代に渡って供養・管理が約束されているため、身寄りがない方でも安心です。
また、メリットとしては他の埋葬方法と比較すると費用が安い点が挙げられます。屋内のため天候を気にせずお参りできるのもポイントです。
しかし、他人の遺骨と混ざってしまい後から特定の遺骨だけ取り出すことはできないため事前によく考えましょう。
5:屋外の合祀タイプ
屋外の合祀タイプは、納骨スペースの上に仏像や石碑などのモニュメントが建てられている慰霊碑型や、墓石の代わりに樹木を墓標としている樹木葬などがあります。いずれも自然豊かな広い敷地にあることが多く、ゆったりと参拝できるのがメリットです。
屋内の合祀タイプと同じように、1度合祀すると他人の遺骨と区別がつかなくなるため後から遺骨を取り出せません。親族間できちんと話し合っておくといいでしょう。
6:個別安置タイプ
遺骨を個別に埋葬する個別安置タイプは、故人専用のスペースに遺骨を安置する方法です。小さなお墓タイプや個別に区切られたスペースに遺骨を安置したりと、施設によって様々な種類があったりします。
合祀タイプと異なり、個人でお供えや参拝ができるのがメリットといえるでしょう。
しかし、三十三回忌など一定期間を過ぎると合祀される場合が多いため、契約内容をきちんと確認する必要があります。
7:集合安置タイプ
集合安置タイプは、遺骨を納骨した骨壺をひとつのスペースに安置する方法です。個別のお墓ではありませんが、骨壺をそのまま安置するため他の人の遺骨と混ざることはありません。また、個別安置タイプより費用が安く抑えられる点もメリットといえます。
しかし、期限が決められていて、期限が切れた後は合祀されることも多いです。契約内容によっては、合祀される前であれば遺骨の改葬や分骨に対応してくれる場合もあるため、確認してみましょう。
8:屋外の納骨塔タイプ
屋外の納骨塔タイプとは、地下あるいは半地下に遺骨を安置する納骨室を設け、地上に霊碑や仏像などを建立して供養する合祀墓を指しています。永代供養の中では、比較的費用を抑えながら利用できるお墓です。
施設によって、毎月合同供養法要を行ったり、石碑などに故人の名前を彫刻ができたりなどの特徴が異なります。気になる点はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
9:屋外の納骨壇タイプ
納骨檀とは遺骨を埋葬するお墓の1種で、屋外用は主に総石造りの建造物であることが多く、大きなものから小さなものまで、寺院や霊園によって様々です。
一定期間を過ぎた後は合祀される場合が多いですが、期間中は自分たちのお墓のようにお参りできます。1人で1つのお墓に入る個人墓の他に夫婦墓や家族墓があり、一般的なお墓にはこだわらないが自分たちのお墓は持ちたいという方にもおすすめです。
永代供養に関連する5つの墓じまいについて

近年は、先祖代々受け継いできたお墓を整理して墓じまいをする方が増えてきました。
それに伴い、墓じまいをした後の改葬先として永代供養墓の需要も高まっています。
以下では、墓じまいや改葬の手順・方法について解説していきます。
1:改葬や墓じまいが増えている
墓じまいとは、現在のお墓を解体・撤去して更地に戻し、遺骨を取り出してから新しい場所に移すことです。墓じまいの他に、改葬ともいわれています。
現代日本では少子高齢化や核家族化の影響もあり、お墓が管理できないなどの理由から墓じまいをする方が増えています。
しかし、墓じまいは行政手続きが必要となり、役所から許可が下りないと実施できませんので注意してください。
2:解体や撤去をする墓じまい
墓じまいをする許可が下りたら、お墓の解体・撤去が可能になります。
民営霊園や寺院では、お墓の解体業者が指定されていることも多いため、墓地管理者に相談してみましょう。もし業者が指定されていない場合は、自分で石材店を探して依頼します。
また、工事の前に僧侶を呼んで閉眼供養をしましょう。閉眼供養とは故人の魂を墓石から抜くという意味があり、お墓の解体・撤去の前に行うのが一般的です。
3:別のお墓に移す改葬
後ほど詳しく説明しますが、遺骨を別のお墓に移すには役所から発行される改葬許可証が必要です。改葬先の規定に則り、遺骨を埋葬しましょう。
そして、仏教では新しくお墓や位牌を購入した際に、開眼供養という法要をすることがあります。
故人の魂を招くために行う開眼供養ですが、位牌を持たない永代供養の場合は必要ないとされています。永代供養でも位牌を用意する場合は、開眼供養が必要になるため、改葬先に相談してください。
4:改葬や墓じまいをする方法
墓じまいや改葬するためには、行政手続きが必要です。まず現在のお墓がある自治体の役所等から改葬許可申請書を入手しましょう。
そして、現在の墓地管理者の埋葬証明が必要になります。通常は改葬許可申請書の所定欄に記入してもらいますが、墓地管理者が定める様式でも構いません。また、改葬先の墓地使用許可書等が必要になることもあります。
必要書類が揃ったら役所の窓口や郵送で申請し、改葬許可証を発行してもらいます。
5:永代供養墓にする方法
お墓の継承者がいないというのは、墓じまいをする理由のひとつです。このことから、改葬先では永代供養を選択する方も増えています。永代供養墓にすることにより、お墓の継承者が不在で無縁仏になってしまうリスクがなくなるため安心です。
永代供養墓にしたいと考えるならば、まず親族やお寺に相談し、予算も含めて納得できる永代供養を選びましょう。
・墓じまいをして永代供養にする手順は?それぞれの違いや費用についても解説!
地域や宗派に関連する永代供養墓

地域や宗派によって、お墓や供養方法は異なります。
沖縄のお墓は本州とは違い、初めて見た方はそのスケールに圧倒されることも少なくありません。また、浄土真宗や浄土宗は他の仏教の宗派と供養に対する考えが違うとされています。
それでは、沖縄のお墓と浄土真宗・浄土宗の供養方法について解説していきましょう。
沖縄のお墓の様式
全国の一般的なお墓に比べると、沖縄のお墓は小さな家のような形で非常に大きいです。
かつて沖縄では、遺体の周りを石で囲って風化させるという風葬文化がありました。遺体を安置し、骨になるのを待ってから遺骨を納骨します。ある程度広い空間が必要だったことから、大きなお墓になったとされています。
沖縄では個人墓が主流ですが、経年劣化したお墓の修繕やお墓の継承者問題から永代供養を考える方も増えています。
浄土真宗や浄土宗の様式
2つの宗派の大きな違いは、浄土宗は念仏を唱える行為そのものが大切という教えに対し、浄土真宗は念仏を唱えようとする気持ちが大切という考え方です。
また、両者とも念仏を唱えることによって極楽浄土に導かれるとされているため、亡くなった方の成仏を願う追善供養をする必要がありません。
この点から永代供養という考え方は存在しませんが、浄土真宗や浄土宗の寺院でも永代供養のように遺族に代わって遺骨を管理してくれます。
永代供養墓の種類を選ぶ6つのポイント

永代供養墓はたくさんの種類があるため、どれを選べばいいか悩む方も多くいます。
自分に合った永代供養墓を選ぶには、埋葬方法やお墓の形以外にも大事なことがあり、事前に確認していれば安心です。
そこで、永代供養墓の種類を選ぶ際に押さえておきたい重要なポイントを6つ紹介します。
1:家族や親族の同意を得る
最初にするべきことは、家族・親族と話し合い同意を得ることです。
家族・親族であってもそれぞれの価値観は異なるため、自分の意見だけで勝手に話を進めてしまうのはトラブルの原因になります。
いずれ遺骨が合祀される方法が一般的な永代供養墓は、受け入れられない方がいてもおかしくありません。
資料請求や施設見学も、家族・親族と話し合い同意を得てから行った方が無難といえるでしょう。
2:申し込み時に維持や費用を確認する
永代供養墓の維持費や費用の内訳を細かく確認しましょう。
永代供養墓の総費用のうちになにが含まれているのか、別料金になるのはなにかを明確にしておかないと、その後想定外の出費を強いられる可能性があります。
また、永代供養墓は1人用にするのか、家族も入れるようにするかも考えておきましょう。1人用の永代供養墓の場合、追加で遺骨を安置することになればまた永代供養墓を購入することになり費用がかさむため注意が必要です。
3:自宅からの距離や場所で選ぶ
永代供養墓は、交通アクセスや立地も考慮して選びましょう。
自宅から行きやすい場所でないと、お参りに行くのも大変です。主な親族の自宅からも行きやすい場所だと、なおいいでしょう。
自宅から永代供養墓まで、公共機関を利用した際の所要時間や乗り換え回数も大事なポイントになります。
また、お盆やお彼岸の時期は混雑する恐れがあります。車を利用する場合は最短ルートや渋滞状況をあらかじめチェックしておくと便利です。
4:納骨場所の広さも確認する
永代供養墓は大きく分けると、初めから合祀するタイプと一定期間個別に安置されてから合祀するタイプがあります。
後者の場合、施設や契約内容によって、夫婦や家族といった単位で納骨することも可能です。納骨するスペースには限りがあるため、何体の遺骨を埋葬できるか、事前に確認しておきましょう。
5:造りや付帯設備の状況も確認する
ひとくちに永代供養墓といっても、造りや規模も多種多様です。上手に永代供養墓を選ぶために、施設の内部や付帯設備をしっかりと確認しましょう。
ここでいう付帯設備とは、本堂や礼拝堂といった法要施設や休憩室のことを指しています。法要施設に関してはほとんどの寺院では備えていますが、霊園ではないこともあります。
また、バリアフリー化している施設だと体の不自由な方でも安心してお参りできます。
6:法要の回数や納骨の期間も確認する
ほとんどの施設は春秋のお彼岸とお盆に法要をしていますが、中には年に1回しか法要をしないところもあるため注意が必要です。その他に、毎月もしくは毎日法要をしているところもあります。
また、納骨期間は初めから合祀の場合や、三十三回忌などの一定期間を目途に合祀する場合が一般的です。中には、合祀するまでの年数を自分で選べることもあるため問い合わせてみてください。
・永代供養の選び方とは?場所や費用などのポイントや注意点も紹介
永代供養の種類を理解して選ぶ参考にしよう

永代供養墓は、お墓の形や種類、遺骨の安置方法など様々な種類があり、それぞれ費用も異なっています。
永代供養墓を選ぶ際は、自分たちの希望をあらかじめ書き出して絞り込んでおいてから寺院や霊園を探すといいでしょう。
ぜひこの記事を参考に、自分に合った永代供養墓を見つけてください。
お電話でも受け付けております















