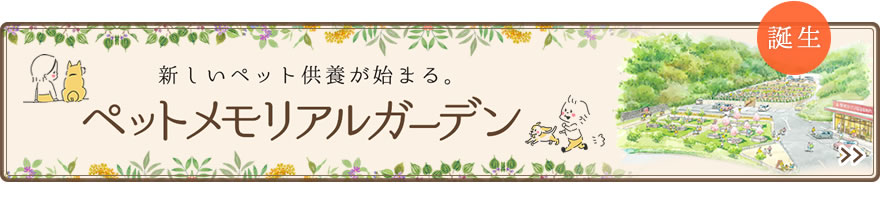認知症と診断されたが遺言を残したい!有効にする5つのポイントを解説|永代供養ナビ
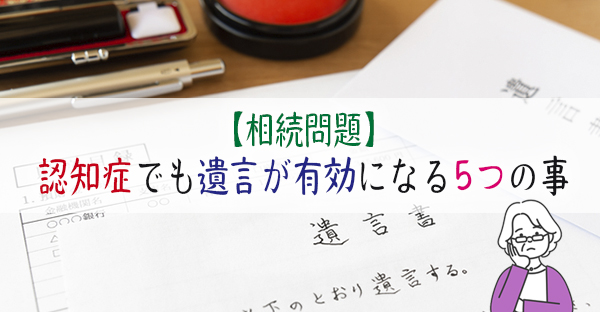
「認知症と診断されたけど、遺言書を書いても無効になる?」との質問は多いです。
自分が認知症と診断されて初めて、遺言書の作成を検討したり、相続対策を始める人は、身近にもありますよね。
結論から言うと、認知症になっても、すべての遺言が無効になるとも限りません。
・認知症の軽度/重度
などにより、その遺言が無効にならないケースがあるのも確かです。
今回は認知症と診断された後、遺言を残したい場合に、どのようなポイントを押さえれば、有効になるのかを解説します。

「遺言能力」とは?
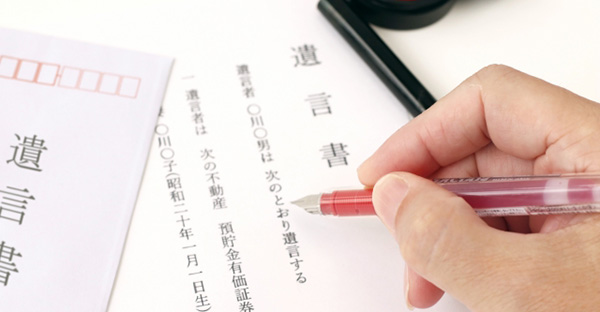
満15歳以上の方が遺言書を作成する前提条件のもと、下記のような事柄が、認知症診断後の遺言能力あるなしの判断材料となるでしょう。
・遺言の内容を把握し理解している
認知症と診断されても、本人に遺言を残す意識や遺言内容への理解があれば他者の指導や介入の心配がありません。
ただ判断能力が低下している状態だと、遺言自体が他者の介入や指導により作成された疑いが出てきます。
そのためこのような状態では遺言能力は認められず、相続も無効です。
認知症患者が遺言を有効にするケースがある
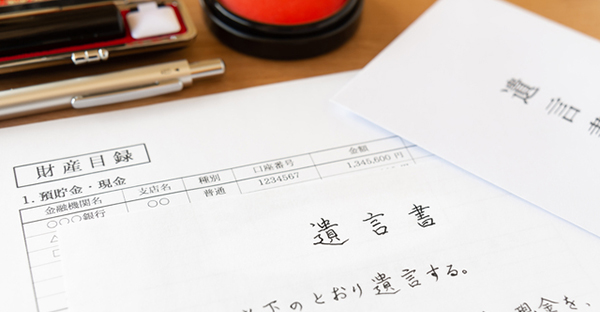
認知症の診断下で書いた遺言の効力を判断するにあたり、軽度と重度があることを解説しました。
けれども実際に認知症患者が書いた遺言を有効にできる事例はどれくらいかと言えば、ハッキリ言ってしまうと、「認知症患者の遺言能力は判断が難しい」点は否めません。
●例えば、認知症の診断後に遺言書を作成した場合、裁判に倣うとされますが、そこで裁判官は、総合的な判断材料として下記のような書類を元にします。
・医師からの診断書
・カルテなどの医学資料
・遺言者の行動を観察
認知症の他にも遺言の効力を判断する際、アルツハイマーも無効になる可能性がありますが、
「遺言を公正証書遺言(※)にしたことで、有効にできた」との体験談も過去にはありました。
一方でこの体験談はあくまで一例でしかなく、「公正証書遺言にしたのに、無効にされてしまった!」と言う人もいます。
・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!
遺言能力を判断するポイント

では認知症と診断されても、遺言を有効にする2つのポイントをご紹介します。
認知症と診断を受けてしまうと、確実にその遺言が有効になる保証はありませんが、基本として、症状が進む前に認知症を受けたら少しでも早く遺言を完成させることです。
(1)シンプルな遺言内容
(2)公正証書遺言
(3)当時の進行具合を証明する記録
(4)長谷川式スケール
(5)相続人が納得している
もちろん、認知症と診断される前に遺言を完成させるに越したことはありません。
認知症の診断後に書いた遺言の効力が争点になると言うことは、相続人のいずれかが遺言能力に疑問を持ち、遺留分の主張をしたことになります。
(1)シンプルな遺言内容
認知症になってからの遺言書において、①本人に遺言の意思があったこと、②遺言能力が充分にあったことを判断する時、本人が遺言内容を理解できるかどうかも基準のひとつです。
そこで「複雑な内容ほど、認知症患者にとって遺言内容を理解しにくい」との考え方から、遺言は複雑なものよりも、シンプルで簡潔明瞭なものの方が認められやすい傾向にあります。
(2)公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場で遺言者本人への聴取のもと、公証人が作成する遺言書です。
さらに公正証書遺言を作成する際には、保証人2人が立ち会います。
保証人2人が見守るなかで、認知症になった遺言者本人が、公証人と話して遺言書を作成するため、遺言書を作成するにあたり、下記の状況が証明されるでしょう。
・遺言内容を理解していた
・遺言を残す意思があった
※遺言書の種類は、この他自筆証書遺言などがあります、詳しくは下記をご参照ください。
・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!
(3)当時の進行具合を証明する記録
認知症の診断後に遺言を残す場合、認知症の症状が軽症であり、充分に遺言能力があることを証明しなければなりません。
けれども日々、認知症の症状は繊細に変化するため、確実な証拠を提示することは、到底難しいでしょう。
・日々の介護記録
・看護記録
そこで役立つ書類が、上記のような具体的な症状や状況を記した書類です。
・金銭管理ができていた様子
以上のような事柄が客観的に判断できる内容が記載された各種書類があるならば、まずは弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
(4)長谷川式スケール
「長谷川スケール」とは、認知症がどれほどの症状に値するのかを計る検査です。
30点満点のなか「20点以下」と診断されてしまうと、認知症とされる人が多いでしょう。
・20点~30点…認知症の疑いがあるレベル
(※)30点満点
この場合、前項でお伝えした公正証書遺言で残した場合には、長谷川式スケールでの診断結果が20点以下であっても地裁において有効と審判されるケースはあるのですが、10以下と診断されてしまうと、遺言能力が認められない可能性が高いです。
(5)相続人が納得している
最後に
ここまで認知症と診断された後、遺言を残したい人に役立つ、遺言書を無効にしないポイントをいくつかお伝えしました。
最後の「相続人全員が納得している」項目において、「正当な遺産分割内容だけど、○○(相続人の一人)が納得してくれるか心配」と言う人もいますよね。
このような場合には、遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」にひと言添えたり、しっかりと説得したい時には、エンディングノートなどを利用して、理由を説明するのも一案です。
・エンディングノートの書き方まとめ☆欠かせない7つの項目と残された家族に役立つポイント
まとめ
認知症の後、遺言が無効にならない5つのポイント
・シンプルな遺言内容
・公正証書遺言
・当時の進行具合を証明する記録
・長谷川式スケール
・相続人が納得している
お電話でも受け付けております