
【大阪の葬儀】御香典を送る時に添えるお悔みの手紙の文例。現金書留で送る5つのマナー
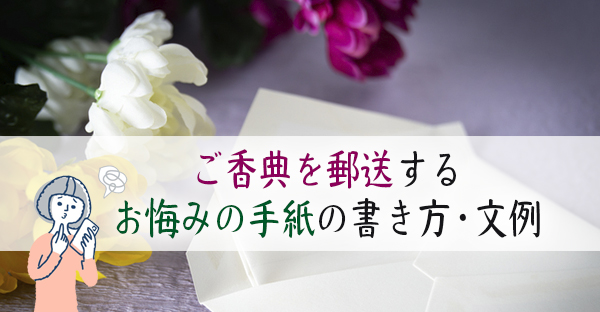
大阪で葬儀に参列できない時、御香典を送ることがあります。
御香典を送る時、お悔みの手紙を添えますが、文例があると助かりますよね。
御香典を送る時ばかりではなく、お悔みの手紙にはタブーがある他、ご遺族への配慮もあり、不安なことも多いです。
また「御香典を郵送することは失礼だろうか?」との質問もありますが、失礼にはなりません。
今回は、大阪の葬儀に参列できない時の御香典の送り方、お悔みの手紙の文例をお伝えします。

御香典を郵送する

御香典に添えるお悔みの手紙も気になるところですが、まず御香典は現金ですので、現金書留で送らねばなりません。
●御香典を送る時には、不祝儀袋に整えた状態で、現金書留の封筒に入れて送ります。
→普通郵便では現金を送ることができないので、注意しましょう。
現金書留の封筒は一般的なサイズと大きめサイズがあります。
不祝儀袋が入るよう、大きいサイズを選んでください。
基本的に現金書留封筒は大きいサイズがありますが、一般的なサイズを超えた不祝儀袋だと入らない可能性があるためです。
●現金書留封筒には、「住所・名前」を書き、不祝儀袋にも「住所・名前」を記入して封筒の宛名は葬儀の喪主宛に送りましょう。
御香典を郵送するタイミング
大阪で葬儀に参列できずに御香典を郵送する場合、葬儀を執り行う日付けによりタイミングも変わります。
①通夜まで日がある
②通夜がすぐ行われる
③通夜や葬儀を終えてから
現代は斎場の安置施設も進化し、ご臨終から七日後の葬儀や告別式も増えました。
葬儀や告別式に間に合うようであれば、葬儀に合わせて郵送します。
①通夜まで日がある
通夜まで日がある場合、特に訃報を知ってから七日後などに執り行われる葬儀や告別式であれば、御香典を郵送しても間に合う可能性は高いです。
この場合は、供花や弔電同様、直接斎場宛に現金書留封筒で御香典を送ることもできるでしょう。
②通夜がすぐ行われる
通夜がすぐ行われる場合、現金書留で御香典を郵送しても間に合わないことが多いです。
訃報の知らせを受けてすぐに投函しても、通常は1~2日で現地に到着します。
従来通りの葬儀では、亡くなった当日~翌日の夕方以降から通夜が行われ、その翌日には葬儀と告別式です。
③通夜や葬儀を終えてから
しかし葬儀後すぐに現金書留封筒を送るのではなく、忙しい時期を超えてから郵送する配慮をする人も多く見受けます。
また喪主は香典をいただいた方にお返しをする「香典返し」を行うので、現金書留封筒の到着が遅れてしまうと、喪主に手間をかけさせてしまうことになります。
そのため、あまり時間を空けなくても、空けなすぎても良くないので注意しましょう。
御香典を郵送する時の金額相場

御香典の金額相場は、故人との関係性で変わってきますが、葬儀に参列する時に準備する御香典相場と変わりはありません。
・知り合い:3000〜5000円
・友人:5000〜10000円
・職場関係者: 5000〜10000円
・親戚:10000〜30000円
①新札をひと折りするのが一般的
御香典を整える時の紙幣は、折り曲がっているものを使用します。
新札をひと折りする方法が一般的でしょう。
新札は「不幸を予測していた」として使ったお札を使いますが、かと言って下記のようなお札は失礼にあたります。
・破れている紙幣
②お札の入れ方
弔事で扱う御香典のお札は、下記のように入れてください。
・お顔は封の底
御香典はお悔やみです。
お札を裏側にするのは「顔を伏せる」という意味が込められています。
御香典にはお悔みの手紙を添えるべき?
御香典を郵送する場合、お悔みの手紙は添えると良いでしょう。
またお通夜や葬儀に参列する時、御香典を包む際に手紙を添えても大丈夫です。
ただし、必ず御香典にお悔みの手紙を添えなくてはならない訳ではありません。
この時、使用する便箋は、白色の縦書き無地を選んでください。
お悔みの手紙、5つのマナー
また御香典を送る時に添えるお悔みの手紙には、マナーがあります。
お悔みの手紙の内容はもちろんですが、形式まで配慮して準備を進めてください。
(1)手紙の色や形式に配慮する
(2)死因についての言及は避ける
(3)故人へ向けた敬称は喪主の視点で
(4)忌み言葉に注意する
(5)時候の挨拶は用いない
「心があれば」と言う人もいますが、失礼のないよう、予め御香典に添えるお悔みの手紙の形式を調べて整えることも、弔意の表し方のひとつです。
(1)手紙の色や形式に配慮する

お通夜や葬儀で服装マナーがあるように、御香典に添えるお悔みの手紙でも、白い便箋を利用するなど、一定のマナーがあります。
①お悔みの手紙は便せん1枚に納める
②便箋は白、縦書きを選ぶ
③ペンや万年筆で執筆する
④封筒は一重を選ぶ
⑤厚手の封筒を選ぶ
以上、5つの形式に配慮して便箋や筆記用具を選んでください。
それでは、下記よりそれぞれ詳しく解説します。
①お悔みの手紙は便せん1枚に納める
故人が亡くなってから四十九日法要まで、ご遺族は法要の準備や御位牌の仕立て、納骨式や四十九日法要の手配など、準備で忙しくなります。
悲しい気持ちを共有したい想いは同じですが、負担の少ないよう、御香典に添えるお悔みの手紙は便せん1枚ほどで、端的にまとめてください。
②便箋は白、縦書きを選ぶ
四十九日法要まではお供え物や供え花も「白」です。
御香典に添えるお悔みの手紙もまた、白で揃えて縦書きを選びます。
③ペンや万年筆で執筆する
御香典に添えるお悔みの手紙など、畏まった場面や正式なものにおいて、カジュアルなボールペンは失礼とされてきました。
万年筆など、フォーマルなペンを利用しましょう。
④封筒は一重を選ぶ
封筒の中にもう一つ封筒が入っている「二重封筒」もありますよね。
丁寧にも見えますが、御香典に添えるお悔みの手紙で利用する場合、二重封筒は「不幸が重なる」として避けられます。
⑤厚手の封筒を選ぶ
二重封筒は避けられるため、一重の封筒を選びますが、かと言って、中身が透けて見えるような薄い紙質の封筒は避けましょう。
厚手の封筒でなかの手紙が見えないようなものを選びます。
(2)死因についての言及は避ける

突然の訃報に触れ葬儀に参列できない状態だと、故人の死因が気になることは分かりますが、御香典を送るお悔みの手紙で言及するのは避けてください。
御香典に添えるお悔みの手紙は、あくまでもご遺族を労わり、その心痛に寄り添うものです。
(3)故人へ向けた敬称は喪主の視点で

御香典に添えるお悔みの手紙は、故人に向けた手紙ではありません。
ご遺族、取り分け喪主に向けたお悔みになりますので、故人に付ける敬称も、喪主から見た関係性で書きます。
①妻…奥様、御令室様(ご令室様)など
②夫…ご主人様、旦那様など
③父親…御尊父様(ご尊父様)、お父様など
④母親…母上様、お母様など
⑤娘…御令嬢様(ご令嬢様)、御子女様(ご子女様)など
⑥息子…御令息様(ご令息様)、御子息様(ご子息様)など
故人との関係性が幼馴染みや親友であったとしても、御香典に添えるお悔みの手紙は喪主へ向けて敬意ある文例で送り、故人との関係性が分かるようにします。
(4)忌み言葉に注意する

御香典に添えるお悔みの手紙で最も注意をしたい事柄は忌み言葉です。
どのよな言葉を使ったとしても、ご遺族の気持ちは推し量れませんが、特に忌み言葉は失礼にあたることが多いため、細心の注意を払うと良いでしょう。
①重ね言葉
②直接的な言葉
③不吉な言葉
以上3点が主な忌み言葉です。
重ね言葉には、不幸の連続をイメージする言葉も含まれます。
①重ね言葉
同じ言葉を重ねることを「重ね言葉」と言います。
この他にも不幸の連続をイメージさせる言葉も避けてください。
【不幸の連続をイメージさせる言葉】追って、次に、再び、続く、引き続き、など。
②直接的な言葉
「死亡」など、直接的な言葉はご遺族の傷に突き刺さることもあるでしょう。
また生についての表現も「生存中」など、直接的な文言は控えます。
・死亡…ご逝去、ご他界、など。
・生存中、生きていた頃…ご生前、お元気でいらしたころ、など。
③不吉な言葉
御香典を包む時には「四(死)」や「九(苦)」を避けますよね。
これは四や九が不吉な言葉とされるためですが、他にも不吉として忌まれる言葉があります。
(5)時候の挨拶は用いない

一般的な丁寧なご挨拶ハガキでは、季節を感じる時候の文言が入りますよね。
けれども御香典に添えるお悔みの手紙に時候の文言は入りません。
お悔みの一般的な文章構成は下記です。
①主文
②末文
③後付け
最初に時候の文言は入れず、冒頭からお悔みの言葉が入ります。
末文は結びの言葉ですので、端的に入れましょう。
①主文
主文では主に下記5点の内容を入れます。
・訃報に触れたことへの驚き
・ご遺族への慰めの言葉
・弔問できないことへのお詫び
・御香典を同封したご報告
御香典に添えるお悔みの手紙は、ハガキ一枚ほど、便箋で一枚ほどで納めるものなので、お悔みの言葉であれば「お悔み申し上げます」など、端的な言葉で問題はありません。
②末文
末文は結びの言葉です。
・ご家族様皆さまには、どうかお力落とされまんよう、ご自愛ください。
・謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
など、端的に伝えてください。
③後付け
後付けは書いた日付けや氏名などですが、下記の順番で記載してください。
・差出人の氏名
・宛名…喪主のお名前に様を付ける
御香典に添えるお悔みの手紙の文例

それでは、以上を踏まえて御香典に添えるお悔みの手紙の文例は、下記のようなものがあります。
「○○様ご逝去の報に接し、突然のことで驚いております。
心よりお悔やみ申し上げます。
昔から、人一倍明るい人柄だっただけに、皆様ご家族の悲しみは計り知れない思いかと思います。
本来であれば、葬儀に参列すべきところですが、遠方にてかなわず、大変申し訳ございません。
御心ばかりではありますが、御香典を同封致しますので、御霊前にお供えくださるようお願い申し上げます。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。」
最後に
今ではコロナの影響により参列できない事例も多いです。
葬儀に参列できない場合は、御香典の郵送で弔意を表すことができます。
この他にも、弔電や供え花の手配などの方法もあるでしょう。
弔電であれば、当日でも対応してくれます。
お花やお線香などとともに贈る弔電もありますので、こちらも検討してみてはいかがでしょうか。
・お葬式に花を贈るにはどうしたらいい?供花・花輪・献花・枕花、4つの種類と贈り方手順
まとめ
御香典を送る方法と、お悔みの手紙5つのマナー
●御香典を送る
・現金書留で送る
・不祝儀袋に整える
・不祝儀袋を現金書留封筒に入れる
・現金書留封筒は大きいサイズが良い
・タイミングに配慮して送る
・お悔みの手紙を添えると良い
●お悔みの手紙5つのマナー
お電話でも受け付けております















