
【家族が亡くなったら】自宅で遺体を安置する、家族が行う4つのポイント|永代供養ナビ
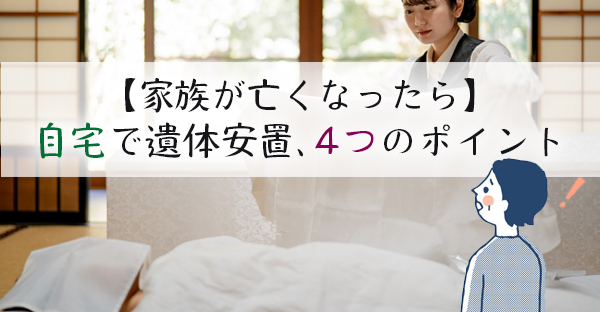
自宅でご遺体を安置する場合、斎場などの安置室と比べて環境が充分に整っていないため、迎え入れの準備をしなければなりません。
今では檀家制度が希薄になり無宗教の人々も多いですが、仏教的な作法もありますし、何よりもご遺体を衛生的に管理できるよう、良い環境のなかで安置する必要があります。
ある程度は葬儀社が整えてくれます。
ただ一日中ご遺体に添って管理する必要があるため、家族も行うべき事柄や、自宅で遺体安置ができるか、確認事項を理解しておくと安心です。
今回は、家族が亡くなって自宅でご遺体を安置すると決めた場合に、家族が行うべき4つの事柄を、注意点とともにお伝えします。

自宅を遺体安置に選ぶ注意点

昔は自宅でご遺体を安置する家がほとんどでした。
今でも地方では自宅でご遺体を安置し、そのまま自宅葬を行う家も多くありますが、特に都心部の大阪では、すっかり少なくなっています。
そのため、実際に自宅でご遺体の安置が可能かどうか、下記の点を確認してから決めてください。
(1)搬送経路の確保
(2)ご遺体に付き添う人がいるか
(3)ご遺体の安置スペースがあるか
(4)ご遺体の安置期間
詳しくは下記よりお伝えしますが、告別式・葬儀会場が別に設けられているのであれば、この他にも火葬場や斎場との距離も考慮した方が良いでしょう。
葬儀社がご遺体の搬送を担ってくれますが、距離が長くなればそれだけ費用が掛かります。
(1)搬送経路の確保
昔の大阪では自宅で遺体安置をするに当たり、搬送に困り事は今ほど多くはなかったものの、現代ではマンションやアパートなどの集合住宅が増え、また密集により家と家の幅も短くなっています。
搬送車は一般的な車よりも幅が広く大きいため、搬送に当たり、下記の点には配慮をしなければなりません。
●戸建ての場合
・搬送車が通るか
・搬送車の駐車スペースがあるか
●集合住宅の場合
・規約を確認
・エレベーターや階段
・扉の確認
またアパートや賃貸マンションの場合には、管理人から許可を得る必要がありますし、分譲マンションでも自治会の承認や規約に合っているか、確認を取る必要があります。
自治会の会長さんや周辺の家の人々へ、ご報告とお挨拶を行うと良いでしょう。
(2)ご遺体に付き添う人がいるか
斎場の安置室を利用する場合、スタッフが管理をしてくれますが、自宅で遺体を安置する場合、複数人で交代してご遺体のお世話をしなければなりません。
・お線香やろうそくなど火元の確認
・お客様への対応
・室温やご遺体環境の管理
ただ斎場の安置室を利用する場合でも、添い人を付けるにあたり料金が掛かることは多くあります。
料金目安としては約5千円~5万円と割高になるため、斎場の安置室でもご遺族から添え人を用意するケースは多いです。
(3)ご遺体の安置スペースがあるか
故人が生前にベッドで寝ていたのであればベッドを安置場所として選んでも良いのですが、一般的に自宅では、座敷を遺体安置スペースとして用意します。
●枕飾りなどの他、弔問客の座るスペースもあるので、少なくとも4畳~6畳以上は確保したいところです。
また奥間の場合、廊下の幅など、自宅に入ってから充分な搬送経路が確保されているかも確認をしてください。
自宅に遺体安置する4つの手順

自宅に遺体安置をする場合、搬送前に一度帰宅して故人を迎える環境を整えます。
現代は枕飾りなどを整える必要があるため、ご遺族のみで行うケースは少なく、葬儀社が準備をしてくれるでしょう。
(1)神棚は「神封じ」
(2)北枕に整える
(3)環境を整える
(4)枕勤め(枕経)の依頼
ご遺体を安置するに当たり、枕飾りや守り刀、布団や数珠などの準備が必要ですが、葬儀社が準備をしてくれます。
ただ白い薄手の掛け布団と敷き布団は準備している家も多い傾向です。
(1)神棚は「神封じ」
神棚がある場合、神道では死を穢れ(けがれ)とするため、神様の目に入らぬよう、故人を迎え入れる前に「神封じ」を行います。
神棚の扉を閉め、その上から半紙を貼り付けて「神封じ」としてください。
(2)北枕に整える
一般的に大阪で自宅にご遺体を安置する場合には、頭を北枕で寝かせます。
これは仏様が入滅(亡くなった)時、北に頭を向けていたためです。
●お仏壇がある仏間であれば、仏壇を頭に寝かせます。
ただ地域によっては西方浄土がある西枕で寝かさせることもあるでしょう。
また浄土真宗では必ずしも北枕である必要はありません。
お布団は逆さ事で整える
自宅でご遺体を安置する場合、掛け布団と敷き布団は薄手の布団を一枚のみで整えます。
これはご遺体が必要以上に温まらないよう、環境的な配慮もあるのですが、それ以上に不幸が重なることのないよう、忌み事を避ける理由が大きいです。
・掛け布団と敷き布団を一枚ずつ
・布団は上下逆さに敷く
布団を上下逆さに敷くことは「逆さ事」などと言い、彼岸(あの世)と此岸(この世)を分ける理由があります。
着物の左前も同じ意味合いですが、こちらも浄土真宗においては行いません。
(3)環境を整える
自宅ではご遺体を安置する場合、室温を冷たく保たなければなりません。
目安は18度ですので、冬場であれば暖房を付けない程度で良いですが、夏場であれば故人を迎える前に冷房を付けておく必要があります。
・室温を18度ほどに管理する
・ご遺体の周囲にドライアイスを敷く
ドライアイスは個人で気軽に入手できるものではありませんが、葬儀社が用意をしてくれるでしょう。
特にお腹などをドライアイスで冷やしてあげてください。
お腹と背中を挟むようにドライアイスを整えます。
安置期間は長くても7日間
斎場の安置室とは違い、自宅はご遺体を安置するための充分な設備が整っていません。
そのためドライアイスや室温で調整をしても、できれば3日間以内、長くても7日間ほどが限度でしょう。
斎場のスケジュールなどで葬儀日程が先になる場合、先に火葬を済ませて焼骨したご遺骨の状態で、告別式・葬儀を済ませる事例も増えました。
(4)枕勤め(枕経)の依頼
「枕勤め(枕経)」とは、人が亡くなてすぐ、故人の枕元で供養をするお経です。
そのため僧侶を手配して枕勤め(枕経)の依頼をしますが、菩提寺(※)があれば、菩提寺のご住職にお願いをしてください。
多くは枕勤め(枕経)が終わってすぐ、ご遺族は僧侶や葬儀社の人々と通夜や葬儀について打ち合わせをします。
(※)菩提寺(ぼだいじ)は旦那寺(だんなでら)とも言い、家が信仰する特定の寺院を差しますが、一般的には先祖代々墓が建つ墓地を管理している寺院が菩提寺です。
最後に
今回は、家族が亡くなってから自宅にご遺体を安置する際、迎え入れで行う4つの手順をお伝えしました。
最後にお伝えした僧侶の枕勤め(枕経)ですが、最近では墓じまいをして、菩提寺から離れる離檀(りだん)が増え、無宗教の家も増えています。
無宗教であれば枕勤め(枕経)を必ずしも唱える必要はありません。
また自宅以外の斎場で遺体を安置する選択でも、枕勤め(枕経)の供養は行われますが、施設や状況によっては、すぐに枕勤め(枕経)ができないケースもあります。
このような場合は通夜の前に行う選択もあるでしょう。
菩提寺のご住職へお願いする、僧侶を手配する際には、最初に葬儀社スタッフや斎場の安置施設に確認をとるようにしてください。
・【家族が亡くなったら】病院でご臨終の後、家族が行うべき8つの事柄とは|永代供養ナビ
まとめ
ご遺体を安置する4つのポイント
●自宅で安置する前の確認事項
・搬送経路の確保
・ご遺体に付き添う人がいるか
・ご遺体の安置スペースがあるか
・ご遺体の安置期間
●自宅に遺体安置する4つの手順
・神棚は「神封じ」
・北枕に整える
・環境を整える
・枕勤め(枕経)の依頼
お電話でも受け付けております















