
認知症の人の財産を守る成年後見制度の種類とは?利用するメリットや手順を解説

「認知症の家族の財産を守るにはどうすればいい?」
「成年後見制度の種類について詳しく知りたい」
「成年後見制度を利用した場合のメリットは何?」
高齢化社会が進む現代において、成年後見制度はますます身近になっています。しかし、このように疑問を抱く人は多いのではないでしょうか。
本記事では成年後見制度種類やメリット、成年後見制度の相談先と手続きの流れ、成年後見制度を利用する時に気を付けることを紹介しています。
この記事を読むことで、成年後見制度について正確な知識を身に付けることができます。認知症になっても安全な生活を送っていくうえで、家族や親族、自分自身の大きな安心につながるでしょう。
自分や家族の財産を守るために、ぜひこの記事をチェックしてください。
認知症の人の財産を守る成年後見制度ができた理由とは?
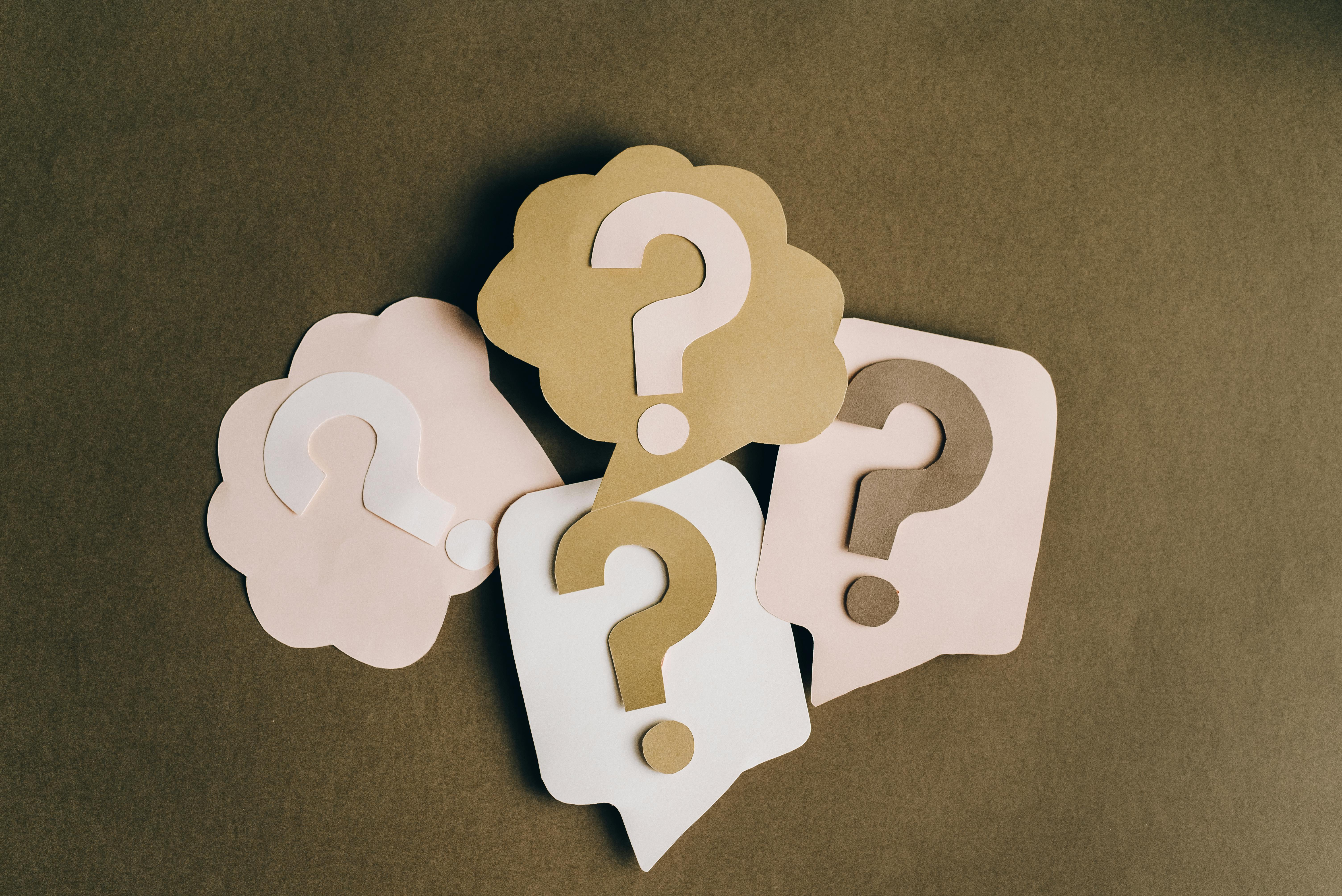
認知症とは脳の障害や病気などさまざまな原因により、脳の認知機能が低下して日常生活全般に支障が出る状態のことをいいます。
従来、日本には現在の成年後見制度と同じような制度として、判断能力が低下した人のために禁治産・準禁治産制度というのがありました。しかし、禁治産者になると本人の戸籍に記載されて、他人から偏見や差別を受けやすいなど問題点が多い制度であったといえます。
禁治産・準禁治産制度から移行された成年後見制度は、認知症の人の人権を尊重し、本人の財産や権利を守るため、平成12年から施行された比較的新しい制度です。
出典:認知症|厚生労働省
認知症の人の財産を守る成年後見制度を利用する3つのメリット

認知症の人の財産を守るために、成年後見制度を利用することで得られる代表的なメリットとして以下の3つが挙げられます。成年後見制度を検討している場合は参考にしてください。
- 契約を本人に代わって締結してくれる
- 悪質な契約を取り消してくれる
- 財産の管理をしてくれる
1:契約を本人に代わって締結してくれる
成年後見制度を利用することで、生活していくうえで必要な契約を本人の代わりに締結してもらえます。例えば、1人暮らしをしていたけれど介護施設に入所したいというのであれば、代理で入居手続きをします。
また、自宅にいながら介護を受けたいという場合は、ホームヘルパーを頼むことも可能です。その他にも、リハビリや医療など、本人が必要とする契約の事務手続きを行います。
2:悪質な契約を取り消してくれる
成年後見制度を利用することで、本人にとって不必要な契約を取り消すなど悪徳商法などから守ってもらうことが可能です。
これにより悪質な通販サイトや訪問販売などから、不要な商品を買ってしまったり、高額な商品を買ってしまったりするという被害を防げます。
3:財産の管理をしてくれる
成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した人の財産や資産を管理してもらえます。不動産屋や預貯金などの財産や資産の管理をしてもらうことで、経済的な破綻や身近な人による使い込みを防ぐことが可能です。
成年後見制度の種類

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。成年後見制度を利用する人にどれほどの判断能力があるのかによって、それぞれ利用できる制度が異なります。
それでは、成年後見制度の種類について詳しく解説していきましょう。
任意後見制度
任意後見制度は、現時点では本人に判断能力があるが将来判断能力が著しく低下した時のために、あらかじめ本人が選んだ任意後見人に代理でしてもらいたいことを決めておく制度です。
本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから、初めて任意後見契約の効力が生じます。
この申し立てができるのは、本人・配偶者・4親等以内の親族・任意後見受任者のみです。本人以外の請求で任意後見監督人の選出を行うには、本人が意思表示できない場合を除き、本人の同意が必要になります。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症など判断能力が十分でないと見なされた人が利用できる制度です。本人の判断能力に応じて、補助類型・補佐類型・後見類型の3つの種類に分かれています。
家庭裁判所で選出された成年後見人等が、本人に代わって契約などの事務手続きをしたり、本人には不必要な契約を取り消ししたりすることによって、本人を支援・保護することが目的です。
ここからは補助類型・補佐類型・後見類型、それぞれの制度について詳しく紹介します。
補助類型
補助類型は重要な手続きや契約をする際など、1人で判断する能力が不十分な人が利用できる制度です。
申し立てにより家庭裁判所が補助開始の審判をし、本人を援助する補助人を選任します。補助人は、本人が日常生活に困らないように配慮をしなければなりません。
また、補助人にどこまで同意権や代理権を与えるかを決め、補助人ができる事柄の範囲を定めるための申し立てを家庭裁判所にする必要があります。
保佐類型
保佐類型は1人で判断する能力が著しく不十分な人が、家庭製番所に申し立てをし、保佐開始の審判をして本人を援助する保佐人を選任する制度のことです。
本人は一定の重要な行為において保佐人の同意が必要になります。また、本人が保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消す権限も持っています。
なお、家庭裁判所の審判により、自宅の新築や増築・修繕など本人が望んでいる一定の事柄について、本人に代わって契約を締結することも可能です。
後見類型
後見類型は判断能力が常に欠けている状態の人が、家庭裁判所に申し立てをし、後見開始の審判をして後見人を選出する制度です。
後見人の権限は幅広く、原則として全ての法律行為が可能で、本人に代わって契約する代理権や、本人の契約を後から取り消せる取り消し権もあります。
成年後見制度を利用したい時の相談先

成年後見制度を利用したい場合、まずは自分が住んでいる区市町村の成年後見制度推進機関に相談してみましょう。成年後見制度推進機関では、後見制度全般に関するさまざまな疑問や相談への対応、後見事務の研修などを行っています。
また、将来認知症になった場合に備えて任意後見制度を検討しているという場合は、日本公証人連合会に相談するのがおすすめです。
成年後見制度の手続きする前に準備すること

成年後見制度を利用するには、本人の住民票上の住所を管轄する家庭裁判所へ必要書類を揃えてから申し立てをすることになります。家庭裁判所の具体的な管轄区域は裁判所のホームページで調べられます。
提出する書類は家庭裁判所や申し立て内容によって異なることもあるため、事前に確認しておいた方が無難でしょう。
また、本人の判断能力がどの程度のものかわかる医師の診断書も必要になります。かかりつけ医に相談し、作成を依頼してください。
成年後見制度の手続きの手順

家庭裁判所で定められている必要書類を用意したら、申し立てをする家庭裁判所に電話して面接日を予約します。
書類審査の後面接が行われ、親族への意向照会、本人の判断能力診断のための医学的鑑定などを経て審判結果が出ます。申し立てから審判までの期間は、おおよそ1か月~2か月程度が目安です。
成年後見制度を利用する時に気を付ける4つのこと

両親や親族、もしくは将来の自分のために成年後見制度を利用したいという人もいるでしょう。成年後見制度は判断能力が不十分な人を支援・保護する制度ですが、注意しておきたい点があります。
ここでは、成年後見制度を利用する時に気を付ける4つのことについて解説します。
1:法定後見人の申し立てできる人には一定の条件がある
法廷後見人の申し立てができる人は、本人・配偶者・4親等以内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官です。
民法上での「親族」は、6親等内の血族・配偶者・3親等以内の姻族を指すため、「4親等以内の親族」には4親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族が該当します。
出典:詳細|法テラス
2:成年後見制度を利用するのに費用がかかる
成年後見制度を利用するには費用がかかりますが、この費用は申し立て人が用意します。具体的な費用は以下の通りです。
・申し立て手数料および後見登記手数料:3400円
・送達・送付費用のための切手代(後見申し立て):3270円
・送達・送付費用のための切手代(保佐・補助申し立て):4210円
・鑑定費用:10万~20万円程度
・医師の診断書の作成費用:数千円程度
・住民票・戸籍抄本:数百円程度
・登記されていないことの証明書の発行手数料:300円
鑑定費用は本人の判断能力がどの程度のものか確かめるために、裁判所が医師に依頼する形で行われます。これらの費用は、申し立て時ではなく裁判所が審理を進め、鑑定が必要と判断した場合に納めます。
3:後見人にはできることとできないことの違いを把握しておく
後見人の主な仕事は、身上監護と財産管理です。身上監護とは、本人の生活を維持するための仕事・施設の入所や入院に関する契約などを指します。財産管理は本人の財産を維持・管理するもので、本人の預貯金や収入・支出、不動産の管理などが含まれます。
一方、後見人にできないことは本人が医療行為を受けるにあたって同意・不同意をすることです。また、本人の婚姻・離婚・養子縁組・離縁・遺言などは代理権がありません。
4:後見人になったら本人の代理であることを自覚する
後見人になるのであれば本人の代理であることを自覚しなくてはいけませんが、本人と成年後見人の間で利害の対立が起こることも少なくありません。
例えば、本人と後見人の双方が相続人である時の遺産分割など、しばしば利益が相反するケースが見受けられます。しかし、後見人に求められるのは本人の意思を尊重し、本人の利益を最優先に考えることです。後見人は後見人の利益になるような行動をすることができません。
そのため、本人と後見人の間で利害関係が生じた場合は、特別代理人の選任が必要になります。
認知症の人の財産守ってくれる成年後見制度について知っておこう

成年後見制度は、認知症など判断能力が低下した人の財産や権利を守る制度です。本人の判断能力の程度により3つのタイプがあるほか、将来本人の判断能力が低下した場合に効力が生じるものがあります。
高齢化社会が進むにつれ成年後見制度はますます身近になっており、安心できる生活を送るうえで成年後見制度の正確な知識を持つことは重要といえます。
この記事を参考に成年後見制度の仕組みを十分に理解したうえで、利用の検討をしましょう。
お電話でも受け付けております















