
不動産のみの遺産分割協議書は作れる?記載内容と作成のポイント
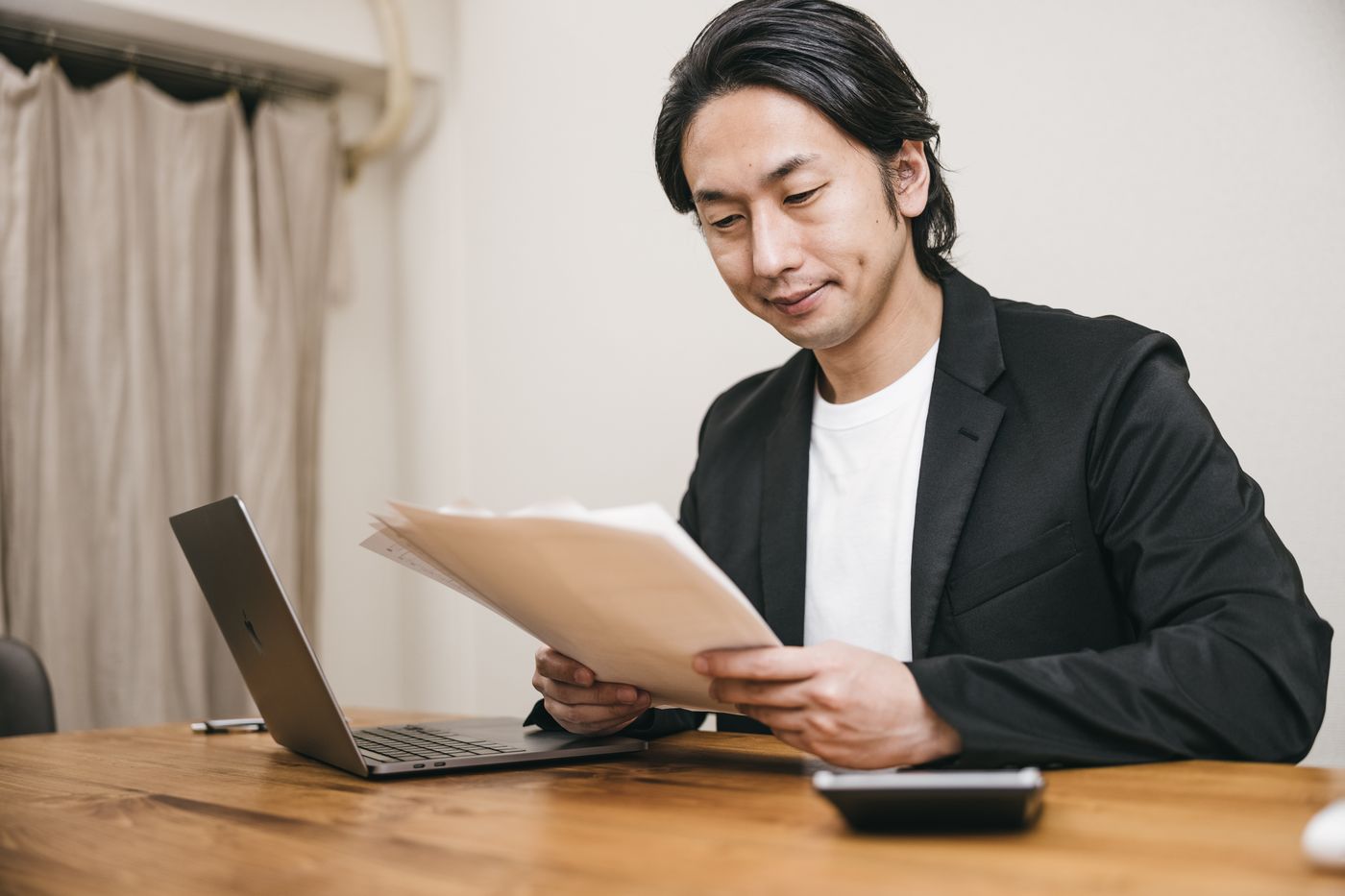
「そもそも遺産分割協議書とは、どういう書類?」
「不動産のみの遺産分割協議書は、相続登記の手続きに使える?」
「遺産分割協議書を自分で作成する時に注意することって?」
遺産分割協議書は自分でも作成できる書類ですが、実際に作成経験がある人は多くないでしょう。
この記事では、不動産のみの遺産分割協議書について詳しく解説しています。作成する際に記載しなければならない項目などのポイントや、相続登記に必要になる他の書類についても紹介しているため、記事を読むことで相続登記をスムーズに進められるでしょう。
相続登記が必要な人はぜひ一読して、自分で相続登記用の遺産分割協議書を作成してみてください。
不動産のみの遺産分割協議書とは
 相続によって不動産を取得した際に、不動産の名義を亡くなった人から相続した人に変更する手続きが相続登記です。この手続きを怠ると、その不動産を売却や担保にするといった行為ができません。
相続によって不動産を取得した際に、不動産の名義を亡くなった人から相続した人に変更する手続きが相続登記です。この手続きを怠ると、その不動産を売却や担保にするといった行為ができません。
この相続登記の手続きに遺産分割協議書が必要になるケースがあります。まずは、どういう場合なのかを詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議書が必要な場合
遺産分割協議書とは、法定相続分と違う割合で遺産を分割する際に、相続人全員が合意した割合であることを証明するために作る書類です。
より簡単な書類である相続同意書というものもありますが、不動産の相続登記では受け付けてもらえません。したがって、遺産分割協議書は不動産を相続した際に作成しなければならない必須の書類です。
不動産のみを対象とする遺産分割協議書は作れる
遺産分割協議書は、相続するすべての財産について詳細を記載するのが一般的です。しかし、不動産の相続登記に使用する目的であれば、内容は不動産に関する項目のみでも構いません。
すべての財産についての情報が記載されていると、見られたくない部分まで人の目に触れてしまうため不安を覚える人も一定数いるでしょう。
そこで、不動産の分割についてのみ記載した遺産分割協議書を同時に別で作成します。同一の内容で作成していれば、一部を抜粋した遺産分割協議書であっても問題なく、相続登記の提出用として使用できます。
登記目的の不動産のみ遺産分割協議書の記載内容

相続登記に使う、不動産のみの遺産分割協議書に記載する内容とはどのようなものがあるのでしょうか。まずは、記載する項目についてそれぞれ確認し、把握しておきましょう。
被相続人に関すること
まずは、亡くなった被相続人についての情報が必要です。戸籍や住民票を見ながら、下記の項目について漏れや誤りなく転記しましょう。登記簿上の住所は、登記簿謄本の住所と最後の住所が異なる場合に記載すれば構いません。
・被相続人の氏名
・相続開始日(死亡日)
・最後の住所
・最後の本籍
・登記簿上の住所
相続する不動産と取得する相続人
相続登記をしたい不動産について、誰がどの不動産を取得するのかがわかるように記載します。いずれも各不動産の全部事項証明書を取得すれば、書く項目について掲載されているため、それをもとに転記すれば大丈夫です。
新たな財産が見つかった場合の対応
遺産分割協議の後に、相続人の誰も把握できていなかった新たな財産が出てくる可能性は少なからず存在します。
新たな財産と以前から判明していた財産がまったくの別物で関連性がなければ、基本的に遺産分割をやり直す必要はありません。新たな財産についてのみ、改めて分割協議を行えばいいのです。しかし、新たな財産の分け方に合意できなければ、トラブルに発展する場合もあります。
この対処策として、遺産分割協議をする際に「万一、後から新たな財産が出てきた場合にどうするのか」を決定しておく方法があります。具体的なルールを定めることで、スムーズに対応できるのがメリットです。
相続人全員の署名・押印
「以上の協議を称するため、この協議書を作成し署名捺印する」として、最後に必要になるのが相続人全員の署名・押印となります。この時に使用する印鑑は実印である必要があり、印鑑登録証明書とセットで用意すれば確実です。
不動産のみを対象とする遺産分割協議書作成のポイント
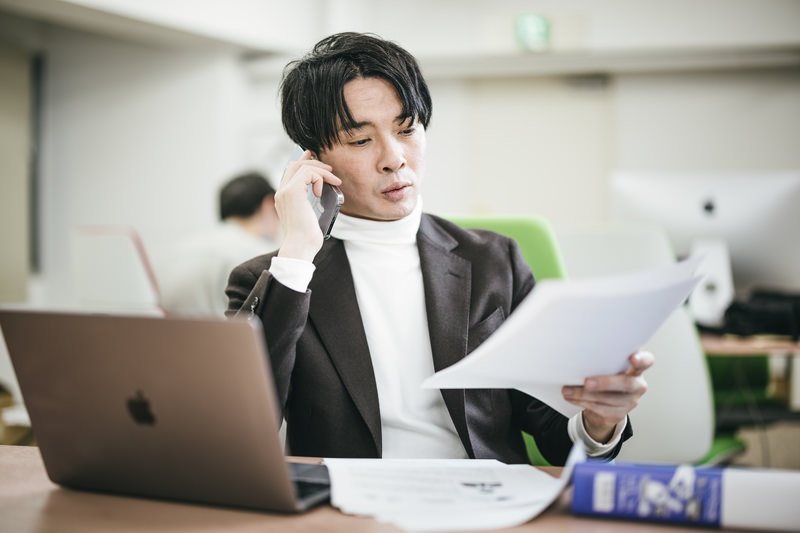 不動産のみを対象とする遺産分割協議書を作成するにあたり、下記で示す点に注意しましょう。いずれもスムーズな手続きや後にトラブルが起こった際に必要となるポイントです。それぞれについてしっかりと確認しておきましょう。
不動産のみを対象とする遺産分割協議書を作成するにあたり、下記で示す点に注意しましょう。いずれもスムーズな手続きや後にトラブルが起こった際に必要となるポイントです。それぞれについてしっかりと確認しておきましょう。
- 不動産の相続人と持ち分を明確にする
- 不動産は登記簿通り正確に記載する
- 代償分割の合意がある場合は明記する
- 遺産分割協議の時点で判明していない財産の対応方針を決めておく
不動産の相続人と持ち分を明確にする
話し合いで不動産の相続の仕方がなかなか決まらなくとも、相続税の申告など他の手続きの期限が先にやってきてしまうこともあるでしょう。この場合、相続人全員で不動産を共有という形にし、法定相続人が法定相続割合に応じた共有持ち分を取得したことにする方法を取ります。
この場合でも遺産分割協議書に記載する不動産についての情報は、共有しない場合と同じです。
ただし、誰がどのような割合で所有するかがわかるように、共有持ち分について追加で記載が必要になります。「次の不動産は〇〇が持ち分1/2、△△が持ち分1/2の割合で相続する」のように、具体的に明記しましょう。
不動産は登記簿通り正確に記載する
遺産分割協議書に不動産について記載する際は、基本的に登記事項証明書に掲載されている内容をそのまま記載します。相続する不動産の種類により記載する項目に違いがあり、土地と建物は下記のとおりです。
・土地の表示:所在、地番、地目、地積
・建物の表示:所在、家屋番号、種類、構造、フロアごとの床面積
マンションの場合は、建物全体の情報を記載したに、相続する部分の表示が必要です。
・1棟の建物の表示:所在、構造、フロアごとの床面積
・専有部分の建物の表示:家屋番号、種類、構造、床面積
・敷地権の表示:所在及び地番、地目、敷地権の種類、敷地権の割合
これらの項目すべてについて、「1丁目1番地」を「1−1」などと省略したり、数字を漢数字に変更したりしないよう、正確に記載することが大切です。
代償分割の合意がある場合は明記する
自宅や土地など、不動産は分割するのが難しい財産です。話し合いがまとまらず相続手続きをスムーズに進めるために、このような財産に対して代償分割という方法が選択肢に挙がります。
代償分割は、分割が難しい財産を相続人の1人が相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うことで調整を行う方法です。
ただし、代償分割を利用して遺産分割を行う場合、遺産分割協議書にその旨についての明記が必要になります。その際は、「誰が誰に対して、何円をいつまでにどの方法で支払うのか」を、はっきりと記載しましょう。
遺産分割協議の時点で判明していない財産の対応方針を決めておく
遺産分割協議の後のトラブルを避けるために、しっかり財産調査を行うことも大切ですが、あらかじめ遺産分割協議の時点で具体的にどうするかルールを決めておくのも1つの手です。
例えば「新たな財産が見つかったら、相続人である〇〇が取得するものとする」と明記すれば、どのような財産であっても指定した相続人が相続となります。
「新たな財産が見つかり、その価値が300万円以下であれば相続人である〇〇が取得するものとする。300万円を超えていたら、再度遺産分割協議をするものとする」のように条件をつけておくのも良いでしょう。
いずれにしても遺産分割協議では、これらのルールについても相続人全員から合意を得ておくことが重要です。
不動産のみを対象とする遺産分割協議による相続登記に必要な書類
 遺産分割協議書を作成した場合であっても、相続登記で用意しなければならない書類は必要になります。まず、各市区町村の役場から入手できる書類は、以下の5種類です。
遺産分割協議書を作成した場合であっても、相続登記で用意しなければならない書類は必要になります。まず、各市区町村の役場から入手できる書類は、以下の5種類です。
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続人の印鑑証明書
さらに、その他から入手する必要がある書類は、以下のとおりになります。
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・登記申請書
・収入印紙
・返信用封筒
相続する不動産の固定資産評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場から入手します。遺産分割協議書と登記申請書は自分で作成する書類です。収入印紙と返信用封筒は、郵便局やコンビニなどで購入できます。
不動産のみに限定した遺産分割協議書は自分で作ってみよう
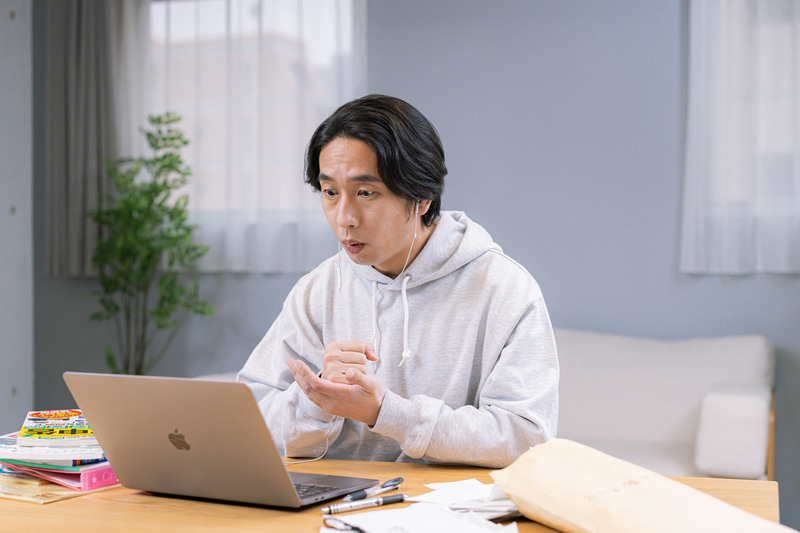
ポイントを押さえて記載すれば、不動産のみの遺産分割協議書を自分で作成するのは難しくありません。むしろ、相続登記に必要になる書類を集めることの方が苦労する場合もあるでしょう。
内容の誤りや誤字に注意して遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・押印をもらいましょう。
お電話でも受け付けております















