
遺言書の作成費用はどれくらい?弁護士に依頼するメリットも解説

「遺言書の作り方って、弁護士や行政書士に頼めばいいのかな」
「相続で揉めない遺言書を作るには、どうすればいい?」
「弁護士に頼むと、お金がかかりそうな気がする」
人生の終活を考えていく中で遺言書を残す方は、このような疑問や悩みを持つ人も多いことでしょう。
本記事では遺言書の作成にかかる費用と、弁護士に依頼するメリットについてポイントと注意点を紹介しています。
この記事を読むことで遺言書の種類や、作成費用の目安、自分に合った遺言作成方法や気をつけたいポイントについて理解できます。その知識をもとに、遺言書の作成依頼ができるでしょう。
遺言書の作成を検討している方や費用について知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
遺言書の種類と作成費用の目安

遺言書にはどのような種類があって、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。大きく分けると遺言書には自筆証書遺言と、公証役場を利用する公正証書遺言や秘密証書遺言といった種類があります。それぞれに必要な費用について詳しく解説していきます。
自筆証書遺言の作成費用目安
民法968条には自筆証書遺言に関する規定があり、遺言者自身がその全文と日付、氏名を自書し、印を押すことを定めています。
自筆証書遺言書の作成にかかる費用は、原則として無料です。ただし、法務局が遺言書の原本を保管してくれるという、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は1件につき3,900円の費用がかかります。
出典:民法|e-Gov法令検索
出典:09 手数料|法務省
公正証書遺言の作成費用目安
自筆証書遺言書は財産目録以外の全てを自筆で書かなければならないため、体力が衰えている方や病気の方にとっては、難しいものです。
民法969条には公正証書遺言の規定があり、証人2人以上の立ち合いがあり、遺言者が遺言の趣旨を口述で公証人に伝えて、公証人が作成、遺言者と証人が確認した上で押印することで作成できるとしています。
この場合の公正証書遺言の作成費用としてかかるものは、公正証書作成手数料と、証人の日当、公証人役場以外で作成する場合の出張費用の3つです。
公正証書作成手数料は、相続する財産の合計額が1億円未満の場合は、5,000~43,000円に加えて、1億円未満の遺言加算が11,000円かかるとされており、さらに1億円以上の場合についても規定があります。
証人の日当は1人につき5,000~15,000円程度で知人に頼めば無料となる可能性もありますが、遺言内容を知られてしまうというリスクもあるでしょう。
遺言者が高齢のため公証人役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。その場合は公正証書作成手数料が1.5倍となり、公証人の日当と交通費も必要です。
出典:民法|e-Gov法令検索
後のトラブルを避けやすい遺言書作成方法

遺言書は相続の対策として重要とされているものですが、遺言書を残したにもかかわらず相続でトラブルが発生するケースが少なくありません。
それでは、どのように遺言書を作成すれば、トラブルを避けられるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
自力で行わず専門家に依頼する方法
遺言書作成を依頼する専門家として弁護士が挙げられがちですが、司法書士や税理士、行政書士も遺言書作成を行えます。
不動産の相続であれば司法書士、相続税の申告が関係するのであれば税理士、費用を比較的安く抑えたい場合は行政書士といった選択肢もあるでしょう。ただ、依頼する場合は遺言書作成の実務をよく知っている人に依頼するようにしましょう。
遺言執行者に専門家を指定する方法
民法1012条には遺言執行者の権利義務の規定があり、遺言の内容を遂行する人を決められます。この遺言執行者に弁護士などの専門家を指定することで、遺言執行時のトラブルを避けられるでしょう。
遺言中に遺言執行者が指定されていない場合、または遺言執行者が亡くなった場合は、家庭裁判所への申し立てにより、遺言執行者を選任することもできます。
出典:民法|e-Gov法令検索
出典:遺言執行者の選任|裁判所
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にする方法
自筆証書遺言は簡単に作ることができ、証人も不要と気軽に作成できるメリットがありますが、紛失や偽造といったリスクがあります。
一方、公正証書遺言は法律の専門家である公証人に依頼して作成するため、安心で確実な形式でしょう。遺言者が口述したものをもとに公証人が作成しますが、内容に法的な問題があれば、問題がない形式に改めるよう指摘してくれることもメリットです。
公正証書遺言は公証人が作成することや証人が必要であることから、偽造の心配もなく、保管も確実という安心感もあります。
遺言書の作成を依頼できる専門家と作成費用の目安

遺言書の作成は、どのような専門家に依頼すればいいのでしょうか。前述した弁護士、司法書士、税理士、行政書士以外にも、日頃から銀行や信託銀行との付き合いがある方は遺言信託といったサービスもあります。
ここからは、遺言書の作成を依頼できる専門家と作成費用の目安を紹介しますので参考にしてください。
弁護士や行政書士に作成依頼する場合
遺言書の作成を専門家である弁護士や行政書士に依頼する場合は、公正証書遺言の作成になります。公正証書遺言の作成は弁護士、行政書士とも同じ方法で行われます。
まずは、遺産の分配をどのように行うかを相談し、次にその内容に応じて、弁護士または行政書士が草案としてまとめることとなるでしょう。
その後、草案を依頼者が確認し、最終的には公証役場で公正証書遺言とします。公正証書遺言の効果は弁護士でも行政書士でも同じものです。
遺言書の作成費用の目安
弁護士に遺言書の作成を依頼する場合の目安は、定型文を使用したものでも10万円以上とされています。遺産の分配の内容が複雑な場合は、20~300万円程度と想定されるでしょう。
行政書士に遺言書の作成を依頼する場合は、弁護士に依頼する場合の半分程度で6~10万円程度が相場です。
遺言執行者報酬の目安
弁護士による遺言執行者報酬の目安としては、遺産が5,000万円の場合は100万円程度であり、遺産の額や特殊な事情がある場合で変化します。
また、遺産執行に裁判の手続きが必要となる場合は、裁判手続きのための弁護士報酬が必要となるケースもあるでしょう。
行政書士による遺言執行者報酬の目安としては、遺産が5,000万円の場合、35~65万円程度で、遺産が不動産のみなのか、動産や預貯金を含むのかで報酬に差があります。
銀行や信託銀行に作成依頼する場合
銀行や信託銀行のサービスの1つに遺言信託があり、遺言の作成と執行を遺言者の依頼により行うものです。
銀行や信託銀行は遺言者の相談により、遺言書の作成を補助し公正証書遺言を作成します。銀行や信託銀行の職員が証人になる場合もあります。
公正証書遺言は公証役場に保管する原本のほかに正本と謄本がありますが、正本を銀行や信託銀行が預かり、謄本を依頼者が持ち帰ることとなるでしょう。
遺言書の作成費用の目安
遺言書の作成を銀行や信託銀行に依頼した場合は、基本手数料は30~100万円程度、遺言書の保管料が年額5,000円程度かかります。遺言書の内容を変更するときは、5~10万円程度の手数料がかかるでしょう。
遺言執行者報酬の目安
銀行や信託銀行の遺言執行者報酬は、契約により異なりますが最低でも10万円~30万円程度です。
銀行や信託銀行と契約している預金や信託商品、保険に関してと、契約以外の預金や不動産などの財産では、金額に対してかかる報酬の計算が異なるように設計されています。そのため、財産によっては、より多い報酬を必要とするでしょう。
遺言書作成費用とあわせて100~200万円程度が最低限の目安と言えるでしょう。
遺言書作成を依頼する専門家の比較

費用面を重視する場合は、弁護士または行政書士に依頼する方が安くなるでしょう。弁護士と行政書士では、行政書士の方がさらに安く依頼できます。
ただし相続人同士で揉めることが予想される場合は、弁護士に依頼した方が死後にトラブルがあった際にも対応してもらえるでしょう。
遺言書を作成するときに気をつけたいポイント

遺言書は遺言者の気持ちを伝えるものですが、トラブルにならないように気をつけるポイントがあります。
推定相続人をきちんと把握すること、記載の漏れがないよう財産を把握するといいでしょう。さらに、気をつけるべきポイントについて解説していきます。
- 遺留分に配慮した遺言書にする
- 自筆証書遺言の書式を確認しておく
遺留分に配慮した遺言書にする
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる、遺言者(被相続人)から相続する財産の最低限の取り分のことです。被相続人の配偶者と子供1人の2人が相続人とした場合は、それぞれに財産の1/4ずつの遺留分が認められています。
遺留分を無視した遺言書は、遺留分を侵害されたとして争いのもとになるためきちんと配慮した遺言書とする必要があります。
自筆証書遺言の書式を確認しておく
自筆証書遺言の場合は、民法968条で遺言者が全文と日付、氏名を自書し、印を押さなければならないと決められています。
平成31年1月13日に施行された自筆証書遺言の緩和されたルールが、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録に関しては、自書しなくていいというものです。ただし、遺言者が目録の各ページに署名と押印する必要があるため、注意しましょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
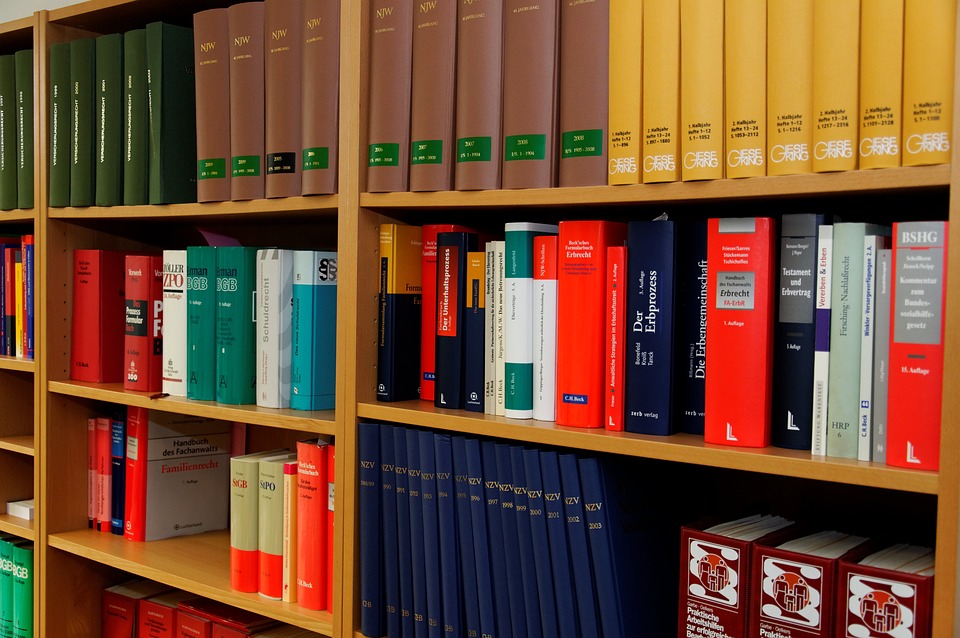
弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットの1つに、遺言執行者に弁護士を指名できる点が挙げられます。
また、弁護士であれば、遺言を執行する際の各金融機関や法務局への手続きもスムーズにできるでしょう。ここからは、その他にどのようなメリットがあるかを見ていきます。
- 正しい遺言書を作成できる
- 遺言書がもととなる相続トラブルを防ぎやすくなる
- 様々なトラブルへの対応をしてもらえる
正しい遺言書を作成できる
弁護士に依頼することで、法的に有効な正しい遺言書を作成できます。遺言書に誤記があったり、法的に決められた形式でなかったりした場合も、弁護士が確認し正しい遺言書としてもらえるでしょう。
遺言書がもととなる相続トラブルを防ぎやすくなる
もし遺言書に添付の財産目録に、把握されていない財産があった場合、別に財産分割協議を行う必要が出てきます。遺言書の作成を弁護士に依頼することで、財産を調査し正しい財産目録を作成できるため、事前にトラブルを防げるでしょう。
様々なトラブルへの対応をしてもらえる
遺言書の作成を弁護士に依頼することで、死後にトラブルが起きた場合も対応してもらえるでしょう。遺言書により相続を受ける人同士がトラブルとなった場合に、行政書士では訴訟の代理人になれませんが、弁護士は訴訟の対応が可能です。
遺言書作成における弁護士と行政書士や司法書士の違い

弁護士は遺言書作成における法律相談、遺言書作成などの法律事務を代理人として行うことができます。行政書士や司法書士の場合は遺言書の作成はできるものの、報酬を目的とした法律相談を受けることや、法律事務の代理人となることはできません。
遺言作成を弁護士に依頼するときのポイント

遺言書の作成を弁護士に依頼するとき、どのようなことに注意すればいいのでしょうか。弁護士に相談する場合、初回無料としている弁護士事務所以外では、30分で5,000円程度の費用がかかります。それ以外で注意すべき点を見ていきましょう。
- 希望や意思をきちんと伝える
- 複数の弁護士事務所で見積もりをとる
希望や意思をきちんと伝える
弁護士に遺言書作成の依頼をした場合、弁護士が遺言者に代わり遺言書の原案を作成します。そのため、遺言者の希望や意思を遺言書に反映できるよう、希望や意思をきちんと伝える必要があります。
複数の弁護士事務所で見積もりをとる
弁護士による遺言書の作成は少なくとも10万円程度、複雑な場合は20万円以上となります。決まった料金はないため、複数の弁護士事務所で相見積もりをとるようにするといいでしょう。
費用やポイントを把握して遺言書を作成してもらおう

遺言書を法的に有効かつ内容として適切なものとするには、弁護士に相談するのがいいでしょう。
この記事で紹介した遺言書の種類と作成費用の目安、遺言書を作成するときのポイントを参考に、弁護士への相談を検討してみてください。
お電話でも受け付けております















