
残されたお墓は、誰が引き継ぐ?

最近では永代供養墓が定着しつつありますが、先祖代々のお墓を守りたいという方も、少なくありません。
その際、よく聞くのが「長男じゃなくても、引き継いでいい?」「相続税はかかるの?」といった声です。また、「生前にできることはあるのか?」「手続きがわからない」という悩みも多いようです。
今回は、残されたお墓を引き継ぐ際の決まりや、必要な手続きについて紹介します。
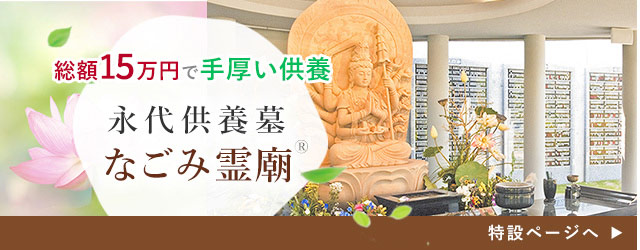
お墓の承継者とは? 承継者を決める方法

ご先祖様を祀るためのお墓や仏壇などは、「祭祀財産(さいしざいさん)」といいます。これらの祭祀財産を受け継ぐことを「承継(しょうけい)」といい、お墓を引き継ぐことは、「相続」とは表現しません。「お墓を承継する」といわれています。
基本的に祭祀財産は、特定の一人に受け継がせます。これはお墓や仏壇を通常の相続と同じように分割できない点や、祖先の祭祀に不都合が生じる点が考慮されてのことです。
また、承継者についても、亡くなったお墓の持ち主が、自由に指定することができます。最も多いのは長男または配偶者が承継するケースですが、それ以外の人でも承継者になることは可能です。
承継者を決める方法には、大きく分けて、3つあります。
その1:亡くなった人からの指定(口頭・遺言書など)
亡くなったお墓の持ち主が、あらかじめ承継者を指定しておく場合です。
指定された人が、お墓を引き継ぐことになります。口頭でも示せますが、できれば遺言書などが望ましいでしょう。また、親族以外の方が引き継ぐ場合は、ご家族や親族内で話し合って、了承を得ておいた方がよいでしょう。
ご寺院や霊園によっては、承継者の範囲(血縁者と宗派)を定めているケースもありますので、注意が必要です。
その2:慣習により決める
承継者の指定がない場合、慣習によって決められるのが一般的とされています。これはご家族や親族内での協議を意味します。その地方や職業などに特有の慣習があれば、それに従い決めていきます。
その3:家庭裁判所からの指定
第三の選択は、承継者の指定もなく、話し合いでも決まらない場合です。これは家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも話し合いがつかないと、審判に進みます。
いずれも事前に細かい条件や状況などを含め、誰が承継者にふさわしいのか、ご家族で相談しておくとよいでしょう。
※地域の文化や故人様との関係性などにより、承継者について決定方法が異なる場合があります
引き継ぎの費用と手続き

次に、気になる費用や手続きについてです。
民法では、祭祀財産は「相続財産」と区別されているため、相続税はかかりません。また、固定資産税もかかりません。
これは、墓地にお墓を建てているものの、土地を購入しているわけではなく、「使用権」を購入しているためです。そのため、固定資産税の負担もありません。
ただ、生前(お墓の持ち主が生きている間)に承継すると、「贈与税」がかかる可能性があります。最近は生前にお墓を承継しても、いざ引き継がれるときに、承継者が近くに住んでいなかったり、配偶者と離縁していたりと、さまざまな事情が増えています。そのため、お墓を生前に承継することを禁止している霊園もあります。十分に注意してくださいね。
また、お墓を承継すると、ご寺院や霊園への管理料や法要の費用、檀家としての寄進などが発生します。墓地の名義人の書き換えも必要になるため、名義変更の手数料も支払わなければなりません。承継者となる場合、年間費用がいくら必要になるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
さて、承継者になった場合の手続きですが、墓地の管理者に、名義変更などの書類を提出します。法的には何の届け出も必要ありませんが、墓地の管理者には届け出が必要です。なかには手続きの期間を過ぎると、墓地の使用権を失ってしまうこともあります。できるだけ早く、届け出を済ませましょう。
手続きに必要な書類は、以下の通りです。
-
・名義変更の申請書
-
・旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本
-
・新名義人の戸籍謄本、住民票(本籍記載)
-
・墓地使用許可証(永代使用許可証)
-
・新名義人の実印、印鑑登録証明書
その時になって焦らなくて済むように、あらかじめ必要な書類が手元にあるか、確認しておきましょう。
※親族以外が新名義人になる場合、遺言書やご家族の同意書などが必要になることもあります
※ご寺院や霊園によって、必要な書類や名称が異なります
※本記事は、2019年10月時点のものです。法律の改正などにより、掲載内容は変更される可能性があります
お電話でも受け付けております
















