
遺品整理はいつからすればいいの?始める時期や失敗しないコツを解説
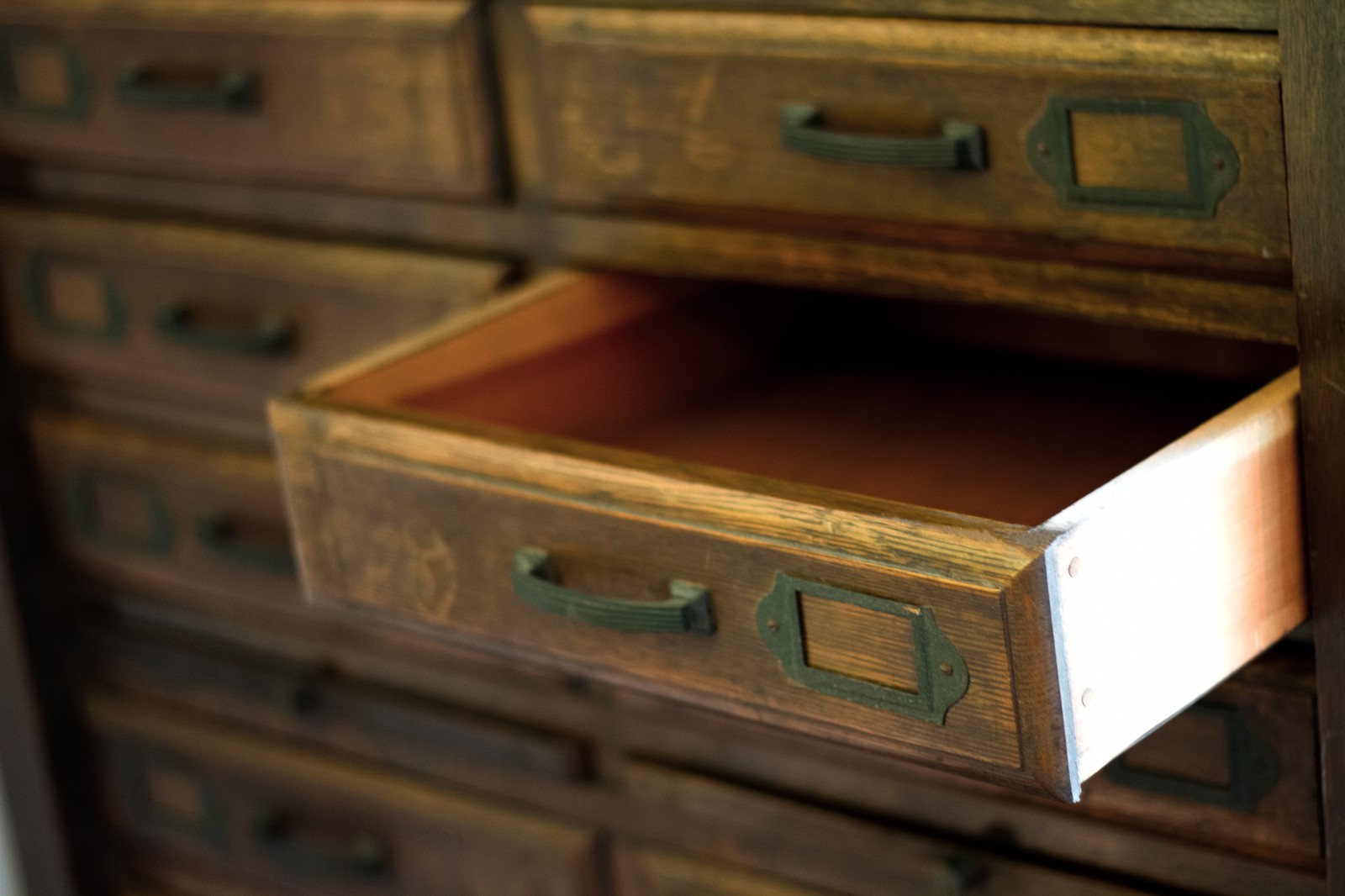
「いつから遺品整理をすれば良いかわからない」
「遺品整理は何から始めるの?」
「遺品整理で損をしたくない」
このように、遺品整理について考えている方にはさまざまな疑問や心配があるのではないでしょうか。
本記事では、遺品整理を始めるおすすめのタイミングとその理由、損をしないように遺品整理前にやっておいた方が良いことなどを紹介しています。
この記事を読めば、遺品整理を始めるのに適した時期や基本的な流れと、おおよその費用について把握できます。遺品整理について知識を得られるため、初めての方でもスムーズに進めることができるでしょう。
現在、終活について考えている方や遺品整理について不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
いつから遺品整理を始めればいいの?

遺品整理とは、家族や親族が亡くなった際に、その方が生前に使用していたものを整理することです。遺品整理は手間がかかることもあり、いつから遺品整理を始めたら良いのか悩む方も多くいます。
遺品整理をすることで、改めて故人の死と向き合うことになり、家族は悲しさや寂しさを感じるでしょう。しかし、遺品をいつまでもそのままにしておいては、部屋が片付かず、相続手続きにも支障が出ます。
また、故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、速やかに部屋を引き渡さなくてはならないため、なるべく早い段階で遺品整理を始める必要があります。
葬儀が終わった後
故人が賃貸物件に住んでいた場合は契約の問題もあるため、葬儀が終わった後すぐに遺品整理を始めなければなりません。また、親族が遠方に住んでいてなかなか集まれる機会がない場合も、葬儀が終わり次第すぐに遺品整理を始めると良いでしょう。
四十九日の法要の後
四十九日とは、命日から数えて49日後に行う仏教の法要のことです。49日後に法要を行う理由は、人の魂は亡くなってから49日まで現世を彷徨っていますが、その後は仏のもとへ旅立つと考えられているからです。
また、忌明けでもあり、喪に服していた家族が日常に戻る日でもあります。四十九日の法要には多くの親族が集まるため、親族間で遺品整理や形見分けについて相談しやすく、四十九日を目安に遺品整理をする方も多くいます。
ひと通りの手続きが終わった後
葬儀後は多くのことを決められた期日内に行わなければならないため、書類申請や解約手続きを終え、落ち着いてから遺品整理する方もいます。
家族や親族が亡くなると、さまざまな手続きが発生します。まず、役所へ死亡届を提出することから始まり、年金や健康保険の資格喪失、住民票の除票の手続き、保険金の請求など、必要な手続きは多岐にわたります。
その他、クレジットカードや携帯電話、インターネットなど故人が契約していたサービスの解約手続きも必要です。故人が契約していた項目を確認し、必要な書類があれば準備して、速やかに手続きを行いましょう。
気持ちが落ち着いたとき
故人との別れの悲しみが癒えていない段階での遺品整理は、辛い場合もあるでしょう。そのような場合は、気持ちの整理がついた段階で、遺品整理に取り掛かるのも一つのタイミングです。
しかし、先延ばしにしたままではトラブルが発生してしまう可能性があります。遺品整理をする時期というのは明確に決まっていませんが、基本的にはトラブルが発生してしまう前に取り掛かるのがおすすめです。
相続税が発生する前
相続税とは、亡くなった親や親族から土地やお金などの財産を受け継ぐ際にかかる、税金のことです。相続する財産の額から葬儀代や借金を差し引いた後の額が「基礎控除額」を上回った場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告には期限があり、通常故人が亡くなった翌日から10か月目の日までに税務署に申告書を提出すると共に、納付税額が算出された場合は納税しなければなりません。また、納付期限に遅れた場合は、加算税および延滞税がかかることもあります。
相続税を算出するには、遺品整理をして相続する財産の金額を調べます。相続手続きの時間にゆとりを持たせるためにも、余裕を持って遺品整理を始めると良いでしょう。
出典|参照:相続税のあらまし|国税庁
出典|参照:相続税について教えてください。|財務省
遺品整理をする前にやっておくこと

遺品整理を先延ばしにすると、トラブルが発生したり、費用がかかったりなどさまざまなデメリットが生じる恐れがあります。あまり先延ばしにせず、計画的に整理することが大切です。
遺品整理に取り掛かる前に、まずやっておくべきことを紹介します。
特定空き家に指定される前に処分しておく
空き家を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。また、所有している空き家が適切に管理されていない場合、防災・衛生・景観など地域の住環境に深刻な問題を及ぼしていると判断され、特定空き家の対象になります。
特定空き家に指定された場合、増税や強制撤去、50万円以下の過料が課せられる可能性があるため注意が必要です。誰も住む予定がなければ、早めに売却するか貸家にするなどの対策をしましょう。
相続税の申請をしておく
故人の財産を受け継ぐ際には、相続税が発生します。この場合の「財産」は金銭に限らず、家電製品や美術品なども対象になります。遺品が多い場合には、遺品整理業者に依頼するとスムーズに進められるでしょう。
相続税の申請は、故人が死亡したことを被相続人が知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。期日内に申請しても、相続税を納期内に納めないと延滞税が発生する場合があるため注意しましょう。
出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
故人の家の賃貸契約を確認しておく
故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸契約書を読んで契約内容を確認してから、管理会社に家賃の支払い状況や退去日について問い合わせましょう。
契約内容にもよりますが、賃貸物件は退去の際に原状回復することが求められます。退去日までに部屋を片づけ、入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。
遺品整理の他に、荷物の移動や家具・家電の撤去、掃除などをする必要があるため、できる限り早めに対応するようにしましょう。
遺品整理の方法

遺品整理する際には、自分で行う方法と業者に依頼する方法の2通りがあります。それぞれメリットとデメリットがあるため、状況に応じて選ぶのがおすすめです。
自分で行う場合のメリットは、故人との思い出となる遺品を丁寧に仕分けられることや、費用が抑えられることです。しかし、全てを自分で進めなければならないため、労力と時間を要します。
一方、業者に依頼することには専門的な知識をもとに遺品整理を進められるというメリットがあります。
その反面、遺品処分で間違いが起きたり、雑な扱いをされたりなどのトラブルが発生する可能性があるのがデメリットです。業者に依頼する場合は、信頼できるところを探しましょう。
遺品整理で失敗しないコツ

自分で遺品整理をする際には、やるべきことがたくさんあります。失敗して親族とのトラブルに発展したり、大切な遺品を手放してしまったりすることがないようにポイントを押さえておきましょう。
事前準備として大切なことの一つは、いつから始めて何から手をつけるのかスケジュールを立てておくことです。
ここからは、遺品整理で失敗しないコツを紹介するため、ぜひ参考にしてください。
● スケジュールを立てる
● 手続きに必要な書類や貴重品を探す
● 遺言書やエンディングノートを探す
● 遺品整理をする前に遺族に合意をとっておく
● 廃棄するものは処分する
スケジュールを立てる
遺品整理は時間がかかるため、あらかじめいつから始めて、いつまでに終わらせるというスケジュールを決めておくと、作業がスムーズに進みます。
遺品がどのくらいあるかによって、作業にかかる日数や必要な人数も異なるため、少しゆとりを持ったスケジュールを組むようにしましょう。
その後、どこの部屋から作業を始めるのかなど、具体的な段取りを決めます。
手続きに必要な書類や貴重品を探す
手続きには、故人にかかわる書類や印鑑など必要になります。どのような場面で必要となるのか分からないため、基本的に書類関係は不要と確定するまで保管しておきましょう。
手続きの際に必要となる書類や物は、次の通りです。
● 公的保険証
● 年金手帳、年金証書
● 預金通帳
● 不動産権利書
● 有価証券
● 保険証券
● 身分証明書
● 印鑑
● クレジットカード
● 公共料金領収書
遺言書やエンディングノートを探す
遺言書やエンディングノートなど、故人の想いが記されているものがある場合、記載された内容の通りに遺品整理を進めていきましょう。
遺言書やエンディングノートには、遺産相続に関することが記載されていることもあります。親族間のトラブルを避けるためにも、個人の想いが遺品の中に残されているかどうかを確認してから手続きを進めることが大切です。
遺品整理をする前に遺族に合意をとっておく
遺品整理は財産分与にも関わってくるため、親族の同意なく物事を進めてしまうと、トラブルに発展することがあります。
良かれと思って自分だけで遺品整理していたとしても、「金銭的価値があるものを持って勝手に持ち出したのではないか」というような疑いをかけられることも考えられるのです。
トラブルが起きないように、遺品整理をする際は親族の同意を得たうえで、誰が・いつから・どこで・何をするのかまで明確にしておいた方が良いでしょう。
廃棄するものは処分する
遺品の仕分け・分類が終わったら、それぞれの品の処理方法を決めます。
専門業者に買取査定を依頼する場合、特に金銭価値の高い貴金属や美術品などは、複数の業者に査定してもらいましょう。廃棄する場合は、あらかじめ自治体のルールや不用品回収業者の料金を調べておくと、スムーズに手続きが進みます。
遺品整理でかかる費用

遺品整理は、時間と費用どちらも要します。いつから始めるのかスケジュールを立てるのと同時に、どのくらいの費用がかかるのかも把握しておきましょう。
ここからは、業者に依頼した場合の費用相場と、自分で行うときに必要となる費用について紹介します。終活について考えている方も、ぜひ参考にしてみてください。
業者に依頼する場合
業者に依頼する場合の費用は、部屋の広さやサービス内容によって基本料金が変わります。依頼する部屋の広さが1Kの場合の基本料金は、3万円~4万円が相場です。3LDKの広さとなると、14万~22万円くらいと考えて良いでしょう。
基本料金に含まれるサービス内容は業者によって異なります。ハウスクリーニングの他に、不用品の回収、貴重品の仕分け・捜索を受けている業者もあるため、事前に確認しておきましょう。
自分でする場合
自分で遺品整理を考えている場合、費用は比較的抑えられます。不用品を処分する際に、廃棄物処理施設に直接持ち込むなどすると、さらに費用を抑えられるでしょう。
また、処分するものをリサイクルショップに持ち込むなどの方法もあります。処分費用を抑えられるだけでなく、買い取りが発生する可能性もあるため、1つの方法として検討してみるのも良いでしょう。
遺品整理をするときに気をつけること

遺品整理を始める時期を決める際には、気をつけておきたいポイントも把握しておきましょう。次に紹介するポイントは、遺品整理をスムーズに進めるためにも、思わぬトラブルを避けるためにも大切なことです。
知らずに放置してしまうと、想定外の出費となってしまう場合もあります。自分で遺品整理したいと考えている方は、特に気をつけましょう。
相続放棄を考えている
「遺産相続」と聞くと、財産が増えることをイメージする人も多いでしょうが、実際はそれだけではありません。
中には、故人が負債を抱えている場合もあります。そのような場合には、「相続放棄」という選択肢も一つの方法です。
ただし、相続放棄する際には、故人の負債を全て明らかにしたうえで申請する必要があります。形見分けなどをしてしまうと、相続放棄できなくなるため注意が必要です。
相続や各種手続きの期日を確認しておく
遺品整理をする際には、相続や各種手続きの期日を把握しておきましょう。期限が迫っているものから取り掛かるのが賢明です。遺品整理に取り掛かるときは、いつから始めるのかだけではなく、いつまでに申請が必要なのか期限を把握しておきましょう。
前述の通り、相続税の手続きは、相続人が故人の死亡を知った翌日から10か月以内が期限です。また、相続人が故人の所得税を確定申告する際には、相続開始から4か月以内が申請期限となります。
出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
賃貸物件であれば早く遺品整理をしておくようにする
故人の住居が賃貸物件であれば、早めに遺品整理を終わらせましょう。遺品整理に時間がかかってしまうと、その分だけ賃料が発生してしまいます。
遺品整理をする際には賃貸契約書を確認し、契約内容にもとづいて原状回復する必要があります。
出典|参照:賃貸借契約に関するルールの見直し|法務省
いつから遺品の整理をしたらいいか知っておこう

法要や各種手続きなどに追われ、悲しみに浸る時間もないまま遺品整理をしなければならないと思うと、精神的な負担が大きいと感じる方もいるでしょう。
遺品整理を行う期限は特に決められていないため、自分ができるタイミングで整理を始めるのがベストと言えます。
しかし、遺品整理を速やかに行わなければならない場合や、自分たちで遺品整理を行うのが難しい場合は、遺品整理業者に依頼するという選択肢もあります。
心残りのない遺品整理ができるように、ぜひこの記事を参考にしてください。
お電話でも受け付けております















