
永代供養墓に変更する際の墓じまいでお布施は必要?様々な場合の値段相場も紹介

「墓じまいでは僧侶を呼ぶ必要があるんだろうか」
「墓じまいではお経をあげてもらうのかな?お布施は必要?」
「そもそもお布施の相場が分からない!」
このようなお悩みはありませんか。
いまのお墓から永代供養墓に移すには、ご遺骨の引っ越し(改葬)を行います。改葬では、僧侶にお経をあげていただき、閉眼供養を行い墓石から魂を抜くのですが、そのとき僧侶に渡すお布施が必要になります。
閉眼供養はめったに行われませんので、お布施の相場や渡す際のマナーなどご存じの方も少なく、分かりにくい点が多いのではないでしょうか。
この記事では、永代供養墓に変更する墓じまいで、僧侶に渡すお布施について、詳しく説明しています。ぜひお布施のルールや相場、不祝儀袋の入れ方、渡し方など知っていただき、滞りなく閉眼供養を行ってください。
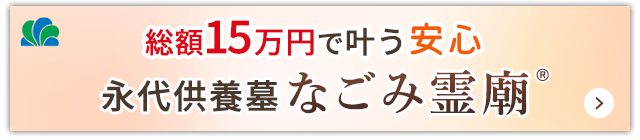
永代供養墓に切り替える際に必要な墓じまいとは

いまのお墓から永代供養墓に切り替えるには、一度お墓を「墓じまい」して、ご遺骨を引き上げ、新しいお墓に納骨します。
これを「改葬」といい、ご遺骨を取り出すだけでは完結せず、法律で定められた役所への手続きや、墓石の撤去・廃棄、区画の整地が必要です。
お墓の管理費の支払いが滞り、放置した場合は寺院や霊園がお墓を撤去します。この時、ご遺骨は無縁仏として合祀されます。
ご先祖のお墓が無縁墓にならないよう、永代供養墓にご遺骨を引越しさせる前段階として墓じまいを行うのです。
墓じまいをする理由

お墓の承継者の中には「お墓まで距離が遠い」「次の承継者がいない」「家族に負担を掛けたくない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、そのような墓じまいをする理由を解説してきます。
自分の代からお墓を継げなくなってしまうため
墓じまいの理由として、お墓の承継者がいないことがあげられます。お墓にも核家族化が進み「子供がいない」「子供たちはみな嫁いでしまった」といった問題を抱えている方も多いのではないでしょうか。
また、宗教的な考え方が希薄化し、お墓へ参拝すること自体あまり行わない若い方たちが増えたことから、自分の代で墓じまいを考える方が増えています。
無縁仏になってしまったため
承継者がいないお墓は、そのまま放置すると、無縁仏になってしまいます。無縁仏とは、供養する人がいない故人のことで、行き倒れや災害などの身元不明者、引き取り手のいないご遺骨が無縁仏となります。
宗教上の無縁仏は、供養されず安らかな死を迎えられない状態になると考えられており、ご先祖をこのような無縁仏にしたくないと考え、自分の代で永代供養に切り替える方が増えているのです。
お布施についての基礎知識6つ

お布施は、お経を上げてくださった僧侶に、お金の形で感謝の気持ちを伝えるものです。様々な場面で、それぞれルールが細かく決められており、マナーを守らないと失礼に当たるばかりか、ご家族やご親族の迷惑にもなりかねません。
この記事では、閉眼供養のお布施の知識として、主なものを6つ解説します。
1:主に閉眼供養の際に必要になる
お布施は閉眼供養の際に、お経を上げてくださった僧侶にお渡しします。
墓じまいでは、ご遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。閉眼供養とは墓石に宿ったご先祖の魂を抜くために行うもので、僧侶にお経を上げていただきます。
お布施はお経を上げていただく前か後に、感謝の言葉を添えて僧侶にお渡ししましょう。
2:不祝儀袋に包む
閉眼供養で僧侶へ渡すお布施は本来、奉書紙で包みますが、不祝儀袋や無地の白い封筒でも失礼にはあたりません。
不祝儀袋は、水引があるタイプと水引が無いタイプがあり、水引のついた不祝儀袋を使う場合、水引の色や形によってルールがあります。たとえば、白と黄色の不祝儀袋は関西地方で使われ、銀色の水引が付いた不祝儀袋は、お布施の金額が5万円以上の場合に使います。
もし、どの不祝儀袋を使えばよいか迷うようであれば、水引なしの不祝儀袋を使いましょう。
3:表に「御布施」と記入する

不祝儀袋の表面に「御布施」と書くか、すでに印刷されているものを使います。お布施とは、お経をあげてくださったお礼です。
筆または筆ペンで書くのが望ましく、薄墨ではなく濃い墨を使い「御布施」と書かれた下には、フルネームか「〇〇家」と書きます。
裏面は何も書かなくても良いですが、受け取られた側の経理上の利便性から、渡した人の「住所」「名前」「金額」を書いたほうが親切でしょう。金額の書き方は、1万円の場合「金壱萬圓」とします。
4:供養の前か後に渡す
「お布施」を渡すタイミングは、供養の前か終えた後が良いとされています。
供養の前であれば「本日は閉眼供養でお世話になります。」と一言添えると良いでしょう。供養の後であれば「本日は祖先の閉眼供養のために供養していただき、ありがとうございます」という一言になります。
また「お布施」の手渡しはマナーに反します。渡す際はかならず、袱紗(ふくさ)の上、または切手盆(きってぼん)と呼ばれる、金封を差し出すお盆に乗せて渡しましょう。
5:新券でも問題ない
弔事では古いお札を使いますが、お布施には新券(新札)またはあまり使われていないお札を使います。
新券を揃えることで「閉眼供養のため準備をして、この度ようやく無事執り行う運びとなりました」という意味で、読経してくださった僧侶にも感謝の意を表します。
6:お札は肖像画の面を表にして上部に来るように入れる
お布施を不祝儀袋入れるときは、お札の向きにも気を付けましょう。
お札は、肖像画のある面が表になります。不祝儀袋の表面と、お札の表側を揃え、お札を出すときに肖像画から現れるように入れます。
・お布施の金額目安はどれくらい?法事や法要の意味とあわせて紹介
永代供養にして墓じまいをする際のお布施の相場

一概にお布施と言っても、行事の規模や、寺院とのかかわり方によって金額が異なります。墓じまいの閉眼供養では、お墓を閉じるため離檀料も含めてバランスを考える必要があります。
お布施を用意する際には、多すぎず少なすぎず失礼にならない金額を入れたいものです。ここからは、閉眼供養の際のお布施の相場について解説します。
お世話になっているお寺に依頼する場合
いままでお世話になっていた寺院で墓じまいをする際のお布施の相場は10万円ほどです。たとえば、特に寺院と懇意にしていた場合などは、10万円を超えることもあります。また、離檀料が必要な場合は、お布施とのバランスも考慮に入れましょう。
御膳料を追加した場合
御膳料とは、法要の後の食事会に僧侶が参加しない場合に渡すもので、相場は5千円~1万円です。
白無地封筒か不祝儀袋に「御膳料」と書き、その下には「名前」もしくは「〇〇家」と記し、
裏面には包んだ「金額」「住所」「名前」を記入しましょう。金額の表記は、1万円では「金壱萬圓」と漢数字の大字で書きます。
渡すタイミングは、供養の前か後です。なお、お布施や御車代と一緒に包むのはマナーに反します。
御車代を追加した場合
御車代の相場は5千円~1万円です。新幹線や飛行機を利用された場合は、その金額を考慮して包みます。寺院内で供養が行われ、僧侶が移動を必要としない場合は不要です。
白封筒か不祝儀袋に「御車代」と、筆または筆ペンの濃い墨で書き、裏面に住所、名前金額を書きます。お布施や御膳料とは意味合いが異なるため、別々に包んで渡しましょう。
ネットで墓じまいを依頼した場合
最近ではインターネットで、僧侶を手配できるサービスも見られるようになりました。菩提寺がなく、霊園や公営墓地で閉眼供養を行う場合は、自分で僧侶を手配する必要も考えられます。
インターネットで僧侶を手配する場合の相場は3万円~5万円で、料金にお布施などすべて含まれる場合と、含まれない場合があります。なお、僧侶を自分で手配する場合は、必ず寺院や霊園へ事前に相談しておきましょう。
離壇料とお布施の違い

離檀料とは、菩提寺に「いままでお世話になりました」という意味で納めるお金のことです。
離檀料とお布施は、どちらも菩提寺に対し「感謝の気持ちを表すお金」という意味では同じです。しかし、離檀料の相場は菩提寺とのかかわりの度合いで決まるため、3万円~20万円と幅があります。
離檀料に関する法律はなく、契約書に書かれていない限り檀家が離檀料を支払う義務はありませんが、寺院の中には高額な離檀料を請求してくるケースもあります。あまりに高額な離檀料を請求された場合は、弁護士に相談しましょう。
墓を撤去する費用

お墓は、石で囲んだカロート(石室)の上に、芝台(しばだい)、中台(ちゅうだい)上台(じょうだい)、竿石(さおいし)と積み重ねた造りが一般的です。墓石の重さは1トンを超えるため、墓じまいは専門の業者が重機を使い撤去・整地します。
墓じまいは「改葬」が必要な場合と、墓石を撤去するだけの場合があり、業者によって提供するサービスの内容も料金も違います。
なお、寺院・霊園に専属の墓じまい業者がいる場合もあり、事前に問い合わせてから手配したほうが良いでしょう。
改葬する場合
改葬する場合、墓の撤去費用の相場は移転先の費用も含めると300万円近くになる場合があります。
改葬では、閉眼供養、ご遺骨の取り出し、墓石の撤去・廃棄、開眼供養といった一連の手続きや作業が含まれ、高額になる傾向にあるため、できる限り見積もりを取り比較・検討しましょう。
使用している墓所の撤去のみの場合
閉眼供養も終えて、お墓にご遺骨が無ければ、墓所の撤去のみとなり相場は1平方メートルあたり10万円ほどです。
この場合は、改葬手続きも供養も不要となるため、墓石の撤去・廃棄、整地のみとなります。
墓じまいをして永代供養に切り替える流れ

墓じまいから永代供養までの流れは、見積もりを取り、役所への届け出、僧侶の手配、供養と多岐にわたります。行う順番も大切で、全体を把握しなければ段取りを組めません。
ここからは、順を追って解説しながら、永代供養の埋葬方法について取り上げています。滞りなく永代供養に切り替えるため、全体の流れを把握していきましょう。
家族や親族に相談する
じつは、何より先に行うのは、ご家族やご親戚への相談です。埋葬されている方が多いほど、埋葬されている方にゆかりのある方も増え、墓じまいに反対される方や、永代供養墓に抵抗を感じる方がいる可能性もあります。
墓じまいが進んでから、反対する人が現れた場合、時間も費用も無駄になる可能性がありますので、お墓に関わりのある方たちから了解を得てから墓じまいに取り掛かりましょう。
納骨先を選ぶ
墓じまいの手続きに入る前に、移転先のお墓を選んでおきましょう。
永代供養墓には、新たに墓石型の墓を作るか、納骨堂や樹木葬などに埋葬する方法があります。また、参拝しやすい立地か、費用はどのくらいかなど検討の材料も多々あるため、ご家族やご親族との話し合いも時間をかけた方がよいでしょう。
個人墓の場合
永代供養の個人墓は、一人またはご夫婦、霊園によっては友人とお墓を持つことができます。お墓の承継者が不要で、契約期間を過ぎると合祀に切り替わり、ほかの方々と一緒に埋葬されます。
種類は納骨堂、一般墓、樹木葬などがあり、最近ではペットと一緒にお墓に入れる霊園もあります。
合祀墓の場合
合祀墓はご遺骨をほかの方々と共に埋葬します。費用の相場は3万円~10万円ほどで、永代供養料、墓地使用料、納骨料などが含まれます。
合祀墓では多くの場合、開眼供養は行われません。しかし寺院によっては、合祀墓に開眼供養を行うこともあり、お布施が必要となります。
安価ではありますが「ご遺骨を取り出せなくなる」「埋葬された場所が分かりにくい」「ほかの人と一緒の埋葬が気になる」などのデメリットがあります。特に、ご家族やご親戚の理解を得るための十分な話し合いが必要です。
散骨をする場合
散骨には「海洋散骨」「山林散骨」があり、いずれもご遺骨を細かく粉状にしてから海や山に撒くため、自然に還したいと考える方に人気があります。
墓所を必要としないため、永代供養料や施設利用料が不要です。相場はご遺骨を粉状にする費用が1万円~3万円、散骨の費用は3万円~となります。
お墓を持たないため、開眼供養を行わないケースがほとんどですが、散骨の際に僧侶が同行し読経していただく場合はお布施を渡します。なお、ご遺骨の一部を手元供養として残すことも可能です。
納骨先が決まれば手続きをする
ご遺骨の移転先が決まりしだい、改葬の手続きに入ります。
改葬とは墓から墓へご遺骨を移動させることを指し、役所への届け出が必要です。
墓じまい業者を手配する際にも、ご遺骨を取り出すとき、納骨するときにも改葬許可証が必要となるため早めに手配しましょう。
埋葬許可証を今の墓地管理者からもらう
いまのお墓の管理者から「埋葬許可証」を受け取ります。「埋葬許可証」とは、現在の墓所に確かに埋葬されていることを証明するもので、寺院・霊園が発行し、手数料は300円~1,500円ほどです。
「改葬許可申請書」の書式は、各市町村で異なり埋葬を証明する欄がある書式もあります。その場合は、寺院・霊園の管理者が直接記入できるため、あらかじめ役所から「改葬許可申請書」を取り寄せておくと良いでしょう。
受入許可証を納骨先からもらう
移転先の寺院・霊園からは「受入証明書」を受け取っておきます。「受入証明書」とは、これから納骨する寺院・霊園がご遺骨の受入を証明するものです。
「受入証明書」は、基本的に無料であり、納骨する方の名前などの情報が必要になります。
改葬許可証を自治体からもらう
「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」が揃い次第、自治体(市区町村)に提出し、「改葬許可証」を受け取ります。
「改葬許可証」は、墓じまい業者、埋葬元・埋葬先の寺院・霊園に提示、提出する書類ですので紛失には注意しましょう。
閉眼供養後に遺骨を取り出し埋葬先に納骨する
閉眼供養を終え、ご遺骨を取り出したら、いよいよ埋葬先に納骨します。
可能であれば事前にカロート(石室)の中を確認しておくと良いでしょう。骨壺が汚れていたり、雨水でご遺骨が濡れていることがあります。その場合は新しい骨壺に替え、洗骨、乾燥等の作業が必要です。
時間や費用の関係で墓じまい当日まで、カロートの様子を見られないのであれば、前述のような事態も想定して業者に相談しておく必要があります。
・墓じまいをして永代供養にする手順は?それぞれの違いや費用についても解説!
墓じまいや改葬を依頼する際の注意点

インターネットで、墓じまい業者を検索すると、様々な墓じまい業者が出てきて、業者選びに迷う方も多いのではないでしょうか。また、墓じまいを行う際、寺院・霊園は快く応じてくれるか、心配される方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、失敗しないための業者の選び方、寺院・霊園とスムーズに墓じまいを行うためのポイントを解説します。
複数の業者を比較検討をする
墓じまい業者は、必ず数社の見積もりを取って検討しましょう。
大抵は全国対応が可能で、無料相談、無料見積りをおこなっています。改葬許可証の手続き、離檀の代行、仏壇の撤去も請け負う墓じまい業者もおり、依頼者の負担を軽減することができます。
最近ではホームページでサービス内容や料金を確認できますが、資料を取り寄せる際、直接電話を掛けて、業者の対応の質を知ることも大切です。
改葬を行うときは霊園のガイドラインを確認する
改葬では事前に、寺院・霊園のガイドラインを確認しておきましょう。
寺院・霊園によって、墓じまいのルールを定めている場合があります。すべて手配した後で寺院・霊園から改葬に異議を唱えられては、膨大な時間や手間、お金の損失になりかねません。
また、寺院・霊園にガイドラインが見当たらない場合でも、問い合わせで確認しておくことをお勧めします。
墓じまいをする前に情報を集める
墓じまいの前には十分な情報を集めておきましょう。墓じまいには業者や寺院・霊園とのやり取りがあるため、情報量が多いほど価格交渉や段取りに役立ちます。
インターネットの情報収集では、サービス内容や料金のほか、業者の口コミも確認しておきましょう。納骨先の寺院・霊園の情報も同様に、できる限り情報を集めておきます。
ホームページの閲覧だけではなく、パンフレットも取り寄せておくと、情報に違いがないか確認できます。
離檀料が高額すぎる場合は弁護士に相談する
墓じまいで、いままでお付き合いのあった寺院から離檀します。本来、お布施と同じように感謝を表す「離檀料」は、契約書に書かれていない限り檀家に支払い義務はありません。
しかし、高額な「離檀料」を請求されるケースがあります。「離檀料」を払わなければご遺骨を取り出せないと言われたり、高額な離檀料を請求された場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
開眼供養のお布施について

開眼供養にもお布施が必要です。開眼供養とは、合祀ではなく新しく個別に作ったお墓の墓石に魂を入れる供養で、僧侶にお経を上げていただくため、お布施が必要になるのです。
開眼供養のお布施の相場は、3万円〜5万円で、閉眼供養と同様に御膳料や御車代も考慮しておきましょう。
なお、納骨も同時に行う場合は不祝儀袋、開眼供養のみの場合は祝儀袋を使います。
お布施の知識を身に付け永代供養に向けて正しく墓じまいをしよう

お布施はマナーや作法が重視されるため、失敗したくないと不安に思うこともあるでしょう。永代供養や墓じまい自体、経験する人が少なく情報を集めるにも、時間や手間がかかります。
この記事では、永代供養墓へ切り替えるための流れや手続きの方法、供養の際のお布施のマナーまで、一通りの情報を紹介しました。
ぜひこのコラムでお布施の知識を身につけて、墓じまいして永代供養をつつがなく行っていただければ幸いです。
お電話でも受け付けております















